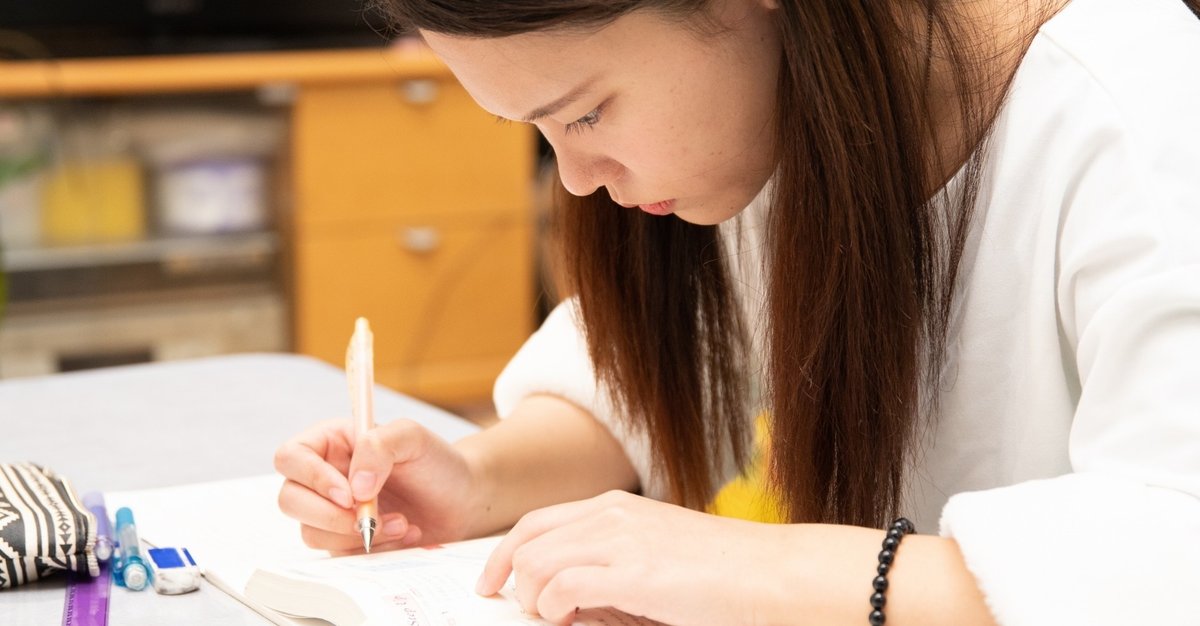
失敗しない勉強方法③検査法(1)(forセラピスト)
臨床科学(2)
前回に続き、臨床科学です。今回は「検査法」についてまとめました。
多くの患者さんは、未病の状態で来店されます。
つまり、ほっておくと病気になる可能性がある中で、状態を悪化させるか、良化させるかの判断をするのが検査です。
私たちセラピストが、施術で「人為的事故」を起こすか起こさないかを左右するのは、この検査の精度になります。
・何をすれば良くなるのか?
・何をすれば悪化するのか?
・どの程度重症か?
・徒手療法は適切か?
・治療ポイントはどこか?
・どの治療法が最適か?
↑が分からなくては、状態の把握も、解決方法も、どこまで改善する可能性があるのかも、お伝えすることができません。
つまり、「臨床医学各論」と「検査法」がしっかりしていれば、未病の患者さんは治ります。
そして、事故を起こすことがなくなるんです。
・検査法
検査法では、その重症度をセラピストが分かる範囲で、判別していきます。
患者さんは、少しでも早く善くしてもらおうと「自分はとにかく重症だ」感を出してくることもありますが、実際はすごい軽度のこともあります。
言われたことを鵜呑みにし、検査もせずに、重症者用の施術をしたら、当然事故が起きます。慌てず、正しい施術を行うためにも、指標となる検査は必要に応じて行うようにしましょう。
また、設備などの問題で、セラピストではできない検査も多くあります。他の医療機関で、検査を受けて頂く必要がある時は、しっかり患者さんに説明し、適切な段階が踏む事が大切です。
治療はギャンブルではありません。とりあえず施術し、行き詰まってから、「実はこんな検査が必要だった」という無責任なことはしないようにしましょう。
<主な検査>
・理学検査(問診・視診・触診)
・身体計測
・関節可動域検査(以下ROM)
・徒手筋力検査(以下MMT)
・整形外科的検査(以下OPT)
・神経学的検査(以下NLT)
・画像診断(X-ray、CT、MRI)
検査が上達するためには
いずれの検査も、以下の3点を守ることが大切になります。
①検査の目的
②注意事項
③評価基準
今回は概要だけですが、各検査ごとの詳細は、別の記事で紹介する予定です。早く上達する方法に近道はありません。コツコツ頑張りましょう。
オススメ図書
検査法は、テキストだけで把握するのは難しいものです。より見やすい本が見つかれば、随時更新していきたいと思います。
・動画で学ぶ関節可動域測定法 ROMナビ 増補改訂第2版
・整形外科テスト ポケットマニュアル臨床で使える徒手的検査法86
まとめ
学生時代、私は
「テクニックさえ習得できれば、ゴットハンドになれる」
と考えていました。
それが勘違いだと気づいたのは、学校を離れて1年後です。
・いつ使うのか?
・どんな方に使うのか?
いくら良いテクニックでも、結局コレが分からなければ、何の使いみちもない、ただの危険な手技でしかありません。
幸い私は、早めに大切なことに気づけたこともあり、事故を起こすことなく、また治療系を諦めるという決断をすることなく、今に至っています。
しかし、多くの仲間は、事故はせずとも、癒やし系へと転換していきました。事故を起こす自分が怖かったんだと思います。
基礎科学、臨床科学は、地味で臨床には関係のないようなものに感じますが、実はここが治療の本質であり肝になります。
書くという表現に限界はありますが、できるだけ多くの【治療系になるための考え方】をこのブログで紹介していきます。
勉強方法と題しているのに、なかなか概要ばかりで退屈かもしれませんが、徐々に詳細部分へと進んでいきます。
しかし、この面倒な話の延長に【治療系】になるためのヒントがあります。ぜひ一緒に頑張りましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
