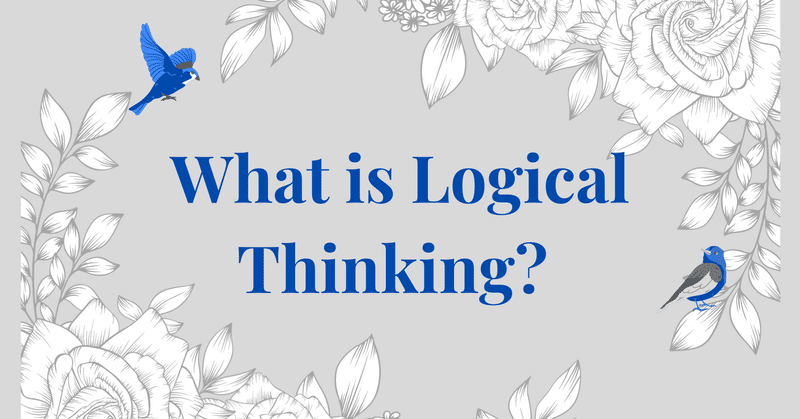
ロジカルシンキングとは何か?──波頭亮『思考・論理・分析─「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践─』の要約を通してロジカルシンキングの構造を明示する
はじめに
「論理的に考えるとは、どういうことか?」──この問いは、”論理的思考力”や”ロジカルシンキング”といった能力が広く求められている現在だからこそ、切実に問われている問いである。また能力として求められているという以上に、「自らの生き方を選択する」という意味での”自由”を獲得するために、つまり日常生活で適切な判断を行い続けるために論理的思考は必要となる。「論理的に考えること」は、21世紀を生きる我々にとって基礎的かつ実践的な関心のもと要請されている態度であると言ってよいだろう。
ロジカルシンキングの重要性は広く認識されつつある一方で、雑多な経験に由来する「このような場合は、こうしておけばよい」程度の定石や、ビジネスの多様なフレームワークを事象に機械的に当てはめるような思考態度が”ロジカル(論理的)”と呼ばれ、もてはやされているようにも思われる。論理や思考の原理・原則が理解されないまま、表層的に”ロジカル”だとみなされている言動や行動も存在してしまっているのだ。
本記事では、波頭亮著『思考・論理・分析─「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践─』の要旨をたどることで、論理的思考の核心を理解することを目指したい。『思考・論理・分析』は、思考や論理の原理・原則の解説からビジネスシーンでの実践の要点まで段階的かつ網羅的に記述しており、他のロジカルシンキング解説本よりも内容の普遍性や構造性、一貫性といった観点で非常に優れた書籍である。本書を手引きとして、改めて、論理とは何か、思考とは何か、論理的思考とは何かといったことについて丁寧に考えてみたい。
1. 思考とは何か?思考とは、情報を突き合わせ比較することである
1. 1「思考」の定義
思考とは、端的に表現するならば、「思考者が思考対象に関して何らかの意味合い(メッセージ)を得るために頭の中で情報と知識を加工すること」である。
波頭によると、疑問が思い浮かんだときにその答え(メッセージ)を求めるために頭の中で行われる作業が「思考」と呼ばれる。
一方で思考対象に関して何らかの意味合いを得るためには、思考に加えて「情報収集」という作業が必要である。情報収集とは、思考者の頭の外に対して働きかけ思考の材料を増やす行為である。思考はあくまでの思考者の頭の中で行われる情報の加工行為であるため、材料が足りない場合は思考材料を外から収集する=情報収集をすることになる。
思考対象に対して合理的な答え(メッセージ)を得るためには、頭の中で情報を整理する思考か、頭の外から情報を取得する情報収集の2種類の方法しか存在しない。
思考のメカニズム
先ほどから用いてきた「情報を加工する」とは、どういう作業だろうか。
情報を加工するとは、端的に言うならば「情報と情報を突き合わせる」こと、「比べること」である。
以上を踏まえると、思考の定義は以下のようにも表現できる。
思考とは、「思考対象に関する情報を知識を突き合わせて比べ、”同じ”か”違う”かの認識を行い、その認識の集積によって思考対象に関する理解や判断をもたらしてくれる意味合い(メッセージ)を得ること」である。
上記のような思考の定義をもとにすると、人が何か(事柄、物事、出来事)を理解すること、物事を分かることが一体どういうことかも”分かる”ようになる。すなわち、「何かを分かる=判る=解る」こととは、その何か(事柄)を構成する個々の要素について、思考者が有する情報や知識と突き合わせて比べ「同じ部分と違う部分に分けつくすことができた状態」と言える。
1. 2 「分ける」ための三要件
正しく「分かる」ためには、思考対象を諸要素に正しく分けなければならない。正しく「分ける」ためには、①ディメンジョンの統一、②クライテリアの設定、③MECEであることの3要件が踏まえられなけばならない。順に見ていこう。
①ディメンジョンの統一
まず「ディメンジョン」とは、「抽象水準」、「思考対象・思考要素が属する次元」のことを指す。適切に分けて比べるためには、比べようとしている事象や要素が同一抽象水準上、同一次元上になければならないのである。
例えば、「フルーツとブロッコリーではどちらが好きか」という質問があったとする。その質問には違和感を覚えるのではないだろうか。それは、比べている2つの対象の抽象水準が揃っていないからである。
②クライテリアの設定
次に「クライテリア」とは「思考対象を分類する場合の切り口」、つまり「分類基準」を指す。分類基準を設定するということは、分析対象の事象をどのような構図で分かりたいのかを決定づけることを意味する。
クライテリア設定で留意しなければならないのは、最も妥当なクライテリアが常に一つだけ決まっているわけではないということである。なぜなら、ある一つの事象を分ける場合には一般にいくつものクライテリアが成立しうるからである。「食べ物」のクライテリアは和食、中華、フランス料理といった「料理の国籍」、野菜、フルーツ、肉などの「材料」といったクライテリア(分類基準)を設けることができる。そのため思考者は思考目的に合致したクライテリアをを選び取る必要がある。
正しく分けるための適切なクライテリアとは、思考者に適切な思考成果(思考者の思考目的を満たす答え)をもたらすクライテリアである。
なお適切なクライテリアの設定を行うためには、そもそも思考者が多様なクライテリアを頭の中に事前に保有していなくてはならない。そのためビジネスシーンにおいては上司や先輩社員から成果物(あるいは成果物を完成させるための構成要素)をレビューしてもらい適切なクライテリアが設定できているかを確認してもらうとよいだろう。
③MECEであること
思考対象を正しく分けるための最後の要素は、「MECEであること」である。
「MECE」とは、「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字を取った語であり、日本語では「相互背反(互いに重なりがないこと)、集合網羅(全体を網羅していること)」となる。さらに言い換えると、「ある同一平面上の複数の要素に、もれなくかつ重複なく部分集合化されていること」、すなわち「モレがなくかつダブりがないこと」である。
ビジネスの文脈では「30代女性」「50代男性」などサービスの購買層を分析する際(セグメンテーション分析)や、「機能」「価格」などのサービスの購買決定要因(Key Buying Factor)といった定性的な分類時に考慮される。
以上、適切に分ける、分かるための要件として①ディメンジョンを整えること、②適切なクライテリアを設定すること、③MECEに分けることの3つを挙げた。
1. 3 思考成果
二つの要素的思考成果
ところで、我々が思考によって得られる「思考成果」には、2つの種類がある。すなわち、思考対象が結局のところ何であり、どのようなものであるのかという「事象の識別(属性の理解も含む)」と、事象に含まれる要素同士はどのような関係になっているのかという「事象の関係性の把握」の2つである。
どれほど複雑で高度な思考テーマであっても、我々がとることのできる思考方法とは「事象の識別」を行い「事象間の関係性を把握」し、それらを組み合わせることに尽きるということだ。この二つに依らない答え(メッセージ)の導出は、単なる観察か、ひらめき、思い付きのような類である。
事象の識別
事象の識別とは、他の事象と異なる部分を認識する行為であると言える。なぜなら、他の部分と”違う”部分こそが”そのものらしさ”を示すからである。よって”そのものらしさ”を的確に際立たせるためには「何と比べるか」、「どの切り口で比べるか」の比較が有効でなければならない。「比較」という行為が有効であるかどうかは、「比較対象」と「クライテリア」次第というわけだ。
なお「これは何である」という的確な識別のためには、「これはどういうものである」という属性の認識も併せて要請されることになることも押さえておきたい。
「事象の識別」と「属性の理解」を助けるのは、知識の分類と体系化である。
まず「分類」とは、”違う”で分け、”同じ”でくくり、考察対象の要素を「複数の類(部分集合)に分けること」を指す。
では”よい分類”とは、どのような分類か。それは端的に言えば「体系化」された分類である。では「体系化」されているとはどういうことかというと、”構造的に整理されていること”と言える。
「構造」とは、ある事象の「構成要素」とそれら構成要素群の「位相(つながり方/位置関係)」によって成立するものである。したがって「体系化された分類」とは、考察対象となっている事象の「構成要素」と「位相」が理解しやすいように明らかにされている状態ということになる。
「構成要素」と「位相」が理解しやすい状態であるための要件は、先に述べた分けるための三要件──ディメンジョンが統一されていること、クライテリアが明確であること、MECEであること──の3点である。これら3つの要件を満たす”体系化された分類”こそ、識別された事象を構造的に理解させてくれるものなのだ。
関係性の把握
次に思考成果の2つ目、関係性の把握について見ていこう。
複数の事象が存在するとき、それらの事象間の関係は「相関」か「独立」のいずれかである。
「相関」とは、二つの事象が何らかの影響を及ぼしたり及ぼされたりする関係である。ギャクに二つの事象が全く影響を及ぼし合うことのない関係、すなわち一方の事象が変化してもう一方の事象は何ら変化する必然性のない関係が「独立」である。
二つの事象を”突き合わせて比べ”一方が変化したときにもう一方が”変化する/しない”の認識を行うことで、二つの事象間の関係性が「相関」か「独立」かを把握することができる。
「相関」はさらに二種類の相関関係に分類できる。一つはある事象が別の事象を引き起こす「因果関係(原因と結果の関係)」であり、もう一つは”原因と結果”にない「単純相関」である。例えば「自動車のスピードと事故率」の関係は「因果関係」、「身長と体重」の関係は「単純相関」だ。
世の中の事象の多くは「独立」である。そのため事象間での関係性、とりわけ因果関係を見出すことは価値が高いことだと言える。
1. 4 因果関係
因果関係に依拠すれば、たとえ未知、未経験、未発生の事象に対しても合理的な判断や振る舞いが可能となる。
しかしながら、現実に生起する事象の因果関係は複雑である。原因が一つであるような場合は極めてまれであり、たいていは複数の事象が原因となっているし、そもそも原因となる事象にも原因となる事象があり、さらにその原因となる事象がありという数珠つなぎのような因果の連鎖がある(無限後退に陥る)。
それでは現実の中からどのように因果関係を見出せばよいのだろうか。ここでは因果を発見・捕捉するための「因果の条件」を二つ紹介する。一つ目は「時間的順序」、二つ目は「意味的連動性」と呼ぶことができる条件だ。順に見ていこう。
時間的順序
時間的順序は、時間をもとにして因果関係を理解することである。相関関係にある二つのうち、あるいっぽうの事象が”先に”起こり、それを原因としてもう一方が”後から”結果として起こるという理解の仕方である。
時間的順序は理解しやすいものの、「相互因果」の可能性は必ず考慮しておかなければならない。「相互因果」とは、二つの事象A、Bがあったとき、AがBの原因となっているのと同時にBもまたAの原因となっているようなケースだ。ビジネスの現場では「やる気があるやつほど出世するという出世の好循環」、「品質低下が売上不振を招き、売上不振がさらなる品質低下を招くという悪循環」といった主張がなされることがあるが、これらは相互因果の関係になっている可能性が高い。
意味的連動性
効率よく因果関係の特定化を行うためのもう一つの視点が、事象間の「意味的連動性」を確認することである。意味的連動性はその表現を定義するのは難しいが、「経験的に納得して受け入れることが可能な関係性」とひとまず言うことができる。
どうして「意味的連動性」が重要なのか。それは、結果が発生する前に起きた事象を機械的に探すとなると、ある結果の過去に生じた無限の事象を検討しなくてはならなくなってしまうからだ。
例えば「二日酔い」の原因は「前日の飲み会で飲みすぎたこと」と特定されるのであって、「昨日の服装がジャケットだった」とか「昨日半蔵門線に乗った」という事象に原因が求められることはない。それは「意味的連動性」を手がかりにして原因としてふさわしい事象を絞り込んでいるからである。
ただ意味的連動性は正しく因果関係を補足するために重要な要件ではあるものの、思考者の経験や知識が乏しい領域においては、意味的連動性の確認が困難になってしまうということには注意しておきたい。
1. 5 因果補足の三つの留意点
ここまで、複雑に絡み合っている事象の中から因果関係を特定するための二つの条件、「時間的順序」と「意味的連動性」について説明してきた。
ここからは因果関係を誤認しないようにするための3つの留意点、すなわち「直接的連動関係」、「第三ファクター」、「因果の強さ」を紹介する。
直接的連動関係
まず因果における「直接的連動関係」の把握とは、結果を引き起こした直接の原因(”近因”)を特定することを意味する。
例えば、「二日酔い」の原因は「お酒の飲みすぎ」に求められるべきであって、「飲み会に行くこと」自体は二日酔いの直接の原因とは言えないのである。(ただし、「二日酔い」は「飲み会に行くこと」とは無関係、あるいは独立の関係にあるとは言えないはずである。よって「飲み会に行くこと」は「二日酔い」の”遠因”と呼べる。)
第三ファクター
次に「第三ファクター」について見ていこう。
「第三ファクター」とは、一つの因子Xが異なる二つの事象A、Bの原因になっている場合には事象AとBの間にも相関関係が生じるが、このAとBの相関関係を生じされる共通因子Xのことを指す。すなわち、”事象Xと事象A”、”事象Xと事象B”がそれぞれ因果関係にある場合、AとBの間に生じる相関関係の背後で、その相関関係を生じさせているA、B共通の原因Xが第三ファクターである。この場合、Xという原因があって生起する二つの結果AとBの間の関係は単純な相関関係に過ぎないが、第三ファクターXの存在が見えていないとAとBとの関係を相関関係だと誤って認識してしまうことがある。
例えば、「傘をさして歩いている人の割合」と「防水の靴を履いている人の割合」は単純な相関関係が成り立っていると言えるが、それらの事象には共通の「強い雨が降り続いている」という共通の原因がある。
因果の強さ
因果関係を正しく理解するための第三の留意点は、「因果の強さ」である。
「因果の強さ」とは、多様な原因がある中で、どの事象が結果に対して強い影響力を持っているかという視点である。
「今日寝坊した」ことの原因を「この世に生まれてしまったからだ」と弁明しても説得力がないのは、因果が弱いからである。
有効な戦略や施策を立案するには、事象(戦略や施策)と事象(実施結果)を因果の関係で結ぶ線の太さ、つまり因果の強さに留意しなければならない。
1. 6 思考の属人性
思考成果は「思考の属人性」によっても左右される。
知識の属人性
思考とは、外から与えられた情報を、思考者が頭の中で自分の知識やそれまでの経験と照らし合わせて同じ部分と違う部分に整理し「それが何であり、それと他の事象がどのような関係であるのか」を理解する行為であった。
したがって、外から与えられた情報が全く同じであっても、思考者各人によって持ち合わせている知識や価値観が異なるために、情報から得られる答え(メッセージ)も異なってくるのだ。それは同じ広告を見たとしても宣伝された商品を購入するかどうかが各人の判断に委ねられることからもわかるだろう。
思考の属人性のもたらす意味
以上、本章では「思考」について詳しく見てきた。
思考は思考者個人の内部で行われる極めて属人的な行為である。したがって思考者の保有する知識と性格によって、思考の成果(アウトプット)として得られる事象の識別や関係性の把握も変わりうる。
留意したいのは、思考には属人性があるからといって「人々の意見が全く一致しない」ことや「客観的な結論は得られない」ことは意味しないということだ。誰もが正しいと認めざるを得ない「論理」という思考の方法論に基づいていれば、他者と共有できる思考成果を獲得できる。
2. 論理とは何か?
前章では、思考者が脳内で情報と知識を加工する行為である「思考」について見た。本章では、思考が思考者に依存してしまうという属人性を超え、いわゆる客観的な正しさを担保するための方法論である「論理」を紹介する。
そもそも論理とは何か?論理の定義
まず波頭による論理の定義を見ていこう。
ある「根拠に基づいて何らかの主張(結論)が成立していること」、言い換えるならば、「ある主張(結論)が何らかの根拠に基づいて成立していること」を「論理構造」という。そして論理構造において「根拠から主張(結論)を導く思考のプロセス、思考の道筋」が「論理」である。
現代では論理は万能なものであるかのように崇められているが、実は論理は正しい思考のための一つの必要条件であることに注意しよう。つまり論理は、正しい思考を成り立たせる要素の一つにすぎず、論理的であれば即正しい思考だとみなすことはできないということだ。
とはいえ論理は正しい思考を担保するために十分ではないが、必ず必要となる要素である。正しい思考のために論理の他にどのような要素が必要なのかについては後述する。
論理構造の二つの条件
論理構造が成立するためには以下2つの条件が必要である。すなわち、①「命題」が少なくとも二つ必要であること、②その二つの命題の一方が「根拠」、もう一方が「主張(結論)」という役割として繋がれうるものであるという2つの条件である。
「命題」とは一般的には「文(主語と述語を持つ文)」と「式(等号、不等号などの記号で左辺と右辺に分けられた式のこと)」といった形式で表される。例えば「雪が降っている」や「y = x²+3x+5」は命題であるが、「雪」や「3x」などは文や式ではないので命題になりえない。
これが「命題が少なくとも二つ必要である」という論理構造に必要な第一の条件の内容である。そもそも「論理」とは「根拠」と「主張」を繋ぐものであるから、「根拠」や「主張」となる命題が一つなのであれば繋ぎようはないことは明らかであるし、単なる単語や記号のみでは「根拠」や「主張」にならないこともまた当然と言えるだろう。
論理構造が成立する条件の2つ目は、「二つの命題が根拠と主張として”繋がれうる”」ということであった。繋がれうるとは、例えば「雪が降っている」ことを根拠として「冬になった」と主張できる(結論づけられる)といったことである。
しかしながら、どうしても繋ぐことができない命題の関係もある。例えば「雪が降っている」ことと「犬は哺乳類である」という命題には何ら意味的関係性を見い出せないだろう。このような命題は「乖離命題」と呼ばれる。二つの命題が乖離命題であるならば、各命題が根拠と主張の役割を担えないので論理構造は成立しない。
論理的であること
「論理的」であるとは、「話(議論/文章)が論理構造を備えていて、根拠から主張を導出するプロセスの納得性が高いこと」である。ここで重要なのは、形式的には論理的であるが、日常的な視点では論理的ではない場合があるということだ。
例えば「タロウは25歳である。したがってタロウは25歳か26歳である。」という命題構造は論理学的論理性の観点からいうと、形式的にも内容的にも極めて論理的には全く正しいのである。他にも例を挙げよう。「賛成の人は手を挙げてください」という指示に対して、反対でも手を挙げることは、論理学的論理性という点では全く誤りではない。しかしながら実際のところは、「賛成の人は手を挙げてください」という言明には「反対の人(賛成でない人)は手を挙げないでください」という意味が持たさせれているだろう。
形式上の論理性だけでは主張の現実的妥当性が担保されるわけではないということには注意しなければならない。
2. 1 論理展開
論理展開と推論
論理的思考の核心をなすのは、「論理展開」である。
「論理展開」とは、論理的な思考を行う場合に頭の中で情報を加工して「論理」を形成・構築することであり、主張/結論を導き出すための中心的頭脳作業である。そして、ある命題を前提にして「論理展開」を行い、主張/結論を導き出す思考行為を「推論」と呼ぶ。したがって「論理展開」によってこそ「推論」は成立するのであり、「論理展開」とは「推論」そのものであると理解してよいだろう。
以下では推論の定義、価値の高い推論の特徴、価値の高い推論によって得られるものについて見ていく。
推論とは何か?
推論とは、「思考によってある命題から次段階の命題を得ること」である。推論はある命題(規呈命題)を素材にし思考することで何らかの結論を得るという思考のプロセスであるため、推論の本質的な部分が論理展開と言える。推論とは論理そのものであり、推論は名詞的意味合いでは「論理」、動詞的意味合いでは「論理展開」と解することができる。
なお論理の原語(英訳)は「logic」であるが、「inference(推論)」を使って表せば「vaild inference(妥当な推論)」となる。したがって、論理的に正しい結論(メッセージ)を獲得するには単なるinferenceではなくvaild inferenceを行う必要があると言えるだろう。
推論の価値:確からしさと距離
推論(inference)という行為自体は、価値中立的である。しかしながら推論は「価値がある」あるいは「価値がない」とみなされることがある。「推論の価値」はどのように測られているのか。
「推論の価値」は、得られた結論が既呈命題に対してどれだけ”新しい意味内容”を持つか、すなわち「既呈命題との距離」と、その結論がどれくらい正しいか、すなわち「確からしさ」の二つの要素によって決まる。どういうことか。
命題の確からしさは、「AはAである」(例:タロウはタロウである)という形式であれば100%確実に担保される。しかし「AはAである」という形式の言明(トートロジー)は既存の情報(命題)に何か新しい情報(命題)を付加しないので、そこにメッセージ(推論の価値ないし成果)はない。
推論の価値を生むのが「既呈命題との距離」とされるのは、命題同士の意味内容の差異が大きいほど意味を繋ぐプロセスである推論の成果が大きくなるからと言える。
推論によって得られる結論は、当たり前のことであってもほとんど価値がないし、誤った内容であれば当然無価値である。現実的に有用な推論を行うためには、どの程度の「確からしさ」を認めるのかという基準を引き、推論における「確からしさ」と「距離」のバランスをとることが肝要である。
「推論の価値」についてもう1点留意すべきなのは、”納得性”という観点である。先述したように、価値の大きい推論は命題間の距離が大きい。そのため、それらが他人に理解してもらいやすいように思考者は論理を組み立てなくてはならない。
2. 2 論理展開の方法論
論理展開の二つの方法論:演繹法と帰納法
繰り返しになるが、論理的思考(vaild infernce)さえできればそれだけで結論の客観的正しさが保証されることはない。とはいえ論理的思考が正しい結論を得るために必ずなくてはならない要素であることは厳然たる事実である。
客観的正しさを担保する論理展開の方法論(形式、パターン)は、大きく「演繹法」と「帰納法」と名づけられている。まずは演繹法について見ていこう。
「演繹法」とは、「既呈命題を大前提と照らし合わせて意味的包含関係を判断し、その意味的包含関係の中で成立する必然的命題を結論として導き出す論理展開」である。
具体的に示すと、「AはBである。」が「既呈命題」で、「BはCである。」を「大前提」とすると、この二つの命題から判断されるA、B、Cの包含関係から、「AはCである。」という「結論」が成立する。
この形式に則った論理展開が「演繹法」である。また、この例からも解るように「演繹法」は、「既呈命題」、「大前提」、「結論」という三つの命題が段階的に示される形式をとるので「三段論法」とも呼ばれる。
例えば、「ブリは魚類である。」が既呈命題で「魚類が脊椎動物である。」を大前提とすると、「ブリは脊椎動物である。」という結論が成立するというわけである。演繹法は、大前提に既呈命題が含まれるような関係にあるので、数学的ないし形式的に明快な判断が可能な純粋論理的な特徴を有する。
では次に「帰納法」について見てみよう。
「帰納法」とは「複数の観察事象の共通事項を抽出し、その共通事項を抽出し、その共通事項を結論として一般命題化する論理展開」のことである。
例えば、観察事象①「ブリはエラで呼吸する。」、観察事象②「イワシはエラで呼吸する。」、観察事象③「サケはエラで呼吸する。」といった観察事象からは、「すべての魚はエラで呼吸する。」という一般名化した結論(メッセージ)が得られるといったことだ。
演繹法の特徴
演繹法は大前提に据える命題がそもそも偽であるならば(例えば「魚類は無脊椎動物である。」とするならば)、いくら論理展開上の形式が適切であったとしても妥当な結論が得られなくなってしまう。よって「年長者を敬うべきである。」や「人は痩せているべきである。」といった道徳律や生活規範は不適切というほどではないが十分な普遍性のある大前提とは言えないだろうし、さらに言えば個人的な経験や好みを演繹法の大前提とするのは妥当ではないだろう。
演繹法では①大前提が既呈命題の意味的内容を包含し、かつ②大前提の意味内容が普遍性を持っていなくてはならない。
帰納法の特徴
帰納法は有限な観察事象の中で成立している共通事項を一般命題とするため、その結論は真か偽かというよりも、どのくらい確からしいかという観点で正しいか、あるいは有意味であるであるかが判断されるべきである。ちなみに論理学において帰納法の結論の正しさの程度は、「強い」「弱い」と表現される。
帰納法で留意すべきなのは、観察する事象の数や性質(人で言えば年齢や性別など)に偏りがないかということと、一般化の仕方が妥当かどうかという点だ。例えば「サバとサンマは魚類である。よって「サ」が名前の最初につく動物はすべて魚類である。」といった推論は観察事象の共通事項が一般化されているが妥当な推論ではない。
演繹と帰納の関係
演繹法のほうが帰納法よりも誤った推論をするといったことは少なそうである。そのため思考の方法論として演繹法のみに頼ればよいのではないかと思う者もいるかもしれない。
しかし残念ながら、演繹法のみで推論を行うことはできないのである。なぜならば演繹という方法において大前提として設定される命題は、帰納によって獲得したものだからだ。論理学や数学の公理を除き、大前提として用いられるすべての自然科学や社会科学の定理や法則は、現実の事象から結論を抽出することによって得てきた(観察と実験によって得られた)ものなのである。
形式的には明快に結論を導ける演繹法であっても、帰納法によって導いた大前提を用いざるを得ない──このことは、演繹も帰納と同じだけの不確実性にさらされてることを意味するだろう。
※演繹、帰納といった推論形式については赤川元昭『仮説構築の論理』白桃書房、2021年も参考になる。
2. 3 正しさの根拠
二つの正しさ
ここまで「正しさ」という言葉を何度も用いてきてきたが、ここで改めて「正しさ」という言葉について詳しく見ていきたい。
結論から言えば、正しさには「論理的正しさ」と「客観的正しさ」の2種類がある。「論理的正しさ」は先に見た演繹法や帰納法のような「形式的正しさ」である。この正しさは論理学の用語としては「妥当(vaild)」と呼ばれる。
一方、「客観的正しさ」は論理学においては「真(truth)」と呼ばれ、万人が認めうる正しさ、現実や事実に合致した正しさである。
形式的に正しい、つまり妥当な論理展開であったとしても、真ではない、すなわち客観的に正しくないということはありうる。
例えば、「テングダケは毒キノコである。」を既呈命題、「毒キノコは食べられない。」が大前提だとすると、「テングダケは食べられない。」というのが演繹法によって導き出される結論である。しかし実はテングダケは毒抜きをすれば実際に食べることができるので「テングダケは食べられない。」という命題は偽である。
ファクトとロジック
客観的に正しい結論(メッセージ)を得るためにロジックが必要だが、それだけではないということも述べた。ではロジック以外にどのような要素が必要なのか。それは「ファクト」である。
妥当な論理展開、すなわちロジックと、そのロジックを適用する対象の思考材料/情報が現実的事実に合致していること、すなわちファクトであることの二つの材料が両方揃うことで、客観的に正しい結論を得ることができる。今まで正しい論理展開の方法論を見てきたわけであるが、その前提としてその論理展開で用いられるすべての命題が”真”でなければならならなかったということである。
本章「論理」の内容を簡潔にまとめると、「命題がファクト」かつ「命題構造がロジカル」で「ロジック自体が妥当」であることが、結論が客観的に正しいものであるための条件だということだ。
最後にもう一つ重要な大命題を付け加えるとするならば、「現実的に正しいことだけが正しい」ということだ。結論が現実の事実にそぐわなければその結論を導くプロセスにおけるファクトの認識かロジックの展開のいずれかに必ず間違いがあると言うことができる。
3. 分析とは何か?
ここまで、正しい結論を獲得するための方法論である「論理的思考」の概要を解説した。以下では、「論理的思考」を活用して正しい結論を得るための「分析」について説明する。そして最後に、人間の精神活動が論理的思考に与える影響についても言及する。
3.1 分析の定義とその特徴
分析の定義
分析も思考と同様に「事象を分けることによって理解に至る」というプロセスである。では、思考と分析は何が違うのか。それは思考が考えることの原理的概念を示すものであるのに対して、分析が「作業」や「実践」という意味合いが強いということだ。思考が思考者の頭の中で完結しうる行為なのに対し、分析は頭の外側の情報やデータ、グラフの活用といった範囲を扱う行為である。
最も基礎的に定義すれば、分析とは「要素に分けること」である。そして実際の行為としては「収集した情報を要素に分ける作業を通して、目的に合致した意味合い(メッセージ)を得ること」と理解してよい。このように分析概念を定義すると、分析は「要素に分ける」という特徴以外に、①目的の存在、②情報収集の必要性、③意味合い(メッセージ)がアウトプットという3つの要件を有すると言える。
つまり、実際の分析作業においては「要素に分ける」という分析の本質的作業の前に、まず何を分かるために分析するのかという「分析目的」が存在し、またその次に、要素に分ける対象となる分析対象に関する「情報」が収集されなければならない。さらに、分析によって”要素に分け尽くす”だけでは分析目的が達成されたことにはならず、”分けて分かった”ことの中から分析目的を満たす「意味合い(メッセージ)」を得ることができてはじめて、分析の成果が得られたことになるのだ。
「分析」は本質かつ狭義の意味では「要素に分けること(分析対象の構造化)」であるが、実践的な視点で広義の意味を表すとすると、「情報収集から意味合い(メッセージ)の抽出まで」という一連の作業を指すことになる。ぜひ両方の意味を押さえておこう。
構造化
構造化は、分析の最も重要なプロセスである。そもそも構造化とは、ある事象の「構成要素」とそれら構成要素群の「位相(つながり方/位置関係)」を明らかにすることであった。では、分析作業を通して事象を構造化することにはどのような意味があるのだろうか。それは、分析作業の構造化ができていれば、事象の特定やその因果関係に立脚した施策の立案を容易に行えるようになるということである。分析対象を構造化して理解することは、対象の重要な構成要素を把握することであり、したがって目標達成のためにどの要素に手を加えればインパクトが大きくなるかを明確にすることができると言える。
実践的分析の要件
ここでは、分析の三要件について少し掘り下げておきたい。
まず「分析の目的」についてだ。我々が「何か分析する」という状況は、「単に事象を分けて分かりたい」という以上に、分析を通して「発生している事象の原因を突き止めたい」、「直面している状況を改善するための手段を見つけたい」といった背景や経緯がはずである。したがって分析の具体的作業──どのように情報を収集するのか、どのような分析手法を採用するのか、何を発見し成果とするのか──は、分析の目的によってすべて決められなければならない。
次に「情報収集」についてだが、これはそもそも分析しようとする対象に関する情報が不足していれば分析作業自体成り立たないため、分析の具体的作業としては情報収集からスタートするということが要点となる。正しさの根拠となる「ファクト」を形成するのが情報収集だ。
最後に「意味合い(メッセージ)がアウトプット」とは、分析のアウトプットが目的に対して有効な意味内容を持った結論(メッセージ)を得ることでなければならないということである。「探していた原因は”これ”だ」、「打つべき施策は”あれ”だ」といったような結論を出すことである。
このようなアウトプットが得られなければ、分析作業は無価値だ。
3. 2 分析作業
本ドキュメントで解説してきた「思考」や「論理」の解説での具体例と比べると、実際の分析テーマや分析事象では構成要素間の関係性は桁違いに複雑で難易度が高い。したがって、以下では優れたアウトプットを得るために求められる基本作業及びその留意点を紹介したい。実際の分析作業は基本的に、分析プロセスの設計、情報収集、情報分析(分析対象の構造化)、意味合いの抽出という4つのステップで行われ、そのそれぞれに勘所とでも言うべき重要事項がある。
分析プロセスの設計
現実の分析は、分析目的が外生的に与えられた後、分析プロセスを設計するところから始まる。例えば「もっとWeb広告の費用対効果を高めてほしい」という上司からの要望に対して、「Web広告を出稿している媒体の中で最も収益性の優れている媒体を探るために、まずは各媒体ごとの広告費用と成約数(CV数)を取得しよう」といった作業内容を実際に作業に入る前に設計するのだ。
設計要件
実践的分析作業のプロセスの設計を行うにあたって、考慮しなければならない事項は3つある。
①分析作業に課せられた制約条件
②具体的作業として何を行うのかについての作業計画
③分析作業を通じてどのような思考成果が得られるのかというアウトプットイメージ
まず①制約条件であるが、これは大きく内在的な条件(時間、手間、費用)といった作業者自身にある程度の裁量がある条件と、外在的な条件(目的、期限)といった分析者本人だけでは自由に決定できない条件がある。条件として微妙な立ち位置を占めるのが作業者の「分析スキル」である。これは作業者を別に任命できる立場にあれば可変的なファクターとなるが分析者当人にとっては限界がある。(筆者注:波頭の記述にはないが、分析者が背伸びをすれば対処できるのであれば、分析者本人に任せる、あるいは分析者自身が手を挙げて作業に取り組む許可を得るといったアクションをとることで分析者のスキルを向上させるきっかけを創出することは可能である。)
次に②作業計画であるが、これは具体的には外生的に与えられた目的と期限は原則的に変更不可の大前提としてみなし、時間と手間と費用の按分を考慮して以下を決定することを指す。
収集すべき情報と収集の方法
情報の分析/処理の方法
各作業に対する担当者と所要時間及び投入費用
この作業計画が分析作業の効率と分析成果の価値を決定づける。
最後に分析プロセスの設計の要となる「アウトプットイメージ」であるが、これは課せられた制約条件と計画した作業によって、どのような分析成果まで辿り着けるのかという具体的イメージである。
例えば新規事業の情報収集のための分析ということであっても、最も有力な事業にまで絞り込み収支計画やアクションプランまで揃えた事業計画書を提出するのか、事業の魅力度を評価しただけの候補事象リストを作成するのか、といったように望ましいアウトプットは変わってくるだろう。
実際のビジネスの現場では、なんとなく分析テーマを意識しながら、とにかく関連していそうな情報をデータをただ集めているというやり方が採られていることが多いのが実情である。このような事態を避けるために、情報収集作業に飛びつく前に5つの制約条件を確認し、具体的アウトプットを想定した上で、収集すべき情報、情報処理の仕方、担当者とコスト按分の3つの計画事項のフォーマットを埋める習慣をつけるとよい。
ウエイト付け
報告(レポーティング)や提案(プロポーザル)のためにどれくらいの時間や手間を投下すべきかを悩んだことのある人は多いのではないだろうか。分析プロセスの設計において、情報収集と情報分析にそれぞれどの程度時間と手間をかけるべきかは重要なポイントである。
あえて大胆に割合を示すならば、情報収集と情報分析の割合は5:5程度にすることが理想である。しかし現実には、情報収集に7-8割の期間が割かれることが多い。
今まで情報収集に作業時間を割いていた人が情報分析に時間を投入できれば、それだけ価値ある結論(メッセージ)を導きやすくなるはずだ。
情報の価値
情報とノイズ
そもそも「情報」とは何か。波頭によると、情報とは「不確実性を減ずるもの」「当為者の目的に対して不確実性を減ずる意味内容」のことだ。一方で何らかの意味内容を持つものであってもそれが当為者にとって不確実性を減ずることに寄与しないものは「ノイズ」と言える。
ある目的が存在して、その目的に合致した意味合い(メッセージ)を得ようとして行う実践的分析においては、ここで説明した情報とノイズの観点を持って情報収集を行うことが極めて重要である。いくら精力的に多くのデータやインタービュー結果を集めても、それがノイズであっては何の役にも立たないのである。
当然、ノイズをいくら分析しても、そこからは分析目的を満たすメッセージは生まれてはこない。またノイズは価値を生まないだけでなく、集計や分類といった処理コストの増大を招くという意味で弊害が大きいことにも留意しておかなければならない。(174-175頁。)
情報収集作業に際して作業者は「情報」を集めることと同等以上に、「ノイズ」を集めないことにも注意する必要がある。
効用逓減
ノイズでな情報も、集めれば集めるほどよいというわけではない。分析対象の情報収集においては、追加的一情報あたりの不確実性低減への貢献度は逓減するという性質があるためだ。一定水準以上の情報がある状態では情報を追加しても不確実性を低減の効用は小さいし、一方で処理コストは逓増してしまう。
よって理想的な情報収集とはノイズを排除し、分析目的に対して寄与度の高い情報だけを必要最小限に集めることである。目的を満たす情報だけを収集するということは現実的には困難だが、このやり方を心がけておくだけでも実際の情報収集手法とその成果は大きく異なってくるはずだ。
グラフ化の効用と原則
収集した情報やデータから、例えば因果関係の存在や事象固有の際立った属性といった有意な意味合いを的確に抽出するための手立てとして有用なのが、データの「グラフ化」である。数字の羅列を見るよりも、グラフから何らかの意味や傾向を読み取るほうがずっと簡単なのだ。
グラフ化の最も重要な原則は、二次元でグラフを描くことである。二次元でデータを視覚化することで、データの持つ傾向性や注目すべき変化点を読み取りやすくなる。二次元でのデータの可視化は具体的には、棒グラフ、線グラフ(折れ線グラフ)、点グラフで表される。
意味の発見
データから読み取るべき有意味な内容とは何か。それはデータの「規則性」か「変化」である。
「規則性」は「ある定まったパターン」ということだが、そのパターンはさらに”増加傾向”や”減少傾向”といった「時間的な変化の規則性」か、”自動車事故の確率は車のスピードが増すにつれて高くなる”といった「関係(相関)の規則性」の2種類に分かれる。この規則性を読み取る価値は、不確実な現実の中で事象の未来を予測することができるという点にある。
対してグラフから読み取るべき「変化」とは、グラフの中で突出している値、すなわち「突出値」と、傾向や相関が変化するポイントである「変曲点」である。データに存在する突出値や変曲点はデータの規則性を破るものであるため、仮にその理由や背景を特定できれば規則性を変えうる手立てを得やすくなる。
合理的分析の手法
これまで実践的分析を行うための具体的な分析作業を解説してきたが、本節ではよい分析作業を行うための手法である「イシューアナリシス」を紹介する。
イシューアナリシスとは何か?
そもそも「イシュー」とは、実践的分析という文脈では「結論を左右する重要な課題事項」という意味の語だ。では「イシューアナリシス」とは何かというと、分析プロセスの早期段階において「まずイシューを設定し、そのイシューに対して集中的な分析作業を施すことによって合目的的な結論を効率的に得ようとする手法」のことを指す。イシューアナリシスは、分析目的がそもそも何かということから結論を左右する「イシュー」を見極め、そのイシューに対して情報収集や分析を行うことで目的を満たす結論を効率的に得ようとする意図がある。
イシューアナリシスの流れと留意点
イシューアナリシスは以下のような3段階で行われる。
①イシューの設定:課題事項をモレなくダブりなく整理し、イシューを特定する
②イシューツリーの作成:イシューを複数のサブイシューに分解しイシューを構造化する
③仮説の検証:設定したイシューに対しYes/Noの結論を出す
このようなイシューアナリシスの流れゆえに、イシューアナリシスには注意しなければならない特徴がある。それは、対象を分析する以前に結論を左右し得る重要事項をいわば”決め打ち”しているという点である。つまり、イシューアナリシスという分析手法は仮説に依拠して分析を進めるという基本的性質を持つのだ。
仮説ドリブンの分析を行うのであるから、正しい結論を得るためには仮説の設定以外の作業においては徹底的に客観的かつロジカルなスタンスを堅持しなければならない。これは、大胆な仮説設定によって一挙に効率性を挙げるイシューアナリシスの行為自体に恣意性と不確実性が介在せざるを得ないという理由による。
※『問題解決プロフェッショナル』や『仮説思考』を参照せよ。
論理と心理
ここまで、論理的思考の実践作業としての分析について有用なテクニックや効率的な手法なども紹介しつつ解説してきた。
人間は理性の力によって現象を合理的に理解する一方で、感情(情動)によって何か物事を判断したり行動を決定したりすることもまた確かな事実である。人間の判断や行動に対して影響を与える要素としての、心のメカニズムである「心理」について、本ドキュメントの最後に解説したい。
心理的バイアス
思考とは、思考者が持つ知識や経験と収集された情報を突き合わせ比べ、事象を識別したり事象の関係性を把握したりするという情報の加工行為であった。したがって、論理的思考であっても思考者の知識や経験をもとに推論する以上、思考は思考者の「心理的バイアス」、「先入観」、「思い込み」といったものから逃れることはできない。
これは原理的な問題である。というのも、公理の中だけで論理展開が成立する数学や記号論理学といった形式論理の世界以外の領域以外では、不確実な情報をもとに様々な仮定と推論を重ね、”真偽”ではなく”確からしさ”に依拠して実践的分析を行うことなるからである。
一般化命題に依拠して判断することを禁じてしまうと、定説も法則も原理も理論も何一つ使えなくなってしまう。極論すると、公理と記号による演繹法だけで営まれる形式論理の世界でしか正しい思考は存在し得ないということになり、現実事象を扱う思考も分析も成立し得ないということになってしまうのである。
原理的に誤りもありうる実践的分析をサポートするのが、本ドキュメントにおいてこれまで解説してきた論理的思考の技術と分析の手法、そして客観的正しさの根拠たる「ファクト」と「ロジック」である。
執着心(inquisitive mind)
先入観や思い込みといった論理的思考に対する弊害があったとしてもそれ以上に、人間が心理的側面を持っていることには有益な側面がある。それは具体的には、人間が「なぜそうなっているのか?(Why so?)」という問いかけを何度も何度も繰り返し行うような「執着心(inquisitive mind)」を持っているということである。
そもそも必要十分な情報収集も、緻密で正確な論理構築も、執着心がなければ到底行い切れるものではないだろう。どこまで「Why so?」を繰り返すべきかというと、それは分析者本人が納得できるまでだ。そのため実際の分析作業の成果の鍵を握っているのは「執着心」という極めて精神的、心理的な要素なのだ。
科学とは理性と論理の所産であると述べたが、森羅万象の因果を解明し、科学を発達させてきた原動力は、「どうなっているのか知りたい。」、「なぜこうなっているのか知りたい。」、「どうしても知りたい。」という人間の情熱と執着心なのである。
このことは、論理的思考にも、またその実践である分析にも全く同様に当てはまる。論理や分析の技法は正しい答えを得るための極めて有用な道具であるが、その道具を使う人間の心理的エネルギーである執着心こそが、われわれを正しい答えに導いてくれるのである。
まとめ:「論理」とは、人類がずっと求めてきた貴重な技術である
人類は言葉を手にしてからずっと、正しく物事を分かるための技術を欲しがってきたし、その技術を習得することの困難に直面してきた。正しいことを解ろうとするための論理的思考の技術とは、時代を超えて人々が強く追い求めてきたものであり、また一朝一夕で作り上げられるようなものではなかった貴重な技術である。
にもかかわらず、現代を生きる我々は基本的な論理的思考の技術ですらも充分に習得し使いこなせているとは言い難い。そのような課題のもと本ドキュメントでは、論理的思考の原理的な理解と実践的手法やテクニックについて、つまり論理的思考の”地力”をつける話と”技”を磨く話を解説してきた。本ドキュメントの読者には、理論と技術をもとにぜひ手を使って、体を使って、頭を使って技術を使いこなせるようになってほしい。論理的思考を習得することで、日々の作業時間の短縮や事象の構造把握の質向上に必ず繋がるはずだ。多少オーバーな表現をするならば、きっと”見える景色が違ってくる”はずだ。
使用文献
波頭亮『思考・論理・分析─「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践─』産能大出版部、2004年
参考文献
論理学・哲学
戸田山和久『論理学をつくる』名古屋大学出版会、2000年
↑論理学を0からがっつりやりたい人におすすめ。解説が丁寧かつフランクなので数学に苦手意識がある人も楽しく取り組める。
植原亮『思考力改善ドリル: 批判的思考から科学的思考へ』勁草書房、2020年
倉田剛『論証の教室〔入門編〕ーインフォーマル・ロジックへの誘い』 新曜社、2022年
↑2冊とも最近出た本で、日本語のような自然言語でのロジカルさを向上させることができるような内容
ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』野矢茂樹訳、岩波新書、2003年
古田徹也『はじめてのウィトゲンシュタイン』NHKブックス、2020年
古田徹也『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』角川選書、2019年
↑論理について突き詰めて考えて考えるとはどういうことか?ということについてのひとつの回答。読み進めるために古田の本を参考にするとよいだろう。
ビジネス
安宅和人『イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」』英治出版、2010年
照屋華子、 岡田恵子『ロジカル・シンキング』東洋経済新報社、2001年
山崎康司『入門 考える技術・書く技術――日本人のロジカルシンキング実践法』ダイヤモンド社、2011年
大石哲之『コンサル一年目が学ぶこと』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年
上記の5冊は定番のロジカルシンキングのための本であり、すべてのビジネスパーソンにオススメできる。ただ内容がやや抽象的であり、何回も繰り返し読むことが推奨される。
最後までお読みいただきありがとうございました!
記事をお読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは、YouTubeの活動費や書籍の購入代として使わせていただきます。
