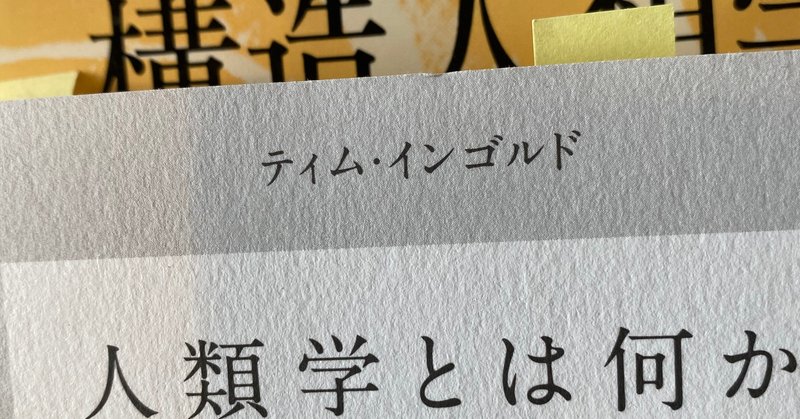
不思議さに驚嘆すること―文化人類学がおもしろい(3)
先日のnoteで人類学における「関係論的存在論」ということを書いた。
関係論的な存在論とはなにかというと、存在ということを「外部と無関係にそれ自体として予め決まった本質によって在るもの」とは考えないで、代わりに存在ということを、他との関係、外との関係を通じて現れるものと考える、そういう存在についての論である。
ここで他との関係、外との関係というのは、「外部と無関係にそれ自体として予め決まった本質によって在る」ような存在同士が、後から衝突したり結合したりするという「関係」ではない。関係という言葉を使うと、どうしても「何か」と「何か」の関係という具合に考えたくなるのだが、このふたつの「何か」を関係に先行してあるものだと考てはいけない。これが関係論的な存在論の考え方である。
関係論的な存在論の<関係>は、存在に先行する。<関係>は存在を、関係の項として生み出すプロセスである。
注意したいのは、この<関係>は「プロセス」つまり動きであって、もの=存在ではないということだ。関係を存在の一種として考えてしまうと関係論ではなくなる。関係自体を「外部と無関係にそれ自体として予め決まった本質によって在る」存在と考えてしまうと、これは関係論的な存在論ではなくなる。
このあたりの話はこちらのnoteに書いているので、よろしければご参考いただきたい。
区別し関係付ける動きの無理由性
さて、存在が関係だとして、その関係というのが「動き」だとして、ここからが問題である。
この動きは、予め計画され設計され、決まったと通りに動くものではない。
項と項を互いに他と区別しつつその関係を関係づける”動き”としての<関係>は、予め確定することが不可能な動きをする。
ややこしいのは、予め確定することが不可能といっても、まったくのランダムというわけでもないことだ。
予め確定することは出来ないけれども、ある動き方を反復する場合があり、動き方の反復から、動きのパターンとしてまるで「もの」のような輪郭を浮かび上がらせることがある。ちょうど振動が水面に描く「波紋」のようなものである。
このように、何らかの動きのパターンとして持続的に存在するものを、予め確定されたものとは考えず、偶然ににそうなったものと考える、というあたりの話。これは「思弁的実在論」哲学者であるメイヤスーの言葉を借りるなら、「無理由」ということになるのかもしれない。このあたりも非常におもしろいのでこちらの本(河野勝彦氏の『実在論の新展開』を詳しく読みたいところである。
関係論的存在論に至るまでの人類学の系譜
さて人類学は、どのような思考を経て存在を関係論的でダイナミックな事柄として考えるようになったのか。人類学者のティム・インゴルドは『人類学とは何か』において、存在論的転回に至るまでの人類学の系譜を描いてくれている。これは人類学の系譜であるが、他の学問、他の科学の営みを考える上でも考えさせられるお話なので、少したどってみよう。
ティム・インゴルドはその著書『人類学とはなにか』において、文化人類学の思考の系譜を大きく次のように整理する。
(1)「制度」の”進化”への問い
(2)制度の”働き方”への問い(→機能主義)
(3)人々が発言したり行動したりすることに、どのような「意味」があるのかを問う(→構造主義)
(4)関係論的存在論へ
(1)制度の進化を問い、その客観的証拠を探す
人類学が最初に目指したことは、近代的なものから「野生の」ものまで、様々な国家や民族や部族の社会秩序を結びつける「制度」に注目し、制度がどのように進化するのかを明らかにすることであったという。
19世紀以来、西欧列強は全地表に広がる非ヨーロッパ世界を植民地として獲得していく。その中でそのヨーロッパとは「異なる」文化や制度のもとに生きる人々を理解し、説明し、そして管理するための知識が求められた。文化人類学が学問として成立する背景にはそうした知識へのニーズがあった。
そうしたところで「未開」な部族の制度が、どのような段階を経て、西欧的な「自由」で「平等」な「最先端」の制度へと「進化」するのか??という形で問題が立てられた。これが第一段階「制度の進化への問い」である。
この問いは、未開と文明、西欧とそれ以外、低い発展段階と高い発展段階の対立と、価値の有無、優劣の対立を重ね合わせた意味のフィールドに、諸民族、諸部族、諸文化を配置するという組み立てになるという。しかしながらつまり「未開」「野生」の部族の制度からどういう系統図を描いて西欧的なものへと「進化」するかという問いに、客観的な答えを与えてくれそうな記録や証拠を得ることは極めて困難であった。
(2)制度の「働き方」を客観的に記述する
制度の進化への問いに代わって登場したのが「機能主義」である。
機能主義は「未開」のものであれ、近代的なものであれ、それぞれの制度が実際にそこに生きる人々の社会関係を結びつける様子であれば「客観的」に観察し、記録することができるはずだと考えた。
進化への問いが「なぜ」そういう制度になったかを説明しようとしたのに対して、機能主義は現にある制度が「どのように」働いているのかを記録することを目指した。現に行われていることの記録、記述を目指す機能主義は、記述の対象として「客観的」な事柄にフォーカスしようとした。
(3)制度の主観的意味を問い、それを生み出す「深層」を問題にする
機能主義の客観的記述への要求に対して、制度の「主観的」な側面、つまり現にある制度を生きる人にとっての「意味」がどうなっているのかを記述しようという動きが現れた。それが構造主義であり、その代表格がレヴィ=ストロースであるという。
主観的な意味の世界を客観的に記述するというレヴィ=ストロースの知性は驚嘆に値する。レヴィ=ストロースの構造主義は主観性を客観的に扱うという「パラダイムシフト」を人類学にもたらした。
一方で構造主義にもひとつの限界があったという。インゴルドによれば構造主義の問題点は「ひと」を飛び越えて、その奥に「深層構造」を見てしまうことにある。
インゴルドによれば構造主義者にとっての問題は、「どのように記号と象徴が意味を選び、またそれらがどのように表象するものと関わっているのかを中心に展開」する。
構造主義者にとって、社会生活とは「コミュニケーション」すなわち記号と象徴の意味のある交換のうちに動いているものである(『人類学とは何か』p.98)
ここから構造主義の人類学は人間にとっての「意味」ということを問い続けてきた言語学へと接近する。
特に、個々人の主観性に先行して、共同主観的に「意味」を成立させる記号の体系のあり方への問いを深めていた「言語学的転回」を経た言語学へと接近するのである。
言語学的転回を経た言語学は、個々人にとっての主観的な意味の経験を、人間という謎の個物の内部から立ち上る何かとしてではなく、記号の体系、煎じ詰めると、対立する二項の関係の重ね合わせ方の反復されるパターンから生成されるものと捉える。
インゴルドはこれを「人間精神の構成に普遍的に備わる生成的な見えない力を考える」アプローチであるとする。そこでは意味の源泉は人間に先行して動いている構造(二項対立の重ね合わせのパターン)である。
話す言葉の深層構造について会話が何を示しているかということだけを知るために会話を観察する言語学者のように、構造人類学者は、社会生活の与えることと受け取ることとの中に、人々が自分ではまったく気づいていない無意識の構造の外に現れた表現【のみ】を見ている。(『人類学とは何か』p.101)
(4)関係論的存在論へ
以上の進化から機能へ、機能から構造へと変化した人類学の問題設定であるが、そのいずれもが根本的に、あるひとつのパラダイムを前提として受け入れている。それは主観性と客観視の区別である。
昨今の「存在論的転回」を志向する人類学がおもしろいのは、この主観性と客観性の区別という従来大前提とされていた大区分を前提として置くことなく、それ自体、ひとつの文化的かつ自然的な人類の活動として捉える点にある。
ティム・インゴルドが書いているように、人間存在は、有機体つまり自然科学の対象である客観的ものでもあると同時に、他者との社会関係のなかで意味を生きる主観的なものでもある。どちらが「本当か」ではなくて、どちらも人間の存在である。
私たち人間は「社会生活の実践的な仕事のなかで、互いの精神と身体をつくっている」のである。
インゴルドによれば、この考え方を可能にするものこそ、「単なる社会の派生物としてではなく社会生活のなりたちそのもの」としての「関係」に焦点を当てる思考である。
人間の関係を「単なる社会の派生物」と考える思考の形というのは構造的な思考である。構造が第一に、まっさきに、まずあって、その中で人間が決まる、と。
これに対して、社会生活の実践、その成り立ちこそが、あらゆる区別が生まれ、互いに他特別される限りでの存在がはじまり、そして区別される者同士の関係が生まれる現場であると考える。そうすることで、現にどこかで生きている人間の存在を大真面目に考えるという道が開かれるのである。
区別を生じる動きを外から観察するのではなく、その動きのなかで共に動くことへ
ここまでくると「客観的」な世界なるものの存在も、誰にとっても(誰の主観にとっても)同じ単一の、予め存在するものとは考えられず、あくまでもある人々のあいだで行われる「区別する営為」のひとつということになる。
このことをインゴルドは、世界は個々の主観とは無関係にはじめからそれ自体で(主観と区別されて)存在するものではなく、世界はあくまでも「私たちが経験するもの」である、と説く。
インゴルドは続ける。
「私たちが経験する世界は私たちがその一部となっているものである」と。
世界と私(私たち)は、元々別々にあったものが後から対決するという関係にはなくて、最初から「ひとつ」なのである。それも「同じでありながら異なる」というありかたでの「ひとつ」である。
インゴルドは更に続ける。「世界は私たちの経験において一時的に存在する。」世界は、私たちとの関係においてのみ、世界として存在する。そして私たちが移ろいゆく存在であるがゆえに、世界もまた私たちとの関係において一時的に存在するようになっているものである。世界は私たちとは無関係にそれ自体として固まって永遠に存在するのではない。
このことをインゴルドは「世界は絶えず生成しつつある。私たち自身もまた、常に形成されつつある」とも表現する。
世界が先か、私たちが先か、主観が先か、客観が先か、という話ではない。世界と私たちのあいだに時間的な前後関係は無い。世界と私たちはひとつであって、どちらも動きながら生成しつつある事柄である。この動きがもし止まってしまえば、どちらも消えてしまうのである。そして「時間」さえも、この動きつづけることのひとつの現れなのである。
こうした生成しつづける世界=私たちは、とにかく「予め決まったもの」ではない。世界=私たちは変化し続ける。それも予め設定された目標も目的もないところで、ただ無理由に変化をし続ける。
この無理由に変化し続けることをうけとめ、意識しつづけることが、インゴルドのいう人類学の課題なのである。
このことをインゴルドは次のような言葉で記す。
常に生成しつつあるがゆえに、世界は不思議で、驚きの枯れざる源泉なのである。
「不思議」
そして「驚き」
不思議さに驚嘆し続けること、これこそが科学としての人類学であるという。
人類学に限らず、あらゆる科学は人間が実は何も知らないのではないか、まだ何もわかっていないのではないか、と考えるところから始まる。そしてどこまでどうわかっていて、どこから先がわからないのかを明らかにしつつ、少しつづ「わかりそうな領域」を広げていく。これが科学である。
この点で科学は、予め正解が決まっている「勉強」とはまったく違う営みなのである。
おわりに
昨今の「存在論的転回」を志向する人類学がおもしろいのは、主観と客観の区別という前提を、それ自体ひとつの「制度」ないし人類の文化的現象として問い直しつづける道を開いてくれるからである。
自然と人間の二項対立や、存在論と認識論の二項対立を前提とせずに、多様な人々、多様なアクターそれぞれにとって存在する「多様な世界が生成される物質=記号的な実践の過程」を存在論的に(認識論的にではなく)分析すること。これが関係論的存在論的へと転回した科学である人類学の問いである。
関連note
今回のnoteの前編にあたるものです。
今回のnoteの中編にあたるものです。
「科学」について
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
