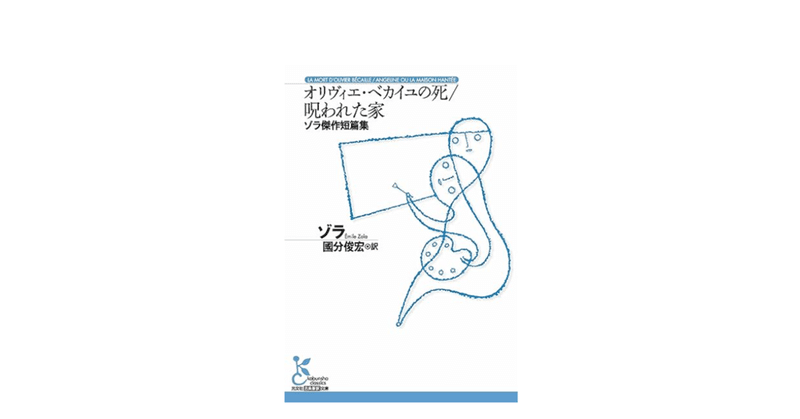
『オリヴィエ・ベカイユの死/呪われた家~ゾラ傑作短篇集』~ (光文社古典新訳文庫) 自然主義の自然は、ほんとは「自然科学」のことで、ゾラの場合特に「遺伝学」にもとづいて、生物学的に決定されちゃう人間を描くものなんだそうだ。知らなかったな。
オリヴィエ・ベカイユの死/呪われた家~ゾラ傑作短篇集~ (光文社古典新訳文庫) Kindle版
Amazon内容紹介
完全に意識はあるが肉体が動かず、周囲に死んだと思われた男の視点から綴られる「オリヴィエ・ベカイユの死」。新進気鋭の画家とその不器量な妻との奇妙な共犯関係を描いた「スルディス夫人」など、稀代のストーリーテラーとしてのゾラの才能が凝縮された5篇を収録。
本を読んだ経緯
ゾラについては「ゾラ=居酒屋=自然主義」くらいの受験用文学史知識しかなくて、全く読んだこともなかったし、興味も無かったのである。
話は大脱線するが、僕にとって「ゾラ」といえば、20年前くらいのサッカー、ロンドンの強豪チェルシーにいた背の小さいイタリア人の名手のことだし(当時はイタリアセリエAが世界一のリーグだったから、イングランドでプレーするイタリア人はゾラくらいしかいなかった)。この小説家ゾラも、お父さんはイタリア人なんだそうだ。なるほど。
「居酒屋」と言えば、1985~7年くらい、新入社員だったころ上司に連れられて行ったカラオケスナック(まだカラオケボックスとかじゃないのである)で、おっさんたちが五木ひろしと木の実ナナのデュエット曲「居酒屋」をやたら歌っていたよなあ、みたいな感じで、ある。文学と全然関係ないな。
文学に話を戻しても、「自然主義」と言えば、国文学科卒の僕にとっては田山花袋の「蒲団」とか、どれだけ情けないことをそのまま赤裸々に告白するかのトホホな私小説、日本の純文学が私小説の呪縛に囚われたその原点が自然主義、という日本近代文学のことしか思い浮かばず、いいイメージは全然無かったのである。なわけで。ゾラ、読んだことも、読む気も全然なかったのね。
なんだけどね、noteで「やどかり」さんという方が、この本の感想文を書いていたのね。
とてもきちんとした感想文で、私がこのようないい加減な文章を書くのに引用してしまって申し訳ないのであるが、中でこの本冒頭の、「オリヴィエ・ベカイユの死」っていうのが、若い男が、死んだはずなのになぜか意識があって、遺された若い奥さんに言い寄る男をどうしようでもどうもできないという「閉じ込め症候群」なのか「臨死体験」なのか、そういう話であると知ったわけ。えー、そういう話なら読んでみようかと買ってみたのでした。うん。「そろそろゾラは読んだ方がいい」と素直に思ったわけでした。
ここから僕の感想
これが、どの短編も、面白いじゃーん、ちゃんとしてるじゃーん。というのがまずシンプルな感想。ちゃんとしているというのは、短編小説というのは、ある種の企み、構成の妙、みたいなものがカチッとしていないと形をなさないと思うのだが、どれも、すごく企みのある小説でした。つまりちゃんと作り物なのである。うまく作られている。そしてそれが見事にはまっている。意外性と納得感のほどよいバランス。ゾラと言えば長編小説のイメージが強いんだそうだが(知りませんでした、すみません)、これ読むと「短編小説の名手」といわれても、そうかと納得するぞ。
「自然主義=私小説=体験の赤裸々告白」というのは、日本で、ものすごく間違って自然主義が定着しちゃったのだ、と解説にも書かれていた。そうだったのか。知らなかった。たしかにこの短編たち、日本の自然主義文学みたいじゃない。全く。
19世紀の社会・世界と自然主義
ということで、この本には、翻訳者 國分俊宏氏の非常に丁寧な解説がついていて、それを参考にしつつ、さらにもうちょっと大きな世界史的視点に立って、「自然主義って、ゾラって」ということについて、つらつら思うことを書いていくのだわ。
まずね、自然主義の「自然」って、日本人的に日本文学的に考えちゃうと無為自然の自然、「自然=そのまんま、加工なし、人工的の反対」ってなんとなくイメージしちゃうじゃん。だから「起きたことをそのまんま、加工せずに正直に告白する私小説が自然主義」ってなっちゃったんだろうな。でもね、違う。全然、違ったんだ。
自然主義の自然って自然科学のことだったんだ。もっと具体的に言うと、メンデルの「遺伝の法則」。えー。
19世紀後半というのは、イギリスのヴィクトリア朝後期の小説を読むと、進化論のことなんかが社会のいろんなところに影響が出ていたりするのだが、なるほどなあ。
Amazonでいろいろ調べてみると。
メンデルが遺伝の法則を発見、発表したのが1865年、ダーウィンが『種の起源』を発表したのが1859年。あらまダーウィンが先なんだ、意外だな。
遺伝学とか進化論が学問の世界だけでなく、社会全体を揺るがすということがイギリスやフランスでは起きていたんだな。
さらに、遺伝の法則を人間に当てはめて、ローンブロゾーというイタリアの学者が「犯罪人類学」というのを打ち立てたのも1870年代のことか。こういう遺伝要素があるこういう体質の人は、こんな風に犯罪者になりやすい、みたいなやつ。そのちょっと前、19世紀前半にブームになった「骨相学」という、頭蓋骨の形と犯罪傾向、みたいな学問があったのだけれど、それを遺伝の法則や進化論と結びつけた学問だな。人種差別や優生学にもつながっていく流れである。
そういう生物学的な当時の最新知見である「遺伝要素」が人間の思考や行動を「決定論」的に支配している、個人についても、一族、集団の性格や行動についても。解説から引用します。
『テレズ・ラカン』第二版の序文で、ゾラは「私は性格ではなく体質を探求しようとした。(中略)神経と血液に支配され、自由意志が全くなく、生涯のどの時期においても、肉体の宿命によって引きずられていく人物を選んだ」という、冷静に読めば驚くべきことを書いている。
つまり19世紀フランス、ゾラの自然主義とは、メンデルからローンブロゾーという、当時の最先端自然科学の知見による新しい生物学医学の知見に基づいて、人間や一族を生物学的、かつ決定論的に描く、そういう科学的な新しい文学を作り出そうという試みだったのだな。
解説の國分さんによると
「バルザックやフローベルという、写実主義文学の模範作家たちを読み込み、その真価を認識したということである。だが、ゾラはそれをもっと推し進めなければならないと考えた。こうして最も過激な写実主義、すなわち自然主義者ゾラが生まれたのである。(「自然主義」とはここではごく簡単に写実主義的な写実主義をもっと徹底し、自然科学的裏付けまで与えようとしたもの、と言っておこう)。(中略)かくしてゾラは『テレーズ・ラカン』において、「生理学的人間」を探求するのだと高らかに宣言し、やがて「遺伝の法則」を縦軸に、ある一族の家系を描く『ルーゴン=マッカール叢書』の計画を構想していくのである。
なんだけれど、また國分さんはこうも書く。
このゾラ流の「小説理論」を今日の目で見て批判するのはたやすい。しかし、ここで強調しておきたいことは、実際に書かれたゾラの作品を読んでみると、遺伝の法則や決定論などは、作品に対してほとんど影響を与えていないように見えるということである。ゾラの小説は、そのような「理論」とはまったく切り離して、それ自体として読むことができる。そして、そう読んだ方が、はるかに面白いのである。
あらら、ほんとにその通り。よくできた面白い小説である。なので、ここからは「理論はともかく面白かった」という方向で、感想を書いていくことにします。
寝取られ恐怖男の文学として読む。ここから盛大ネタバレあり。
はじめに書いたことと反対のことを言うようだが、日本的自然主義「赤裸々な情けない男の正直告白文学」という風に、間違ってゾラの自然主義が受け取られちゃったというのも、分からんでもないなあ、という特徴が、実は、この短編集のいくつかの作品で見られる。ここからは、そのことを書いていこうと思います。性的欲望と嫉妬とコンプレックスに翻弄される、情けない男の話、というのが多いのである。
初めの『オリヴィエ・ベカイユの死』は、若く貧しい夫婦がパリに上京直後に夫が死んじゃって、死んだのになぜか意識はあるのに、身体は動かないし、周囲の人からは明らかに死んだように思われている。で、意識があるのに埋葬されちゃう男の話なのだけれど、それ自体はこの時代、そういう小説が他にもあったんだそうだ。この小説で面白いのは、遺された若いきれいな奥さんに、親切な若くてたくましい男が、いろいろ助けてあげようと近寄ってきて、死んでいる貧弱な男がすごく嫉妬に苦しむ、妻が取られちゃうー、妻が惚れちゃうー、みたいな心配をしまくる、というのが描かれるわけ。
次の『ナンタス』では、パリに出てきた貧しいが野心だけはある若者が、食い詰めて困り果てた時に、ある不思議な提案を持ちかけられる。お金持ちの令嬢がさる妻子持ちのお金持ちと不倫をしてしまい妊娠してしまう。その、体面を保つために、彼女の形だけの結婚相手となる代わりに、経済的社会的地位を得る。彼はさらにその才覚野心で成り上がる。最後、財務大臣まで成り上がるのだが。しかし彼は、背が高く美しいその偽装結婚相手の妻に、形だけという初めの約束にも拘わらず、どうしても愛されたい、妻を愛してしまうのだな。、でも愛されないということに苦悩して、成功をすべて捨ててしまおうか自殺しようか、と苦悩する。初めの小説とは別バージョン別事情だが、「もてたい、のに、もてない」男の話なのだ。
その次の「呪われた家」だけ、ずっと後に書かれたものでそうじゃない。
次の「シャプール氏の貝」は、これまた成り上がってお金持ちになった後で中年になってからすごく若くて背が高くて魅力的な女性と結婚した男の話。なのだが、子どもができないことに悩み、「貝をたくさん食べれば子供ができる」という主治医の謎理論によって、海辺の町にひと夏を過ごしに行く。そこで若くてたくましい青年と若い妻が浮気しちゃうのだが、泳げないし不器用な男は、海で妻と若い男が浮気しているのに気づかないし、そして、予想通り、貝のおかげではなく、めでたく妻は妊娠するわけだ。とほほ。
最後の「スルディス夫人」は、これは浮気をされるわけではないのだが、才能はあるが、放蕩癖があるだらしない画家の男性と、彼を愛する、やはり絵を描く、美しくない(背が低くずんぐりしていて顔色も悪く指も短いなど、克明にその美しくなさが描写される)妻の物語。夫の方は大胆で革新的な絵を描くことで成功するのだが、妻の方はすごく器用に精緻に絵を描く技術がある。放蕩でだんだん絵が描けなくなる夫の創作を、はじめは背景など部分的に手伝っていたのが、だんだん立場が逆転し、最終的には夫はアイデアだけを出して、その絵のほとんどを実は妻が描くようになっていく、その夫婦の関係の変化を描いていく。「ダメ男」と「強い妻」の物語である。
貧弱な自分はたくましい男に美しい妻を取られてしまうのではないか。お金を稼いで偉くなったら、そういう若く美しい女性に愛されるのじゃあないか。そう思って一生懸命偉くなることお金持ちになることを追い求めても、それで妻に愛されるかというと分からない、それは保証されない。若くたくましく美しい男に、妻が取られてしまうのではないか。不安は消えない。かといって、美人ではなくても自分を愛してくれる優しく気立てが良く優しい女性と結婚しても、実はそういう女性はしたたかな側面があり、年を経るごとに、いやたしかに自分を愛してくれているのは事実でも、いつのまにか、人生の主導権を握られてしまい立場が逆転し、自分は女性の従属物のようになっている。
ねえ、これ、「遺伝学」でも「決定論」でもなくて、実にある種の人生と愛における不安とコンプレックスというようなことが、まるごとリアルに描かれているようではないか。人間観察として優れているではないか。
これはゾラ流科学的自然(科学)主義理論で書かれたにしても、日本流の「トホホな情けない男の、特に恋愛と結婚生活と性的生活における、トホホな自信のない男の告白小説」として、よく出来ているではないか。
いや、それを客観視して、実に短編小説として、シャレの利いたものに仕上げている。そこのところの小説技法とか構成の巧みさ、作り物としての腕前という意味では「日本の自然主義」とは違う感じなのだがね。
というわけで、僕には思い当たることがあまりにたくさんあって、すごく面白かったのである。
そういうわけで、長編『居酒屋』も買ったので、ゾラ、もうちょっと読んでみるのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
