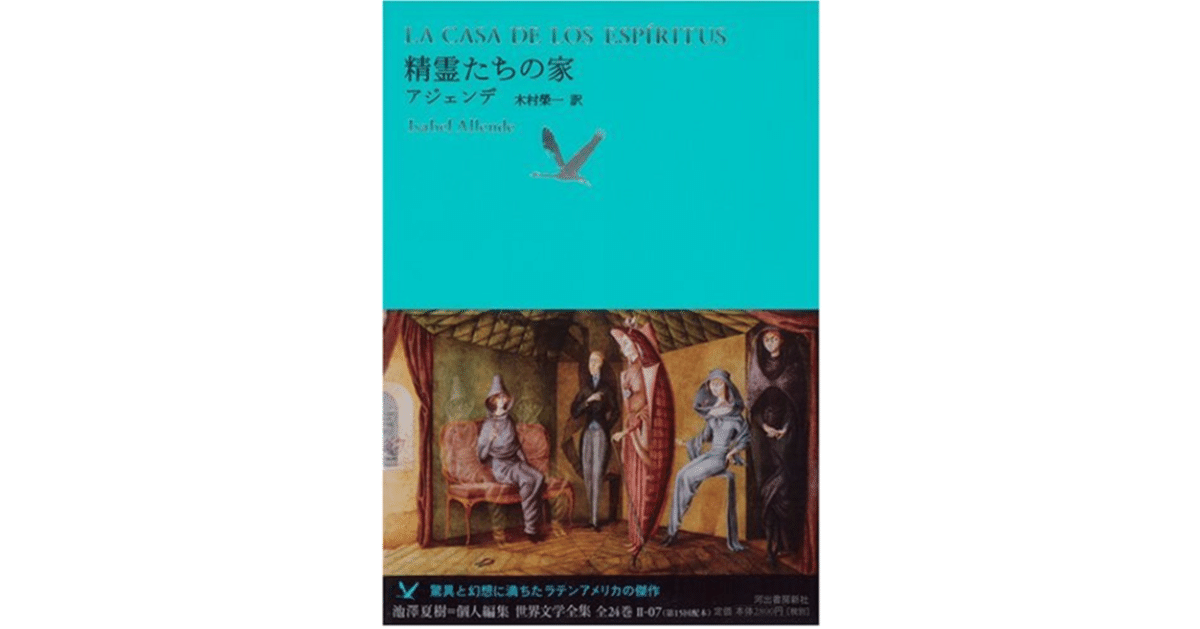
『精霊たちの家』 (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 2-7)イサベル・アジェンデ (著), 木村 榮一 (翻訳)マジック・リアリズムの傑作ということで『百年の孤独』文庫話題の今、読んでみたら、マジックな導入からチリ現代史のリアリズムに着地していく傑作でした。読後感とても清々しい。おすすめ。
『精霊たちの家』 (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 2-7)
単行本 – 2009/3/11
イサベル・アジェンデ (著), 木村 榮一 (翻訳)
Amazon内容紹介
不思議な力をもつ少女クラーラは、緑の髪をした美しい姉の死から9年間沈黙した後、姉の婚約者と結婚し、精霊たちが見守る館で暮らしはじめる――。三世代の女たちの運命を描く、驚異と幻想に満ちたラテンアメリカ文学の傑作。
作者紹介
1942年生まれ。ペルー生まれのチリ作家。ジャーナリストとして活躍中の73年、叔父のアジェンデ大統領が軍事クーデターで暗殺され、その時代に執筆した『精霊たちの家』が絶大な反響に。作品は多数ある。
ここから僕の感想
ガルシア=マルケス『百年の孤独』と比較されることが多いらしい本作、あちらの文庫化話題のときに、こっちを(8年前に買ったまま積読だったのを)ひっぱりだして読んでみた。
いやまあ、面白かったよ。予想を超えた展開、小説を読み進めると読み初めと印象がどんどんと変わっていく。
『百年の孤独』との比較だけれど、似ているかなあ、と思われるのは冒頭、しばらくの間だけ。池澤夏樹氏個人編集の世界文学全集で読んだので、池澤氏の解説が挟み込み冊子でついているのだが、この二作の比較は池澤氏が正確に書いている。この小冊子解説は素晴らしかったな。
作者紹介の通り、イザベル・アジェンデの叔父は世界初、選挙で成立した社会主義政権のサルバドール・アジェンデ大統領だが、社会主義の南米への拡大を恐れたアメリカの支援を受けたピノチェト将軍のクーデターにより、殺された。社会主義政権の成立からクーデター、その後のピノチェト政権により数万の人が殺された恐怖政治が小説後半の中心になる。『百年の孤独』も、コロンビアでアメリカ資本のバナナ会社労働者が数千人殺された事件を描いているが、池澤氏は書く。
「ガルシア=マルケスは抑制を利かせてこの虐殺を大きく扱わなかったが、イザベル・アジェンデは話の後半で虐殺を舞台の真ん中に据えた。」「ガルシア=マルケスは神話の外に出ないようにしたから、『百年の孤独』は全体として先細りである。」「それに対して『精霊たちの家』は先に行くにつれて、現代に近づくに従って、記述が耐えがたいほどに濃密になり、時間の流れが遅くなる。」
小説の冒頭は、大変に可愛らしい幻想小説のように始まる。もちろん登場人物がどんどん死んだり大騒ぎではあるのだが、1900年ころの、20世紀にはいったばかりのチリを舞台にしたまさに「マジック・リアリズム」のうちの、「マジック」のほうに重点がいった話である。ものを動かせたり、未来を読んだりできる10歳の女の子クラーラが主人公で、それをまあ普通のことと受け入れているお金持ち家族のお話が進んでいく。
しかし、この小説、その家族の女性四代にわたる話なのだが、話のはじめのほうから最後まで出てくるのは、エステバーン・トゥエルバというおよそ破天荒な男性である。女系家族の、クラーラの姉ローサは緑の髪の、この世のものとも思われぬ美女で、エステバーン・トゥエルバはその婚約者なのだが、自身は没落した家の貧しい暮らしをしていたため、金持ちローサとの結婚資金を作ろうと、山の中で金山を掘っていて、やっと掘り当てたと思ったらその長女が死んじゃう。ショックを受けて、チリ北部の荒れ地・田舎に唯一の遺産として死んだ父から譲り受けていた荒れ果てた農場を10年かけて再建し、やっと金持ちになった。そこで、急に思い立ち、死んじゃった婚約者の末の妹クラーラ(冒頭主人公として出てくるいろいろ超能力のある女の子が、19歳になっている)と結婚する。
その後、エステバーン・トゥエルバは有能だけれで横暴な農場主から保守政治家へと出世していき、家庭では横暴で暴力的な夫、父、祖父として、そして農園から社会全体に次第に広がっていく左翼活動家を憎んで弾圧し続ける男になっていくのだ。で、その家の女の子たちは、当然のようにそういう左翼活動家たちと恋に落ちたりするわけで、そういうことを家族の物語として追いかけていくのである。
というわけで、その家の女性を描くとき、ずっとお話の中心に居続ける困った男の人がエステバーン・トゥエルバなわけだが、この家族の物語が、時代が現代に向けて進むにつれて、だんだんとアジェンデ政権の成立からピノチェトのクーデター、恐怖政治という現実の歴史と合流していく、という小説なわけである。
こう書くと、この前読んだウィリアム・フォークナーの『アブサロム・アブサロム』の、貧しい家の出身で、金持ちになろうと南部の町に農園と屋敷を築く暴力的な主人公、サトペンを思い浮かべてしまうのだな。あの小説も南北戦争という歴史の現実に、神話的な暴力的男性の人生が重なっていく物語だったのだな。
そう、『百年の孤独』と『精霊たちの家』の関係というのは、『百年の孤独』の影響を受けて『精霊たちの家』が生まれたという「親子関係」ではなくて、フォークナーの「ヨクナバートファ・サーガ」、特に『アブサロム・アブサロム』の影響のもとに生まれた「兄弟姉妹関係」にあるようにも思われるのだ。
「マジック」と「リアリズム」で言うと、この小説、はるかに「リアリズム」側に重心があって、しかも小説が進むほどにリアリズム側にどんどん傾いていくのである。
この「マジック」から「リアリズム」への重心移行のちょうど境目あたりに、「大地震」というのがあるのが、チリという国、文化の個性としてあるなあ。ああ、ちょうど今日は関東大震災の9月1日だなあ。
チリは日本同様、太平洋プレート(とナスカプレート)が大陸プレートにぶつかる、環太平洋の地震多発地帯に位置するので、日本と同じくらい壊滅的な大地震が同じくらい高頻度に起きる国である。
日本では1960年のチリ地震による津波が日本にも大きな被害をもたらしたのが有名だけれど、1939年にも、チリ全土で5千人とも1万人とも言われる死者が出た大地震と大津波が起きている。
チリは第二次大戦には参戦していなかったのだが、小説の中では、エステバーン・トゥエルバは、農場のお屋敷でこの1939年の大地震で被災し、屋敷が崩れてそのがれきの下敷きになり、全身の骨が骨折する瀕死の重傷を負う。が、使用人頭の男の父親がインディオの民間療法の達人で、そのときすでに目が見えない盲目の老人になっていたのだが、「動かすと死ぬぞ」と、その場で全身の骨折箇所をすべて見事に骨接ぎ固定してくれて、九死に一生を得るというエピソードがある。
チリのそういう地震があり砂漠があり険しく貧しい山岳地帯が広がる自然条件、インディオなど原住民農民と都市のスペイン系の支配層の関係、これはカリブ海沿いのコロンビアを舞台とするガルシア・マルケスの描く小説世界とは、またずいぶんと異なる世界なのである。
イザベル・アジェンデの小説といえば、わりと最近の『日本人の恋人』を数年前に読んだが、あれも素晴らしい傑作だったな。
政治的暴力や性的暴力の、最も悲惨で凄絶なことが小説の中心にあるのだが、それでも、全体として人間について、その明るい側面を見ている印象があって、明るい可愛らしい小説を読んでいる、という時間が、読書している時間の八割くらいを占めるのだな。あちらの小説も、本作も。
登場人物たちの恋愛や結婚も、必ずしも成就しないものもあるけれど、何人かの登場人物、カップルは幸せな結末を迎える。
この世界も、人生も、すごく悲惨なもの、どうしようもない暴力性を抱えている。だから、それへの巻き込まれ方では、悲惨な人生を終える人も多数いる。でも、その中でも、明るく楽しい、幸せな時間や体験も人間はする。できる。
そういう世界のありよう、人生のありよう全体を、たくさんの登場人物、たくさんの事件エピソードを重ねて、一つの大きな小説世界を織り上げていく。
この『精霊たちの家』も、そして最近作『日本人の恋人』も、そういう小説でした。
読後感というか、そうじゃないな読書している時間体験の「読書中体験感」が、なんというか、素敵なのである。だから割と、多くの人にお勧めできる小説なのでした。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
