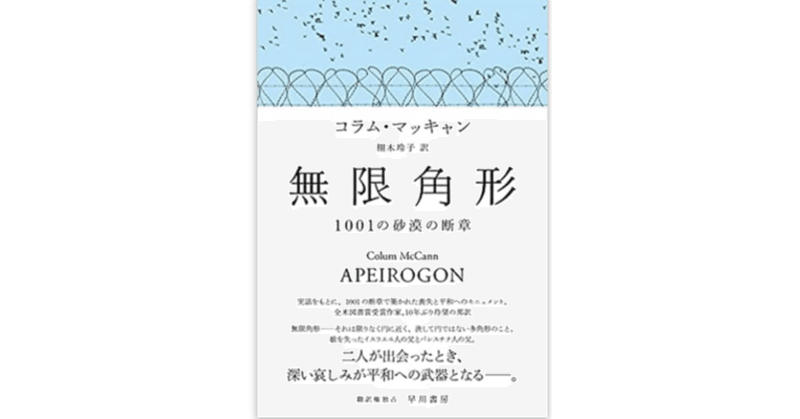
『無限角形 1001の砂漠の断章』コラム・マッキャン (著), 栩木 玲子 (訳) 戦争について考える8月の課題図書、に勝手に選んで挑戦しました。そして考えたこと。
『無限角形 1001の砂漠の断章』 単行本 – 2023/5/1
コラム・マッキャン (著), 栩木 玲子 (翻訳)
Amazon内容紹介
「全米図書賞受賞作家コラム・マッキャン、『ゾリ』、『世界を回せ』に続く待望の邦訳!
無限角形……それは限りなく円に近く、決して円ではない多角形のこと。
バッサム・アラミンはパレスチナ人。ラミ・エルハナンはイスラエル人。
二人の住む世界は紛争に満ち、車の通行が許される道路、娘たちが通う学校、そして検問所まで、日常生活のあらゆる場面で、物理的にも精神的にも生きるための交渉が必要となる。
バッサムの10歳の娘アビールがゴム弾で命を落とし、ラミの13歳の娘スマダーが自爆テロの犠牲となったことで、彼らの世界は取り返しのつかないほど変化する。
互いの境遇を知ったバッサムとラミは、自分たちをつなぐ喪失感を認識し、いつしかその悲しみを平和のための武器にしていく。
紀元前から現代まで、エルサレムを中心とした世界の神話、政治、文学、音楽など1001の断片を編み込んだ、家族と友情、愛と喪失にまつわる、私たちについての物語。」
ここから僕の感想
戦争を考えるこの時期に、今年はこの本と格闘していたのでした。
中東戦争に何度か従軍したものの、その後は広告グラフィックデザイナーとして政治に距離を置いて生きてきたイスラエル人のラミは、13歳の娘スマダーをパレスチナ人による自爆テロで亡くす。これが1997年。
その10年後の2007年、パレスチナ人のバッサムは10歳の娘アビールのことを、イスラエル兵の打ったゴム弾が後頭部を直撃、亡くす。バッサムはそもそも貧しい生まれで、生まれた家をイスラエル入植のために追い出され、その後投石、手りゅう弾を投げた罪状で17歳から24歳までを獄中で過ごす。しかし獄中でヘブライ語を学び、ほとんどのイスラエル看守たちからはひどい虐待を受けたが、バッサムのヘブライ語学びを手助けしてくれる看守の1人と出会い、出獄後、イスラエルとパレスチナをつなぐ「平和の戦士」と言う活動をしていた。
スマダーは繁華街に新学期の準備の買い物に行って自爆テロに巻き込まれ、アビールは学校の向かいの駄菓子屋にキャンディーを買いに行ったところを撃たれた。二人とも全く何の落ち度もないのに殺されてしまった。
2人の父親は、イスラエルとパレスチナの争いで子供を亡くした「親の会」で、ともに自らの体験を語り、二人の語る場所は国内だけでなく、海外にも広がっていく、バッサムはパレスチナ人でありながらホロコーストを理解したいと英国の大学に留学をしたりもする。
という重たい話なのである。どう考えても、生真面目に語るしかない話なのである。
で、僕は生真面目に語らざるを得ないような重たい戦争についての小説というのは、正直、苦手なのである。
この作者のコラム・マッキャンさんも、生真面目に重たく語らざるを得ない、何と言っても実在の人物の実際の事件とその後の活動の話なんで、それをどうやって小説にしようかということで、ものすごく工夫をしている。
たとえば、なんとなくイスラエルのエルサレムとパレスチナのヨルダン川西岸地区のあたりというのは、日本人のイメージだと全部「砂漠と荒野」みたいなイメージだと思うのだが、実はエルサレムとヨルダン川の間には、この小説の主たる舞台となるベイトジャラ地区という山と言うか森というか、そういう場所があって、そこにあるホテルや修道院で、親の会の会議とか講演会は行われる。そこはまた、欧州からアフリカの間を渡る鳥たちの通り道になっていて、世界でいちばんたくさんの種類の鳥たちの渡りの中継地点になっている山なんだそうだ。
で、そこを渡るいろんな鳥たちと、この地域の古代から現代までの、様々な歴史的なエピソードが、短い断章で語られる。話の本筋とは違う素敵な断章と、二人の娘の事件の経緯、二人の父親とその家族の生い立ち、そして二人が世界のいろいろなところで粘り強く語り続ける活動、二人の交流が、断章の間をゆるい連想ゲームのようにつなぎながら、行ったり来たりする。
鳥の話だけじゃなく、この地区の歴史の中での音楽の話、亡くなったスマダーが好きだったシンニード・オコナー(この前亡くなった女性歌手)が歌っていたプリンスの曲の話、とか、本当に幅広いテーマの挿話断章であっちにいったりこっちに行ったりしながら小説は進む。
イスラエルとパレスチナのこの地域の古代から現代までの歴史、現在の分断と抑圧の生々しい状況を示すエピソード、そして人間の営みを超えた自然の目で、鳥の目で見ればどういう自然条件の土地なのかも、読み進んでいくうちに、なんとなくいろいろなことが漠然とだけれど見えてくる。
そんな風にこの小説は書かれているのである。
なので、「ひたすら真面目で重苦しい」かというと、自然や芸術や古代の歴史なんかの美しさ不思議さに心が持っていかれる。
それらもまたとても上手に、この主人公たちのおかれている問題へと紐づいて戻ってくるのである。
ということで、まずはこの小説自体についての感想としては、読むのにひどく苦労したのは事実なのだが、読み終えた今は、「読んで良かった」と思える。
とはいえ本編650ページくらいあるので、誰にでもおすすめかというと、読書体力ある人にはおすすめ、と書いておこう。
脱線論考
でここから、感想と言うより、この本を読みながら、この時期、戦争について考えたことと言う、「この本に触発されつつ、ウクライナの戦争と、日本の戦争について考えたこと」という脱線論考に進みます。
この本は世界でおおむね高評価だったようなのだが、訳者あとがきによると
一方で、普遍性を持ちながら極めて政治的な読み方が可能なために一部では論争が生じ、とりわけパレスチナ作家スーザン・アブルハワが『アルジャジーラ』紙に寄せた書評「アペイロゴンー植民地支配主義による商業出版の過ちふたたび」は、彼女が多くの尊敬と信頼を集める作家だけにかなりの衝撃をもって受け止められた。
ということがあったのだそうだ。
その書評そのものは読めていないのだけれど、僕が考えても、イスラエルとパレスチナにおいては、非対称性というか、パレスチナ人の立場になれば、一方的に大国イギリスやアメリカの支援でユダヤ人が勝手に国を作ったためにパレスチナ人は代々住んでいた土地を追い出され、そして今もイスラエルの入植地が広がり、パレスチナ人は壁に囲われた地域に押し込まれ貧しい生活と、移動や様々な自由を奪われて生活している。
そのパレスチナ人の娘がイスラエル兵に打たれて亡くなったことと、パレスチナ人の必死の抵抗の自爆テロでイスラエル人の娘が亡くなったことが「同じように娘を失った体験を共有し、それに対する抵抗の戦いを語りとして、ラミとバッサムが手を取り合って行うという美談」小説にまとめてしまっていいのか、という批判は、これはパレスチナ側からは出るよなあ、と思うわけである。
これは戦争とか紛争において、「どっち側の犠牲者も、その家族も悲しみを同じ様に共有できる」という語りが妥当なのか。という問題だと思うのである。
戦争紛争には、「明らかに仕掛けた、侵略した悪い方と、侵略された被害者の国があるのではないか」という、指導者とか「国」という単位で見た時の、加害者被害者がある。
どっちがすごく悪くてどっちが悪くないとか、力関係がどっちかが圧倒的に強くてどっちかが明らかに小さくて弱い、みたいな関係がある。
あるのに、「娘を殺された父」という共通点で、この本の人物の場合、お互いを「憎しみあい復讐しあう」というふうに考えずに、そう思う心を乗り越えて、「どちらも娘をなくせば全人生を失ったようになる人間同士だ」と気づくことで、連帯して活動をしている。
しかし、「善悪強弱」みたいなことは国同士、国と地域、みたいな対立にはあるだろう。そのことが個人の美談の中で覆い隠されていないか、という批判は、それはそれで分かるのである。
終戦の時期に、毎年戦争関連のNHKスペシャルについて感想を書いてきたのだが、僕の基本問題意識は「被害者としての体験視点で語る番組と、加害者としての日本日本軍を批判的に語る視点」のバランスが取れているか、という点にずっとあった。
これはもっと根本的には、加藤典洋の『敗戦後論』における、アジアはじめ2000万人の犠牲者(日本人が加害者である)と、日本人(これは軍人も民間人も含めた350万とも500万ともいわれる)犠牲者、そのどちらももちろん追悼すべきだが、その順序において「まず日本人」と書いたことで大論争と言うか、左右両方から大批判を受けた事件にまで、僕の問題意識は遡るのである。
そして、今年は、ウクライナ戦争の「ロシアとウクライナ」の善悪強弱問題と言うのがこれに重なる。
ロシアの今回戦争を起こした理屈「大ロシア主義」と言うのは、大東亜戦争で大日本帝国が唱えた「大東亜協栄圏」という理屈と、実際には国防線をどこに引くかと言うその設定、ロシアの言う「NATO東方拡大」というのと似ているし、NATOがロシアを締め付ける感じというのは、欧米列強がabcd包囲網で日本を締め上げたのに似ている。
「ロシアにも理屈はある」というのが「大日本帝国にも理屈がある」「やむなく起こした戦争だ」「いやむしろけしかけられたのだ」みたいなのも似ているし。
そして満州あたりで何度も偽旗作戦をやって、中国のせいにして開戦した日中戦争、宣戦布告が事務手続きで間に合わないうちに奇襲しちゃった真珠湾攻撃、みたいに「国際法上、明らかにやっちゃあいかんやり方で開戦しちゃった日本」と言う意味で、先の大戦は「戦争の始め方は一方的に日本が悪い」。そのことと「戦争の始め方は国際法上、ロシアが100%悪い」というのとすごく似ているのである。
で、こういう立場状況で、日本兵がこんな苦しみを味わいました。日本国民がこんな苦しみを味わいました、という「被害者としての戦争体験」ばかり語っていいのか、日本は先の大戦においては加害性をまず見つめないとダメなんじゃないか、という立場はあるわけだ。
たとえば神風特攻隊や回天、桜花のような自爆型特攻攻撃、兵器についても、日本人は「悲劇」としてこの時期、回顧するわけだけれど、戦争当時、アメリカから見ると、今の「イスラム自爆テロ」に今の日本人も感じるだろう「狂信的で非合理的な行為への恐怖」を感じていたのは間違いない。日本人のことを「狂信的で理解不能な国民、だから、何をするか分からないから、徹底的に叩かないと本土上陸したとき大変な抵抗にあう」という恐怖心をあおり、原爆投下を正当化する論理がアメリカ側に形成され、今もそれを妥当と考えるアメリカ人が多数いる、ということになっているわけである。特攻攻撃についての受け止め方だって、これくらい「日本人の悲惨な被害体験として語る」のと、「狂信的加害者日本」として見るのでは、文脈が変わるのである。
そういう「紛争・戦争における加害被害、善悪、強弱大小」が、明らかにものすごく非対称なのが、イスラエルとパレスチナの関係にはある。そうであることが、この小説を読むと、ますます具体的にくっきりと分かってくるのである。それだけ非対称な関係にありつつも、そうであっても「娘をなくした父」として、イスラエル人のラミと、パレスチナ人のバッサムは、お互いを憎しみあうのではなく、ともに、協力し、同じ場で、その体験を語り伝え続けるのである。
今回のウクライナ戦争でも、戦争初期にロシアで「ロシア兵の母の会」みたいな組織が戦争反対運動をしていたけれど、その後とんと聞かなくなっているが。ロシアの10代の若者がわけもわからず徴兵されて演習だと言われてポンコツ戦車に乗せられてウクライナに攻め込んだものの、米英の提供した対戦車兵器で戦車ごと丸焼けになって死んだ。そのロシアの若者とその母親。というのは、この戦争で何万人かもう出ているのであるが、その母親の悲しみと、ロシアの侵攻で子供を失ったウクライナの母親の悲しみを「同じ、子どもを失った母親の悲しみとして、共感しあい、憎しみあうことをやめよう」と言いうるのか。
いやあ、非対称だろう。侵略兵士の死と、防衛で死んだ兵士の死は、同じように考えていいのかよ。という意見は当然ある。
でもそれが戦争心理のいちばん恐ろしい所でもある。日本人から見れば、本当は戦争が始まる前まではロシア人もウクライナ人もほとんど区別ついていない筈だったのに。今はウクライナ軍がロシアを攻め立てると(当然その時はロシア兵がたくさん死んでいる)やったー、ウクライナ頑張れーってなって、ウクライナが劣勢になると「ロシア死ねー」みたいになる。「敵味方」っていうことで、死んでいい、死ねば嬉しいやつと、死んだらかわいそうなやつに、くっきり心の反応が分かれるようになるのが、戦争の恐ろしい所なのだよね。前からいろんなところで書いてきたけれど。
この本の場合、どちらサイドも罪のない女の子の死ということでいちおう小説内では「どちらもかわいそう」って思えるようになってはいるのだけれど、でも本質を突き詰めていくと、実はそういうこと、「殺していい奴、心が痛まないやつらと、殺されると可哀そうなやつ」に、戦争紛争は人の心をしてしまう。そのこと自体に、ラミとバッサムは抵抗し、言葉で、語ることで、そういう人の心の働き自体に抵抗しているのである。
この本を読んでいて、表面的に読めばすごく美談のようだけれど、小説中にも何度も出てくるけれど、ラミもバッサムも自国の人から「裏切者」と激しく批判もされているわけで、そこのところの難しさを読み取り、日本の過去の戦争をどう考えるかとつなげて考え、そしてウクライナとロシアの戦争とつなげて考える。ということをしながら読んだので、読み始めてから一か月以上かかってしまったのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
