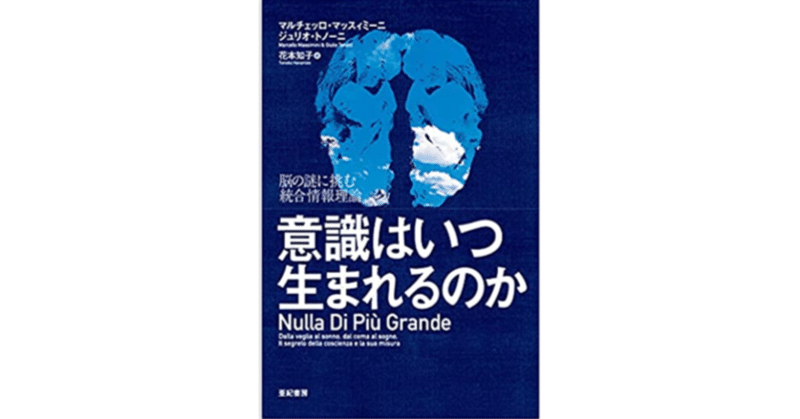
『意識はいつ生まれるのか――脳の謎に挑む統合情報理論』ジュリオ・トノーニ (著), マルチェッロ・マッスィミーニ (著), 花本 知子 (訳) 医学生としての驚き、医師としての患者への共感、苦しみから救いたいという思いをベースに研究が進む点が、他の「人工知能」志向のものとは異なる。そこが最大の魅力でした。
『意識はいつ生まれるのか――脳の謎に挑む統合情報理論』
ジュリオ・トノーニ (著), マルチェッロ・マッスィミーニ (著), 花本 知子 (翻訳)
Amazon内容紹介
「NHKスペシャル『立花隆 臨死体験』出演の天才脳科学者、初の翻訳!脳は意識を生み出すが、コンピューターは意識を生み出さない。では両者の違いはどこにあるのか。クリストフ・コッホが「意識に関して唯一、真に有望な基礎理論」と評した、意識の謎を解明するトノーニの「統合情報理論」を紹介。わくわくするようなエピソード満載でわかりやすく語られる脳科学の最先端、待望の翻訳!」
ここから僕の感想。
Amazon内容紹介に文句をつけて申し訳ないのだが、「天才脳科学者」というのとは、ちょっと違うのだよな、この二人の著者。本の帯の筆者紹介でも、マッスィミーニ氏は「医師・神経生理学者」で、トノーニ氏は「医師・精神科医」なのだよね。
この本のスタート、そして最終章とも、医学生が初めての解剖実習で、掌の上に遺体の脳を載せたときに感じた衝撃と疑問、そこから話はスタートする。それはアポロ計画で月面に立った宇宙飛行士が、自分の親指で隠れてしまうビー玉ほどの大きさな見える地球の上に、人類の営み全てがそこにあるという衝撃に匹敵すると筆者は書く。
「この湿ったゼリー状の物質が、あなたの宇宙と同じくらい広大な宇宙を宿していたのだ、と感慨にふけることもできる。それがいま、あなたの手のひらに重みを伝えながら載っているのだ。あなたのすべてが、知識、記憶、想像、夢のすべてがつまっているのは、そのへんにころがっている物体とおなじようにとったり渡したりできる“モノ”なのだ。」「この物体はなにがほかと違うのか、いったいなにが特別なのか」
この初めの体験だけではない。脳と意識について彼らが考えていく過程は、医療の現場で日々接する、起きている具体的な患者さんに起きる現象や症例に基づいているのだ。
麻酔で意識がなくなるとはどういうことか。時に手術中に意識が戻って、手術中の出来事を体験してしまうのに、身動きも声を出すこともできない患者が1000人に一人くらいいるが、彼らの体験はどういうものか。(私の妻は医師だが、この本のことを話したところ、妻の患者さんにも一人だけこの「手術中に意識が戻ったのに体が動かない」体験をした患者さんがいたと言っていた。妻は内科、リハビリ科の医師なので妻が執刀した手術でというわけではなく、患者さんの思い出話として聴いた、ということである。)
睡眠中、意識が無い状態と、夢を見ている状態では脳の状態はどう違うのか。
事故や病気で「昏睡状態」になる、僕らのような素人は意識が無い=昏睡状態と漠然と思っているが、いくつもの異なる状態が存在し、それは、脳のどこにどういう障害が起きると、どういう状態になるか、その各状態の間を患者は移動することがあるということを詳しく解説していく。
この分類は大切だと思うので書いていく。
⑴脳死⇒生命を維持する脳幹のうち、下部の延髄までが機能停止し、呼吸と心臓心拍維持の機能が失われている。(人工呼吸と人工的に心拍維持して血液循環する装置を外すと死んでしまう)状態。
⑵植物状態⇒延髄は生きているが、「橋と中脳」という脳幹のうちの上部の「意識オンオフスイッチ」が機能停止してしまっている状態。意識は無いが自発呼吸や心拍は維持できている。それだけではなく、目は開き、様々な動きが観察される。時に言葉を発したり笑ったりするのだが、これらはすべて自動的で無意識な運動として起きている。意識がないのである。言葉もしゃべるのに意識がないというのはびっくりな状態である。
⑶閉じ込め(Locked in)状態。閉じ込め症候群ともいう。大脳皮質から脊髄への動作を指示する繊維が集まっている部位が損傷すると、意識はあるのに、カラダが全く動かない「閉じ込め状態」ということになる。この人たちは、全くからだを動かさないために、意識が無いと思われていることが多い。しかし、この人たちはまぶたを開け、目を動かすことだけができる。この神経回路だけが、からだの他の部位を動かす神経回路と別回路だから。なので、家族や医療者が、こちらの言っていることに目を動かして反応しようとしていることに気が付くと、閉じ込め状態であることに気付いてもらえることがある。視線入力のキーボードなどで意思疎通を図ることができる。
この閉じ込め症候群=意識があるのに、不幸にして「植物状態」と誤診されたまま意識がないものとして扱われている患者さんがたくさんいる。その不幸を何とかして解決できないか。というのも、この著者たちの研究動機のひとつである。
この本、全体の話に戻る。この手のテーマの他の本は、最近のどちらかというと人工知能開発側からのアプローチだったり、人間の意識をまるごとコンピュータに移植するための研究だったり、そういう方向のものが多い。「哲学・現象論」→「コンピュータ的認知科学」という視点から、脳科学にアプローチする、という感じである。著者が発見提唱する「統合情報理論」という名称の語感から、この本もそういうアプローチと思われそうだが、違うのである。
この本には、医師の立場での、具体的な一人一人の患者さんそれぞれへの『不幸や恐怖や苦しみから救いたい』という人間的な動機がある。
この本の後半では、意識が無いと思われている患者さんの脳を刺激し、それによる脳波の反応パターンにより、植物状態と閉じ込め状態を明確に判別する実験方法を開発し紹介している。その結果、植物状態と診断されている五人に一人は閉じ込め症候群、意識があるということが分かったという。
その「意識がある」と「意識がない」の違いを判別するための基礎的な考え方が「統合情報理論」なのである。
ものすごく平たくいうと、いくつかの大切な知見から、その主張は組み上げられる。
⓪統合情報理論の肝は、ある思考実験を通じて説明される。
ある壁だけがある部屋の中で目を覚ましたとする。そのときの状態を「闇」と「明るい」のどちらかを報告するように、と言われている。
被験者が人間でなく、光を感じる半導体素子フォトダイオードなら、間違いなく「暗い」「明るい」を報告するだろう。
人間も、真っ暗なら「暗い」と意識するわけで、間違わない。
ところが、人間の場合、フォトダイオードと違って、反対の「明るい」ということについて、こういうことが起きるだろう。目をあいた瞬間、部屋中が真っ赤な光に充たされているとすると、意識は「明るい」ではなく「赤い」と意識する。「明るい、と答えていいのかな、と躊躇する」。青い光に充たされていれば「青い」と意識するだろう。部屋中の壁に絵画が一面に書かれていたら「絵がたくさんあるな」が意識される。
もし人間の意識が、光を判別する半導体のようなものなら、「暗い明るい」の二択しかないだろうが、人間の意識「暗い」は、そうではない(反対側の)膨大な意識状態を判断の基盤として持つ。
毎回、刺激があるごとに、脳の異なる部分が異なる反応をし、それを別の、それぞれ統合された体験として認識する。そういうシステムは意識がある、と著者は定義するのである
次が統合情報理論の核である。引用します。
「意識を生み出す基盤は、おびただしい数の異なる状態を区別する、統合された存在である。つまり、ある身体システムが情報を統合できるなら、そのシステムには意識がある。」
こうした定義を、脳の様々な部位や状態に対して、実験で確認していくのである。
①小脳と大脳。
脳の中で意識に関わるのは大脳である。小脳ではない。小脳のニューロン数は80億、大脳は20億だが、小脳は互いに独立した高速プロセッサーのは集合体であるのに対し、大脳は緊密かつ複雑かつ不均質なネットワークである。ニューロンの数では意識の有無は計れない。「多様で不均質なネットワーク」が大事なのである。小脳はいわば「フォトダイオード」が大量に集まっているシステムである。そこに意識は無いのである。
②睡眠中、夢を見る脳と夢を見ていない脳
夢を見ていないときも大脳のニューロンは活動しているので、(起きているときよりも活動量自体は多いという直感に反する状態にあるという)。単なる活動量の多寡では意識の有無は判別できない。では何が違うのか。そこを追及していく。
ここがいちばんポイントで、全て脳細胞が等距離かつ同じ強さで繋がっている場合、どのポイントに刺激を与えても、脳全体に信号が伝わってしまう。全部の回路が同じようにつながっている電気回路では、どこから電流を流しても電灯が全部ついてしまうのと同じように。全体がオンになるかオフになるかの二択しかなくなる。こういう反応しか示さない脳には意識はない。刺激に対してオンオフの反応しかしないシステム=脳に意識は無い。
電気刺激を与えたときに脳の異なる場所で、タイミングも少しズレて様々な反応が起きる。こういう反応が起きるとき、脳には意識がある。
ノンレム睡眠の脳に電気刺激を、与えても全体が単調な反応をするだけである。(意識がない)
夢を見ているレム睡眠のときに脳に電気刺激を与えると、脳の異なる場所に多様な波形が広がる。(意識がある)
③植物状態と閉じ込め状態
植物状態で意識がない人の脳は電気刺激を与えてもノンレム睡眠の脳と同様の、単調な反応をする。
閉じ込め症候群の人の脳ではレム睡眠のときと同じような、異なる場所に多様な波形が現れる。
ある刺激に対し脳の各所で起きる多様な反応している状態、それを全体として統一的に把握している状態を「意識(がある)」ということなのである。
こうして、「統合情報理論」と、その具体的実験を通して、「意識がある」「意識が無い」を判別していくのである。
本の終盤では「では、動物には意識があると言えるのか。どの程度高度な動物には意識があると言えるのか」というような考察や、脳と意識に関わる「自由意志に関する考察」など、多様な関連テーマに話は広がっていく。が、そこには明確な結論は無い。そのあたりは「科学エッセイ」である。
この本の本当に価値あるところは、やはり、医師としての、いや、解剖実習の医学生として感じた驚きとおののきを元に、医師としての患者への共感をベースに「意識とは何か」を科学的に把握しようとした部分にあると思うのである。
人工知能的なアプローチや、哲学的なアプローチによる「意識」論に、もやっと不満を感じている人にこそおすすめな一冊でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
