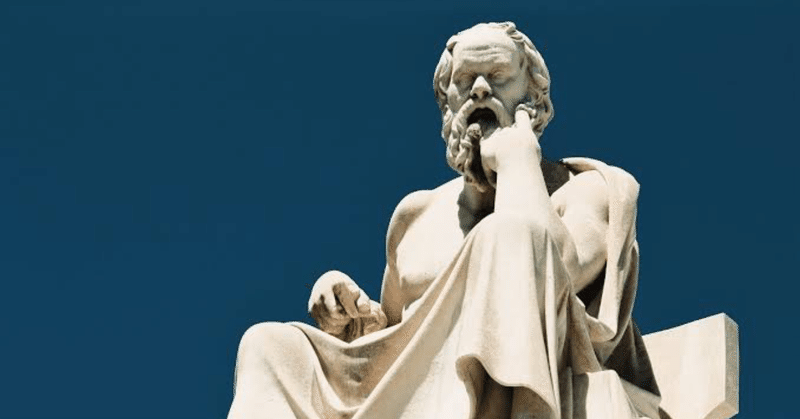
早稲田卒ニート41日目〜ソクラテス以前以後とテツandトモ〜
「宮城げんき市ほや祭り」なるものが勾当台公園で開催されている。ほやは酒飲みとして当然の好物であるが、それより、あのテツandトモがライブをしに来てくれるということで、嬉々として会場へ行った。

「昆布が海の中で出汁が出ないの、なんでだろう」という、トリビアの泉でも検証されたあの伝説のネタを初め、相変わらず面白く且つ納得させてくれる疑問を我々に提示してくれる。
それにしても、「なんでだろう」と何度も執拗に繰り返すせいで耳にこびりついて仕方が無い。そういうネタだからそれはそうに決まっているのだが、ちょっと頭から離れない。
・
・
・
ソクラテスが世界史上の偉大な哲学者であることは最早言うまでもないが、『ソクラテス以前以後』という著作があり、そこに「以前以後」という言葉が使われなければならないくらいだから、如何にソクラテスが歴史の重大な転換点として位置付けられているのかが確認できる。
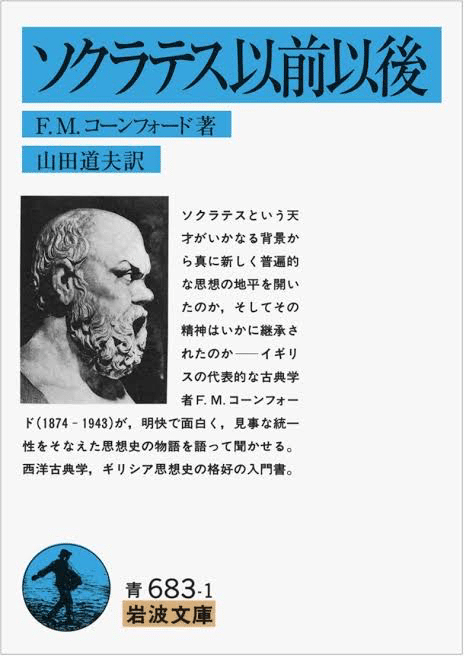
コーンフォードはその序文の中で
ソクラテスによって哲学が自然の研究から人間の生の研究へと方向転換した
と書いている。
どうあれ世界は混沌である。「イオニア自然学」として括られるソクラテス以前の哲学者たちは、例えばタレスが万物の根源を「水」にあると考え、ピタゴラスは「数」に求め、やがてデモクリトスは「原子論」としての調和を試みる。万物の根源がそれぞれで違おうと、それは説明の原理が違うだけで、彼らの動機は何一つ異なることはない。彼らは皆、世界に対して「コスモス」を見出そうとしていたのである。「コスメティック」という言葉がある様に、「コスモス」とは元々「女性の装身具」を意味し、「美しさ」を持つものである。古代ギリシャの哲学者たちはみな、混沌の中に美しい秩序を見ようとしていた。
世界を見ること。見ることは距離を取ることである。そこで、まず哲学は、人間と世界とを分離するところから始まった。この世界観は西洋という文化圏に特有の見方である。人間を自然から切り離し、自然を対象化して分析する。が、これは思考対象を人間から切り離すこと、即ち、「思考の非人格化」を引き起こすのである。
思考と人間がバラバラになること、これをソクラテスは「役に立たない」と言った。「汝自身を知れ」の格言と共にその生涯を全うしたソクラテスは、「善く生きる」ことを第一に考え、常に己の無知と伴走し、魂を磨くことにその人生を尽くした。そんな彼にとって、世界の秩序を探ることは、己の魂を善くすることに何らの貢献もしない「役立たず」な考えなのである。
そこでソクラテスは、思考を人格的行為へとひっくり返した。思考という行為を、世界の「説明手段」から、人間の「発見」に転換したのではないだろうか。ここで特に抽き出しておきたいのは、その「視線の向く先」である。ソクラテス以前は自然という世界の構成原理、即ち「外部」へと視線が注がれていた。一方でソクラテスが現れた後の視線とは、「汝自身を知れ」というアポロン神殿の格言に表れているように、己自身へ、即ち自己という「内部」へと向けられるのである。
なぜこの「視線の方向転換」を取り上げたいかというと、このことはちょうど、私たちの一生においても発生する転換だからである。幼少期、子供はあちこちを触って、「コラ、汚いから触らないの!」などと母親から説教されたりする。蟻の行列に見入り、飛び舞う蝶々を追いかけ、降り積もった雪に飛び込む。子供の視線は世界への好奇心で満たされている。ところが、青年期にでもなれば、いつの間にか蝉の鳴き声に耳を傾けることもなくなれば、落ち葉をカサカサ言わせて楽しむこともなくなる。その代わり、「どうやって生きていけばいいのか」とか、「自分には何が出来るのか」とか、そんな切実な問いを抱えるようになる。つまり、視線が世界という「外部」から自己という「内部」へと向き変わるのである。
哲学史の経験した視線の転換と、私たちの一生で体験する視線の移り変わりとは相似の関係ある。「私」という「個」の中に、「歴史」という「全体」が反復されるのである。私は歴史と一体化する。
こうして、視線が自己という「内部」へ向くことによって自己を省みる態度が生まれ、それが魂の成長を促し精神の充実をもたらす。子供から大人になるというのは、視線が向き変わることでもある。視線をどれだけ「内部」へ向けられるか、それが精神年齢のあらわれであると思う。
・
・
・
視線の向く先ということに限定するならば、大人になってもなお、「あの娘はカワイイなあ」とか「めっちゃイケメンいるんだけど〜」などと、視線が「外部」にばかり向いている人は精神年齢が幼稚であると感じられるのである。その時その人は、自己の魂の成長など頭には無い。
学歴の問題も同様である。社会的体裁とか何とか知らないが、いずれにせよ「外ヅラ」に視線が向いているだろう。将来のナントカがどうとか、そんなことを考えて勉強している時、そいつは勉強による自己の内的成長とは無縁になっている。勉強を内的鍛錬において追求せず、受験という外的制度の作業とみなすのもまた、思考の非人格化から生まれる虚無だろう。
ところが今、「汝自身を知れ」という格言は蔑ろにされているようである。どれだけ気の利いた教育的発言にさえ、「努めて人格を涵養せよ」や「人生を善く生きよ」などという声は聞こえてこない。どうしてそうなってしまったのか。
ここに世界思想史上の、「近代科学の発展」が関係していると思われるのである。敢えて勉強を例に出したのも、入試というものが、あくまで科学的合理性の追求された試験だからである。
科学とは何か。間違ってはいけないのは、科学は理性そのものではないということである。科学とは、人間の理性が生み出した単なる方法に過ぎない。そしてその科学という方法は、物の法則を我々に提示する。雨が降るメカニスムとか地震が起きるメカニスムとか、それに英語の文法だろうが数学や物理の公式だろうが、それらは全て世界の混沌に見出され得る法則である。しかし、世界とは、その法則に従って演繹されさえすれば完結するほど合理的に出来てはいない。科学には限界がある。
それでも、科学が誕生しそれが社会制度化されると科学は発展の一途を辿る。実際、ここ3〜400年くらいはそうして発展した科学に伴ってこの世界が進歩してきたことも事実である。超高層ビルをそこらじゅうに建て、ハイスペックなコンピューターの開発を競い合う。IT革命などという現象は、他ならぬ科学の発展抜きにしては成し得なかったことであろう。しかし、科学の発展はあくまで物の発展でしかなく、それは精神の発達には何の貢献もしないのである。科学がどれだけ発達しようと、僕らの幸福が法則に従って生産されるわけではないし、悲痛な悲しみが消去されるわけでもない。科学は精神に無関心だ。
ここで、我々が、科学は精神の発達に寄与しないということから目を逸らし、科学の発展による物の発展ばかりに浮き足立っていたのではないかと問い直したい。
精神に実体は無い。が、物体は実物である。ならば、精神の充実による人生の豊かさは我々の目には見えないが、実在する物体の充実は生活を目に見えて豊かにすると思われる。するとみな、即物的にしかなれなくなるのである。コロナ黎明期にあった先行きの見えぬ日常の息苦しさで社会が逼迫していた頃に国民は、かかる困難な時代を生き抜く強固な思想よりも、一律10万円の現金給付をこそ求めたのであった。これを生活のリアリティと見るか、精神的豊かさの喪失と見るか。それはそれぞれの人がそれぞれで考えるべきことだ。しかし、即物的になっている割には、アベノマスク1枚の配達には文句ばかりを言うのだから、人間はまことに身勝手なものである。自分が即物的に生きているのか、それとも精神的に生きているのか、自らの立ち位置をわかってすらいないのである。そんなことには無自覚のまま生きている。それゆえ、状況に翻弄されるしかなくなるのである。
あの時受け取った10万円などは忽ち消えてなくなっただろうが、その一過性の喜びのあと、あなたは果たして幸福に近づいたのか、と問うておきたい。
わざと何かを炎上させるだの陰謀論だの、路上喫煙を成敗する動画をYouTubeに載せるだの、「外部」にばかり向く視線はやはり、人間の精神から反省の機会を奪い取っている。窮状に陥った時代を生きる時の揺るぎない思想などもう誰も求めていないし、格闘の末に獲得しようという努力も無いのである。全く虚しい社会になってしまったと嘆くことくらいは許してもらいたい。こうなったのも、僕らが科学の発展に現を抜かし、精神的充実を軽んじてきた歴史の必然的帰結ではないか。
今の教育が虚無化したのだって、事情は大して変わらないだろうと思う。
・
・
・
ソクラテス以前の哲学者たちは、philosophy(知を愛する)の基本的な語源通り、世界を「よく知りたい」という純粋な好奇心に基づいた欲求があったのだと思う。その好奇心によって、視線は「外部」へ向いたのである。
例えば「昆布が海の中で出汁が出ないの、なんでだろう」と言う時、「なんでだろう」とは、世界を知りたいという希求によって「外部」へ向けられた視線である。その意味でテツandトモは、ソクラテス以前のイオニア自然学派に分類できるだろう。我々に問いを投げかけるという点に於いて、彼らは哲学者の様である。尤もここでは、視線が外部への向くことへの非難ではなく、純粋な好奇心に基づく知的欲求という性格の共通性に目を移しておきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
