
ハラールの屠畜でさえ大規模工場で実施されており、祈祷は録音されたものをエンドレスで流す場合が多い
ゲーム理論の教科書には、現代幾何学の教科書に円と三角形があまり出てこないのと同じように、ゲームはあまり出てこない(中略)『利己的な遺伝子』は新しい事実を何一つ報告していない、何らかの新しい数学的モデルを含んでいるわけでもない───そもそも数学がまったく含まれていない。それが提供しているのは、一つの新しい世界観なのである(中略)DNAの真の「目的」は生きのびることであり、それ以上でもなければそれ以下でもない(中略)訳文中、淘汰ということばがたくさんでてくる。これは当然ながら selection の訳である。この訳語は本来「ふるいおとす」というニュアンスの強いことばであるが、この本ではむしろ「自然淘汰の過程で生き残る」という意味に使っている
《種をまく人》がまいているのは何か?
リチャード・ドーキンスいわく、書籍の分類法は図書館によってまちまちで、客観的により優れた方法というものはないが、生命を客観的に分類するには唯一「正しい」方法があり、それは系統樹に則ったものだ。
新(ネオ)無神論者は「明るい者(ブライト)」を自称している〔ヒッチンス、ドーキンスと、あとに出てくるサム・ハリス、ダニエル・デネットの四人は、ネオ無神論者の4騎士とも呼ばれる〕(中略)ネオ無神論者とは、映画館の外に立って、レオナルド・ディカプリオが本当にタイタニック号とともに沈んだわけではないのだと告げる人のようなものだ。そんなことなど、言われなくてもわかっている(中略)ネオ無神論者の懐疑的な態度は、たしかに私も持っているが、宗教に価値を見出している多くの人たちを侮辱したところで何になるというのか?(中略)イギリスの哲学者ジョン・グレイは次のように述べている。「科学は魔法ではない。知識が増えれば人間にできることも増える。それでも人間を各自の境遇から救い出すことはできない」(中略)「私の隣人とは誰ですか?」と尋ねたのは、「隣人を自分のように愛しなさい」というイエス・キリストの勧めに困惑した法律の専門家だった。とても愛せそうにない人もいるので、彼はもう少し範囲を狭めてもらいたかったのだ。イエスは善きサマリア人の寓話でそれに答えた。道の傍らに放置された瀕死の旅人は、まず祭司に無視され、次にレビ人(びと)〔祭司の下で神殿に奉仕する役目を世襲で司っていた人々〕に無視された。どちらも倫理の細部まで熟知している信仰者だった。
デネットが、クオリアはあるのでもなく、ないのでもないと説き、自己はあるのでもなく、ないのでもないと説くとき、彼は中観・空観の哲学と文字通り同一の論理的基盤に立っているように思われる。デネットが自己の、世界の、意識の、「ヴァーチャル・リアリティー(仮想現実)の哲学」を説いて、あくまでも存在の仮の姿としての限りでの現実に耐えていこうと決意するとき、いかなるものをも神格化することなく、無常の定めに耐えて存在のあるがままの姿で尊んでいこうとする、仏教の慎ましい世界を思わせる───日本ヴェーダ―ンタ協会理事 山口泰司教授(中略)存在の本質は、有と無の、肯定と否定の、絶対と相対の、二次元対立を越えたところにしかないことになり、存在の本質のそうしたあり方が、中とか空の概念で指し示されているのである。だとすれば、中観・空観の哲学は絶対・相対の対立を越えたものとしての限りでしか相対主義の哲学を説くことはなく、有と無を越えたものとしての限りしか虚無主義の哲学を説くことはないことになり、厳密な意味では、この哲学は相対主義にも虚無主義にも無縁だということになる(中略)デネットが、クオリアはあるのでもなく、ないのでもないと説き、自己はあるのでもなく、ないのでもないと説くとき、彼は中観・空観の哲学と文字通り同一の論理的基盤に立っているように思われる。デネットが自己の、世界の、意識の、「ヴァーチャル・リアリティー(仮想現実)の哲学」を説いて、あくまでも存在の仮の姿としての限りでの現実に耐えていこうと決意するとき、いかなるものをも神格化することなく、無常の定めに耐えて存在のあるがままの姿で尊んでいこうとする、仏教の慎ましい世界を思わせる───日本ヴェーダ―ンタ協会理事 山口泰司教授
種蒔く人はキリストである(中略)デネットは無神論者である。したがって、宗教を冷ややかに否定したり、ドーキンスのように悪しきウィルスのように扱うような無神論者ではない。デネットは、このような無神論者から自分を区別するために、自分のことを「ブライト」という新語で呼んでいる。私は、無神論者としてのニーチェを研究している神学者を知っているが、それと同じように、デネットは、宗教に理解のある無神論者である(中略)デネットは、すでに述べたように、検証可能と思われる仮説を組み合わせて理論を提示しているが、それは答えではない。それは、無神論者、有神論者を問わず皆で議論をして行くための叩き台にすぎない。デネットも主張しているように、それを肯定するも良し、それを否定するも良し、である───訳者あとがき

イエスは言った。「行って同じようにしなさい」(中略)「善きサマリア人」と言えば、困っている人を進んで助けるよき隣人のことだ。もともとは聖書の物語だが、 聖書のなかの「善きサマリア人」はそれ以上に深い意味を持つ(中略)現代の読者のために、背景を補足する必要がある。物語に登場するサマリア人は、ただの善人ではない。彼は、社会的立場の大きな違いを乗り越えて怪我人を助けた善人なのだ。当時、サマリア人とユダヤ人(他の登場人物はすべてユダヤ人だ)は激しく敵対しており、サマリア人は今で言う「無神論者の暴走族」と同じくらい社会ののけ者だった。

聖書にある「善きサマリア人(びと)」は、殴られ身ぐるみはがされて道ばたに倒れ苦しんでいる旅人を見かけたときに足を止めて助けた人の話だ。その旅人の姿を見た人はほかにも二人いたが、その二人は自分の身に降りかかる危険を案じて、道路の反対側に渡り、通り過ぎてしまった。 マーティン・ルーサーキング・ジュニアは、旅人を助けなかった二人は 「ここで足を止めてこの男を助けたら、自分の身に何が起こるだろう?」と考えたのであろう、と指摘した。しかし、「善きサマリア人」は別のことを考えた。 「もしわたしが足を止めてこの男を助けなかったら、この男の身に何が起こるだろう?」と。 同情は共感の上に成立し、共感は他者に対する集中を必要とする。自分のことしか考えていなければ、他者のことには気づかない。困っている人がいても、まったく気がつかないまま通り過ぎてしまう。しかし、いったん気がつけば、その他者に波長を合わせ、気持ちや窮状を察し、その人を心配して行動を起こすことができる。

道を尋ねられた時、サイコパス傾向の参加者で立ち止まって教えた人は少なかった。書類を道にばらまいて慌てて拾おうとしている女性を助けたのは、サイコパスの人もポジティブな人も同じ割合だった。見知らぬ怪我人が不自由しているのを見て親切に手助けした割合は、サイコパスの人たちの方が、ポジティブな人たちよりずっと高かった(中略)関わり合いになるのに不安があるような状況では、サイコパスの強みが光る。そういう状況では、ふだん親切な人たちの方が、かえって何もせずに通り過ぎてしまう。

同調と服従に関する私の結論にふさわしい言葉を揚げておこう。ハーバード大学の心理学者、マーザリン・バナジの言葉だ(中略)善きサマリア人とは、イェルサレムからエリコへ向かう道の脇で苦しんでいた人を立ち止まって助けたただひとりの人のことだ。ルカによる福音書には、この人物は天国で当然のほうびをもらえるだろうとある(中略)実験では、神学生に時間の余裕があるときほど、助けてくれる可能性が高くなった。このことから。“時間的なプレッシャー” という状況の要因が、助ける者と何もしない者の違いを生むことがわかる。

モーセ集団(モーセは死ぬが)は、BC1200年ぐらいに、ヨルダン川を渡って、エリコの都市を攻め落とす。そして次々と他のペリシテ人の町を奪い取る。この時から数えて「ユダヤ人3200年の歴史」と私は推定する。すぐにエルサレムに到着すべきなのに、どうもそこには別の人々がいたようだ。ペリシテ人(phikisine フィリスティーン)が、今のパレスチナ人だ。彼らはモーセ集団よりもエジプトから少しだけ(何十年か)早く来た先住民だ。彼らの町(都市、集落)に次々にモーセ集団は襲いかかって、攻めて取って回った。これが「出エジプト記」の後半の「士師記」の200年間(BC1200 - BC1000年)(中略)士師の始まりは、モーセの後継者のヨシュアである。ヨシュアは優れた軍事指導者だった。ユダヤの民をよく率いて戦いに勝ち続けた。こうやってエズレル平原=イスラエル平野を自分たちのものにした。『旧約聖書』では、ここを大きくグルリと回るようにして、最後にエルサレムに到着したように書いてある。エリコ占領のあと、なぜ、さっさと、エルサレム(シオンの丘)に向かわせなかったのか。分からない。どうもエルサレムに別の王がいたようだ。カナーンの土地には、ペリシテ人の他にアッカド人という人たちもいた。聖書の中によく出てくる。モーセ集団はこのアッカド人を、北の方に追い払って、「自分たちはユダヤの民だ」と言い出した。あるいは、「イスラエル人だ」と言い出したようだ。ペリシテ人、ユダヤ人より1000年後のイエス・キリストの時代に、「パリサイ人(びと)」という人々が現れる。『新約聖書』にたくさん出てくるイエスを虐めた人々だ。パリサイ人は、英語では、「ファラシー」( pharisee )と言う。パリサイ人というのは、紀元後30年に、キリストが36歳で処刑されたときに、「神官職」だった人たちとされる。パリサイ人が、イエスというおかしな男をさっさと処刑しろと騒いだ。このファラシー(パリサイ人)も、本当はペリシテ人と同じだろう。今のパレスチナ人だ(中略)今はみんなイスラム教になって、即ち、アラブ人になっている。彼らはずっとこの地で農民だった(中略)『旧約聖書』ではモーセが引き連れて来たとされるユダヤ12支族が、今のイスラエルの全土に、それぞれ分かれて住んだ、となっている。でもペリシテ人たちもいる。きっと混在している。今もそうなのだ。
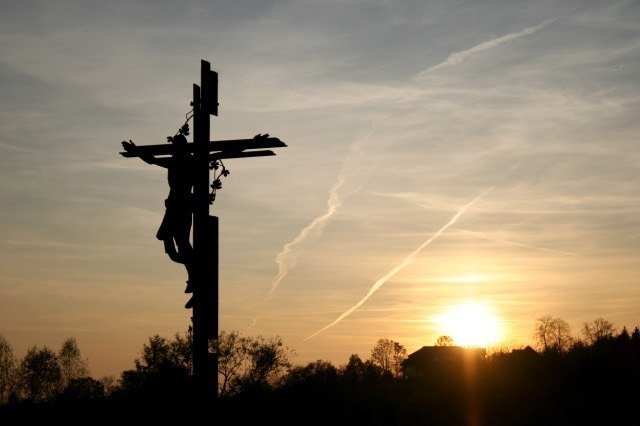
「ミーム(meme)」という言葉は、動物行動学者で進化生物学者リチャード・ドーキンスが、一九七六年に著書『利己的な遺伝子』のなかで使ったものだ。これは遺伝子(gene)を意識してつくられた。ミームは文化的にそれに匹敵するものだからである。ミームは複製や真似のプロセスを通じて脳から脳へ広がっていく言葉、アクセント、アイデア、メロディなどをいう。
「いや、あれはおれの宿命だったんだからあれしかなかったんだ」と思ったりもする。が、デネットの回答というのはこういうものだ。複雑な条件の下ではシミュレーションするより実際にやるほうがはやい───訳者 山形浩氏
進化は体や脳だけではなく、観念にも見られる。「ミーム」は、リチャード・ドーキンスがこの言葉を作ったときの定義では、インターネット上で拡散されるキャプションつきの写真のことではなく、人から人への伝達が何度も繰り返されることで形成されてきた共有可能性の高い観念のことだった。たとえば耳にこびりついていてつい口ずさんでしまう歌や、伝えずにはいられないと思わせる物語もそこに入る(中略)練習すると認知能力が高いほうがより大きく力を伸ばしていく(中略)主効果と交互作用の違いを知っていれば、誤った二分法に陥らずにすむし、根本的な原因がどのようなものなのかを深く見抜くこともできるようになる(中略)原因が複数あるという発想がすでに浮かびにくいのだから、複数ある原因同士が互いに作用するという発想はもっと浮かびにくい(中略)こうした発想が浮かびにくいのは、わたしたちが複数の原因について考えたり語ったりするための語彙を身につけていないからでもある(中略)一般的には道徳の進歩は闘争によってもたらされると考えている。権力者が特権を自ら手放すことはないので、民衆が連帯して力ずくで奪い取るしかないという考え方である。ところが、道徳の進歩の実態を解明しようと調べてみたところ、ドミノ効果の最初の1枚が理路整然とした議論だったという例が歴史上非常に多いことがわかり、わたしは大いに驚いた。たとえば一人の哲学者が、ある行為がなぜ許されないのか、なぜ非合理なのか、なぜ人々の価値観と矛盾するのかについてはさほど長くない文章を書く。その小冊子ないし宣言文が人々のあいだに広まり、他の言語に翻訳され、パブやサロンやコーヒーハウスで議論の材料になる。そしてついには指導者に、議員に、そして世論に影響を与える。
もともと生物学者のリチャード・ドーキンスによって提案されたミームは、複製し進化するものであり、遺伝子によく似ているが、媒介するのは文化である(中略)ミームと遺伝子は進化し、しかも互いに補強し合うように進化することができる。
あまり効率的ではない宗教を崇拝する集団も、必ず淘汰されるわけではなく、より効率的な宗教に鞍替えする場合がある。要するに、実際に進化するのは宗教であって、人間や遺伝子ではない。
「生贄」を意味する英単語 sacrifice はラテン語に由来し、「神聖なものにする」という意(中略)古代の習慣の名残は、ユダヤ教のコーシャとイスラム教のハラールの規定にいまも見られる(中略)神々との敬意に満ちた関係を維持するために、一連の手順と祈祷が必要なのだ(中略)最も近代的なコーシャやハラールの屠畜でさえ大規模工場で実施されており、祈祷は録音されたものをエンドレスで流す場合が多い。
贈り物をするにあたって社会的な評価を最大にするためには、自分がどれほど犠牲を払ったかを他者に見せる必要がある(中略)余分な「よい」行動は望ましくないコストである。脳にとって理想的な状況とは、自分は神の怒りを恐れていると相手に信じ込ませながら、神などまったく恐れないような行動をとり続けることなのだ(中略)ムハンマドが最後の預言者だと信じることは、混乱をもたらす新しいお告げがそれ以上出てこないようにするにあたって好都合だ。キリスト教では、神と一般信徒の仲介役として聖職者が必要である(あるいは必要でない)と信じることが、教会組織における聖職者の役割を決定している。そのような信念の利点は見ればすぐにわかる。すなわち、神学という名の政治である(中略)特定の信念を持つことの価値は、それにしたがって行動することではなく、自分がそれを信じていると他者に思わせることにある
もしドーキンスが苦手だという人には、アンリ・ポワンカレのこんな言葉がある。「学者が自然を研究するのは、それが役に立つからではなく、楽しいからであり、楽しいのは、自然が美しいからだ。もし自然が美しくなかったら、知る価値はないだろうし、人生も生きる甲斐がないだろう」
教養のある人は時間を大切にするので、時間を節約するための用語を学びます。サイコパスという用語は、教養のある人が時間を大切にするために使用する用語です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
