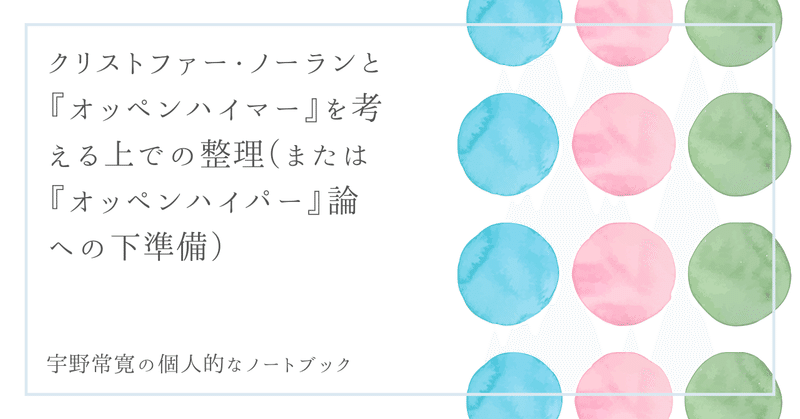
クリストファー・ノーランと『オッペンハイマー』を考える上での整理(または『オッペンハイパー』論への下準備)
先日、クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』をようやく観てきた。この映画については、森直人さん、藤えりかさん、張彧暋さんとの座談会を配信したが、ここでの議論を踏まえた上で、改めて書いてみたいと考えてる。
結論から述べると、僕はこの映画にそれほど肯定的ではない。それは広島、長崎の原子爆弾投下による惨状を克明に描写すべきだ……といった表面的なものではなく、ノーランが反復してきた劇映画という表現について内在的な批判(問い)が、本作においては大きく空回りしているように思えるからだ。
そして今日は議論の前提を確認するために、かつて僕が書いた『TENET』までのクリストファー・ノーラン論(『水曜日は働かない』(ホーム社)収録)を特別にここに掲載したいと思う(『オッペンハイマー』論は明日以降掲載する)。決して、断じて、絶対に「週末に書き終わらなかったから」ではない。ホーム社からは、『水曜日は働かない』の宣伝につながるのなら、という理由で許可を貰ったので、気になる人は購入して欲しい。このような作品表に加え、僕の私生活や時事問題についてのエッセイが多数収録されている。)それでは、早速始めよう。
※
もう何年も前のことだ。批評家の石岡良治は、僕が司会を務めたトークセッションで、こう述べた。クリストファー・ノーランの映画を考えるときは、そのタイトルに注目すべきであると。それぞれの作品を「映画とは○○である」というノーランの態度表明であると「見立てて」思考すること。そうすることによって、ノーランの映画の本質は見えやすくなるのではないか、と。このセッションで石岡は時間の関係もあり具体論には踏み込まなかったが、このときの彼のアイデアはノーランという作家について考えるときに強力な補助線となるだろう。念のために断っておくが、もちろんこれ自体は石岡の考案した言葉遊びの類にすぎない。しかしこの言葉遊びを用いた思考の飛躍を通じてノーランの諸作品を解釈することによって、僕たちは意外な側面からその本質に迫ることができるのではないか。
たとえばクリストファー・ノーランの初期の代表作を考えたとき、それは映画とは『メメント』(2000)つまり、記憶のことだという宣言であると「解釈」できる。そう、この映画は記憶をめぐる物語であり、そして劇映画という制度は鑑賞者の記憶を混乱させることで、現実には体験し得ないものを体験させることを証明する映像として結実している。
あるいはクリストファー・プリーストの小説『奇術師』を原作に用いた『プレステージ』(2006)は、映画とはプレステージ(Prestige マジックショーを完成させる「最終段階」の意)であるという宣言として受け取ることができる。では一体何の最終段階か。それは物語を追えば一目瞭然だ。同作では巧妙なトリックだと思われていた手品が、実はクローン技術という魔法的なテクノロジーを用いたものであることが結末で明かされる。そしてこれこの設定の開陳の衝撃によって成立している映画である。したがって同作を繰り返し観る動機を調達することは難しい。このような映画を、ノーランはなぜ撮ったのか。その答えは究極的には想像するしかないし、当人が自覚しているとも当然限らないのだが、想像することはできる。それはこの映画が魔法的なテクノロジー、具体的には情報技術によって映画という表現が臨界点、つまり「最終段階」に達しつつあることを示したものであると「見立てる」ことだ。
誕生したその瞬間はそれ自体が魔法的なテクノロジーだった「映画」は、やがて物語の器に選ばれ劇映画という20世紀を席巻した表現に進化した。しかし現代においては初期映画の持っていたような魔法的な体験を与えるテクノロジーが次々と生まれ、映画という表現そのものを相対的に過去のものにしている。実際に同作の公開当時既に劇映画は岐路に立たされていた。情報環境の変化によって、20世紀において支配的な表現形式であった「映像」はインターネット上のコミュニケーション形式の一つである「動画」に変化した。劇映画はこの「動画」のクラシカルな形式を持ったサブカテゴリーの一つに過ぎなくなった。少なくともそうなる予感が、当時は既に漂っていた。
実際に劇映画は大きく変質した。人々が劇場に足を運ぶ理由はその後ほどなくして、巨大なスクリーンとリッチな音響設備を楽しむことに集約されるようになり、物語や演出を味わうだけならばNetflixで十分だと人々はなんの悪意もなく、考えはじめるようになった。
そしてそれ以前の問題として、人々は相対的に紙やスクリーンの上の他人の物語を受信して感情移入することよりも、自分自身の体験を発信することのほうに夢中になりはじめた。休日はカウチに横たわりテレビのスポーツ中継を眺めるというのは、20世紀の工業社会を生きた戦後の西側諸国の中産階級のライフスタイルであり、21世紀の今日を生きる情報社会下のクリエイティブ・クラスは自然の中に自分の身体を置き、その体験をFacebookにシェアする。『プレステージ』の魔法的なテクノロジーによってそれまで描かれてきた世界観が根底から覆される結末は、今振り返るとこうした変化に到る直前の「最終段階」を描いたものとして見立てると面白い。手品の種が、演出ではなく本当にそれを技術的に起こしていたというこの映画の結末は、まさに映画の映像の時代の「最終段階」だったのだ。
だとすると『ダークナイト』(2008)とは、もはや映画という古い制度にできることは、悪(反動)を装うことで世界を善導する闇の騎士(ダークナイト)であるという宣言として解釈できるし、『インセプション』(2010)とは『メメント』のアップデートとして劇映画に残された可能性を記憶の「植え付け(インセプション)」的なアプローチによる観客の体験の演出に見出したものだと考えればいい。その意味において映画とはもはや「ダークナイト」であり「インセプション」なのだ。
ではこの見立てに『ダンケルク』(2017)を当てはめたらどうなるか。
ここから先は

u-note(宇野常寛の個人的なノートブック)
宇野常寛がこっそりはじめたひとりマガジン。社会時評と文化批評、あと個人的に日々のことを綴ったエッセイを書いていきます。いま書いている本の草…
僕と僕のメディア「PLANETS」は読者のみなさんの直接的なサポートで支えられています。このノートもそのうちの一つです。面白かったなと思ってくれた分だけサポートしてもらえるとより長く、続けられるしそれ以上にちゃんと読者に届いているんだなと思えて、なんというかやる気がでます。
