
同じ勉強をしているのになぜ差がつくのか?―『考える力』を高める魔法の言葉~日本人が大切にしてきた「言霊の本質」を探る~―(前編)
こんにちは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
その一環として、
小学校教諭として学校現場では、
「和の心」を軸に、喜びあふれる豊かな学級集団を作り上げるために、
自らの持ち味を社会に貢献する「『和』の学級経営」を目指して
日々奮闘しています。
前回の『自己肯定感』を高める魔法の言葉に引き続いて、
第二弾は、
『考える力』に焦点を当てて、
国の宝である子供たちがいきいきと輝くために、
私たち大人に何ができるのか?を考えていきたいと思います。
最後まで、お付き合いいただければありがたく存じます。

1)同じ勉強をしているのになぜ差がつくのか?

例えば、教室でこんな場面に遭遇したことはありませんか。
定期テストの直前。
「ねえ、勉強した?」
「え~!全然してない!やばいよね!」
「どうしよう~。」
そして、テスト返しの日。
テストをしていないといった人ほど、点数がかなり高い。
そういう人ほど、見えないところで一生懸命勉強をしているのだろう。
僕はずっとそう思っていましたし、自分もしていました。
しかし、
本当にたいして勉強をしていなくても、
本当に高い点数をたたき出す人も稀に出会います。
「どうしてだろう?」
僕はずっと疑問に思っていました。

「同じ勉強をしているのに、なぜ差がつくのだろうか?」
「きっと頭のつくりが違うんだ。」
「あいつは天才だから。」
努力だけでは乗り越えられないこともある。
そう思っていました。
しかし、実は
「なぜ、同じ授業を受けていて、同じ勉強をしていて、差がつくのか?」
には、
明確な理由があったのです。
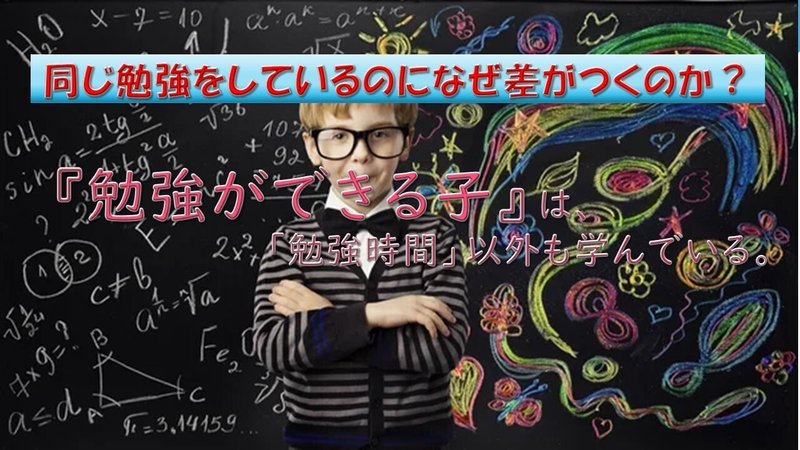
なぜ、同じ勉強をしていて差がつくのか?
差がつく理由はかなりシンブルです。
シンプルであるだけに、人は意識すらしていないかもしれません。
それは、
「勉強時間以外も学んでいる」
ということです。
2)「学び」のタイプとは?

彼らは、机に向かって勉強している以外にも、
生活すべてにおいて学んでいるのです。
「学び」のタイプは、大きく分けて3つあります。
①授業を受けていても学んでいない人
②授業だけが学びの人
③寝ているとき以外の日常全てが学びの人
です。

1つ目の学びのタイプは、
「授業を受けていても学んでいない人」です。
この学び方の特徴として、
・席について授業を受けているが、授業の話をほとんど聞いていない。
・席に座って一応は授業を受けているが、黒板に書いてあることだけをただ
写経のように書き写しているだけ。
要するに、
学んでいるように見えても、学ぼうと思っていないタイプです。
このタイプは、
まったく授業内容を聞いていないわけではなく、
雑談時や先生が面白いことを言ったときのみスイッチが入ります。
そのため、
知識が断片的となり、それが頭に体系的に蓄積されることはなく、
一過性の『体験』で終わります。
仕事に置き換えると、
マニュアル化されたルーティンワークどまりで、
特にそれ以上のことを学びたいとは思っていない人です。

2つ目の学びのタイプは、
「授業だけが学びの人」です。
いわゆる、
子どもであれば勉強をしている時間、
働いている人であれば仕事をしている時間でしか学んでいない人です。
特徴として、大きく3つあります。
まず、
「両立」という言葉をよく使います。
子どもであれば、
「勉強と部活の両立」「勉強と遊びの両立」というように使います。
働いている人であれば、
「仕事とプライベートの両立」という表現をします。
「両立」というからには、
それらを分けて考えているということであり、
それゆえそれらのバランスをどう上手にとるのかが、
このタイプの人の課題になるのです。
次に、
「気合」「根性」「努力」がよいことだと思っています。
もちろん、
これらの言葉が悪いわけではありません。
しかし、
精神論で動いているので、いつまでも持続させることはとても難しいです。つまり、
やる気が萎えてしまえば、
即落ちていくというリスクをはらんでいるということです。
最後に、
できない自分を責めてしまう傾向にあります。
努力をすれば報われると思って努力をしますが、
努力をしてもトップになれない自分を卑下したり、
罪悪感を持ったりすることがあります。
ごくまれに、劣等感が変容し、嫉妬に変わる場合もあります。
そして最後にあきらめに変わります。
一生懸命に頑張るのですが、この学びのタイプにはいずれ限界が来ます。

3つ目の学びのタイプは、
「寝ているとき以外の日常全てが学びの人」です。
子供においては、
机の上で勉強することだけが学びであると勘違いしている子が多く、
親も子供が机で勉強している姿を見ると安心するという謎の現象も起こっています。
しかし、
それは、学びの一部であって、
本当に勉強ができる子は、机上の勉強時間以外の学びが圧倒的に多く、
それが机上の勉強へと応用されているのです。
このような学び方の人は、
人と話をするときも、テレビを観ているときも、
街を歩いているときも、
感じ、考え、自分の意見を持つ習慣を持っています。
OFFタイムで得られたアイデアや思考、方法を
ONタイムに自然と応用できています。
つまり、
表面的なON/OFFはあっても、意識・無意識の世界では境目がないのです。
起きている時間全てが学びになっているので、
学校での6時間、塾での1時間、
家での3時間だけを学びの時間と捉えている人とは、
学ぶ時間の絶対量が圧倒的に異なります。
では、
このような学び方をしている人は、
どのようなことを考えて過ごしているのでしょうか。
今回は、
魔法の言葉によって日常で「考える力」を高めることで、
学びの量を圧倒的に増やしましょう!という提案です。
次回の記事から、
詳しくお話していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『学び』って
もともと
「なんか気になる」
「なんか面白そう」 という
知的好奇心を満たしたり、
知る楽しさを満たしたりするもので
テストでいい点を取るためでも
試験に受かるためのものでもない。
そんな何かに「没頭できる」体験を
学校でできるようにしたいと考えています。
僕は、こう思います。
学校教育の役割は、
みんな同じように能力を高め、平均点を上げることではない。
それぞれに個としての能力を高め、
自分の持ち味を自覚し、
社会の中で自分をうまく活かせる場所を見つける力を養うことだと。
極端だけど本質的なこと。
『学び』とは、知識を得ることではない。
『学び』とは、「学ぶことの意味」を知るということ。
本当に教員がやるべきことは、
「学ぶことの意味」を子供が実感できるようにすること。
これさえおさえておけば、
「勉強しろ」と言わなくても
勝手に子供自ら学び始める。
『一隅を照らす これ即ち国宝なり』
私たちが小さな灯火として
周囲の一隅を照らす。
その灯火がたくさん集まって、
国家全体を明るく照らし、
将来への希望の灯りを点すことができるようになる。
大人が輝けば、子供も輝く。
今日も子供を信じて。
今日も自分を信じて。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
