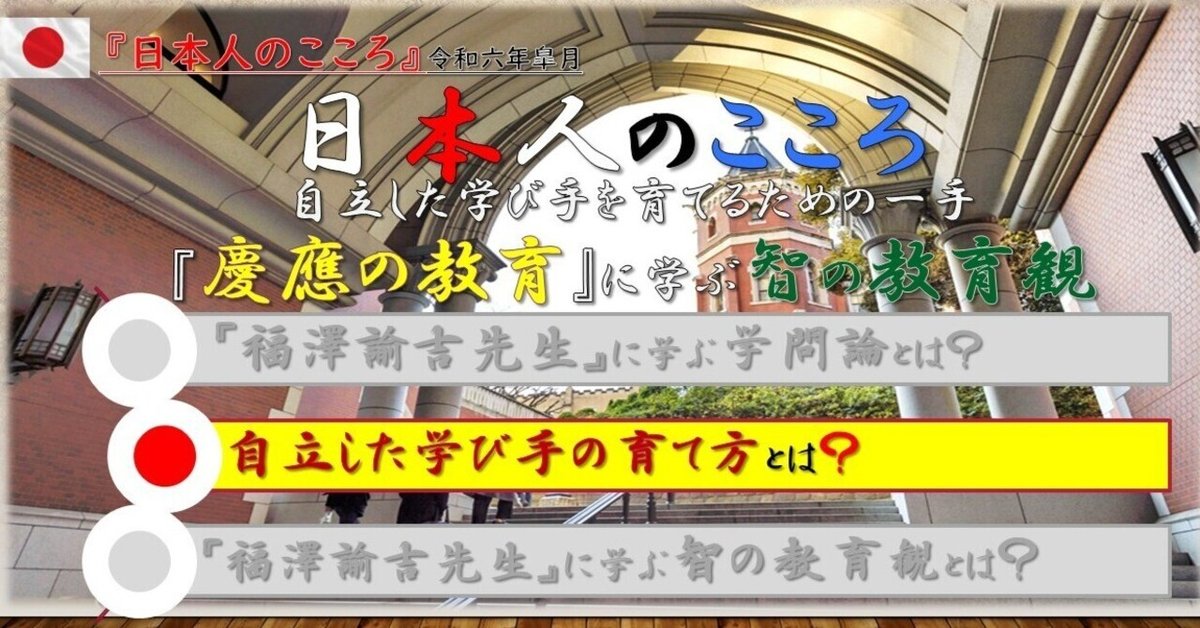
自立した学び手を育てるための一手『慶應の教育』に学ぶ智の教育観(後編)~自立した学び手の育て方とは?~ー『日本人のこころ』20ー
こんばんは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
5月もいよいよ終盤です。
運動会に向けての準備もいよいよ大詰めになってきています。
考えることが山積みですが、
最上位目標を見失わずに、
教育の最前線から我が国を守るために
これからも力を尽くしていきたいと思います。
さて、
教育を考えるうえで、
とりわけ学ぶべき福澤諭吉先生の教育観が息づいている
「慶應の教育」について、詳しく考えていきましょう!
最後まで、お付き合いください。
よろしくお願いいたします。
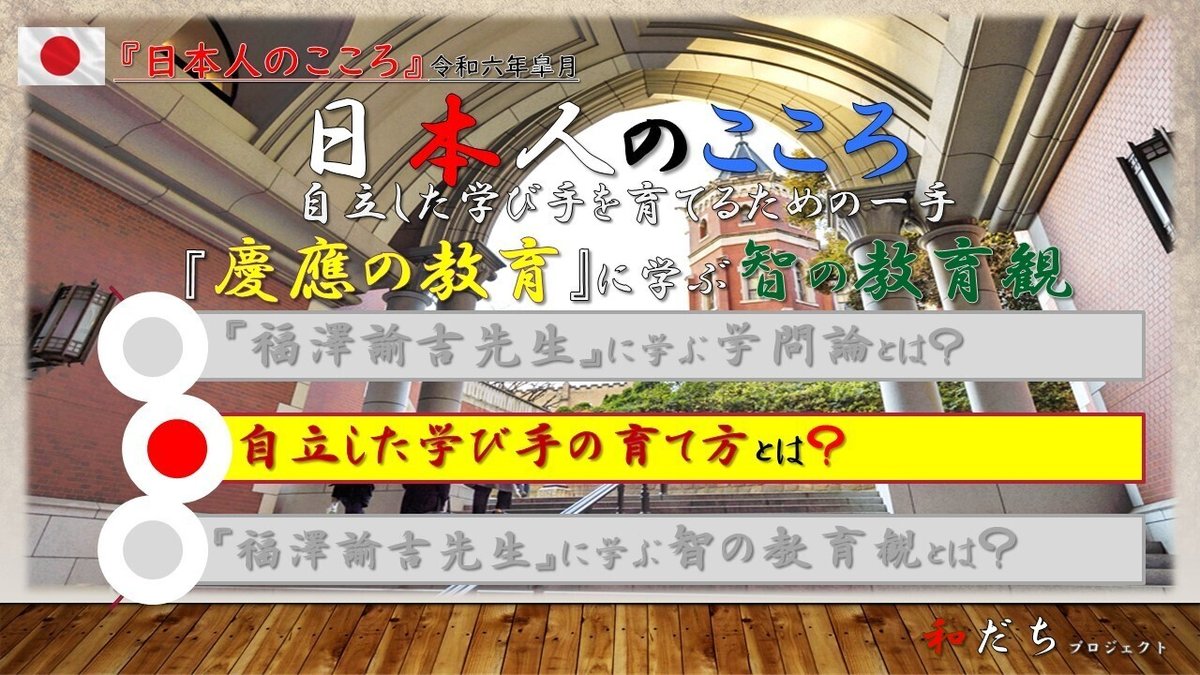
1)『慶應義塾』はどのように誕生したのか?

そもそも「慶應義塾」はどのように始まったのでしょうか?
安政5(1857)年、
大阪の緒方洪庵塾で蘭学を学んでいた中津藩士の福澤先生は、
藩の命令を受けて江戸に移り、
築地鉄砲洲の中津藩中屋敷の長屋で藩士らに蘭学を教え始めました。
この時、
「大阪の書生は修行する為に江戸に行くのではない、行けば教えに行くのだ
と云う自ずから自負心があった」(『福翁自伝』)
ものの、
のちに慶應義塾と命名される蘭学塾は、
藩からの命令という受動的な形で始まりました。
しかし、
福澤先生は
次第に塾の経営を自分の使命として強く自覚するようになります。
その過程で重要な出来事は、文久2(1862)年の渡米でした。
英学に転換した福澤先生は、
すでに万延元(1860)年、
木村摂津守の従者となって咸臨丸で渡米しましたが、
この文久2年に、
日本の最初の遣欧使節に翻訳方として加わることになったのです。
この使節の第一の目的は、
五カ国条約に基づく開港開市時期の延期を求める交渉でしたが、
同時に欧州事情の調査も目的としており、
福澤先生らは日程の合間を縫って、
フランス、イギリス、プロシア、ロシアなど
各国の事情を精力的に探索しました。
さらに、
インド洋経由の長い船旅は、
西洋列強に虐げられたアジア諸国の状況を目の当たりにし、
日本の行く末を思案する貴重な機会となりました。
福澤先生は、
この経験によって洋学による人材育成の必要性を切実に認識したのです。
帰国後、期待をかけた中津藩が洋学教育に転換できないと知るや、
塾の経営に自ら本腰を入れて取り組むことになります。

文久3(1863)年には、
今は「入社帳」と称される「入門帳」をそなえ、
翌年の元治元(1864)年には、中津から塾の中核となることを期待して、
小幡篤次郎、仁三郎兄弟、浜野定四郎ら優秀な若者6人を連れて行きます。
さらに、
慶応3(1867)年、2度目の渡米の際には、
一人一人が同じ教科書を持って授業ができるように
大量に図書を購入しました。
「福澤塾」は、
慶応4(1868)年、戊辰戦争の最中に築地鉄砲洲の中津藩邸を離れ、
独自に土地建物を購入して芝新銭座に移転しました。
そうして、
時の元号をとって「慶應義塾」と命名されることになります。
「自分たちが日本の洋学の伝統を引き継ぎ、
さらに新しい時代を切り拓いてゆくのだ」
という強い使命感に溢れていました。

そのように誕生した「慶應義塾」ですが、
現在の小学校段階での教育は、
「慶應義塾幼稚舎」と「横浜初等部」があります。
今回は、「慶應義塾幼稚舎」に焦点を当ててお話をしていきます。
2)『慶應義塾幼稚舎』はどのように誕生したのか?

「幼稚舎」の前身は、「和田塾」と呼ばれ、
1874(明治7)年に始まりました。
我が国で最初の私立小学校の誕生です。
その6年後には、「慶應義塾幼稚舎」と、現在の校名になりました。
創始者は、福澤諭吉先生の高弟・和田義郎です。
初代舎長(校長)を務めました。
創設は、福澤先生の要請によるものでした。
4男5女の子だくさんの福澤先生は、
自分自身の子供が小学校に進学する頃になると、
もっと理想的な学校があればよいと切望するようになっていました。
そこで、
白羽の矢を立てたのが、
慶応義塾のある三田の山の上に住んでいた和田義郎だったのです。
和田義郎は、紀州藩(和歌山)の出身です。
藩の選抜留学生として上京し、福澤先生の塾に入りました。
その聡明さ、温厚な人柄を福澤先生は早くから買っていましたが、
同時に荒々しいい性格も持ち合わせていました。
福澤先生は、『福翁自伝』で、
書生時代の和田義郎の豪傑ぶりを示す逸話を紹介しています。
和田義郎が、仲間2、3人と赤羽橋あたりを散歩していると、
前方から壮士(職業的政治活動家)の大集団が歩いてくる。
それを見た和田義郎は、道の真ん中で立ち小便を始めた。
壮士たちが怒り出すかと思いきや、
その気迫に押されたのか、小便を続ける和田義郎を避けて通り過ぎて行ったという。
このエピソードは、福澤先生を相当喜ばせたとのことです。
和田義郎に対する評価を一気に高めたのです。
福澤先生は、粗野な部分を持つ人間を好みました。
たくましく、粗削りな面がなければ、
本当の意味で子供の教育などできない。
和田義郎は、駆け回る子供と一緒になって遊ぶことができる人間でした。
大の子供好きだったのです。
夫人との間に子供を授かることのなかった和田義郎は、
福澤先生の独自の小学校を創りたいという要請に喜んで応じ、
幼い子ら数人を自宅に寄宿させ、
「和田塾」、そして「幼稚舎」が開校することになったのです。

福澤先生が、和田義郎を抜擢したのは、もう一つ理由がありました。
それが「英語力」です。
自ら『英吉利(イギリス)史略』という翻訳を手がけ、
私家版として発刊するほど
当時としては傑出した英語能力を持っていました。
明治維新後の日本国において、
いかに英語が大切かに気づいていた福澤先生は、
その習得のためには、
勉強をできるだけ早く始めた方がいいとも感じていました。
小学校教育の段階で英語を取り入れるには、
和田はうってつけの人材だったのです。
福澤先生は、1859年に咸臨丸によって渡米します。
1862年には、幕府遣欧使節団に参加し渡米しています。
特に、
この2回目の洋行は福澤先生の教育に対する姿勢に
大きな影響を与えました。

ロンドンに45日間滞在した福澤先生は、
欧米の国々と互角に渡り合うためには、
何より英語力が不可欠であることを再認識させられました。
ロンドンのサマセット・ハウスにある
キングス・カレッジ・スクール・ボーイズを見学します。
子供から大人までが学ぶ現場を目の当たりにして、
ぜひともこうした教育システムを取り入れたいと考えるようになりました。
それがのちの、
小学校から大学までの一貫教育の構想につながっていきます。
真の「塾生(慶應生)」を生むべく、
一貫教育のカリキュラムが練られていったのです。
カリキュラムの出発点を担う「幼稚舎」から学ぶことによってしか、
完結しないのです。
そして、
その一貫教育の出発点となる「和田塾」「幼稚舎」では、
最初から英語を教科として組み込んだのです。
和田義郎も英語の授業で教壇に立ちましたが、
さらに寄り寄り英語教育を取り入れるために、
開校から5年後の1879年には、
ネイティブスピーカーであるアメリカ人教師を雇い入れています。
今でこそ、英語の授業を取り入れる私立の小学校は珍しくありません。
2020年度から、
いよいよ全国の小学校5・6年生で英語が正式に教科化されることになりました。
それを140数年前から慶應義塾では行っていたのです。
3)国内屈指の「英語教育」

「慶應義塾幼稚舎」では、
長年の経験によってカリキュラムが確立しています。
1年生から3年生は、歌や遊びを通して英語に慣れ親しむ期間。
4年生以降は、少人数制を取り入れ、会話する機会を増やしています。
1992年から1999年にかけ、幼稚舎長を務めた中川真弥さんは、
英語科のカリキュラムを作るにあたって、次の5つの目的を挙げています。
①子供たちが英語は楽しいと思うような環境づくりをする。
②言葉は使ってこそ面白いことを子供たちに発見させる。
③英語が世界の共通語としての役割を果たしている現在、
コミュニケーションのツールとして有効であることに気づかせる。
④異文化に接する際に「顔は違っても根は同じである」という認識を
子どもたちがつくり上げることができる実際の場面をなるべく多く
提供する。
⑤世界のどんな人と会っても、自分らしい自然な振る舞いができるよう、
子どもたちを励ます。
幼稚舎の英語教育が目指すところは、
福澤諭吉先生が掲げる
「世界に通用する真の国際人を日本から輩出する」ことです。
英語を通して、
幼稚舎生に自然に国際間カウを身につけるにはどうしたらいいのか?
長い間時間をかけて導き出したのは、
子供たちに海外経験の機械を与えることでした。
中川真弥さんが舎長に就任すると、次々に実行に移していきます。
最初の試みは、
1994年8月に始めた『モホーク・デイ・キャンプ』です。
1990年に慶應義塾が中学3年生から高校3年生を対象にした
「慶應義塾ニューヨーク学院」を創設しました。
夏休みの期間は個々の学生寮が空くので、
幼稚舎が使わせてもらえることになったのです。
こうして安全が確保させる環境が整い、
準備期間がわずか半年足らずで実現することができました。
このキャンプは、アメリカ東部の子供たちを中心に、
毎年900人近くが集まる有名なイベントの一つです。
幼稚舎からは4~6年生の有志が参加しており、
1994年以降、現在までずっと続いている人気のプログラムになっています。
1995年からは、
イギリスのオックスフォードにある世界的な名門小学校
「ドラゴンスクール」との相互ホームステイが実現します。
毎春、
幼稚舎の6年生12人がドラゴンスクールに通う生徒の家庭に
ホームステイしながら、学校の授業を受けます。
また、秋には、ドラゴンスクールの生徒が来日し、
幼稚舎生の家庭にホームステイします。
これも現在までずっと続く重要なプログラムになっています。
イギリスでのプログラムでは、
6年生を対象にしたサマースクールもあります。
8人の生徒に一人のイギリス人教員がつき、
教室で英語の勉強や、野外でのフィールドワークが組まれています。
午前中は朝食後に、午後の活動ための英語の予習。
例えば、水族館に行く予定が入っているとしたら、魚や海洋動物の名前や海に関する用語など必要な単語を学習しておきます。
この他にも、水泳、川遊び、野外や名所でのスケッチ、
さまざまなゲーム、宿舎でのお菓子作りなど、
子供たちを飽きさせない企画がたくさん組まれ、
最終日の夜はディスコ大会。
濃縮した1週間があっという間に終わり、
一生忘れない思い出となるのです。
140数年にわたって試行錯誤を繰り返して創り上げてきた
英語教育の歴史は、決して他校では真似できない成果なのです。
4)全国で注目される「幼稚舎の理科」

英語と並んで、
幼稚舎が圧倒的に力を入れているのが「理科」です。
幼稚舎が授業に理科を取り入れたのは、
英語と同じく、学校が開校した1874年。
かつて蘭学を学んだ福澤諭吉先生は、
科学的分野を非常に重視していました。
ただし、
まだ科学を総合的に取り扱う「理科」という科目はなく、
幼稚舎の授業では、地質学、生物学、博物史などに細分化されていました。
その後、生物学、化学などが科目として加えられていきました。
科学全般を網羅する「理科」として採用するのは1892年。
公立の小学校ではすでに1886年に採用されており、
幼稚舎があとから採用されたのです。
しかし、
1991年、「幼稚舎の理科」が注目を集めることになります。
それは、
小学校としては日本で初めて、理科実験室をつくったからでした。
幼稚舎が三田の山の上にあった時代で、
そこに木造2階建ての本格的な実験室を建造したのです。
この時から、
理科の授業はクラスの担任ではなく、
科学の専門的知識をもつ専科教員が受け持つことになりました。
「幼稚舎の理科」は、ひとつのブランドとして定着しています。
特別視される最大の理由は、
理科の専科教員の間で継承されてきた基本となる哲学があるからなのです。
それは、「直接経験重視」と「採集理科」の2本柱です。
①「直接経験重視」
「直接経験重視」とは、自分の目で対象物を直接、観察することです。
教科書を見て、
文字、表、絵、写真などから情報を得るだけでは不十分です。
現代社会においては、
パソコンやスマートフォンでインターネットを開けば、
大半の情報は簡単に得られることができます。
パソコンやインターネットを使いこなすことは、
重要ですが、自分の頭で考える前に、
そうした手段で情報を引き出すことが日常化してしまうと
成長期にある子どもにとって、プラスにはならないのではないでしょうか。
本やインターネットから情報を得るやり方にに慣れても、
それは決して考えることにはつながりません。
情報が氾濫するこの時代に大切なのは、
自分の頭で考える習慣を身につけることなのです。
それは、
福澤諭吉先生が提唱する「独立自尊」の精神につながります。
その意味は、
「自他の尊厳を守り、何事も自分の判断・責任で行う」ということ。
つまり、
大事なのは自分で物事を見極める能力を養うことなのです。
当然ながら、それは幼いうちからの経験によって身に付くのであり、
幼稚舎の使命はその支援をすることにあります。
幼稚舎では、子供たちのそのような能力を向上させるための教科として、
理科が位置付けられているのです。
子ども自身が実験を行い、
何が目の前で起こるのかを自分の目で確かめる。
本を読むだけでは決して得られない生きた情報を
目、耳、鼻、肌、さらには場合によっては舌で感じ取るのです。
②「採集理科」
「採集理科」とは、文字通り採集することです。
昆虫、魚介類、植物、化石、鉱物などを、
子供たちが自分の手で採集する大切さを表したものです。
その場で自然と触れ合うだけではなく、
採集したものを持ち帰って、じっくり観察することもできます。
さらには、
昆虫やゴカイ類を飼育したり、植物を育てることによって、
生き物のの成長や変化を追うこともできるのです。
その場所での採集が規制されている場合、
スケッチしたり、デジタルカメラなどで写真や動画を撮影して授業で活用します。
また、教員が採集してきたものを教室に運び、
それを子どもに観察するような授業も行っています。
毎年6月初めに8~10泊の日程で行われる6年生の高原学校では、
山菜採集を行います。
子供たちがより楽しむことができるように、
ゲーム要素を取り入れています。
子供たちをグループ分けをして、採集を開始します。
教員があらかじめ指定した山菜を採ってくると、
その数に応じて、ポイントが科せられます。
反対に、間違って毒のある植物を採集したら、ペナルティが課せられます。
そのようにして、グループごとにポイントを競うのです。
そうして、
「採集理科」を楽しんだあと、
今度は舌で「直接体験重視」を実体験します。
採集してきた山菜を自分たちで調理して、旬の味を堪能するのです。
子供がいかに面白がり、楽しめるかを最優先し、
遊び感覚で学習に取り組むことができる環境をつくり、
無理なく子供の意欲を髙めていくのが幼稚舎教育の神髄
なのです。
5)幼稚舎最大の教育システム「6年間担任持ち上がり制」

幼稚舎の教育システムの最大の特徴は「6年間担任持ち上がり制」です。
6年間、クラス替えがなく、担任教諭もかわらないという制度です。
1
897(明治30)年、
森常樹さんが第4代舎長に就任すると導入され、
それ以来ずっと続いています。
森常樹さんは、
熊本の士族の家に生まれ、
西南戦争の官軍側として参加したのち、東京に進学。
慶應義塾に入学し、首席で卒業します。
福澤諭吉先生の次男、捨次郎さんと同級だったことから、
福澤家にもたびたび出入りをしており、
福澤先生からの信頼も厚く、
乞われて幼稚舎で教鞭をとるようになりました。
なぜ、
6年間担任持ち上がり制を進めようとしたのかは定かではありませんが、
ちょうどこの前後に、慶應義塾の学事改革が進められていて、
それが影響したのではないかと考えられています。
1898年の学事改革により、
幼稚舎は正式に慶應義塾の初等科という位置づけになり、
6年制になり、
それに合わせる形で6年間担任持ち上がり制が導入されることになります。
これまで年齢がばらばらだったものが学事改革により
学年ごとの年齢がほぼ横並びになり、
各教科ごとに教員が異なる専科制度は維持しつつ、
その一方で各クラスを見守る担任の重要性が増し、
6年間担任持ち上がりという制度が浮上したのでした。
学力がまちまちの子供たちが同じクラスに入ることになる。
しかも、
小学生の頃は成長の度合いにも子供によってかなり差があります。
担任はそうしたものを見極めながら、子供たちと接しければなりません。
そのため、
1年ごとに担任がころころ替わるより、
子供たち一人ひとりをしっかり把握している教員が
6年間ずっと見守る形の方がうまくいくと考えたのです。
6)最先端を取り入れる「情報教育」

幼稚舎では、「教科別専科制」を敷いて、
担任が教える科目と、専科教員が教える科目が分かれています。
担任は、国語、社会、算数、生活総合、体育の一部を受けもち、
それ以外の科目を専科教員が受け持ちます。
専科授業としては、
英語と理科以外に、音楽、絵画、造形、体育、習字、情報があります。
これら専科科目の中で、特に注目するのは「情報」です。
3年間を試行期間を経て、
2001年度から1~6年生の全学年が学ぶ教科として、正式採用されました。
全科目の中で、もっとも新しい科目です。
情報科のカリキュラムは、
1~2年生はマウスの操作、キーボードでローマ字入力、ファイルを開く、などの基本操作ができるようにすることが目標です。
1年生は、
ウィンドウズのグラフィックソフトウェア「ペイント」を使ったお絵描き。
さらには、
パソコン基礎ソフトスキル教材「ポケモンPCチャレンジ」でマウス操作の
練習をする。
2年生は、
お絵描きソフト「キッドピクス」で絵を描いて、
そのファイルを保存したり印刷したりします。
3~6年生はデジタル作品作りに挑戦します。
パワーポイントやワードを使いこなせるようにします。
5~6年生はパワーポイントを使って、
研究発表するためのデータをまとめることを目指します。
また、
6年生ではエクセルを使いこなせるようにして、
クラス内のアンケート調査をグラフを使ってまとめて、
その結果を基に考案する。
さらには、
インターネット上の著作権にまつわる問題を取り上げて、
その取扱いについても学んでいきます。
いずれにしても、楽しくなければなかなか身に付きません。
パソコンになじむことができるように、
遊び心を前面に出して行っているのです。
これまで慶應義塾幼稚舎の教育内容について見てきましたが、
いずれも子供にいかに楽しく学問に触れさせるかを重視する教育観で
あふれています。
次回は、福澤諭吉先生の教育観に触れながら、
学ぶ上で大切な考え方について見つめなおしていきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民一人一人が良心を持ち、
それを道標に自らが正直に、勤勉に、
かつお互いに思いやりをもって励めば、文化も経済も大いに発展し、
豊かで幸福な生活を実現できる。
極東の一小国が、明治・大正を通じて、
わずか半世紀で世界五大国の一角を担うという奇跡が実現したのは
この底力の結果です。
昭和の大東亜戦争では、
数十倍の経済力をもつ列強に対して何年も戦い抜きました。
その底力を恐れた列強は、
占領下において、教育勅語と修身教育を廃止させたのです。
戦前の修身教育で育った世代は、
その底力をもって戦後の経済復興を実現してくれました。
しかし、
その世代が引退し、戦後教育で育った世代が社会の中核になると、
経済もバブルから「失われた30年」という迷走を続けました。
道徳力が落ちれば、底力を失い、国力が衰え、政治も混迷します。
「国家百年の計は教育にあり」
という言葉があります。
教育とは、
家庭や学校、地域、職場など
あらゆる場であらゆる立場の国民が何らかのかたちで貢献することができる分野です。
教育を学校や文科省に丸投げするのではなく、
国民一人一人の取り組むべき責任があると考えるべきだと思います。
教育とは国家戦略。
『国民の修身』に代表されるように、
今の時代だからこそ、道徳教育の再興が日本復活の一手になる。
「戦前の教育は軍国主義だった」
などという批判がありますが、
実情を知っている人はどれほどいるのでしょうか。
江戸時代以前からの家庭や寺子屋、地域などによる教育伝統に根ざし、
明治以降の近代化努力を注いで形成してきた
我が国固有の教育伝統を見つめなおすことにより、
令和時代の我が国に
『日本人のこころ(和の精神)』を取り戻すための教育の在り方について
皆様と一緒に考えていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
