
自立した学び手を育てるための一手『慶應の教育』に学ぶ智の教育観(完結編)~「慶應の教育」に学ぶ智の教育観とは?~ー『日本人のこころ』21
こんばんは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
いよいよ5月も最終週となりました。
だんだん初夏の気候になっています。
今回は、
いよいよ『慶應の教育』の集大成です!
創始者である
福澤諭吉先生の考え方から学んでいきましょう!
今回も、
最後までお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
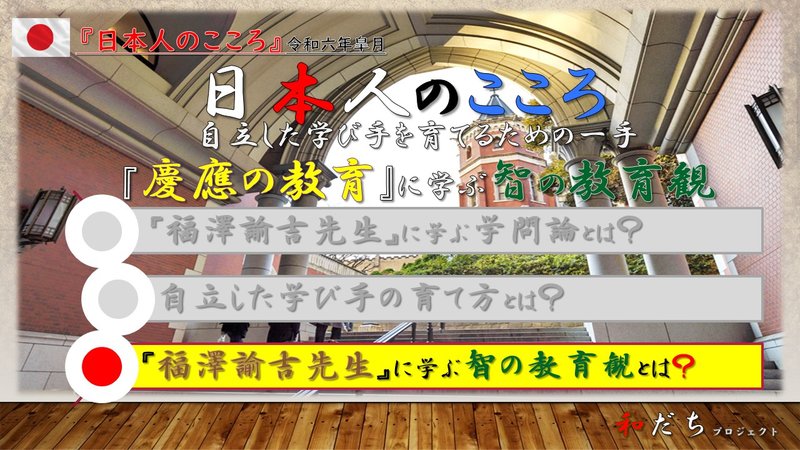
これまで慶應義塾幼稚舎の教育内容について見てきましたが、
いずれも
子供にいかに楽しく学問に触れさせるかを重視する教育観で
あふれています。
最後に、福澤諭吉先生の教育観に触れながら、
学ぶ上で大切な考え方について見つめなおしていきたいと思います。
1)『独立自尊』の真意を問う

福澤諭吉先生は、
「自立した国」「自立した人間」を育てることを目指しました。
では、
なぜ「自立した国・自立した人間」を目指したのでしょうか。
明治に入り、
我が国は一般市民の生活にも西洋の文化が入ってくる
激動の時代を迎えます。
慶應義塾では、洋学の普及に努めましたが、
それは、
外の世界を知り、
日本人としてしっかりと自分の足で立つ『独立心』を
身につけてほしいという思いがありました。
そして、
その心がひいては「日本の独立」につながると考えていました。
国民一人一人が学ぶことで、日本という国を強くしたいと考えたのです。

『独立の精神』は
福澤諭吉先生の生きた明治時代だけではなく、
令和時代を生きる私たちにとっても大切な考え方だと思います。
人生は、
生まれや家柄によって決まるわけではなく、
「学んだか、学んでいないか」
つまり、「個人の努力」によって決まる。
家柄の低い武士の家に生まれ、
差別さながら育った福澤先生ならではの考え方です。

学問をするにあたっては、
自分が何をすべきか、
つまり「義務」を知ることがとても重要となります。
人は、生まれながら、何にも縛られない存在です。
しかし、
ただそのことを言い張って義務を知らなければ、
ただのわがままになります。
自由とわがままを区別するのは、
他人の害とならないかどうかです。
酒や色事にふけってやりたい放題するのは、
一見自由でまわりに影響していないように見えます。
しかし、そうではありません。
一人の勝手放題は悪い手本になります。
やがて世の中の風俗を乱し、
人としての正しい生き方を邪魔することになるのです。

一人の人間も一国も、何物にも縛られない自由な存在です。
もしも、
この国の自由を妨げようとする者がいたら、
世界中を敵に回そうとも恐れる必要はありません。
とは言うものの、
人にはそれぞれ境遇というものがあって、
相応の才能や徳を身につけるには、物事の道理を知る必要があります。
道理を知るためには、学ぶ必要があります。
だからこそ、学問を始めなくてはならないのです。

世の中で、無知、文盲な国民ほど哀れなものはありません。
知恵のなさが極まると、恥知らずになります。
貧乏になって寒さや上に苦しむのは無知のせいなのに、
そういう人の限って反省もせず、
やたらとまわりの裕福な人を恨みがちです。
ひどいものになると、
徒党を組んで強訴だ一揆だと暴動を起こしたりします。
法律があるおかげで自分自身の身も安全で、
家々の暮らしも安泰なのに、
法を頼るだけ頼っておきながら、
私欲のために平気で法を破る。
これほど筋違いなことはありません。
「愚かな民の上には苛酷な政府がある」
という言葉がありますが、
政府がひどいのではなく、
国民が愚かで、国民が自らまいた結果ともいえるのです。
今の我が国も、国民の程度に応じて政府があります。
今の時代に生まれ、国のためになりたいという心がある人ならば、
大切なことは、
人の感情に寄り添った正しいふるまいをすること。
そして、
熱心に学問を志して広く知識を吸収し、
それぞれの社会的な境遇にふさわしい知識や徳を蓄えればよいのです。
そのようにすれば、
政府は政治を行いやすくなり、
国民は政府から支配されて苦しむこともありません。
お互いに利益を得ながら、
日本中の平和を守ることに専念すればいいのです。
これが学問をする所以なのです。
2)福澤諭吉先生に学ぶ『智の教育観』

では、
どのようにして学ぶことがよいのでしょうか?
知見をひろげる方法は3つあると、福澤先生は語ります。
それは、
①観察、②仮説、③読書です。
さらに、
④議論を通じて、知見を交換する。
そして、
⑤著書を記したり、⑥演説を行ったりすることは、
知見を広める手段になります。
人の見識や品行は、
ただ見聞が広いからというだけで高まるものではありません。
たくさんの本を読み、広く世の中の人と交際していても、
それでも自分自身の明確な意見を持てない人もいます。

では、
人の見識を高め、
それにふさわしい振る舞いができるようになるには
どうしたらよいのでしょうか?
それは、
物事の様子を見比べて上を目指すことです。
決して自己満足しないようにすることです。
人としての使命として、
一流の人物と見比べて、長所や短所を考えるのです。

ただ生活ができればそれでいい。
そのような考え方を多くの人がしてしまうと、
社会は成り立たなくなります。
会社の規模や給料といったステータスではなく、
「誰のために、どのように役立てるのか?」
を考えることで、
より高い活躍ができるようになるのです。
リーダーというのは、
先頭に立って道を切り拓いていく存在だからこそ苦労が多いもの。
人が切り開いたあとを歩こうとしても、新しい発見や考えは生まれません。
ビジネスでも人がやっていない分野に挑戦する気概が大切なのです。
いつの時代も新たな挑戦をできる人が成功をつかむものなのです。

学ぶ人が増えていくと、
一人一人に判断力がつくので、
国がおかしなことをやろうとしても、
きちんと抗議することができます。
学ぶことが抑止力になるのです。
学ぶ意味とは、
自分の頭で考え、物事を判断する力を得ることにあります。
「バカでも構わない」
「お金さえ儲ければいい」
という価値観が主流になった時、国は亡国の道を歩み始め、
私たちの未来は真っ暗なものになってしまうのです。

みなさんは、
困ったことがあった時に、すぐに人に頼っていませんか?
人に頼るばかりでは困難を乗り越える力は身に付きません。
自分で物事を考え、判断していくというのは、
いわば、生きる力を養っているともいえるのです。
人生でどうしていいか困った時には、
まず自分の頭で考える習慣をつけましょう。
正しいかどうかを考える必要はありません。
仮説を立て、解決策を導く。
そのうえで
その考えが正しいかどうかを周りに聞き、助言をもらうのです。
福澤諭吉先生が、最も伝えたかったことは、
「自分の足で立って、考え、行動する力を養うこと」
です。
「学問を通じて、
人は生まれながらの状況や立場を変えていくことができる」
ということです。
社会人になって、
仕事をしていく中で、徐々にやりがいや目的を見失い、
何のために働いているのか、
何のために生きているのかに迷うこともあるかもしれません。
忙しさに身を任せていると、
いつしか何のために働くのか、何のために生きるのか、
その方向を見失ってしまうことがあるかもしれません。
そのような時にこそ、
今、目の前に与えられたことを全力でこなしていけばよいのです。
すると、
いつしかその時の経験が自分の成長の糧となり、財産になっていくのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民一人一人が良心を持ち、
それを道標に自らが正直に、勤勉に、
かつお互いに思いやりをもって励めば、文化も経済も大いに発展し、
豊かで幸福な生活を実現できる。
極東の一小国が、明治・大正を通じて、
わずか半世紀で世界五大国の一角を担うという奇跡が実現したのは
この底力の結果です。
昭和の大東亜戦争では、
数十倍の経済力をもつ列強に対して何年も戦い抜きました。
その底力を恐れた列強は、
占領下において、教育勅語と修身教育を廃止させたのです。
戦前の修身教育で育った世代は、
その底力をもって戦後の経済復興を実現してくれました。
しかし、
その世代が引退し、戦後教育で育った世代が社会の中核になると、
経済もバブルから「失われた30年」という迷走を続けました。
道徳力が落ちれば、底力を失い、国力が衰え、政治も混迷します。
「国家百年の計は教育にあり」
という言葉があります。
教育とは、
家庭や学校、地域、職場など
あらゆる場であらゆる立場の国民が何らかのかたちで貢献することができる分野です。
教育を学校や文科省に丸投げするのではなく、
国民一人一人の取り組むべき責任があると考えるべきだと思います。
教育とは国家戦略。
『国民の修身』に代表されるように、
今の時代だからこそ、道徳教育の再興が日本復活の一手になる。
「戦前の教育は軍国主義だった」
などという批判がありますが、
実情を知っている人はどれほどいるのでしょうか。
江戸時代以前からの家庭や寺子屋、地域などによる教育伝統に根ざし、
明治以降の近代化努力を注いで形成してきた
我が国固有の教育伝統を見つめなおすことにより、
令和時代の我が国に
『日本人のこころ(和の精神)』を取り戻すための教育の在り方について
皆様と一緒に考えていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
