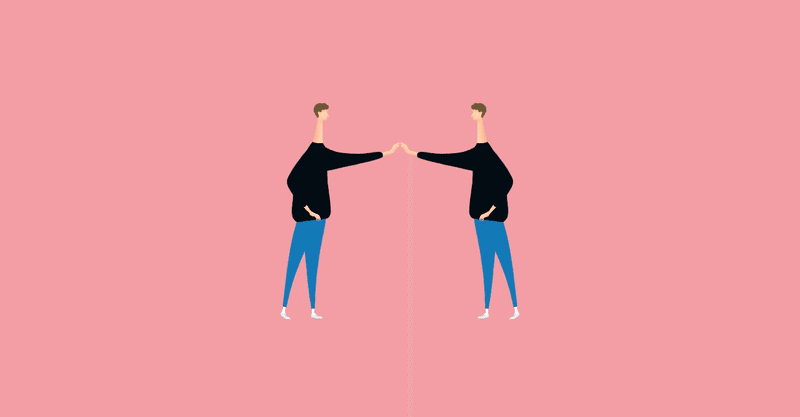
【書評】上野千鶴子『女ぎらい:ニッポンのミソジニー』②―男性論としてのミソジニー
前回の記事は、上野千鶴子の『女ぎらい』を読むための基本的な知識として、「ミソジニー」とは何なのかについて紹介し、第1章の内容について触れるところでいったん切りました。
今回の記事では、より本書の深い内容に入っていきたいと思います。
〇上野千鶴子の知識を借りる
本書の文体は全体的にエッセイと批評の間くらいで、言っていることの複雑さのわりにかなり読みやすく仕上がっています。
しかし書き手があの上野千鶴子ですから、文章全体に社会学の様々な知見が散りばめられています。
「あの上野千鶴子」と言っても、ご存知ない方もいるかもしれません。Wikipediaからの引用になりますが、一応上野千鶴子について、紹介しておきましょう。
上野千鶴子(1948年~)は、日本のフェミニスト、社会学者。専攻は、家族社会学、ジェンダー論、女性学。東京大学名誉教授。NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長、日本社会学会理事、元関東社会学会会長(2005年~ 2006年)、日本学術会議会員、シューレ大学アドバイザー、「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」共同代表を務める。
※引用はWikipediaの「上野千鶴子」項より。ただし、読みやすくするために表現を一部改めました。
ずらずらとすごそうな肩書きが並んでいますが、実際にすごい人です。日本のフェミニズム、あるいはもっと大きく言って社会学を語るうえで欠かせない人物ですし、多種多様な論文で彼女の知見が引用されています。
すごい人なので、すごく広い範囲の知識を有しておられます。なので本書を読み進めるだけで、断片的にではありますが社会学の様々な知識を得ることができます。
例えば、第2章では社会学者作田啓一の議論を紹介しつつ、「なりたい欲望」と「持ちたい欲望」という観点からホモソーシャルな集団について説明しています(「ホモソーシャル」という用語については、前回の記事でも説明していますので、よろしければご覧ください)。
フロイトの理論を踏まえた「なりたい欲望」と「もちたい欲望」、精神分析的な家族論として理解することができます。上野の解説を引きましょう。
「父と母から生れ、家族の三角形の中で育つ子どもにとって、父に同一化し、母(と似た者)を「持ちたい」と思った者が「男」となり、母に同一化し、父(と似た者)を「持ちたい」と思った者が「女」となる。現実の母を所有することはできないから(すでに父親によって所有されているので)、母のような者を求めて、母の代理人を妻に求める者が異性愛の男となる。他方、自分と同様に母にファルス(象徴としてのペニス)がないことを発見して父のファルスを欲望した者は、ファルスの代用品としての息子を求めて母に同一化することで、異性愛の女になる。すなわち、「なりたい欲望」と「持ちたい欲望」を異性の親にそれぞれふりわけることに成功した者だけが、異性愛の男もしくは女となる。」(第2章「ホモソーシャル・ホモフォビア・ミソジニー」より)
※ここでいう「男」や「女」が生物学上の性別と一致しないことに注意してください。性別については、少なくとも生物学的(sex)/社会的(gender)/性的志向(sexuality)の3つの観点から考える必要があります。例えば、生物学上は女性のトランスジェンダー男性が、性的には男性を好きになるというケースを想像してみてください。
前回の記述とつなげれば、「持ちたい欲望」を持つものは性的主体として、「なりたい欲望」を持つものは性的客体として位置づけられることになります。
上野はセジヴィクを参照しつつ、ホモソーシャルな集団は性的主体である「男」たちによって構成されるので、互いのまなざしは常に相手を性的客体化する危険があることを論じます。つまり、ホモソーシャルな集団はホモセクシュアルを内側に抱え込むわけですね。それを否定しようとする身振りにより、ホモフォビアが加速します。
そこから上野は、「男」の歴史を「持ちたい欲望」と「なりたい欲望」の調整の歴史として再設定します。それは差別の歴史と重なってきます。前回も申し上げた通り、集団の同質性は異質なものの排除によって担保されるからですね。上野はそれを説明するのに、社会学者佐藤裕の次のような言葉を引いてきます。
「差別とは、ある人を他者化することによって、それを共有するある人と同一化する行為である」(佐藤裕『差別論―偏見理論批判』)
ここまで記述してきたことの、簡潔にして要を得た答えですね。
ここでは主に第2章の内容に注目してきましたが、本書にはこうした社会学の知見が随所に登場します。
本書巻末の参考文献一覧にはおおよそ150にも及ぶ論文・書籍・資料が記されています。この量の書籍を自力で読むのは相当な手間でしょう。しかし私たちは、上野千鶴子の知識を借りることで、間接的にそれら150の資料にアクセスできるというわけです。
〇「もてない男」の問題
本書の第4章「「非モテ」のミソジニー」と題して「もてない男」の問題について扱っています。私がこの章に関心を抱いたのは、小谷野敦『日本売春史―遊行女婦からソープランドまで』で同じ問題が扱われていた時に「面白いな」と思った記憶があるからです。
※小谷野さんにはまさしく『もてない男―恋愛論を超えて』と題した新書もあるのですが、そっちはまだ読めていないので宿題にさせてください。
小谷野の「もてない男」論は、簡単に言えば恋愛至上主義へのカウンターであり、恋愛至上主義の世の中において恋愛できない男はどうするのか、という問題を提起しています。そのうえで『日本売春史』では、「もてない男」がいるからこそ性風俗が必要とされるのだという議論を展開しています。
小谷野に限らず「もてない男」、性的弱者として男性を規定する論はしばしば見かけるところですが、この手の議論はなかなか厄介です。「弱者」という言葉から「社会的弱者」=マイノリティに「もてない男」をつなげられるからですね。レトリックの上だけでもマイノリティにつなげられてしまうと、批判には慎重な手続きが求められます。
しかし、上野はそうした議論に真っ向から挑みます。彼女は、「もてない」論がもてない「男」の理屈でしかないことを批判します。
上野によれば、男性が全員結婚できる社会とは、女性から見ると結婚以外の選択肢がない社会です。女性に結婚以外の選択肢が多い社会では未婚率と離婚率が上がる傾向にあり、必然的に「もてない男」は発生します。逆に言えば、「もてない男」は自らが性的主体となるために、女性の選択肢を縛ろうとしているのだ、ということになります。もちろん売買春の問題も同じラインの上にあります。
このような構造をもつ「もてない男」論が、ミソジニーに行きつくことは想像に難くありません。「もてない」ことの原因を自らの内面性に求めない思考は、「見た目だけで判断する女ばかりだから、自分に彼女ができないのだ」という方向へと簡単に流れるからです。
そうした男たちに対し、上野はコミュニケーション力の必要性を説きます。結局それに落ち着くのか、とも思ってしまいますが、「もてない」ことを改めて個々人の問題に返して検討した場合、「関係性を構築できない」ということになりますから、なんだかんだまっとうな見解でしょう。やや定型的すぎる気はしますが。
そうなると次に必要とされるのは「もてない男」のためのコミュニケーション論ですが、この第4章はコミュニケーションの必要性を説くところで終わっています。
「片手落ちじゃん」と言いたくなるかもしれませんが、それは上野の責任ではありません。「もてない男」のコミュニケーション論は、結局のところ「もてない男」自身が立ち上げなければならないからです。
本書が論じているのは「ミソジニー」であって、男性がどのようにして主体を立ち上げ、関係を構築するべきか、という議論を行う責任は上野にはありません。
しかし、女性を排除することで「男」になるというミソジニーの構造について論じている本書は、確かに男性の主体構築を考える糸口を示しているようにも思われます。
次回の記事では、書評の締めくくりとしてミソジニーと男性主体のことについて検討したうえで、本書の欠点にも言及します。
よろしければサポートお願いします。
