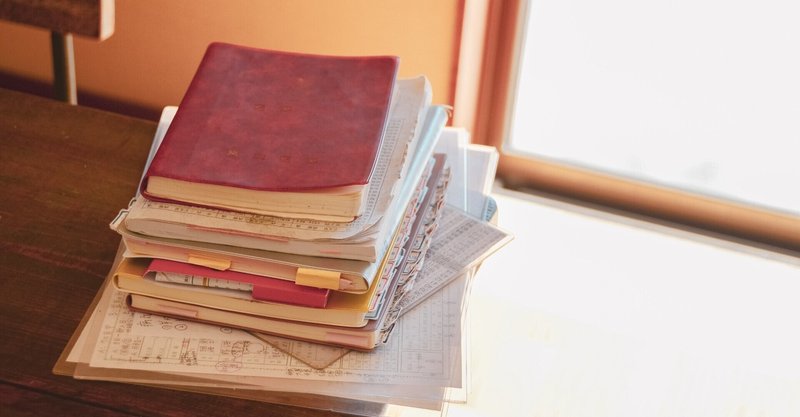
国語教育に多読を!―精読主義批判
国語教育に関しては、教育業界でも文学研究業界でも喧々諤々の議論が繰り広げられ、さまざまなトピックが提出されてきました。
高校のカリキュラムに古典は本当に必要か、文学研究と国語教育とのあいだをどうつなぐか、いかにして実のあるディスカッション、アクティブラーニングを行うか……ここには論じられるべき数々の問題点があります。
そのどれも個人的に興味のある問題なのですが、この記事ではシンプルな問をひとつ立てたいと思います。
国語教育は精読に偏り過ぎなのではないか?
○国語教育と精読
僕はいままで8年間ほど教育関係の仕事に携わり、多くの授業を見てきました(ただし中高の先生として勤務したことはないので、そこは割り引いて聞いてください)。
そしてつねづね思うのが、「国語科はどうしてこんなに丁寧に授業を進めるのだろう……」ということです。
例を挙げましょう。たとえば、評論教材なら1コマで進むのは多くて2ページ。10ページの評論なら、最低限5コマ+まとめ1コマくらいはかけて授業されます。
古典はもっと丁寧です。1コマで1段落しか進まない場合もあります。文章が短いからそれでなんとかなっていますが、4ページほどの教材が4,5コマかけて教授されます。
なるほど、たしかに丁寧なのはいいことです。言葉とゆっくり向き合い、多様な言語活動を行うのは国語教育の本分でしょう。僕も丁寧な読みの重要性には同意します。
しかし、こうした精読主義には根本的な問題があるようにも感じます。4時間も5時間もかけて1つの教材を読む。それって面白いでしょうか?
○精読は退屈である
これは完全に僕の主観と経験による意見ですが、高校の科目の中でも生徒に特に不人気なのは数学と古典です。数学はその難解さゆえですが、何人かの生徒は古典に対して「退屈さ」を指摘します。
1コマかけて1段落進める授業。たしかにそこでは、細かい古典文法の知識や、当時の文化的背景、古文単語などを学ぶことができます。しかし、いくらもともとの話が面白くても、そんなにゆっくり、繰り返し読まされては、楽しいものも楽しくなくなってしまいます。
多くの場合非常に丁寧になされる古典文法についての解説も、どの程度必要なのか批判的な検討がなされるべきです。高校の古典は大抵本文の学習と文法の学習が並行して進んでいきますが、生徒がある程度古文に親しんでからでなければ文法事項のありがたみや面白さは伝わらないのではないでしょうか。
少なくとも、助動詞「む」や「べし」の意味を6つ覚えて識別、断定の「なり」と推定の「なり」の識別、補助活用うんぬんなど古典というよりはパズルゲームのような煩瑣な文法事項の教授が学校教育においてどのような意味をもっているのか、改めて問い直されてもいい気がしています。それなら、くずし字を学ぶほうがよっぽど古典に触れる教育としてはいいのではないでしょうか。
細かすぎる文法教育が、古典の精読主義→授業進行の遅延→古典の退屈さにつながっています。
もちろんこれは現代文でも同じです。あまりにも丁寧に進む授業は、文章を読む本来的なスピードを混乱させ、生徒から読書の楽しみを奪います。
僕は文学の研究者なので、精読することで初めて引き出される文章の面白さというものは知っているつもりですが、それを楽しませるには教師の腕前と生徒の国語的素養が求められます。精読の面白さを理解してくれる生徒は、必ずしも多くはないでしょう。
国語における精読主義は、国語の授業の退屈さにつながってしまっているのではないでしょうか。
○精読+多読
僕の主張は、国語科の精読主義をなくせ!という過激なものではなく、精読に加えて多読を取り入れてもいいのではないか、という極めて穏当なものです。これが国語教育でなく読書論の話だとすれば、質と量が車の両輪だということは一般常識の類のはずです。ならば国語の教材でも同じことが言えるのではないでしょうか。
そして、リテラシーを鍛える上でもいくつかの情報を並べて読む訓練は重要なです。特に、ポスト・トゥルースの時代だといわれる現代では、情報を多角的に見る能力は必須技能でしょう。実際、賛否両論ありますがセンター試験改め共通テストの国語でも多数のテキストを並べて読む能力が求められるようになっています。
今までのように5、6時間かけて1つの教材を読むような単元と、同じ作者やテーマで集められた複数の文章を読む単元とを混ぜてみてはどうでしょう。あるいは、中心となる教材を丁寧めに扱ったのち、関連するいくつかのテクストを読み比べてみるのもいいでしょう。ハイブリット型です。
こうした多読の取り組みからは、さまざまな授業実践の可能性が生まれます。
たとえば『源氏物語』。教科書で扱われることが多いのは「桐壷」「若紫」「葵」あたりでしょうか。これだけだと、古典の王様を扱うにしては読む分量が少なすぎ、物語の全体像が全くつかめません。物語のクライマックスとなる「若菜」や、紫の上の死を描く「御法」、源氏の死後の物語である宇治十帖ぐらいは触れたいところです。玉鬘系列のストーリーも重要ですね。
ただ、難しい作品なのでさくさくとは読めないかもしれません。なら、もはやそれも古典となりつつある与謝野晶子訳や谷崎潤一郎訳で、つまり現代語訳でストーリーを追ってもいいと思います。そこに最新の角田光代訳も並べて、原文と複数の翻訳とを読み比べるというのも面白そうです。
あるいは、「葵」から話を広げて謡曲「葵上」、さらに三島由紀夫の『近代能楽集』の「葵上」とつないでいけば、ある作品がのちの時代にどのようにアダプテーションされていくかという、文化受容の過程を学ぶ授業にもなり得ます。
芥川の「羅生門」をやるにしても、中期の開化ものや保吉もの、後期の「点鬼簿」「歯車」などと並べて読めば、作家の全体像がぼんやりとでも分かってくるでしょう。
また。山崎正和の「水の東西」でも、同時期の評論をいくつか読むことで当時が日本文化論ブームだったことを体感できますし、のちの日本文化論批判と合わせて読むことで批判的な読書のあり方を学べます。評論教材は特に書かれた年代が無視されやすいですが、評論とは多くの場合その時代に対して書かれるものなのであり、周囲にどのような言説が存在していたのかを知ることは非常に重要です。
その点、精読主義は歴史性に欠けます。国語の必須カリキュラムから文学史が抜けているというのがそもそも大きな問題ですが、1つ1つの教材を丁寧に読んでいけばそれ以外のテクストを読む時間がなくなり、周辺の文章は暗記のための「名前」でしかなくなります。授業中に関連するテクストをいくつか並べて読むことで、その教材がタテとヨコにどのように広がっていくのか、見通しがつくようになるはずです。
僕はいまの生徒が漱石・芥川・太宰・三島を時代順に並べられなかったとしても驚きませんが、それは果たして生徒だけの問題でしょうか。
○多読主義の問題点
たしかに、多読の試みにはいくつかの問題点があります。
たとえば、授業のスピードについていけなくなる生徒が出るのではないかという問題。多くの教材を読むなら1つ1つの教材にかけられる時間は減りますから、教材の理解にムラができやすくなることが予想されます。
このあたりについては、従来の精読主義の国語教育と考え方を変える必要があります。教材を並べて読んだときにどのような理解ができるのかということに重点を置き、個々の教材理解は表面的な次元であってもひとまず良しとすべきでしょう。
また、教員の教材研究の負担も懸念されます。複数の教材を扱うなら、それぞれの教材を読み込まなくてはなりません。授業で扱わないような深い内容も、多数の生徒を相手にしている以上誰かから質問が来る可能性があります。いまの学校教員に現状以上の負担を求めるのは不可能なので(それは制度設計上の問題も大きいですが)、指導書や副読本の内容を充実させる必要があります。
しかし、これらのデメリットを差し引いてもなおメリットのほうが大きいと考えています。
やはり、量が伴わなければ質も担保できませんし、小説も評論も全体的な部脈の中での位置づけが非常に重要です。多くの高校生や大学生が活字慣れしていないのも、国語教育の少数精読主義が影響しているかもしれません。
なにより、初めに述べたとおり精読はある程度の素養がなければ退屈なものです。新しい文章は、とりあえずその新しさというだけでも生徒の目を惹きます。授業中はどうせ寝るか読むかしかないのですから、電車の吊り広告を見るような感覚であっても、とりあえず文章は読んでくれるはずです。「数撃ちゃ当たる」とも言いますから、多読の中で生徒が好みの文章を見つけられるかもしれません。
国語教育は、もっと多読を取り入れてもいいのではないでしょうか。
○おわりに
読書に慣れている人なら、数を読むことの重要性は理解しているはずです。中学生高校生にその理屈が適用できないということはないでしょう。数学の授業を考えてみてください。大量の類題を解くという反復練習によって、各単元の理解度は深まるのです。
もちろん、すでに多読を実践している先生もいらっしゃると思います。しかし、そうした方は全体で見ればまだ少数でしょう。僕から見ると、国語教育はやや精読主義に囚われすぎているように見えます。
何度も言いますが、質と量は車の両輪だというのが読書法の基本です。国語科で量的な教育を行ってはいけない理由があるでしょうか?
精読主義の再検討が求められています。国語に、もっと多読を。
よろしければサポートお願いします。
