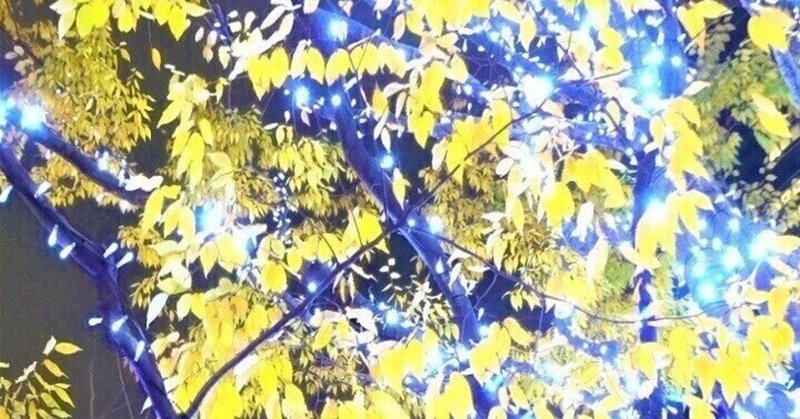
インターネットの人間関係
普通、人間関係というと学校とか職場が中心になるだろう。
だが私の人生は振り返ると、大半がインターネットを主軸にした人間関係だったように思う。
この前「最近コロナで人付き合いなくって…」と誰かが話しているのを聞いたが、当然学校とか職場中心の人間関係だった。
聞いてて「自分って結構特殊な人間関係を経てきてるんだな」と再認識した。
そこで今までのネットの人間関係を振り返ってみることにした。
年寄りがグダグダ昔話しているような纏まりのない文章になった。
昔話のくだりは正直読み飛ばしてくれていい。暇な人だけ読めばいいと思う。
mixiを始めた高校時代
初めて明確にインターネットの人と関わり合ったのは、高校時代にやったハンゲームだった(懐かしい)。
同級生の悪友に誘われて始め、社会人も交えて夜通し話しながらゲームしていた。
徹夜などした事もなかったただの高校生にとっては、ネットでの夜ふかしはまさに未知の体験だった。
友達は実際オフで会ったりしていたようだが、私は特に会ったりはしないで、ネットのみの関係だった。
しばらくするとmixiが流行り始めた。これがSNSライフの始まりである。
当時音楽ライブにハマっていた私は、好きなバンドのコミュニティ経由でオフ会に参加するようになった。
ライブ後など会場のそばで集まって、その場で軽く話すなりファミレス行くみたいな感じだ。
だいたい5〜10人、多い時はそれ以上いた。
安全性を考えて、少人数では会わないように心がけていた。
決定的だったのは、とあるフリーライブだ。
やはり「みんなで集まって一緒に楽しみましょう」みたいな書き込みを見て参加した。平日で学校があったがサボった。ちょっとした冒険心である。
そのフリーライブでかなり盛り上がった結果、コミュニティとして定着する。
コミュニティの構成メンバーは20〜30代が中心で、様々な人がいた。30人くらいいたのではなかろうか。
当時高3だった私から見ると、完全に未知の世界だった。
高校の友達はいない事もなかったが、コミュニティの大人達と比べたらおそろしく退屈でつまらなく感じられた。背伸びしたいお年頃というやつだろうか。
コミュニティ内の大人達は割と賑やかでアクティブな人たちだったのもあって、仲良いメンバーで夏フェス行ったりもしたし、ライブハウスを借りてDJイベントなんてのもしていた。
3年くらい入り浸っていたように思う。
mixiのそういったオフ会経由で、特に仲良くなった何人かでつるむようになった。歳も近かった。
その友達はバンドやってる専門学校生だったので、ライブも見に行った事があるし、学園祭も行ったりした。
その中の一人の家に集まってだらだらゲームやったりもしていた。
高校最後のマラソン大会が終わった途端に、直でその友達の家に向かったりしていた。もう高校の事などほとんど眼中に無かったのだ。
今思えばこれもまさに青春だったなと思う。
そんなわけで、高校生の頃はmixiコミュニティの大人達と関わったり、バイト先の大学生やフリーターとよく話していた。
そこで世の中には様々な人がいる事を知った。
その結果、大学行って卒業して就職するというレールに沿った人生がバカらしくなってしまったわけである。
青い鳥と囀り続けた20代前半
しばらくするとmixiが廃れ、Twitterが主流になってくる。20歳過ぎたくらいだろうか。
ミーハーな自分は当然Twitterを始めてみた。しかし使い方がイマイチ分からない。
”検索”と”ハッシュタグ”の使い方を理解してから、めちゃくちゃ活用するようになった気がする。
mixiの頃のようにライブを通じて知り合う人たちもいたが、Twitterはとにかくリナカフェの存在が大きかった。
リナカフェというのは当時秋葉原にあったごく普通のカフェなのだが、当時まだレアだったコンセントが使えるカフェなのもあって、重宝されていた。
リナカフェに行ってTwitterで「リナカフェなう」と呟くと「もしかしてフォロワーの○○さんです?」と話しかけられたりして、交流が始まる。そんな文化があった。
フォロワーのフォロワー、そのフォロワー…
だんだんと交流の輪が広がっていき、知り合ったばかりの数人でその後飲みに行くなんてのも度々あった。
秋葉原に入り浸っている時点で「アニメが好き」「PCが好き」などの共通点があるわけだ。その共通の話題で盛り上がったりした。
結局そのうちの何人かと特に仲良くなって、秋葉原で部屋を借りて6人くらいで溜まり場にする、なんて事もやっていた。
シュタゲの影響である。これも今思うと青春してたなぁ。
リナカフェに顔を出すようなTwitterの人間は、大学生から社会人、高校生もいたしとにかく様々な人間がいた。
この時期はリアルとネットの境目がない…というか、もはやネットがリアルみたいなところがあった。
”大人”と年齢は関係ない事を学んだIngress
20代も後半に差し掛かると、Ingressというゲームにハマり出した。
ポケモンGOの前身のようなスマホ位置情報ゲームである。ポケモンGOより対人要素が多い。
Ingressのコミュニティというと、今は亡きGoogle+中心だった。
Google+経由で地域ごとのハングアウトに入り、そこで情報共有などのやり取りをするのが主流だった。
プレイヤーは基本的に30〜40代の人間が多かった。
そのゲーム性から、財力と時間がある会社員が圧倒的に多かった。
オフ会というか、実際にプレイヤー同士顔突き合わせるようなゲームだったので、それでよく色々な人と会っていた。
当然近所のプレイヤーと多く関わる事になるので、その流れで飯に行ったりして仲良くなった人もいた。
ちなみに夫と出会ったきっかけもIngressである。ちょっと話が合って仲良くなったと思ったら気付いたら同棲して結婚してた。
夫もとんだ貧乏くじを引いたもんである。
でも毎晩深夜1-5時くらいIngressで出かけるのが許される夫婦関係というのも珍しい気がするので(今もなお続いている)、ある意味ラッキーだったんじゃないでしょうか。
当時の私にとって、30〜40代となると大人なイメージだった。実際、結婚して子供がいるような絵に描いた大人がたくさんいた。
そんな大人たちも時には領地争いでガキみたいにヒートアップしてレスバトルしてたし、人間の陰湿な部分も垣間見た。クソガキみたいな50代のおっさんもいた。もちろんいい人もたくさんいたけど。
年齢を重ねたからといって誰もがみな”大人”なわけじゃないんだなと悟ったのはこの頃だ。
今思うと、Ingressはゲームそのものより人間観察の方が面白かった。
ゲーム以外の事にも広がった某ゲームのコミュニティ
Ingressにも飽きてきた(というか人間関係のドロドロさに嫌気がさしてきた)頃合いに、某ゲームにハマった。
それ関係のコミュニティに出入りするようになった。
年齢層は10代後半〜40代くらい。大学生と20代の社会人が多かったように思う。
最初は当然ゲーム関連の話しかしなかったが、コミュニティ内で親しくなるにつれ、野球の話やキャンプの話で盛り上がった。
実際に何人かで一緒に野球を見に行った事もあるし、キャンプに行ったりもした。
きっかけは一つのゲームだったが、相手の事を知るうちに他の共通点が見つかるのはよくある。
そしてそういうタイプの人とはなんだかんだ長い付き合いになるなぁと思う。
さて昔話はこんなところか。
飲み屋の常連コミュニティ
いきなりネットの話ではなくなるのだが、飲み屋の常連客コミュニティとインターネットの人間関係はどことなく似ている。
個人経営のアイリッシュパブでバイトしていた頃の影響で20代前半、色々な飲み屋を1人で飲み歩いていた時期がある。
1つの飲み屋に足繁く通っていると常連客とよく会うので、当然顔馴染みの人が何人か出来る。店主とも親しくなる。
常連客同士お互い本名もろくに知らない。近所に住んでる事だけは分かるが、具体的にどこなのかも分からない。
大半は飲み屋だけで完結する関係だが、中にはめちゃくちゃ仲良くなる人もいる。
うん、ネットと似ている。
まあ最初から顔を突き合わせているところとか、20歳以上しか参加出来ない点、趣味じゃなくて地域の繋がりという点では違うが。
ネットの人間と会うのに抵抗がある人はまだまだ多い
SNS人口もすっかり増えた今日この頃だが、ネットの人間と会うのに抵抗がある人はまだまだ多いと思う。
まあ無理に会う必要もないんだが。危険な人だっているし、何でもかんでも会うのがいいわけではない。
私は上記の通りの特殊な人間関係を築いてきたので、いまやオンラインの人と会うのはあまり抵抗がない。
もともと首都圏在住でオフ会などに参加しやすいというのもあったのかなと思う。
1対1で会うのは相当仲良くなければあまりやらないが。危機管理は忘れてはならない。
ちょっと意外だったのが、学生時代からTwitterやLINEをやってる10代〜20代前半も、ネットの人に会うのは結構抵抗あるらしいという点だ。
しかしよく考えれば、Twitterなどやっているとはいえ基本はリアルの人間関係中心でフォロー・フォロワーを形成しているものだ。
なら全く知らない人と会うのに抵抗があるのも頷ける。
インターネット人間関係の利点
私が今でもインターネットに入り浸る理由。ネット中心で人間関係を構築する理由。
それは、刺激である。
インターネットの人間関係の魅力はズバリ、リアルでは絶対に会わないような人と交流する機会がある事だ。これが刺激になる。
高校生の私の世界を広げたのはインターネット。
20代前半接客業のフリーターやってた私がやたらPCに詳しくなったのはTwitterで交流した人たちの影響。
ネットが無かったら有名大学出て大手起業に勤めてるような優秀な人と交流する機会なんてまず無かったし、クリエイティブな職業に就いてる人とも関わり無かっただろう。
インターネットが私の視野を広げたし、世界は広く様々な人がいるという学びをくれた。生き方に正解など無い事も。
本を少し読んだ影響もあるが、ネットの人間関係がもたらした”経験”による影響はかなり大きい。
最近は自分の立てたDiscordの作業サーバーに入り浸っているのだが、そこでも様々な人がいる。
そもそも30代になってから中高生や大学生と直接話す機会など、それこそインターネット以外にほぼない。
自分の全く知らないような活動をしている人もいるし、すごいクリエイティブな人の活動の軌跡が垣間見れるのも面白い。
実を言うと、真面目に絵の練習をする気になったのはこのサーバーの影響である。
イラストを描く人が多いのでいい刺激になった。
立てた本人が言うのも何だが、なかなかいい場所である。
ネットの人間関係のいいところ その2。
困ったら切るのが楽。
ネットの人間関係もリアルと同じく、当然全てが上手くいくわけではない。
なかには合わずに上手くいかない時もある。
そんな時はブロックしてしまえばそれで関係は終わる。そうすれば後腐れなしだ(最終手段ではあるが)。
ブロックまでいかなくても、ちょっと連絡を取らなければそのままやんわりフェードアウト、なんて事も可能だ。
ネットで仲良くなる人がいても、結局こちらが教えなければ本名や住所、職場などは知らないわけだ。会わなければ顔すら知らない。
ネット上の関係さえ切ってしまえば赤の他人である。
職場の人間関係などだと、上手くいかない事があっても毎日顔を合わせなければならない。嫌すぎる。
まとめ
纏まらないけど雑に纏めちゃおう。
結局何が言いたいかっていうと、「インターネットで未知の人間関係構築するのも自分の知らない世界が垣間見えて結構面白いよ、視野広がるよ」という事だろうか。
家族、学校、仕事、ご近所付き合い…。
それだけだととてもとても狭く感じてしまう。
もし私の人間関係がこれだけだったら、私はもっと自我が弱くて何となく生きてるだけの人間だっただろう。
別にインターネットでも飲み屋コミュニティでもいいんだけど(飲み屋は今の情勢的に難しいか)、自分の未知の世界に飛び込んでみるのも悪くないんじゃないでしょうか。
そもそもこんな偉そうな事を言っているが、私の世界もまだまだ狭いな。
サポートして頂けたらとても嬉しいです。頂いたサポート金はイラスト本やツールなどの自己研鑽用、noteにおける創作の環境強化に使っていきたいです。
