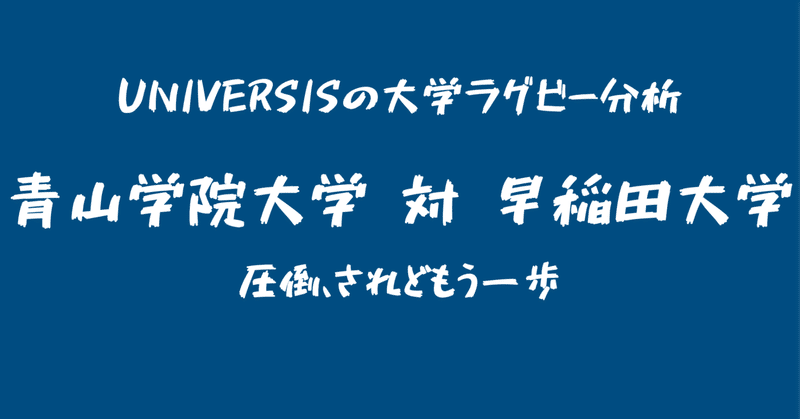
2023大学ラグビー関東対抗戦:青山学院対早稲田を簡単な数字で見てみた
みなさんこんにちは
少し間が開きましたが今日も分析です
今回は10/14に行われた関東大学対抗戦、青山学院大学対早稲田大学についてレビューをしていこうと思います
まずはメンバー表から

次いでスタッツです

それでは順番に見ていきましょう
青山学院のアタック・ディフェンス
青山学院のアタックシステム
基本的にはボックスキックを主体に50:50の確率でアタックを構築し、うまく獲得できればそこからアタックをしていくといったものが主な流れになっていたかと思います
一応はスクラムからの1stフェイズでサインプレーを使ったアタックでトライを取り切っていましたが、再現性が高いとは思えないのでおそらくメインの感覚は「キックからのアタック」にあったのではないかと思っています
アタック全体のイメージとしては、なかなか早稲田のディフェンスを崩すことができていませんでしたね
崩す以前にゲインを切ることができる選手も限られていて、8番の辻村選手などがメインキャリアーとして頑張っていたようには見えましたが、全体的に押し込まれてしまっており、そこからなんとか立て直すためにキックを用いているようにも見えました
アタック自体は9シェイプに3人を置くことを基本に、10シェイプを用いずFWのキャリーなら9シェイプ、BKでの展開なら外へ回すといったあたりを考えながらアタックしていたように思います
ただ、先述したようにFW戦の部分で前に出ることが叶わずにアタックのテンポが出ておらず、BKに展開しても早稲田がラックに人数をかけていないことから揃いきったディフェンスの壁に阻まれて効果的なアタックはほとんどできていませんでした
その中でアタックに活路を見出すとするならばダブルラインやトリプルラインのように階層的にアタックラインを敷いた構造かと思います
特にトライをとることのできた2つのアタックでは9番の亀井選手がループしながらバックドアへ移動してパスを受け取ることで人数的な優位を生み出し、外のランナーへ回しきってトライを取り切る形となっていました
早稲田のディフェンスも前に出るプレッシャーや対面の選手への意識が強い分、外に膨らみながらループプレーでもらう亀井選手に位置的な優位性を取られてしまっていたように思います
一方で2ndフェイズから続く一連のアタックでは効果的なアタックは見られず、意図的か結果としてそうなったのかはわかりませんがシンプルなアタック構造に終始していたと思います
一ついい形でアタックできていたのは前半のラストプレーでしょうか
15番の穴澤選手が階層的なアタックの中でいい位置とアングルでボールをもらい、最終的にはグラバーキックが外に出る形にはなりましたが、ほぼ崩しかけた状況だったように思います
このように、どのフェイズであっても階層的なアタックができればチャンスが作り出せるということは見えてきました
ただ、青山学院のアタックにはその部分の一貫性が見られず、選手内の意思統一やコミュニケーションは少し不足していたかなという印象です
ポジショニングの遅れやズレ、細かいミスを改善すれば早稲田相手にも十二分に戦うこともできたかと思います
逆に言えばその辺りが上位校との差かもしれませんけどね
青山学院のキャリー
目立って前に出ることのできたキャリアーはおらず、あえて言及するとしたら8番の辻村選手かと思います
残念なことに圧倒的な突破力というものは見られませんでしたが、体の使い方やあたり方がうまく、相手のタックルを受けても一発で倒れることなく前にじわじわと出ることができていました
惜しむらくはその前進もスピードがないために早稲田のディフェンスが容易に後ろに下がりながらディフェンスラインをセットすることができており、相手に対して優位なアタックへつなげることができなかったですね
BKの選手はパスを回すことが多く、積極的にキャリーをしていたのはセットピースからの1stフェイズでもらうCTBの選手だったように思います
一応はシェイプ外のエリアでもキャリーは生まれていますが、ある程度はFWの選手がキャリーをになっていたような印象です
詳細を見ていきましょう
キャリー回数は全体を通じて53回となっており、ポゼッション的にもアタックの質的にもかなり押し込まれていたと言える結果かと思います
ノックオンやフォワードパスなどハンドリングエラーとしてプレーが止まることこそ少なかったものの、ターンオーバーは合計で13回とかなり自分たちのミスで相手にボールを渡してしまっているということがわかります
キャリーとして最も多かったのは9シェイプでのキャリーによる20回のキャリーで、10シェイプでは1回のみキャリーが起きていました
シェイプ外のキャリーは15回と、回数的には少し少ないですね
ポッドでのキャリーが多く、展開をあまりしていなかった(できていなかった)ということが回数を見てもわかるかと思います
青山学院のパス
パスの質自体はもう少し高めることができるかと思いますが、パスそのもののミスはそこまで多くなかったように思います
もちろん表裏を使ったアタックなどの選手へスキル的・認知的負荷のかかるプレーがそこまで見られずにシンプルなアタックに終始したということも影響しているかとは思いますが、パス回しに関してはしっかり鍛えられているという印象でした
回数を見ていくとキャリー・パス比は5:8と若干パス優位のアタックをしていたように見受けられ、思っていたよりはパスを工夫してアタックをしようとしているといった結果が見られました
ただ、キャリーの項目でも述べたように長くフェイズを重ねることができずにミスでアタックが途切れてしまうこともあり、意図的にフェイズを重ねてアタックを繰り返していくという段階には持っていくことができていなかっったように感じます
パス回数を見ていきましょう
全体は80回、ラックからのパスのうち9シェイプへのパスが20回でバックスラインへの展開は9回となっています
少しFWでのキャリー・アタックに重きを置いているような形ですね
ただポッド内でのパスは見られず、ボールをもらった選手がそのまま相手にコンタクトするという形のキャリーがほとんどでした
バックスの選手がラックからボールを受けた後は、10シェイプへのパスが3回でバックスライン上での展開が16回となっています
そもそも10シェイプの位置に意図的にFWの選手が立っている様子もそこまでなかったので、決まりがそこまで厳密ではないか、もしくはポッドを生かし切ることができなかったのかもしれません
キャリアーもオフロードを繋ごうとする意図はそこまで見られず、オフロード自体も少なくキャリーは単発で発生していたような形です
FWの選手によるキャリーが多く、選手のコンタクト姿勢においてもボールを完全に抱え込んでいるような形でしたしね
青山学院のディフェンス
相手にボールを持たれている時間がほとんどだった割には早稲田のスコアが伸びておらず、そうなる要因となったのは青山学院側のディフェンスの健闘であるように思います
ディフェンス内でのタックルミスこそ多かったものの、100点ゲームにならない程度にはディフェンスがうまくできていました
タックルの質そのものはもう少し良くすることができるかとは思いますが、ディフェンスラインの整備がある程度組織だって行うことができており、あとはディフェンスラインを揃えるところとエッジまで回された時に対応さえしっかりやれば一般的なアタックに対してはかなり抑えることができるかと思います
課題になってくるのは上記のようなディフェンスライン自体の上がりの部分と、もう一つはキックレシーブのところになってくるでしょう
ディフェンスから少し外れる要素ですが、バックスリーの選手やSHに入った選手のバックフィールドを守る意識が強いのか、相手の長めのキックをノーバウンドで確保することがあまりできていませんでした
もしかするとスカウティングの結果早稲田がコンテストキックを蹴ってくることを予想していたのかもしれませんが、試合中にある程度改善をすることができればここまでキックで押し込まれることはなかったかと思います
早稲田の選手はキックチェイスのスピードが速かったため、バウンドしている間にかなり詰められていましたしね
キック処理はノーバウンドで行うことが望ましいことを実感する試合でした
早稲田のアタック・ディフェンス
早稲田のアタックシステム
今回の試合、早稲田のメンバーの中で目立ったのは軸となりうるHOの佐藤選手とBK3の矢崎選手の不在でしょうか
理由は分かりませんがその2選手が今回の試合では外れており、早稲田がどのようなアタックをするのかは正直楽しみにしていました
結果として早稲田は普段通りのアタックをしていたような印象ですが、いい意味で捉えると「主軸となる選手が一部いなくてもアタックの一貫性を保つことができる」ということを見てとることができました
特に2番に入っていた安恒選手の活躍は目覚ましく、プレースタイルこそ若干の違いはありますが相手を弾き飛ばす強いキャリーやバックドアへのスイベルパスなど、高いクオリティで早稲田のHOとしての役割をこなしきっていたと思います
またBKラインで見ていくと矢崎選手は不在でしたが、今年台頭してきた11番の福島選手や15番に入った久富選手が良いランニングを示していたり14番の守屋選手が走りきってトライを取ったりと、突出したスキルを持つ選手の不在を感じさせないほど安定感のあるアタック構成をしていたように思います
アタックの観点で言うと10番に入っていた野中選手が主にアタックのタクトを振っていましたが、13番の伊藤選手や15番の久富選手が1stレシーバーに入ったりとSOの位置で状況判断をすることのできる選手が複数名いることが早稲田の強みになってくるかと思います
野中選手がキャリーすることがほとんどなかったためSOがラックに巻き込まれているシチュエーションはありませんでしたが、SOに立って状況判断とパス回しを担当することのできる選手が複数名いることでアタック方向を変えたりテンポをあげたりすることができたりするので良いですね
アタックの特徴としてはかなり規定されたポッドシステムをしているように見えるスタイルをしており、エリアに対してポッドが決められた形で立つといったスタイルに見えます
そのため、必ずしもラックからの1stレシーバーになりうる位置にポッドの選手が立っていると言うわけではなく、意思決定をこなすことのできる選手たちが立ち位置を適宜変えてポッドの間をつなぎ、決められたエリアでFWの選手がキャリーをすると言う形をしているように感じました
基本的には1−3−3−1のようなメンバー分けをしているかとは思いますが、エッジでのキャリーは両FLに入った永嶋選手と村田選手が担当しており、中央エリアではSHからのシェイプ、SOからのシェイプ、CTBからのシェイプなどバリエーションのある立ち位置を見せていました
また、ポッド内の位置関係を見てみると、特にSOから・もしくはCTBからのポッドにおいてFWの選手が浅い三角形か平行に近いポジショニングをしており、どの選手がもらうかがわからない、パサーの状況判断に選択を委ねたような形をしていたように思います
必ずしも中央の選手がもらうわけではなく、外側の選手がもらうこともあるためポッドの対面に立つ相手のDFの選手に迷いを生むことができるわけですね
アタックのテンポもよく、昨年度試合に多く出ていたSHの宮尾選手を書いた中でも島本選手が素早い判断でボール出しを担っており、ラックが形成される前にボールを取って展開したりと、かなり速さを意識したプレースタイルをしているように見えました
青山学院のディフェンスも、止めることこそできていましたが振り回されていましたね
早稲田のキャリー
主にキャリーを担った選手の誰もが前に出る強さがあり、どの選手がキャリーしてもコンタクトした位置から前に出ることができていたように思います
特に目立ったところで言うとPOMをとった安恒選手や8番のm、厚沼選手が挙げられるでしょうか
相手を弾くコンタクトもできますし、タックルで倒されずにひたすら前に出るキャリーもできていました
今回の試合で気になったのは8番の松沼選手のキャリーですね
スピードが突出して優れていると言うわけではないのですが、スピードのコントロールがうまく相手を翻弄しており、細かいステップの他に大きなステップで方向を変えることもできることから相手ディフェンスを外すことに成功していました
安恒選手が弾くようなキャリーをしていたのに対して、松沼選手は相撲の立ち合いのような印象を受けましたね
キャリーを量的に見ていくと恐ろしいことになっており、全体で142回のキャリーと100回以上のラックが起きています
前半だけで53回と、青山学院側の試合全体を通じたキャリー数53回と並んでいますね
キャリーを細かく見ていくと9シェイプでのキャリーが48回、10シェイプでのキャリーが9回と、FWの選手が主となるアタックでは57回のキャリーが生まれています
シェイプ外のキャリーは中央エリアで27回、エッジエリアで23回の合計50回のキャリーとなっており、ポッドのようなシステマチックなアタック以外にもキャリーを引き起こしていると言うことが伺えます
ただ、少し懸念点としては「キャリー数の割にトライが取れていない」と言うことが挙げられます
キャリー数は基本的にポゼッションに直結すると思うのですが、単純に回数だけで計算すると割合として7割を超えるポゼッションを早稲田側が獲得しています
正直なところここまでポゼッションに差があると100点ゲームになりうるレベルのものだとは思いますが、所感としては単純に青山学院のディフェンスが良かったからと言うわけではないような気がします
特に後半のスコアが開いた後のアタックの一部では意思統一に乱れのようなものが見られており、スコアこそできていたものの少し「らしくない」アタックをしていたようにも見えました
つなぎのところで無理しているようにも感じましたしね
早稲田のパス
ポゼッションの高さと早稲田の展開ラグビーのスタイルがうまくかみ合わさって、パス回数は合計で221回となっています
ここまで多かったのは春シーズンの東海大学対東洋大学の100点ゲームくらいだったので、それがどれほど多い数字かは分かるかと思います
その中で早稲田は回数の割に質の高いアタッキングラグビーに繋がるパスワークをしていたように思います
先述したようなアタックの乱れこそあるものの基本的に意図的なアタックのフローは崩さずにパスワークをこなしており、パスミスもあまりなかったように見えました
細かく回数を見ていくと、ラックからのパスとしては9シェイプへのパスが50回でバックスラインへの展開が44回となっており、アタックの傾向としてもどちらかに偏っていると言う形ではなさそうです
試合を見ている印象でも、10番の野中選手をはじめとするSOの位置に立っていた選手のボールタッチが多かったように思います
早稲田の特徴としてはポッド内のパスワークが比較的多いと言うところにあるかと思いますが、今回の試合でも同様の傾向があったように思います
回数こそ9回と少ない数ではありますが、必要なタイミングでうまく相手をずらす意図でパスができていたようにも見えたので、かなり効果的な用い方をすることができていたのではないでしょうか
また、他のチームと比べると10シェイプへのパスが多いことも目立つ部分になるかと感じます
傾向としては伊藤選手がSOの位置に入った時に10シェイプへのパスが多くなる印象ですね
結果的に試合を通じて16回の10シェイプへのパスが生まれていました
バックスライン内での展開も合計で42回とかなり回している様子が見受けられ、方針としてはかなり「外へ外へ」といった感じかもしれません
一方でOtherに分類されるようなパスも多く、後半にかけてワンバウンドするパスなど「ミスパスにはならないが意図的なつなぎ方にはなっていないであろうパス」も一定数見られたことは少し課題になってくるかと思います
早稲田のディフェンス
ポゼッションで圧倒していて青山学院にそもそもアタックを許していなかったと言う点を鑑みても、完璧に近い試合運びをすることができていたのではないでしょうか
2本のトライを奪われましたが前後半合わせてもミスタックルは4回で95%と言うタックル成功率を誇っており、ディフェンス面でも相手を圧倒することができていたと思います
その中でも自分が気になったのは12番の岡崎選手のタックルシーンです
前半にあったプレーですが、相手の動きに合わせて若干下がりながらも自分の体の向きや勢いをうまくコントロールしており、下半身をうまく使って相手のコンタクトの瞬間に自身も瞬間的に強い姿勢に入ることができていました
他にも優れたタックルは何度も見られましたが、早稲田のこだわりやスキルを感じると言う点で、前半に起きたこのタックルをTOM(タックルオブザマッチ)にしたいと思います
映像が準備できないのが重ね重ね残念です
ラックへのプレッシャーも過剰にかけることはなく、捨てる判断の早さとタックラーの動きの速さでディフェンスには常に15人の選手が立っていると言う状態がほとんどでした
この辺りにも早稲田の強さを感じますね
一点気になるところを挙げるとすれば、相手のボックスキックなどのコンテストキックの処理に関するところです
何度か相手に再獲得を許し、チャンスこそ与えなかったもののアタックを継続させてしまうと言う状況が何度か見られていました
BK3の選手が極端に深いというわけではなかったのですが、前に立つ選手のエスコートの動きも悪く、ボールを獲得に行こうとする動きも少し遅いような印象を受けたためもしかすると課題になるかもしれません
まとめ
早稲田が圧倒的なアタック能力を示しながらも、青山学院のディフェンスに阻まれてスコアがそこまで伸びなかった試合となりました
青山学院としては、前半のディフェンスを後半も継続して実行すること、またアタックのバリエーションを増やすなどして効果的なアタックを仕掛けることができればより良い試合運びをすることができたかもしれません
今回は以上になります
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
