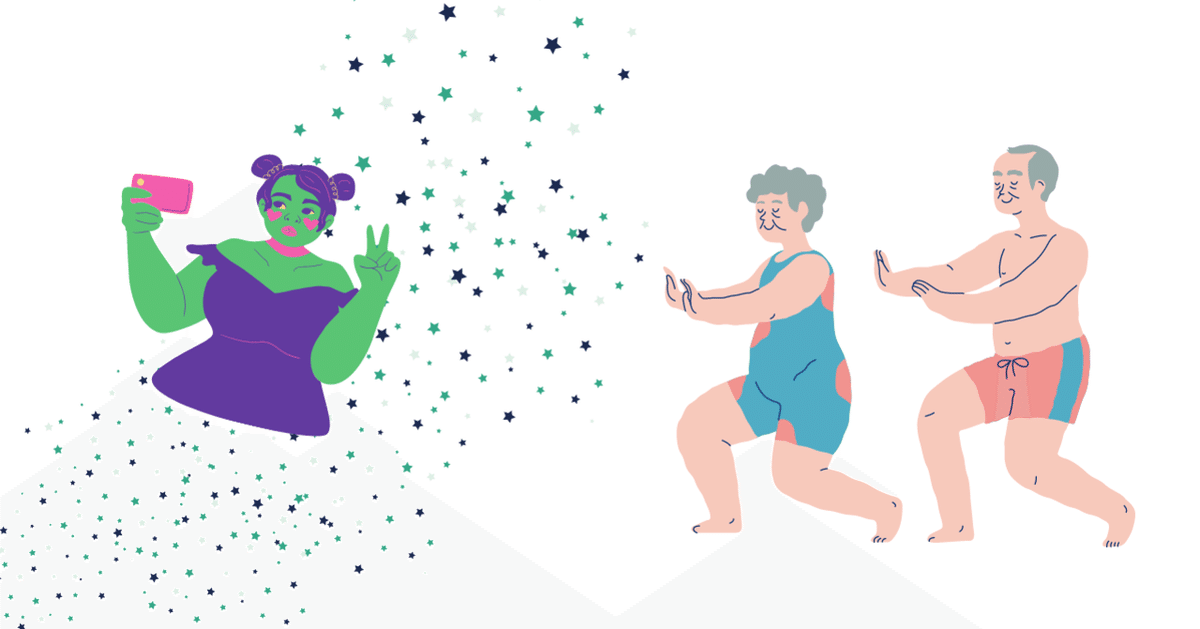
小さい頃は神様がいた
[平成最後の紅白歌合戦と演歌問題(なぜおじさんおばさんは、おじさんおばさんになるのか問題)について。]
十二月に入ってから、曇りや小雨の日が多く、空はいつももったりと灰色、家の中はさらに湿っぽく暗い。昼二時ごろには既に電気をつけている。
こうなると、どこか身体ものろのろと錆びた自転車のペダルのように重くなり、つい長い昼寝を取ったり、面倒な仕事を後回しにしたりして、気分も灰色。季節性うつになるのも無理ないよ。(季節性うつになっているわけではないけど。)
ところで、季節性うつに関しては、日光の照射時間の短さによるビタミンD不足などなどによるだけではなく、目から光を取り込む際に、脳の中で幸福を感じる神経を刺激する部分が働いているから(なので日照時間の短い冬には必然的にその幸福感が欠乏していく)、という研究が発表されていました。人間はどうしてまたそんな要らない進化を遂げてしまったんでしょうね。人間のばか!
平成最後の紅白歌合戦を観ていて、以前、川上未映子さんが書いていた「演歌問題」について思うところがあった。演歌問題というのは、いわゆる、人はいつから演歌を聴くようになるのか、なぜ、いつから、ほとんどのおじさん、おばさんは一見しておじさんおばさんと分かるような服装をするようになるのか、などなどの問題をひっくるめた総称です。(『すべてはあの謎にむかって』より)
演歌問題に関して言えば、ビートルズ以前の日本の音楽が所謂演歌、歌謡曲中心に構成されており、その時代に音楽をよく聴く年頃を過ごした人々が、いつまでもその類の音楽を聴き続けるために起こる現象だと、子どものころの私は考えていた。
その証拠に、ビートルズ全盛期に青春時代を過ごした私の両親は今でもビートルズ系の音楽や古い時代のジャズを好んで聴いており、演歌を聴くことはない。
とはいえ、物心ついたころから見てきた紅白歌合戦で、演歌歌手が登場すると大声で声援を送るおばさんたちは、私が子どもだった三十数年前のあの時からいつの時代もだいたい70代くらいのおばさん達で、三十数年前と同じおばさんが今もあそこに座ってぎゃーぎゃーと騒いでいるわけではないのだろうから(もう、ぎゃーぎゃー言ってる場合じゃなくなってしまった方もいるだろうし)、確実に世代交代、演歌好きのおばさんの刷新は行われてきたに違いないのです。
ということは、三十数年前は三十代で、山下達郎の「ライドオンタイム」とか、オフコースの「さよなら」、西田敏行の「もしもピアノが弾けたなら」なんかを聴いていた人が、ある日突然、天童よしみや石川さゆりなんかを聴くようになっていったということになる(おそらく)。
それはそうと、私は子どもの頃、西田敏行さんの「もしもピアノが弾けたなら」の主人公が、何らかの事情で両腕を無くしてしまった人だとずっと思っていた。「だけどーぼくにーはぴあーのがーない、君にー聴かせーるうでーもない」ですから。(勘違いって怖いね)
さて、紅白歌合戦というのは、その年の日本の音楽界を象徴する、代表する、人気者たちが出場する旬の音楽の式典であるので、その年ごとに出演者の顔ぶれ、披露される音楽の傾向、合間合間に挟まれる短いショウも変わり、NHK目線で流行りものを一挙公開するお祭りであります。
移り変わる歌い手の面々、たくさんの知らない歌、踊り続けるJ-Soul Brothers。次々と現れるアイドル集団、浅はかな歌詞、心を揺さぶらない音楽。勿論、心を揺さぶるだけが音楽の役目ではなく、それぞれの音楽にそれぞれの果たす役目があるのでしょうから、それがいけないということではなく。
そんな中、踊るJ-soul Brothersの間から突如現れる坂本冬美。
そしてそれまでの出場歌手とは次元の違い過ぎる歌唱力で歌い上げる「夜桜お七」。
子どもの頃から見てきた紅白歌合戦で唯一不変のこの感じ(昔は坂本冬美さんの足元で激しく踊る謎のダンサー集団こそいなかったものの)。いつの間にか覚えてしまっている歌詞、口ずさめてしまう夜桜お七。その圧巻の歌唱力に震える胸。
石川さゆりさんの「天城越え」なんか、涙さえ頬をつたってしまったよ。
なんだこの妙な心の故郷感は?こここここれがまさかの演歌問題の一つの答えでは?紅白によって巧妙に仕組まれた罠?こうして日本人の心に生き続ける演歌?
はっとして、いやいやいやいや、だからと言って日常生活の中で演歌を聴こう、とはならないし、カラオケでも歌おうとはならないのだから、私はセーフでしょう、と慰めてみて、そこに現れた郷ひろみの歌う「ゴールドフィンガー」にも同じ理屈でつい親しみと懐かしみの心で聞き入ってしまう自分に不徳の致すところ。A-chi-chi-A-chiと言ってる場合じゃないんですよ。ほんとに。
演歌問題、それは深いなぞであると同時に、40代の私にとっては具体的に現実的な問題でもあります。
演歌問題に関連して川上未映子さんは、なぜおじさん、おばさんが十代と同じような服を着るとそこに「キツさ」があるのだろう、と疑問を呈する。逆に若い人がおじさん、おばさん風ファッションをしていても、ダサさはあっても、キツさはないのに。
私のアメリカの友人に、他人のファッションを「年不相応(age inappropriate)」という言葉で批判する人に真っ向から立ち向かうアクティビストである方がいます(アクティビストも主張の数だけ色々存在して、それはそれですごいなぁとぼんやり見てしまうところもありますが。)
誰かが「四十代が絶対してはいけないファッション」というスレッドを立ててSNSでシェアすれば、そこに挙げられたファッションをすぐさましてみせて、それをSNSに載せて反論するということをしている。
そしてやはり、しわしわのおでこの上で二つの団子結びをした写真には、明らかな「キツさ」がある。(アクティビストとしては失敗なのでは?という疑問も湧きつつ)、なぜある程度の年齢を超えて、ある種の装いをするとキツさがでるのでしょうね?
誰もが年老いてその先にある逃れ難い死に向かっていくという、敢えて毎日口には出さないけれどみんなが知っている人生の絶対ルールを、それに必死であらがうという行為で露見させてしまう、というところが、キツさのもとなのかな。見せないでよ、そっとしておいてよ、みんな年老いて死んでいくって知ってますってば、という。
また単純に、十代のファッションって、ファッションの迷走期、開花前的な、安っちい、一過性の素材・格好、花火のようなその年頃のその目つき、顔つき、ぎらぎらのピークに向かう勢いみたいなものとセットになってこそ見ていられるものであるというのもあるかもしれません。
だから色々を知ってしまった深い目・顔つきを持つ者がそれをまとっても成立しない、とか。そもそも年を重ねて変わっていく肌色や体型と、その素材、形が合わないということもあるかもしれない。(逆に、十代のファッションをそのまま模倣するより、オトナのファンキーさを表現したエレガントなファッションなどは、すっかり着こなしている素敵な大人も多いです。)
それはそうと、紅白では生歌を披露するのが苦しそうだったとはいえ、松任谷由実さんの「やさしさに包まれたなら」、やっぱり素敵な曲でしたね。これこそ幼い頃から親しみ続けた曲。思わず涙が出てくる名曲です。
そう、小さい頃には神様がいた。そして毎日夢を叶えてくれた。けれど全ての子どもは平等に刻一刻と年をとり、おじさんおばさんへと変貌し、演歌に涙し、アチチアチと口ずさみ、いつかはみんな死んでいくのです。
やさしい気持ちで目覚める事すら少なくなってしまった演歌問題の狭間に揺れる私にも、奇跡、起こるでしょうか。大きなものじゃなくていいんです。新しい素敵な友人と出会うとか、もう会うことのなくなった古い友人と再会するとか、ヘアカットがばちっと上手くきまるとか、ずっと探しているイメージに合ったスカートに出会う、とか。
そんなささやかな奇跡をどうか。今年は宜しくお願いします。
(*平成最後の紅白歌合戦を見てすぐの頃に書いたものです)
