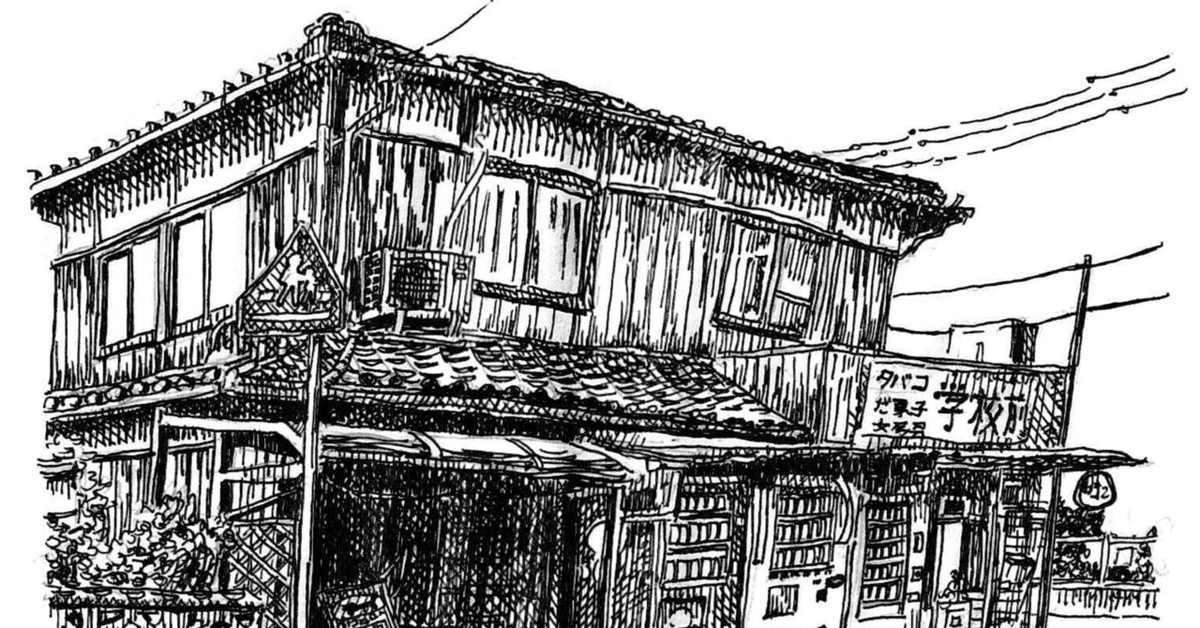
短編小説「少年たちの秘密基地」【後編】
秘密基地の外に、誰かがいる。
その事実は、一瞬にして僕らに緊迫感を与えた。
シーツの向こうからは微かに人影が見えている。控えめな蝉の鳴き声が四方八方から聞こえる中、僕らは数秒間声を出せなかった。
「誰やっ」よっちゃんが叫んだ。
乱暴にシーツを捲り、基地内に侵入してきたのは、おさげを三つ編みにした女子だった。
掛布美宇だ。
僕らと同じ5年2組のクラスメイト、掛布は仁王立ちで、呆然とした様子の僕らを見下ろしていた。
気が強く、口が悪い。背丈は男子の平均以上あって、自分に歯向かう男には容赦なく暴力という名の制裁を加える。そのため、一部の男子からは『おとこおんな』と密かに呼ばれ、恐れられている。
「お前、何でここにおんねんっ。俺らの基地やぞ、ここは」掛布をおとこおんなと呼んでいる男子の1人、よっちゃんが言った。
「給食に出たプリンの犯人、あんたらやろうと思ってな。放課後、絶対ここに集まると思ったんや。そしたら案の定やったな」
「どうやってここがわかった」
「聞いたんや」
「誰に」
「あんたらの中の1人に」
僕らは互いに顔を見合わせた。
よっちゃんは首を振った。「勿論、俺ちゃうで」
「俺でもあらへんよ」マナブは言った。
「俺もちゃうよ」シゲチーは言った。「言うてへん。言うわけないやん」
「いや、僕でもないよ」
僕らはまた互いに顔を見合わせた。
「ほなら誰やねんっ、裏切り者は」
「本当にこの中の誰かから聞いたんか?」マナブは訊いた。
「聞いたで」掛布は頷いた。「せやけど教えてくれた義理があるから、そいつの名前は明かせんな。あんたらの関係性に亀裂走らせたないし」
「いやいや、ここは潔ぎよく名乗り出ようや」よっちゃんが言った。「ほんで、何でよりによってこいつなんかに教えたんや」
「誰が、こいつなんかや」掛布はよっちゃんの尻を蹴った。よっちゃんは呻いた。
「でも、案外一番喚き散らしてるお前やったら、それはそれでおもろいけどな」マナブはココアシガレットを咥えながら、よっちゃんを見た。
「はあ? 俺なわけあるかい。ほんまに俺ちゃうで。メリットがないもん」
僕だ。僕が掛布に、この基地の所在を教えた。
先週の金曜日のことだ。放課後の教室で、僕と掛布は日直の当番で雑務をやっていた。周りには僕と掛布の他に誰もいなくて、話の流れから僕は彼女にそれを話してしまったのだ。
勿論、普通ならそんなミスは絶対に犯さない。
だけど、僕は掛布のことが好きだった。そのせいで正常に頭が働かなくなって、ついうっかり口を滑らせてしまった。
きっと心のどこかで、掛布に気に入られたいという魂胆があったんだと思う。
そして僕が掛布を好きだということは、今まで誰にも話していない。勿論、掛布自身にも。
「まあ、どうでもええやん。そんなこと」と掛布は言って、よっちゃんとシゲチーの間に座り込んだ。
それから掛布は当然のようにシゲチーのうまい棒を手に取って、それを開封して食べ始めた。
よりによって彼女が選んだうまい棒は、シゲチーが最も好きなテリヤキバーガー味だった。
だけどシゲチーは掛布のその行為に対して、何一つ非難しなかった。正確には、非難することができなかった。
「お前、何を平然と俺らの基地に居座って、人の駄菓子食べてねん」マナブが呆れたように突っ込んだ。
「あっ、ウチ、そのちっこいドーナツ好きやわ。小山内、1個貰ってええ?」
「まあ、ええけど」僕はヤングドーナツを掛布に渡した。
彼女はその中の1つを手に取って、僕にヤングドーナツを返した。「おおきに。小山内は素直でほんまに可愛いわ」
「おい掛布。お前は俺らの仲間ちゃう。部外者や」よっちゃんは言った。「せやから、今すぐこの基地から出て行けよ」
「断らせてもらいますう」掛布はドーナツを食べながら言った。それからショルダーバッグからカルピスウォーターを取り出して、それをゴクリと飲んだ。
「この、おとこおんな」よっちゃんは呟いた。
掛布は横目でジロリとよっちゃんを睨んだ。「お前、次ウチのこと『おとこおんな』って言うたら、ほんまにしばくからな」
「あ……すんません」
僕はそのやりとりを見て、思わず笑いそうになった。見ると、マナブとシゲチーも笑いを堪えていた。
「今日、ウチらのクラスにだけ出たプリンやけどな」掛布は言った。「あれ、やっぱりあんたらの仕業やってんな。ウチな、全部外で聞いとってん」
「証拠がないやろ。俺らがやったっていう証拠が」
「マルハチで買ったって、話しよったよな? 店員さんに、大量のプッチンプリンを買うあんたらの姿が目撃されてるんとちゃうか? 防犯カメラにもばっちり映っとるやろうなあ。そや、このことをバラせば学校で大問題やな」
マナブは溜め息をついた。「目的はなんやねん?」
「ウチを、この秘密基地のメンバーに入れてほしい。あんたらの話聞いとったら、なんか楽しそうで興味持ったわ」
「駄目や。断る」
「黙れ青柳。お前には頼んでへん」
よっちゃんは掛布の命令通り口を閉じ、不貞腐れた様子でキャベツ太郎を口に入れた。
「なあ、矢野。矢野はウチに入ってほしくないんか? 紅一点やで」
「いやあ……ううん」シゲチーは頭を掻いた。「掛布が紅一点じゃあなあ……華がないっていうかさ」
掛布はシゲチーの頭を引っ叩いた。
「掛布、この基地のメンバーに入ったら、プリンのことは誰にも言わへんのやな?」僕は訊いた。
「勿論。入れてくれるなら誰にも言わへんよ。当然やん」
「ちょっと、オサ。本気で言うてる?」シゲチーが小声で訊いた。
「せやけど仲間に入れんと、掛布は多分みんなに言いふらすで」
「あら、ウチのことようわかっとるやん。小山内、もしかしてウチが好きなん?」
僕の心臓は跳ね上がった。「んなわけあるかいっ」
「冗談て」掛布は笑って言った。「小山内ってさ、からかい甲斐あるよな」
僕は掛布から目を逸らして、チェリオのメロンを飲んだ。
「うん」それまで腕を組んで黙っていたマナブが頷いた。「ええで、入れよ」
「おい、マナブまで何言うてんねや」よっちゃんは言った。
「オサの言う通りや。掛布を仲間に入れんかったら、プリンのこともこの基地のことも言いふらされて、俺たちは終わりや。掛布を迎え入れるという選択肢しかないねん、俺たちには」
「いや……せやけどな」よっちゃんは阪神の帽子を取って、頭を掻いた。「男だけの集まりみたいなとこ、あったやん」
「別にええないやか」マナブは言った。「こいつ女やけど男みたいなもんやろ」
「あ、それもそうか」
「おい、お前ら。この基地壊されたいんか」
マナブとよっちゃんは慌てて首を振った。
「とにかくっ、消去法的に考えれば、掛布は僕らの仲間になるしかないっちゅうことやな」僕は言った。「僕とマナブは賛成の立場。よっちゃんとシゲチーは? どないする?」
シゲチーは「ほな、賛成」と言い、よっちゃんは「本当は反対やけど賛成や」と言った。
「決まりやな」
「よっしゃ。みんな、これからよろしゅう頼むわ」
「ああい」と僕らはそれぞれ気の抜けた返事をした。
だけど僕は内心、掛布が基地のメンバーに入ったことが嬉しくてしょうがなかった。表面上は3人のテンションに無理やり合わせただけで、本当は心の中でガッツポーズをしていたのだ。
「にしても掛布、俺らがプリン騒動の犯人やって、なんでわかったん」マナブが訊いた。
「そんなんあんたらが悪ガキ集団で、一番そういうこと仕出かしそうやからに決まってるやろ。給食当番も、あんたらの中の3人被っとったしな」
「ふうん。なるほどな」
「なあ、これまでも今日みたいな悪戯やってきたんか? 初犯じゃないんやろ?」
「ああ」僕は頷いた。「教室に大量の風船が浮かんでるのとか、教室のメダカの水槽に金魚が泳いでるのとか」
「ええっ、あれもあんたらやったん? 驚きやわあ。あんたら凄いなあ」
掛布はただでさえ大きくて丸い目を、さらに大きくしていた。
本来、掛布が僕らに感心するなんてまずあり得ないことで、そのことが僕は嬉しくもあり誇らしくもあった。
「今日のプリンやけどな、ほんま嬉しかったわあ。ウチのクラスだけやったからな、めっちゃ得した気分」
「そうや、俺らのおかげで、お前はええ思いをしたんやからな」よっちゃんは言った。「そのことを心に留めて、しかと感謝せえよ」
「あ? なんや、自分めっちゃ上からやな」
「と言ってもさあ」シゲチーは苦笑いした。「今回の計画思いついたのはオサで、プリンのお金出したのは殆どマナブやん」
「いや、まあ確かにそうやけどさ」
シゲチーの言う通り、今回の計画の発案者は僕で、出資者はマナブだ。
マナブの家は両親が弁護士で、お小遣いを僕らの何倍も貰っているため、彼はプッチンプリンの支払いを全体の9割請け負うことになった。
これはそれぞれのお小遣いの金額を考慮して、公平になるように出すべき金額を決めたのだが、結果的に出費の割合はかなり偏ることになってしまったのだ。
「凄いなあ、おもろいなあ。なっ、この基地でこれまでいろんな悪戯を考えてきたんか?」
「そうや。悪戯を思いついては、それを実現するために計画を立ててきたんや」
「次の悪戯は? もう考えてあるん?」
「それを今から考えようって思ってたところやな」
「ええ、楽しそう。学校でどんなんが起こったらおもろいやろか」
「おい、新入り。お前にアイデアを出す権利はない」よっちゃんは言った。「新入りは鼻くそほじりながら黙って聞いとけ」
「あ? うっさいねん、ドアホ。算数のテストで赤点取ってばっかのアホが、ウチに口出しするなや」
「今そんなん関係ないやろがっ」
「やめーや、2人とも」マナブは言った。「仲間になったばっかやのに、これじゃあ先が思いやられるわ。なあ、シゲチー」
「うん。何事にも協力っちゅうもんがないと、いいアイデアは浮かばんで」
僕は2人の喧嘩の様子を尻目に、基地の外から聞こえるある音に耳を澄ませていた。
僕らの秘密基地がある森の傍には県立の高校があって、そこからアブラゼミの鳴き声に混じって、吹奏楽部の演奏が聞こえてきているのだ。
「音楽室」僕は呟いた。
全員がさっと僕の方を向いた。
「これまで悪戯の舞台は、全部僕らの教室に限られてきたやんか? 次は音楽室でやってみるってのはどうかな?」
「音楽室か。ええね、おもろそうやな」マナブは言った。
「音楽室で何するん?」シゲチーが訊いた。
「そこはあれやろ、夜中にピアノの音が聞こえてくんねん。ポロローンってな」よっちゃんは言った。
「そんな時間に学校に侵入できんやろ」マナブは言った。「却下や」
「ほな、ドラムの音が聞こえてくんのは? ドシャーンって」
「同じ理由で却下や。よっちゃん、そのボケ全然おもんないで」
基地内が一瞬だけ笑いに包まれた。
「なあなあ、音楽室ってさ、あれがあるやん」掛布は人差し指を立てた。「ほらあれ、なんやったけ。あかん、言葉出てこんわ。あのベートーヴェンとかモーツァルトとかの」
「肖像画?」
「そうっ、肖像画。ウチな、あれずっと前から気味悪かってん。なんや今にも動き出しそうでさ。でな、肖像画を使って、何かやってみるってのはどうやろか?」
「肖像画かあ、確かに何かできそうやな」僕は腕を組んだ。
「せやろ、せやろ」
「ほならさ、肖像画に落書きしてさ、全員に鼻毛描くのはどうや?」
「あかん。それは悪戯の範疇超えてるで、よっちゃん」マナブは言った。「あくまでも俺らの悪戯は、人を楽しませることが目的やねんから」
「そうそう」シゲチーは頷いた。「そんなんしたら先生カンッカンに怒るで。プリンの比じゃないくらいに」
「ううん。ほな、どうすねん?」
「他の肖像画を貼るのはどうや?」僕は訊いた。「写真でもええけどな、気づかれない程度に、ワーグナーとかの隣に他の人間の肖像画を貼ったんねん」
「おっ、それおもろそう」よっちゃんは僕を指差した。「決定、採用やっ」
他の3人も『新たに肖像画を貼る』という僕の意見に同調したようで、うんうんと頷いている。
「問題は誰にするかやな」マナブは言った。「気づかれない程度なら、同じ西洋人が望ましいと思うわ」
「マリオとかええんちゃう? あいつ西洋人やで」
「あんなあ、よっちゃん。それはゲームのキャラクターやん。実在する人物やないと」
「ほんならウチ、好きなハリウッドの女優おんで。スカーレット・ヨハンソン」
「ううん、女は多分目立つやろなあ。肖像画は基本、男しかおらんからなあ」
「おい、マナブ」よっちゃんは言った。「お前は人の意見否定してばっかで、自分の意見はないんか?」
「そうやなあ……ジョー・バイデンとかどうや?」
「誰やそれ?」
「アメリカの大統領や。ドナルド・トランプでもええけどな」
「トランプやって、変な名前やな」よっちゃんは笑った。「そいつマジシャンなんか?」
「アメリカの前大統領や。シゲチーは? 何か案ある?」
「そやねえ」シゲチーは頭を掻いた。「ジェフリー・マルテは? 俺好きな選手やねん」
「阪神の助っ人外国人か。ううん……クラシックの音楽家って雰囲気じゃないもんなあ」
「そっかあ」とシゲチーは言って、新たなうまい棒を開封して食べ始めた。
今日シゲチーがうまい棒を食べるのは、これで7本目だ。
「シゲチー、それ何味?」僕は何気なく訊いた。
「これ? チキンカレー味やで」
「チキンカレーかあ」僕はぼそりと呟いた。「チキン……うん? チキンと言えばケンタッキーやんな? ほならさ、カーネル・サンダースとかどう?」
「おっ、ええやん。カーネル・サンダース」マナブは言った。「肖像画の中に混じってても、目立たなさそうやし」
「ウチも賛成」
「俺も」
「ええ、俺はカーネルよりドナルド・マクドナルドの方が好きやわあ」
「黙れ青柳。ピエロは目立つんじゃ」掛布はピシャリと言った。
そういう訳で話し合いの結果、僕らの学校の音楽室にはカーネル・サンダースの写真が貼られることが決定した。
「時期的に、これが1学期最後の悪戯になるな」マナブは言った。
「絶対成功させような。ほいで気持ちよく夏休みを迎えんねん」
「あれ、よっちゃんにしては珍しくまともなこと言うやん」
「何言うてねん。俺はいつだってまともや」
「お前のどこがまともやねんっ」掛布はよっちゃんの頭を叩いた。
「よっしゃ、名付けて『カーネル・サンダース計画』、これから具体的に練っていくでっ」
* * *
帰り道、シゲチーと別れた後、僕は掛布と2人きりになった。
あれから2時間以上かけて基地で計画を練っていたため、僕らが解散した時間は午後6時半を過ぎていた。
夏の夕方。辺りはまだ少し明るいけど、暑さは日中と比べればだいぶ和らいでいる。
遠くの方で、ヒグラシの鳴き声が聞こえる。
見慣れた住宅街の中、夕日の方角に向かって、僕と掛布はゆっくりと自転車を漕いでいた。
「なあ、オサってさ、好きな人とかおるん?」不意に掛布が訊いた。
「えっ、なんで急にそんなこと聞くん」僕は驚いて訊き返した。
「あんなあ、真理恵ちゃんがなあ、あんたのこと好きなんやって。可愛いって」掛布は言った。「せやからなあ、あんた他に好きな子とかおんのかなあって」
同じクラスの近本真理恵が僕のことを好きだって? 性格が良くて、見た目はクラスの中でも可愛い方で、勉強もできるあの近本さんが?
だけど僕はそんな話を聞いても、ちっとも嬉しくなんかなかった。寧ろ複雑な気持ちだった。
なぜなら僕が好きなのは近本真理恵ではなく、今僕の隣にいる掛布美宇だからだ。
僕は何も言葉を発せなかった。ただ黙ってペダルを漕ぐことしかできなかった。
「あら、どしたん? 何で黙り込んだん? あ、わかった。真理恵ちゃんがあんたのこと好きって知って、照れてねんやろ?」
「照れてへん」
「うっそやん、照れてるやん」
「照れてへんって」
「いいや、照れてるて」
「うっさいわ、ボケ。おとこおんな」
「ああ? なんやと? しばくぞコラ」
どうして僕は、こんなにも口の悪い奴を好きになってしまったんだろうか?
それは多分、口が悪くても掛布が本当は心優しい性格の持ち主であることを僕は知っているからだ。幼稚園からの仲だ。僕は掛布の本質を知っている。
表面上はガサツで乱暴なイメージがあっても、困っている人を率先して手助けしようする親切心や、間違ったことには面と向かって間違っていると言える度胸が彼女にはある。
他の女子みたいに人の噂話で盛り上がったり、周りに流されたりしない。常に自分を持っている。
そんな掛布を、いつの間にか僕は好きになったんだ。
それに、掛布は黙っていれば結構可愛い。
「ほな、また明日な」
「ああ、また明日」
分かれ道で交わした僕らの会話は、どこかぎこちなくて素気なかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
