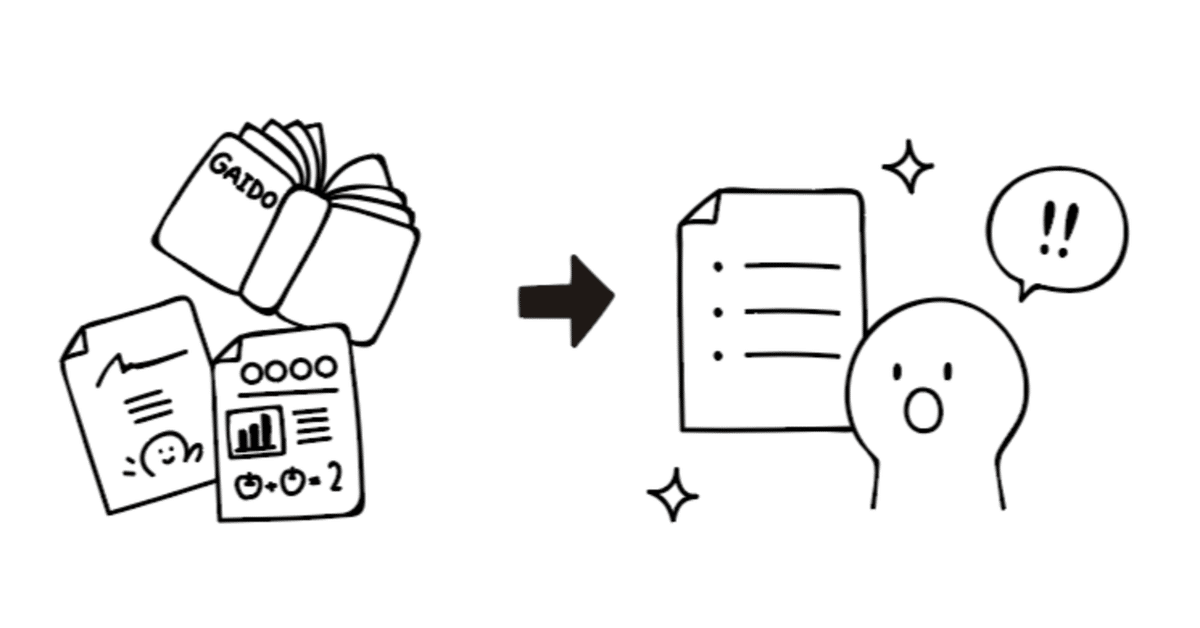
2022年4月8日:数学文章作法 基礎編(最近読んだ本について)
(画像は、情報をわかりやすく整理しているイメージを与えてくれて、今回の本の内容に少し近いなーと感じたので、選びました。素敵な画像です。)
本を読んだ
数年前にTwitterで知って、ずっとほしいものリストに入れていて、何かの勢いで最近購入した本。そんなに緊急性のある読書ではなかったのだけれども、息抜きがてら手に取ってみた。
思いのほかすんなり読めた。7割くらいは既に自分の中にあったような気がする。それが言語化された感じ。
軽い本&自分の中に感覚としてあったことが多かったので、再読の優先度は低い。ただ、それで終わってしまうのももったいないので、せっかくだからここに簡単にまとめてみたい。
読んだ本はこちら
数学文章作法 基礎編 (ちくま学芸文庫) 結城 浩
では早速。まずは、目次を書き写して、本の構造を整理してみたい。
個人的に面白いと思った部分は、太字で表示します。
目次
はじめに
本書について/読者について/私について/本書の構成/謝辞
第一章:読者
この章で学ぶこと
読者の知識
読者の意欲
読者の目的
この章で学んだこと
第二章:基本
・この章で学ぶこと
・形式の大切さ
形式を学ぶ/形式を大切に/形式の指示を守る/神は細部に宿る
・文章の構造
語句/語句の役割/漢字とかな/アラビア数字と漢数字/書体/記号/書き言葉と話し言葉/同音異義語/要注意語句
・文
文の役割/文は短く/文は明確に/「だ・である」と「です・ます」/場合分け/事実と意見を意識する
・段落
段落の役割/段落は明確に/接続詞と文末を意識する/引用
・節、章、・・・・・
節、章、・・・・・の役割/見出し
・この章で学んだこと
第三章:順序と階層
・この章で学ぶこと
・順序
自然な順序/時間の順序/作業の順序/空間の順序/大きさの順序/既知から未知へ/具体から抽象へ/定義と使用
・階層
読みやすい階層を作るとは/ブレークダウンする/もれなく、だぶりなく/グループを作る/階層ごとに順序を整える/少しずつ整える
・表現の工夫
箇条書き/列挙/書体/字下げ/パラレリズム
・この章で学んだこと
第四章:数式と命題
・この章で学ぶこと
・読者を混乱させない
二重否定を避ける/同じ概念には同じ用語を使う/異なる概念には異なる用語を使う/異なる概念には異なる表記を使う/呼応を正しく/必要な文字だけを導入する/添字を単純にする/定義の確認、指示語の確認/省略のテンテン/順序は一貫して/左辺と右辺の順序/一文は短く
・読者に手がかりを与える(メタ情報)
メタ情報/文字に対するメタ情報/数に対するメタ情報/メタ情報の意味を明確に/文字の使い方/定義なのか定理なのか/接続詞は道案内/あいまいさをなくす/別行立ての数式/等号を揃える/文章中の数式を「ほげほげ」する
・この章で学んだこと
第五章:例
・この章で学ぶこと
・基本的な考え方
典型的な例/極端な例/あてはまらない例/一般的な例/読者の知識を考慮した例
・説明と例の対応
内容の対応/表記の対応/対応の確認/対応する例の存在
・例の働き
概念を描く/説明を助ける
・例のを作る心がけ
自分の知識をひけらかさない/自分の理解を疑う
・この章で学んだこと
第六章:問いと答え
・この章で学ぶこと
・問いと答えは呼応する
問いには答えが必要/問いと答えは呼応する/答えがない問い/先延ばしせず答える/問いかけ型のタイトル
・どう問うか
否定形を避けて問う/〇×式で問う/ヒントを使って問う/難易度を示して問う/明確に問う/指示語に注意して問う/シンプルに問う/混乱を避けて問う
・何を、いつ問うか
知識を問う/理解を問う/重要な点を問う/あたりまえのことを問う/答えた後に
・この章で学んだこと
第七章:目次と索引
・この章で学ぶこと
・目次
目次とは/内容を明確に表す見出し/独立して読める見出し/粒度の揃った見出し/形式の揃った見出し/章・節以外の目次/目次の作成/目次を読む意味
・索引
索引とは/索引項目と参照ページの選択/索引項目の表記/索引項目の順序/参照ページの表記/索引の作成/索引を読む意味
・トピックス
電子書籍/参考文献
・この章で学んだこと
第八章:たったひとつの伝えたい事
・この章で学ぶこと
・本書を振り返って
読者は誰ですか/形式を大切に/順序立て、まとまりを作る/メタ情報を忘れずに/例示は理解の試金石/問いと答えで生き生きと/目次と索引は大事な道具/たったひとつの伝えたいこと
・この章で学んだこと
参考文献
索引
整理直後の雑感
目次を整理して感じたし、本のことを知らなくてもわかることだと思うんですが、この本は、文章の書き方に関する本だ。
私のこの文章を見て、「なんだ、本から何も学んでないじゃないか」というツッコミが入っても仕方ないとは思う。
そこは容赦してください。この記事は、テキトーに書くのがモットーなので…。許してください。
でもこの本は本当にいい本。わかりやすくて、ガイドラインになる。
全てを取り入れるには、推敲が必要になるので、私のこの記事には合わないけど、所々本から学んだ要素が入ってきて、読みやすい文章になったらいいな、と思う。
各章で心に残ったメモ
各章でどんなこととが心に残ったか、メモ程度に書いていきたいと思う。
完全に引用していたり、一部解釈が乗っかっていたりしますが、それもご容赦してほしい。
各章と言っておいてあれだけど、まずは全体的な話。
各章に、これから学ぶことと、学んだことをまとめている節がある。これは地味に助かる。要するに何なのか、を予測したり、振り返ったりするのにとても役立つ。
はじめに
考えを伝えるために、「読者のことを考える」という原則を大切にする
第一章:読者
文章を書く目的は、「考えを読者に伝えること」
伝わればいい文章だし、伝わらなければ悪い文章である。
読者の何について考えるのか
知識…読者は何を知っているのか
意欲…読者はどれだけ読みたがっているのか
目的…読者は何を求めて読むのか
読者の知識は変化するもの。知識を積み上げるように、順序良く書くこと。
意欲が低いなら、意欲が向上するような工夫を。
意欲が高いなら、伝えたい内容に集中。
意欲向上には、変化が大切。
抽象←→具体、具体←→まとめ、言葉←→図・グラフ・表
「なるほど」を適切な形で伝える
目的に合わせた内容にする。
第二章:基本
形式の大切さ+ 文章の構造( への理解)
文章の構造
部品1つ1つが正確で読み取りやすいこと
部品同士の関係が分かりやすいこと
(※部品とは、語句、文、節…などの文章を構成する要素のこと) )
文の役割。文は、主張を行うために存在している。何を主張しているのか、が分かりやすいようにする。 文、段落、節、章も同様に、何かを主張するために存在している。
主張は何か、主張同士のつながりはどうなっているのか、が分かりやすいように文章を作る。
文章の各レベルで「何を主張しているのか」を意識すること
第三章:順序と階層
順序・・・読みやすく並べること
階層・・・読みやすくまとめること
読者が読み進む苦労を軽減するために、順序と階層を整理する。
時間的順序、方向的順序、など。
特筆したい順序
既知→(未知交じりの既知)→未知
具体→抽象(似た言い換え:特殊→一般)
定義→使用(用語の定義を導入してから使う)
階層…どこに何が書いてあるのかわかりやすくすること。
読者の期待通りのことを期待通りの場所に書く。驚きを最小にするように書く。
ブレークダウンする(細かく分割する)
もれなく、だぶりなく(過剰な繰り返し+説明不足をしない)
グループを作る(同じ粒度の要素をまとめる)
第四章:数式と命題
読者を混乱させない
読者に手がかりを与える(メタ情報)
混乱させないための表現の工夫。
メタ情報とは、情報についての情報。
第五章:例
読者は例で納得する。
抽象的な話で疑問を持ち、具体的な例で納得する。
例は、読者の心に概念を描く。抽象的な話に、輪郭を与える。
概念の中にある例(=典型的な例)、概念の外にある例(=当てはまらない例)、概念の際にある例(= 極端な例)によって、輪郭を明確にイメージしていく。
例を作るときには、読者の理解を助けるという目的を大切にする。
自分の知識をひけらかさない。自分の理解を疑うために、例を作る。
第六章:問いと答え
問うと、読者は考え出す。適切な問いが、思考を導き、理解を促す。
思考させる問い。理解を確認する問い。
知識を問う。
理解を問う。
重要な点を問う。
あたりまえのことを問う…理解がされているか、を確認することができる。
答えた後に補足することで、理解が促進される。
(問いに答えた後、読者の思考が活性化しているため)
問いと答えは小さな対話。対話があると、文章は活き活きする。
理解を一歩ずつ確かめる。小さななるほど、を積み上げる。
第七章:目次と索引
目次は見出しを集めたもの。文章のアウトラインを提示する。
(見たいところにジャンプするときの助けにもなる)
第八章:たった一つの伝えたいこと
読者のことを考える
読者の知識・意欲・目的を捉える
1つの極印は1つに意味、1つの文には1つの主張、1つの段落には1つのまとまった主張がある。
読みやすいように順序を整える。大きな概念を階層にまとめる
読者を混乱させず、メタ情報を与える
良い例は、知識を増やし、意欲を向上させる。例示は近いの試金石。
問いと答えは、思考を活性化させる対話
読み返してみた感想
うーん。すごい、という感じ。
文章の書き方を書いている本なので、目次をまとめるだけでかなり思い出せる。
本で大事にしていることを、正直目次だけでかなり理解できる。目次写しちゃっていいのかな、と心配になるくらい、わかりやすい。整理されてて、別にいうこともない。
自分が大切だと思ってそれを整理しようと思うけど、そこは既に本の中で整理されていて、変な解釈が乗ったりすることも少ない。
まるで、本をそのまま書き写しているような気持になる。いや、実際ほとんど書き写したようなものだ。そのくらい、文章の精度が高かったような気がする。文章の1つ1つに、ちゃんと主張が乗っていて、その主張が分かりやすい形で整理されている。
こういう文章はほれぼれします。
簡単に読めたのは、既知のことも多かったと思っていたけど、それ以上に、本自体の構成がすばらしかったからなのではないだろうか。
息抜きに、良い本が読めた。長年の積ん読も1冊解消できた。いい機会でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
