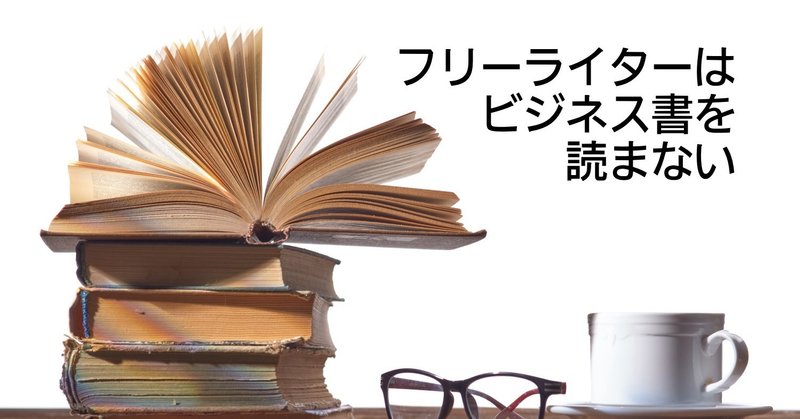
フリーライターはビジネス書を読まない(35)
ミニコミ新聞の制作現場
その夜、相澤と名乗る女性から電話がかかってきた。昼間訪ねたミニコミ新聞のライターだ。社長から番号を聞いて、さっそく挨拶がてらかけてきてくれたのだった。
話を聞いてみると、相澤は私と同い年で、しかも独身という境遇も同じ。ただこのときは電話で話しただけの感じとはいえ、ちょっとせっかちで落ち着きのない性格じゃないかなという印象を受けた。しかも、よくしゃべる。言葉に切れ目がなく、こっちが相槌を打つ隙さえ与えてくれない。
相澤がほぼ一方的に数十分しゃべり続けて、電話は終わった。
話の内容から、相澤は取材記事のほか、紙面のレイアウトもやっていて、それも含めて月に固定給のような形で契約しているらしい。ちなみに私は、記事ごとの報酬である。
翌週から、さっそく取材に出ることになった。老舗の薬局を訪ねて、記事広告のためのインタビューと写真撮影をするのだ。
じつをいうと、記事広告の取材をするのは、このときが初めてだった。阪神淡路大震災の被災地を取材したときみたいに、見たまま聞いたままをルポするのとは、別の視点が必要だ。
そのあたりは、ベテランの相澤が詳しいだろう。電話をかけて、尋ねてみた。
「あそこは漢方を扱ってるから、漢方を求めるお客さんの年齢層とか、あとは今頃の季節によく出る薬の傾向とかかなぁ」
なるほど、とにかく行ってみよう。事務職のあのおじさんがアポを取ってくれてるはずだから、先方でも何かしら用意してくれているかもしれないし。
案ずるより産むが易しというが、そんな取材だった。
記事広告というのは、取材を受ける店が掲載料を払う。それゆえか「これを伝えてほしい」というポイントが明確で、こっちからあれこれ質問しなくても、向こうからしゃべってくれた。それを記事の体裁にして、原稿を書くだけでよかった。
写真は、当時はまだフィルムが主流だった。デジカメの前身のような、フロッピーディスクに画像を記録する「電子カメラ」というものが発売されていたが、画像が粗くて取材用に使える代物ではなく、新しいもの好きが飛びつきがちなホビーツールだった。
デジカメも初期のタイプが出始めていた記憶はあるが、値段が高いうえに、やはりフィルムカメラの代わりに使えるほどの画素数がなかった。
撮影したフィルムは、街の写真屋さんに現像とプリントをお願いする。事務所の近くに、3時間で仕上げてくれる写真屋さんがあって助かった。
そんな感じで、ミニコミ新聞はライター2名体制で紙面づくりをすることになったわけだが、同時に厄介な問題を抱えていることも見えてきた。
相澤がおそろしく遅筆で、レイアウトをなかなか提出しない、取材をしてから原稿が上がってくるまで日数がかかりすぎる、事務所で制作作業に入ったあとでも原稿を修正したがるというので、デザイナーの子としばしば衝突するのだという。。
「よくいえば仕事熱心、悪くいえばズボラ。ミニコミ紙に、そこまでこだわらんでもええのに」と、相澤がいないときに社長がこぼしていたことがある。
相澤の遅筆は、やがて私の身にも累が及ぶことになる。
(つづく)
―――――――――――――――――――――――――――
◆最近の記事/まいどなニュース
知っていますか「模擬原爆」のこと…広島・長崎の前に、日本各地で投下訓練 大阪に今も残る被害の跡
列車の座席予約で→「アメリカ、ボストン、チャイナ、OKです」って何のこと? <旅行会社編>
きょうの運行は→「イチエム」「エムツー」「MMG」!?「ヨコ乗り」もあるよ…<バス業界編>
◆電子出版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

