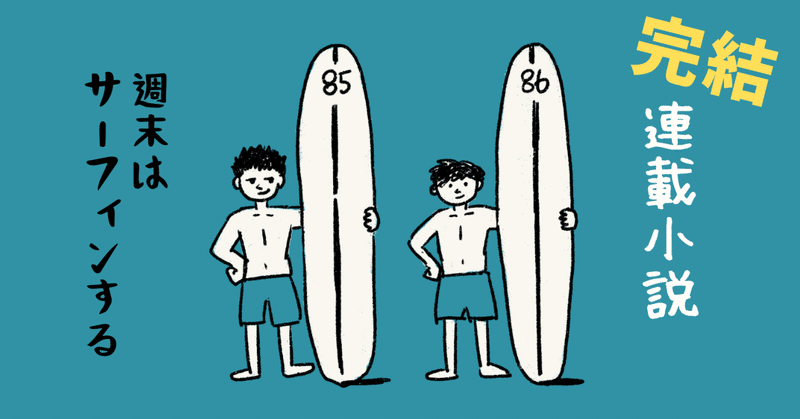
連載小説 | 週末はサーフィンする #8 完結
▼前回の話
「大丈夫そうでしょうか?」
木本さんはパソコンを操作するおれの後ろで、強張った面持ちで覗き込んでいる。
「ええ、どうやらこのファイルは問題なさそうですね。新しいファイルなので、ウイルスチェックで警告が出てしまったということでしょう。セキュリティソフトでこのファイルはチェックの対象外に登録しますので、次からは大丈夫ですよ」
「よかった。ありがとうございます」
そう言って木本さんは胸を撫で下ろした。
午後の光がオフィスの窓際に置いた観葉植物を明るく照らしている。風にそよそよと揺れ、なんだか気持ちよさそうだ。
「直ったんですね。よかった」
優しげな社員の男性が声をかけてきた。紙コップに入った淹れたてのコーヒーを「どうぞ」と差し入れてくれた。
「あっ、どうも」
木本さん以外の社員さんは全部で5名。普段はみんな黙々と仕事しているが、昼休憩になると、海に散歩に出たり、ロードバイクで海沿いのおいしいカフェに行ったり、みんな思い思いに過ごしているようだ。
「なんだか楽しそうでいいな……」
おれはつい、心の声が出てしまった。
「そうですか?」
社員さんは応える。
「そうですよ。なんだか海が近くにあるってだけで、気持ちが全然違う気がします。うちのオフィス、窓が開けられないんです。だから、なんとなく息がつまってしまって」
「たしかに。働く環境って大事かもしれませんね」
「はぁ、うらやましい」
「お住まいも都内なんですか?」
「そうですね、会社の近くです」
「じゃあ、こっちに住んじゃえばいいじゃないですか」
「えっ」
社員さんは優しく笑う。
「僕も都内から鎌倉に移住してきたんですけど、やっぱ楽しいですよ。自然は多いし、おいしいご飯屋さん多いし、なにより人がいい」
「移住ですか……」
そんなこと、考えた事なかった。会社の近くに住むのが普通だと思ってたから。
「木本くんも移住組だよね」
背後でパソコンをカタカタさせながら、木本さんが答える。
「そうですね。まぁ、僕は家でゲームしかしてないんで、どこ住んでも構わないんですけど」
「はは、あんまり変わらないか」
「あ、でも」
木本さんは手を止め、こっちを見た。
「近所においしいパン屋がありますね。そこでよく明太フランス買うんですけど、移住してよかったなって思ったくらい美味しいんです」
「ああ、パン屋おいしいとこ多いよね。チェーンじゃなくて個人やご夫婦でされてたりする。ああいうとこは素材も良くて美味しいんだよね~」
「外カリカリ中もちもちです」
「いいねぇ、おれも近所の中華料理屋がさーー」
木本さんと社員さんの会話をぼんやり聞きながら、《移住》という思ってもいなかった選択肢の衝撃が今も自分の心に余波を残していた。
窓から西陽が差す頃、おれはシステム復旧を無事に完了させた。
「これでもう大丈夫です。また何かあればいつでもご連絡ください」
「ありがとうございます。助かりました」
木本さんがぺこりと頭をさげた。
「じゃあおれはこれで……」
そう、荷物を持ち、帰ろうとしたところ……
「お! 鹿島くん、終わったの!?」
背後のドアが開き、南田さんが声をかけてきた。
「あ! はい! ちょうどいま終わったところです」
「よかった! じゃあサーフィン行かない?」
「え! 今からですか? もう夕暮れ時ですけど」
窓の外の庭は、オレンジ色に染まっている。
「だからだよ! サンセットサーフィンしたことないでしょ?」
「サンセットサーフィン???」
「そうそう、とにかく急いで着替えておいで!」
南田さんは俺の背中を押し、半ば強引にサーフィン部屋へ押しこんだ。
久しぶりにウェットスーツに袖を通す。なんだか懐かしい。
部屋の隅には、洒落た深いブルーの色をした、おれのボード、88が横になっていた。
「放置しててごめんな」
おれはそう言って、ボードの上の埃を払った。
やっとマイボードに乗れる……。
おれはボードを大事に抱え、足取り軽く部屋を出て行った。
由比ヶ浜の海は多くの人で賑わっていた。
おれと南田さんは海辺のサーファーたちを見ながら、屈伸や準備運動をして体を慣らしていた。
「もう日暮れなのにこんなに人いるんですね」
「この辺に住んでる人はみんな仕事終わりに来てるんじゃない? おれもそうだし」
「湘南の人ってどこで仕事してるんですか?」
「都内で働く人もいるだろうけど、だいたい自営業じゃないかな。自分の会社持ってたり、フリーランスの人とか」
「なるほど」
フリーランスか。そういう働き方、考えたことなかったな。
おれがフリーランスだったら、何の仕事をしてるだろう?
「フリーのシステムエンジニアは結構稼げるらしいよ」
「えっ、そうなんですか?」
「俺の知り合いから聞いた話だと、月60~70万とか」
「そんなに……?」
今のおれの給料の倍じゃないか。
「まぁフリーランスは保険とか年金は自分で払うし、パソコンやコピー機とか設備も自費だからね。そういうとこ差し引きで、それでいて稼げるかどうかだよね」
「そうか、そういうのも考えなきゃですよね。あと確定申告とか……」
「まぁ色々面倒はあるけどね。でも、おれも最初はフリーランスだったけど、なんとかなるもんだよ」
「ふむ、そういうもんなんですか」
「ん~、一概には言えないけど。……そうね。一つ言えるのは、《自立心》がある人は向いてるんじゃないかな」
「《自立心》?」
「《自分で考えて、自分で行動できる》ってこと」
「なるほど、……おれにあるのかな」
「これはね、最初なくても鍛えられるから大丈夫」
「そうなんですか」
「そう、そういう環境に身を置けば、だんだん鍛えられる。筋肉と一緒」
そういって南田さんは、鍛えられた上腕二頭筋をムキッとさせた。
「わあ、さすが……」
「さぁ、行こう。良い時間になってきた」
「はい!」
おれと南田さんは駆け足で海へ向かった。
浅瀬に足を入れる。この感覚、久しぶりで嬉しくなってくる。
「結構あったかいですね」
「海の水温は2ヶ月遅れでやってくるからね。10月くらいが一番暖かいよ」
「へぇ~不思議ですね!」
おれは、膝下くらいの深さの場所で新しいボードを海面に滑らせた。よっ、と勢いよく乗り込む。
わ、結構ぐらつく。
借りてたボードより一回り小さいから仕方ないのか。
おれはバランスを取りながら、パドリングを始めた。
ボードが軽いからか、前よりパドルを軽く感じ、ぐんぐん前へ進んでいく。
おお! 早い! 楽しい!
おれは調子良く進みながら、先を行く南田さんの後を追いかけた。
次々に向かってくる小波は、ボードを腕立て伏せのように海中に押し込み、プッシングスルーでかわしていく。前はこれが出来なくて、小波がぶつかるたびに押し戻され、なかなか沖へ出れなかった。
「お、慣れたもんだね」
「はい、なんとか」
一足先に沖でゆったり波待ちしている南田さんが、到着したおれに声をかける。
「ボード調子どう?」
「今のところいい感じです。なんかしっくり来るっていうか」
ボードに跨り、おれは前面に印字された88の文字を撫でた。
「そりゃどうかな」
「え?」
「まぁやってみたらわかるさ」
と、南田さんは意味深に笑う。
「ええ……」
「お! きた!」
振り返ると大きな波が押し寄せていた。南田さんはボードを方向転換させ、波に合わせるよう大きくパドリングし始めた。
おれにはこの波の大きさは無理と判断し、沖へパドルして波を避ける。
振り向くと、南田さんは無事テイクオフ(波に立つ瞬間)したようで、大きく右にターンして波の上を気持ちよく滑っていく。
さすが、南田さん。おれも負けてはいられない。
しばらく沖を眺めていると、ちょうど良さそうな波が来た。小さいがきれいな波だ。おれはパドリングを始める。
『波のスピードに合わせるようにね』
南田さんが言うには、パドリングは速いから良いという訳でもなく、その時々の波のスピードに合わせるのだという。
今回の波はだいぶメローな波だ。おれは大きくゆったり、腕を回し水をかく。
よし、波を掴んだ。
ボードは進み始める。しかし、おれが立ちあがろうとした途端、グラグラと揺れ始めた。
あれ⁉︎
と思った瞬間、おれは海に投げ出された。海面から顔を出すと、南田さんが向こうでにやにや笑っている。
なるほど……、借りていた大きなボードがいかに安定感があったか思い知らされる。軽くて、小さい分、やはり揺れるらしい。ただ乗ってるだけでよかったボードと違って、上手くバランス取らないとだめだ。
くっそ~。難しい……。
難しいけど……、楽しい!
「よっしゃ、もう一回!」
おれは新しいボードに乗り込んで、沖へパドルした。
それから数十分は乗っては揉まれてを繰り返し、おれは疲れきってボードに捕まってへたり込んでいた。休んでいる間も、波は容赦なくおれの顔にぶち当たる。
「鹿島くん、そろそろだよ」
ボードに乗ってゆらゆら揺れる南田さんがおれを手招きした。おれはバタ足で南田さんの元へ近寄った。南田さんの背中ごしに突然、キラッと赤い光が視界に入り込んだ。
「わっ」
細めた目を開けると、目の前には大きく真っ赤な夕日が煌めいていた。
遠い山の稜線に触れ、眩い光がまさに沈んでいくところだ。
いつの間にか海面は真っ赤になっていた。
辺りのサーファーも、南田さんも皆真っ赤に染まり、同じ方向へ向いている。
皆、夕日に魅入っている。
きれいだ……。
上から下までの赤。
海の中から夕日を見るのは初めてだった。
まるで、自分も自然の中の一部なんじゃないかって、そんな事を思った。
「おれ、移住しようかな」
思わず口に出ていた。
聞いていた南田さんはニカッと笑った。
「いいね、来ちゃえば?」
毎日こんな夕日が見れたら最高だな。
海の近くで生活したら、そんな生活ができるかもしれない。
そんな思いがすとん、と降ってきた。
会社はどうしよう、遠くなってしまう。
今の家からまた週末通えばいい話じゃない?
引っ越す必要ってあるのかな?
お金がかかるぞ。
しばらくして、おれを正気に戻そうとする声が聞こえる。
でも、そんなこと考えるのがどうでもいいくらい夕日はきれいだ。
おれは一回、乗せられたレールの上から降りてみたい。
嫌だったらまた戻ればいいし、戻らなくてもいい。
きっとそれが自由ってことだ。
おれはきっとずっとそうなりたかった。
あとのことは引っ越してから考えよう。
波の音に溶け込んで、江ノ電の踏切音が遠く聞こえた。
《了》
最後までお読みいただきありがとうございました!
あとがき▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

