
【未来が広がる読書術を伝授!】選書マエストロによる本のお悩み相談室
テーマ別に展開しているオンラインイベント『TSUKURU SDGs NIGHT』。
今回は”選書マエストロ”こと川上洋平さんがパーソナリティを務める「読書の極意101(いちまるいち)」第2回です!
book pick orchestra代表で選書のプロとしてご活躍中の川上さん。
前回のイベントでは、読書の価値観が変わるような、本とのつき合い方の多様性を伝えてくださいました。
今回のテーマは「自分の未来の可能性を広げる読書術」ということで、
人生が豊かになる読書術を伝授いただきました!!
ちなみに本イベントの呼び名101(いちまるいち)には、アメリカでは”初心者コース”といった意味合いがあるそう。誰もが気軽に集える場です。
初参加の方から、リピーターまで、今回も様々な年代・立場の方が集まりました。
それぞれの人生の可能性を読書で説く…川上さんの深イイ話、満載です!!
ちなみに第一回の内容はこちら↓ ぜひ合わせてお楽しみください^^
嫌いな本もプラスになる!?

トップバッターの相談者は、新卒2年目で休職中のYさん。
「会社の上司は大きなビジョンを持っており、自分の価値観をはっきり言う人なんですが、そりが合わなくて、、。」
言われるがままに仕事を引き受け続け、精神的に病んでしまったという。
「部下目線から上司にうまく提案していける力になるような本、知恵をお聞きしたいです。」
川上) 上司の方はビジョンをもっていて情熱がある方なんだと思います。
でもそりが合わないと、正面から向き合ってしまっているとどうしても違いが目についてしまいますよね。
本を読むときに中のキャラクターに心を重ねたりするように、一度上司の側についてみましょう。
会社の経営者側と社員を例えに出すと、
社員は懸命に働いているのに上から評価してもらえないと不満になります。
社員は目前の仕事を一生懸命やっている。
一方で経営側はお金が回っていることを重要視し、経営全体を見ている。
見ているところがそもそも全然違うと、気持ちが通じ合わないんですよね…
相手の気持ちを知って提案するのとそうでないのとは通りが違います。
上司とあなたを同じ向きにする、そうすると絶対ぶつからない。
些細なことからで良くて、例えば、頷き方ひとつでも、上司の方と同じ方向向いてたら上司の方は気持ちいい。
やっていることがわからなければ聞いてみるっていうのも大事。
なるべく仕事とか”目的”にとらわれない時間、余裕があるときに、”上司と部下”ではなく、同じ”人間”としてどういうことなのか考えて接するといいと思います。
上司も威圧的にやろうとはしてないはず。
気持ちがわかれば、自分の意見を通そうとするまでもなく、自然と通るのではないかなと思います。
本でも、合わない本、苦手な本はありますよね。
大抵の人は愉しい、面白い本を求めがち。
でも、嫌な本は、合わないタイプを知っておく、という点でプラスになると思います。
嫌な人であっても、心寄せる面がまったくないってことはないのと同じで、
どんな本であっても、どういう観点で読むかが大事
例えば、上司と似ている本の中のキャラクターを思い出して、そのキャラのふるまいを観察してみると、上司の気持ちも見えてくるかもしれません。
本はまだ見ぬ自分に出会えるツール
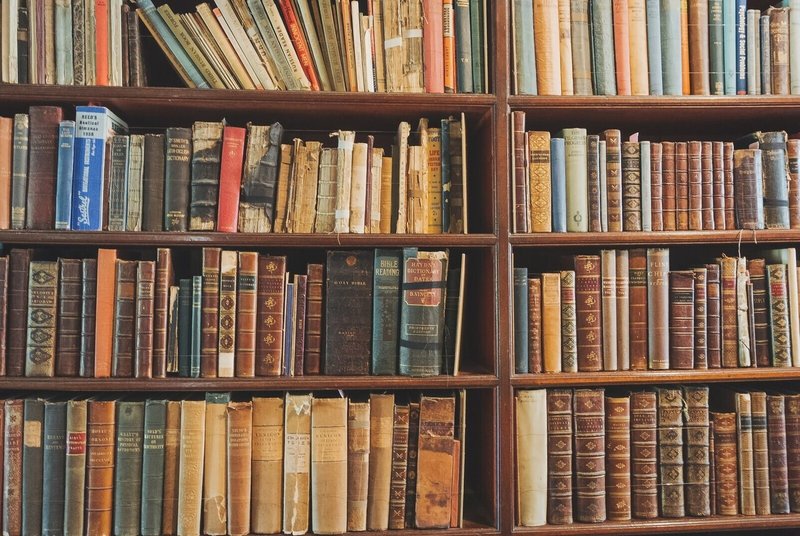
続いての相談者は、定年後の自分の人生について考え始めている、という某大手メーカー勤務のMさん。
「あと10年ほどで定年を迎えますが、まだキャリアの棚卸ができていない状態で、、自分に何ができるのか模索しており、色々本を読んでヒントを得ようとしてますが、答えを見いだせてません。」
川上) 誰しも長く同じ仕事に就いていると、その延長線上で物事を考えようとする傾向にあります。
逆に可能性を広げるっていうことでいうと、自分が今までやってきたことの中に10年後があるってのを一回外してみるといいかもしれません。
誰もがスーパースターとかある分野での天才にあこがれますね。
自分があるひとつのことにすごく長けていたら、周りも薦めるでしょう。
本人が良ければそれでいいでしょうが、人間って思ってる以上の可能性があると思うんです。
褒められる状況の中だと、自分の中に眠っているかもしれない可能性を掘り下げる機会がなかなかないですね。
もし気づきさえすれば、世界的なレベルに達せられるポテンシャルがまだ自分の中にあるかもしれない…。そういう考え方すると、手に取る本も変わるかもしれません。
本屋や図書館で普段行かないようなコーナーに行ってみる。
可能性がぐんと広がると思います。
人の役に立つこと、自分にできることを...と、会社に勤めていると、無意識にハードルあげてしまいがちだったりします。
周りの人から見て意味なくても、自分が楽しい、と思えることが大事です。
言語化がすべてでない
続いては、前回の川上さんのイベントに参加したことで、本を読みたくなり、最近は通学時間を利用して本を読んでいるという大学生のNさん。
「最近は啓発本を読んでいて、いいと思った言葉をスマホにメモしたりしています。でも、結局メモ見返してなくて…手間のわりに無駄なのかなと思ったり…良い読み方、アウトプットの仕方はあるのでしょうか。」
川上) 読み方ってたくさんあるので、これ!という答えはないですね。
メモを振り返らないとしても、メモをとるという”体を動かすこと”には意味があると思いますよ。
今は会社内でも見える化、言語化を重要視されたり、とにかく伝えようって意識が強すぎる。想いを誰かに伝えるときに、どう思ったか、説明を求められがちですよね。
でも昔の和歌とかって情景を見て”心を寄せている”っていうことに焦点を当てている。
例えば、松尾芭蕉の有名な一句。
柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺
これ、何も考えがない。情景に溶け込んでいる。
本を読んで心に響いたら、熟読したり説明したりする必要は必ずしもなくて、これいいなってなってる状態がいいんです。
言葉にするのは大事ですが、自分の必要性が出てこないと生まれないもの。
誰に評価されるでもなく、自分がよいと思うのが一番です。
本に書いてあったことを実際に実践してみる、というのもひとつのアウトプットですね。
言語化だけではありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「読書」というと気を張ってしまいがちかもしれませんが
川上さんは「あ、それでいいんだ」と思えるような、それぞれに合った本の楽しみ方を教えてくださいます。
この記事を読んで、明日、何か一冊手に取ってもらうきっかけになりましたら幸いです。
* * *
2021年もイベント開催を予定しております。
随時更新していきますので、ご興味のある方はぜひ下のイベントページをフォローください!!
【SDGs関連事業相性診断はじめました】
弊社では、SDGsに関連した事業やCSRに関する取り組みについて、ご興味のある方を対象にSDGs関連事業の相性診断をはじめました!
3分程度で答えられてしまう相性診断、答えきった後には弊社からのささやかな”お返し”も待っていますのでぜひチャレンジしてみてください!
【お仲間募集も年中無休でやってます】
弊社ではSDGsに関わる事業開発を進めていくにあたって、弊社のお手伝いをしてくださるお仲間を年中無休で募集しております。
職歴や学歴、性別は不問です。「まずは週末だけのコミットから...」というのも大歓迎なのでご興味ある方は、ぜひ下記のアンケートフォームからご応募いただければ幸いです。
頂いた情報は、当社プライバシーポリシーに準じ、取扱いさせていただきます。
* * *
この記事を書いた人は
yuri
読みたい本が多すぎる
今日この頃
もしよろしければ、サポートも宜しくお願い申し上げます。 この記事を通して、貴方とご縁を頂けたことに感謝です(^^)/ 頂いたサポートは、発信させて頂くコンテンツの改善に活かさせて頂きますm(__)m
