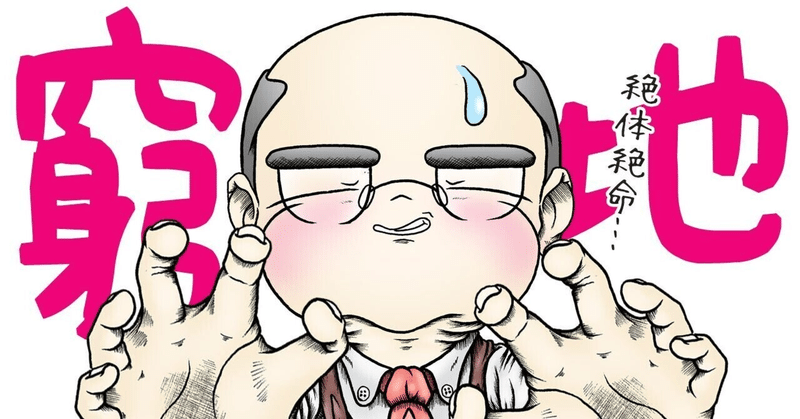
政治講座ⅴ1223「ロシアの核兵器使用」
核の恫喝はロシアの常套手段化しているが、先般のロシアのミサイル失敗率60%と言われている。兵器の火薬の劣化は数年と言われている。核兵器の起爆剤の三重水素(トリチウム)も3年で劣化すると言われている。劣化した起爆装置では核分裂を起こせないのである。6000発保有するロシアの核兵器の保守管理が出来ているのであろうか?ウクライナが核兵器を放棄した理由は保守管理が大変だからとも言われている。今回はロシアの核兵器の報道記事について紹介する。
皇紀2683年7月25日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
「核兵器の使用はプーチン次第」防衛研究所・高橋杉雄が考える、ロシア・ウクライナ戦争で「核兵器」が使用されるタイミングとは
高橋 杉雄 によるストーリー • 4 時間前
「戦争の長期化は間違いありません」防衛研究所・高橋杉雄が語った「ロシア・ウクライナ戦争終結のための“2つのシナリオ”」 から続く
2022年4月に火蓋を切った、ロシア・ウクライナ戦争。この戦いで、核兵器が使用される状況とはいったい?
防衛省防衛研究所防衛政策研究室長で、ロシア・ウクライナ戦争の解説者としてニュース番組でもおなじみの高橋杉雄さん編著 『なぜウクライナ戦争は終わらないのか デジタル時代の総力戦』 より一部抜粋してお届けします。(全2回の2回目/ 前編 を読む)

◆◆◆
ロシア・ウクライナ戦争は、核兵器使用の可能性が常に意識される戦争でもある。事実、開戦以来ロシアが何度か核恫喝を行っており、現在は、冷戦終結後、最も核使用のリスクが高まっている状況といえる。であると同時に、2023年5月現在、核兵器は使用されていない。その意味で、核抑止は機能しているといえる。
ただし、この戦争においては非対称な形で核抑止が作用している。言うまでもなく、ロシアは米国と並ぶ核の超大国であるが、ウクライナは核兵器を保有していない。そのため、ウクライナに対しては、条約上の同盟国ではないが、やはり核の超大国である米国がバーチャルな核抑止を提供している状況にある。
そのことが、ウクライナが核兵器を保有していないにもかかわらず、ロシアの核使用が抑止されている大きな理由になっている。ロシアは、米国の直接参戦はもちろん、武器支援をためらわせる効果を核抑止に期待している。
一方、米国は、ロシアによる核兵器の使用を抑止することが核抑止の役割になっている。
核兵器使用が想定される場面
では、この戦争において核兵器が使用されるとすればどのような状況だろうか。ここではその点を考える上での前提を二つ確認しておきたい。
一つは、核兵器の使用の決定についてである。ロシアの場合で言えば、軍事ドクトリンという形で、核兵器を使用する状況の基準をある程度明らかにしている。しかし、核戦略の専門家の間では、何らかの条件が設定されていて、その条件が満たされれば核兵器が使用される、あるいは条件が満たされなければ核兵器は使用されない、と考えるのはアマチュアであると言われている。
核兵器の使用は、事前に公表された基準に基づくものではなく、その瞬間におけるその国の最高指導者自身の主観に基づいて決定されるからである。つまり、ロシアの核兵器の使用はプーチン大統領という個人が下す判断によって決まるのである。
もう一つは、核兵器の使用のされ方である。核兵器には、戦術核と戦略核とがある。戦術核は、基本的には戦場で使うことを主目的として設計された兵器であるから、一般的に威力が小さくなる。
一方、戦略核は、相手の核戦力や本土の都市を攻撃するために設計された兵器であり、一般的に威力は大きい。こうした違いがあることから、威力の小さい戦術核の方が使いやすいと考えられることが多い。
しかし筆者は、この戦争について言えば、爆発威力から使用の可能性の大小を推測することは適当ではないと考えている。理由は、爆発威力が大きかろうと小さかろうと、核兵器は核兵器であり、威力が小さければ「使いやすい」というような単純なものではないからである。
むしろ爆発威力は、どのような目的で使用されるかによって決まるだろう。そこで、具体的に核兵器の使用目的を考えるとすれば、相手の軍事力を破壊する軍事的効果のために利用されるか、相手の抗戦意思の破壊を期待する政治的効果のために使用されるかのいずれかであろう。前者の場合にターゲットになるのは前線の戦闘部隊であろうし、後者の場合には都市が狙われる可能性が高い。
ここでポイントになるのは、後者の政治的効果を狙った核使用の場合に重要なのは心理的インパクトであるから、「核兵器」でさえあれば、威力にかかわらず効果が期待できることである。すなわち、都市攻撃に使うとすれば核兵器の威力は小さくても十分であるといえる。
一方で、戦場で前線の戦闘部隊に対して使うとすれば、物理的な破壊力の大きさが必要になるため、核兵器の威力が大きくなければならなくなる。つまり、逆説的だが、政治的効果を重視した都市攻撃に対しては戦術核が使われる可能性が高く、軍事的効果を重視した戦場での核使用においては戦略核が使われる可能性が高くなると考えられるのである。
プーチンが核兵器の使用を考える状況とは
以上の前提で、プーチン大統領が核兵器の使用を考えるとすれば、まず核使用による利益が、それに伴うコストを上回ると認識することを前提として、大まかに言えば以下の二つの状況においてであろう。一つは、「核兵器の使用によって決定的な勝利を得ることができる」ときであり、もう一つは、「核兵器の使用によって決定的な敗北を回避する」ときである。
しかしながら、開戦直後ならまだしも、全体の戦局が膠着している現在、前者のシナリオはなかなか考えられない。前線ないし都市で核兵器を使用したとしても、ウクライナが抗戦を諦めるとは考えにくいからである。
ウクライナ国内においては、既にマリウポリやバフムトは核攻撃を受けたのとほとんど変わらないような破壊を受けており、新たに別の都市が同じような破壊を受けたとしてそれでウクライナ側の抗戦意思が砕けるとは考えにくい。また、仮に核兵器の使用によって一時的な優位をつかんだとしても、核使用が米国の介入を招いた場合には、せっかくの優位を失い、状況はむしろ核使用の前よりも悪化してしまう可能性もある。
では後者の「決定的な敗北を回避する」シナリオはどうか。これは具体的には、戦場においてロシア軍が大敗し、通常戦力ではウクライナ側の進撃を阻止できなくなった場合に現実化する可能性がある。
核兵器を使用しなければ占領地を維持できない、あるいはウクライナ側からロシア領への逆進攻のリスクまであるというような状況になれば、プーチン大統領が核使用を考慮する可能性は一定程度存在する。
もちろんこの場合でも、核兵器の使用が米国の介入を招く可能性はある。しかしながら、どのみち戦場で負けているということであれば、米国の介入によってもそれほど状況は変わらないと判断する可能性もある。
むしろ逆に、米国の介入に対しても核使用で対抗すると恫喝することで、米国の介入自体を抑止できると考える可能性すら存在する。ウクライナが2022年9月にハルキウ反攻を成功させ、北部戦線でのロシア軍が壊滅状態に陥り、ウクライナ軍がロシア国境まで進出したときが、開戦後にこの種類のシナリオに最も近づいた状況であった。
そのため、このタイミングで米国もロシアに対して極めて強いメッセージを送っている。ただし、この時はプーチン大統領は核使用の決断を行わなかった。むしろ30万人の動員令を発することで、通常戦力を再建する道を選んだ。つまりこの段階でも、プーチン大統領にとっての「決定的な敗北を避ける」ためのファーストチョイスは通常戦力の再建だったといえる。
核兵器使用のタイミングは「利益>コスト」であること
いずれにしても、プーチン大統領が核兵器の使用を考慮する際、核兵器使用による利益だけでなく、それに伴うコストも検討するであろう。コストが利益よりも大きいとプーチン大統領が考える限り、核兵器が使用される可能性はない。そのコストのうち、最大のものが米国の介入である。その意味で、米国の反応についてのプーチン大統領の認識が、核抑止を機能させる上で最大の変数だということになる。
なお、ここで言う米国の介入は、核報復に限られない。通常戦力による介入もオプションとしては考えられる。実際、仮にロシアが核兵器をウクライナに対して使用し、米国がウクライナにいるロシア軍に対して核兵器を使用するとすれば、ウクライナは2波にわたる核攻撃を受けることになる。そう考えていくと、米国が介入するとしても、それは核報復の形ではなく、通常戦力による介入の形を取る可能性の方が大きいと言える。
しかしながら、ゼレンスキー大統領が、米国の核兵器による報復を望んだ場合にはその限りではない。実際、これまでもウクライナの国土は通常戦力によって大規模な破壊を被っている。もし米国の核報復が戦局を大きく変えるとゼレンスキー大統領が考えるならば、核使用を容認する可能性はある。そのとき、米国は、核報復に踏み切るか、あくまで通常戦力による介入にとどめるか、重大な決断を迫られることになる。
(高橋 杉雄/文春新書)
参考文献・参考資料
「核兵器の使用はプーチン次第」防衛研究所・高橋杉雄が考える、ロシア・ウクライナ戦争で「核兵器」が使用されるタイミングとは (msn.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

