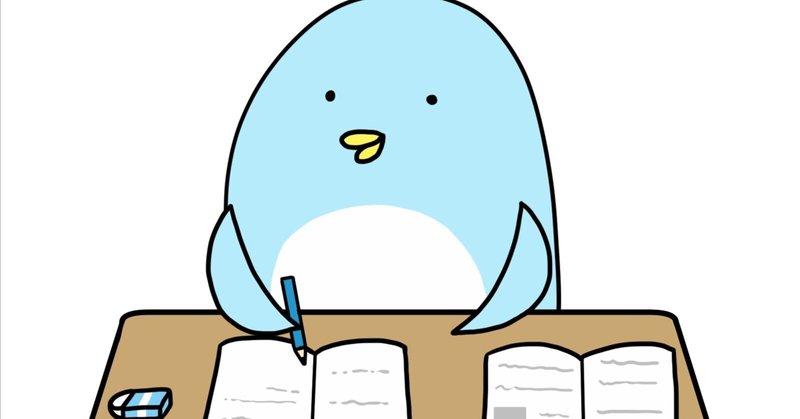
上下運動をどう対処するのか?
まず前提として置きたいのが中立論は基本的に不要という事だ。
従来の中立論というのは本人の姿勢ではなく、その運動体そのものだ。だから「私は中立です。中庸です。」というのは誤謬と言わざるをえない。「客観的総合的に判断する」という姿勢も権威側に委ねられる事が多々あるのである。
アホリベラルが大政翼賛会を生み出すのも当然である。アホリベラルはすべてを中立や等価にすることで上下運動を委縮させ、一元権力社会の構成員として活躍するようになる。
正統主義は、まさに相互運動でバランスを調整する事であった。王権貴族社会が終焉しその役割が市民社会に委ねられるようになったという話でしかない。
まず上からの激流にどう対応するのかという話である。
上が発している激流が人治的なものなのか法治的なものなのかが重要な判断基準である。すなわち「〇〇さんの御意向だから聞きなさい」については絶対に許容してはならないのである。
人治的なものであれば、権力層の恣意的な思惑が入っている可能性が高い。「はいそうです。」と同意してはならない。この激流に鯉のように遡及していかねばならないのである。それがあたかも神治や科学や因襲や社会性や通俗道徳を謳っていたとしても実際は権力層の「お気持ちや権益や忖度」で動いているのである。
人治に依らない法治的なものであれば、手続き通りに理詰めで交渉をしていかざるを得ない。しかしここはいい加減ではなくきちんと手続きに則ることが大事だ。
次に下からの激流にどう対応するのかという話である。
下が発している逆流が批判的なものなのかクレーム的なものなのかが重要な判断基準である。
すなわち「オレは客だぞ。客の云う事を聞くのは当然やろ」については絶対に許容してはならないのである。
批判的なものであればきちんと受容をして、構造面を変革していけばいい。相互の議論を深めてよりよい妥協点を見つけていけばいいのである。しかし社畜メンタルの日本人はこの作業がきわめて下手である。それゆえ似非先進国なのである。
クレーム的なものであれば聞く価値はない。
クレーマーのカタルシスを得るためのやり取りになってしまうからだ。かまってちゃんや独居老人が許容される場所はない。社会構造がどう変わっても連中のメンタリティは変わらない。
再度言うが中立論なんてものはいらない。価値相対主義になってしまうからだ。
「権力者と服従者」「加害者と被害者」「人治主義と法治主義」「批判者とクレーマー」は等価ではない。仮に中立論があるとしたら戦いのなかにある。運動のなかにある。その外にはない。
上からの激流はなるべく人治性を希釈するように、下からの逆流はなるべくクレームを希釈するようにする。
法治や批判に則って社会を少しずつ変革していく。これが上下運動の対処方法である。
学習教材(数百円)に使います。
