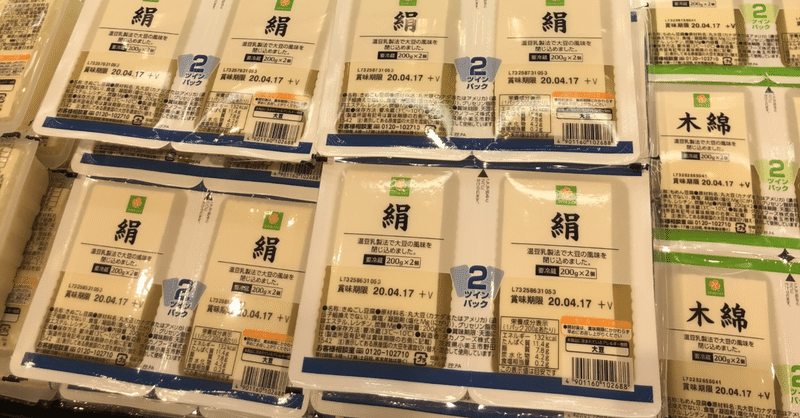
浮世渡らば豆腐で渡れ(1) 藤井豆腐店の1日
豆腐の仕込みは重労働
豆腐屋の仕事は、朝早く始まる。
開業当初、父と母は、午前2時には、寝床から起き出していたものだ。
年月がめぐり、豆腐づくりの機械で作業の手間を省けるようになると、ふたりの起床時間は、午前3時、そして4時へと遅くなりはしたものの、朝から晩まで働き詰めなのは、引退するまで変わらなかった。
夜明け前から、それぞれ仕事を分担し、開店に備えた。豆腐づくりは、もっぱら父の役割。そのほかの作業が母の役割だった。
早朝、父は、豆腐のもととなる豆乳を作りだす。
ゆうべのうちに水に浸しておいた大豆を、水から引き上げ、水切りをする。
水を含んだ大豆は、そのぶん重くなっていて、引き上げるのも、なかなか重労働だ。
つぎに、引き上げた大豆を「石擦り」する。
石臼の入った機械に大豆を入れ、少量の水を足しながら豆を挽くのである。
機械の口からは、ドロドロになった大豆の汁が出てくる。これは「生呉(こし)」と呼ばれるもので、豆乳ではない。
できた生呉を、大きな釜に入れ、高温で炊いていく。
このとき大量の泡が出るので、店によっては、炭酸カルシウムといった消泡剤を入れることもある。
うちの店では、泡は手作業で取っていた。煮えたぎる釜のそばで、これもまた重労働だった。
こうして炊きあがった生呉から、豆乳を濾(こ)して絞る。絞った残りのカスがおからである。
おからにも栄養がたくさんつまっているので、当時は畑にまいて肥料にしたり、いまでも家庭料理に使ったり。母はよく、
「むかしから、大豆は捨てるところがないと言ったものだ」
と、姉とわたしに語ってくれた。
豆乳ができたら、いよいよ「豆腐づくり」に入る。
直径1メートルほどの桶に豆乳を入れてから、そこへ「にがり」を加える。にがりは、豆腐をかためる役割をするもので、平棒でかき混ぜていると、ほどなく、豆乳が固まり出す。これが豆腐の元だ。
最後に、型にさらしを敷いて、ひしゃくで豆腐の元をすくって流し込む。
ふたのうえから重石を載せて、豆腐の元のなかの水が抜ければ出来上がり。
にがりの量は、絹ごし、木綿、焼き豆腐の種類によって違う。
また、木綿豆腐の独特のざらざらした風合いは、豆腐が固まりかけたところで一度崩して、ふたたび枠に入れ、固め直すことで生じる。
藤井豆腐店は、豆腐のほかに、がんもどきと油揚げも作っていた。
がんもどきと油揚げは母の担当だった。
開店したばかりのころ、母は、和服に割烹着の出で立ちで働いていたが、豆乳やおからなどの汚れがひどいので、間もなく機能的な洋服に切り替えた。
美しい和装で、甲斐甲斐しく働く母の姿は、いまも目に焼きついている。
母の作るがんもは、姉もわたしも、大好きだった。
母は、前日に作った木綿豆腐を、水槽から上げて、しっかり水切りしてからよくすりつぶす。そこに、おろした長芋や銀杏(ぎんなん)、ひじきなどを混ぜて、まるく成形する。
最初は、やや低温の油で揚げ、段階を踏んで、次第に高温で油で揚げていく。そのため、中身はフワッと、外側はカリッと仕上がるのだ。
うちの店のがんもは、3度も揚げる工程があり、母は大変だったと思うが、その分、他所よりも、美味しかった。
美味しい水がつくる美味しい豆腐
豆腐作りには、原料の大豆を浸すところから、完成して水切りするまで、常にきれいな水が必要だった。
美味しい水のある土地では、美味しい豆腐を作ることができるのだった。
わたしたちの長屋のあった、東富山町は、町なかにコンクリートで覆った大きな共同井戸があり、各家へ配水されていた。
これが、美味しい水との評判で、水質調査をしたところ、富山県で4番目に美味しいとのお墨付きをもらうほどだった。
この水を、遠くからわざわざ汲みにくる人もあり、良い水を求めてか、近所には、金魚屋さんも店を構えていた。
父の豆腐職人としての腕や、母の料理の腕があったのは、もちろんだが、町の中にある美味しい井戸水が、藤井豆腐店の豆腐の味に一役かっていた。
ありがたいことに、豆腐の売れ行きは順調だった。
最初のお得意さまは近所の方たちだった。
さらに父は東富山の食料品店や、不二越や、三菱アセテートなど地域の工場を回って、そこへも販路を拓いた。
ただ、郊外の農家の方たちは、慎重だった。
これまで買っていた店を変えたくないのか、誰も買わない、まったく売れないという日がずいぶん続き、父も母もずいぶん苦悩したようである。
それでも父は、週に必ず行く日を決めて、作り立ての豆腐を売りに運んだ。
ある日、ぽつんと一人のお客様が、豆腐を買ってくれた。
父は、手応えを感じるものがあったのか、
「これで行ける、これで行ける」
と、何度も繰り返して言った。
父の言う通り、しばらくすると、
「ここなち(この家)の豆腐は、美味しいから」
と言って、少し離れた町や村から買いに訪れるお客さんが増えていった。
近所で、最後まで買ってくれないお客様がいたが、いちど買ってくれてからは、最後まで長く続いたお得意様となった。
当時、店で働いていたのは、父、母のほかに、従業員のおばさん一人の、三人だけ。みんな、コマネズミのように、忙しく動き回っていた。
それなのに、である。
豆腐は売れているのに、なぜかいつもお金が足りない。
父も母も、忙しすぎて、台帳をつける暇がなかったのだろうか。開業して1年ほどしたころは、資金繰りに困り、大豆を買い付けたお金も、返せないほどになったしまった。
借金と目くばせ
その日は、仕入れた大豆の集金日だった。
店には誰もおらず、がらんとしずまった土曜日のことだった。なぜだか父は、奥の部屋に引っ込んで、布団を頭までかぶっていた。
たまたま、家にいたわたしが、ひとりで遊んでいると、表の戸が開いて、大豆屋さんが顔をのぞかせた。
「藤井さーん。だんなさん、おられるけ?」
父は返事をしなかった。
居留守を決めこんでいるのだ。
だが、幼いわたしは、そうとは気づかなかった。
「おじょうちゃん、お父さん、おられる?」
大豆屋さんに聞かれると、
「うん、おるよ、お布団かぶっとるよ」
素直に、奥の部屋の父を指差した。
父は、黙っとけとでもいうように、片目をつぶって、なんどもわたしに目くばせをした。
「お父さん、どうしたが?」
また、大豆屋さんに聞かれて、わたしは
「お父さん、目っこしとる! わたしに目っこしとる!」(目っこ=目くばせのこと)と、元気よく答えた。
大豆屋さんは、それですべてを察したのか、ちょっと気の毒そうな顔をして、何も言わずに店を出ていかれた。
奥の部屋でそれを見届けていた父は、すぐに布団から抜け出すと、金策のために出かけて行った。
(写真はイメージです)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
