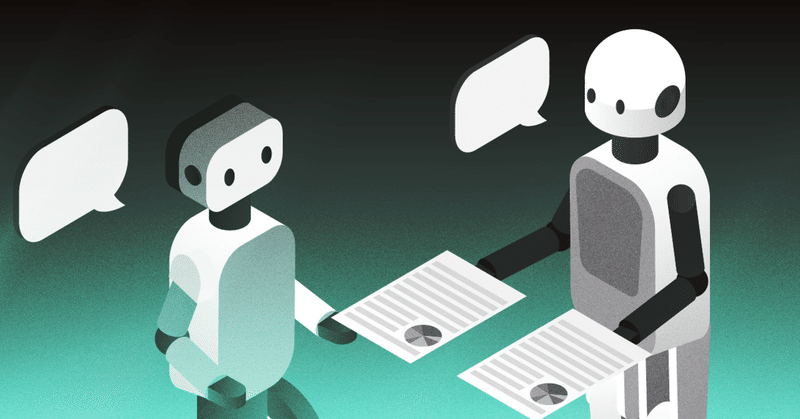
サービスは人。技術も人。
先日の記事で、『商品力のあるアナログ会社』について書きました。M&Aにあたって実は狙い目であり、そこにITを加えるなど上りエスカレーター(時流)を取り込むと、古い業界であっても成長できる可能性が出てくる。
無人化技術も有人開発
『商品力』とは幅広い概念ですが、マテリアル(物品)だけでなく、高い技術力がある人(従業員)も、その会社の商品力です。しかも、業界によってはとても強い商品力です。技術というとモノを連想しがちですが、モノの技術も人がいないと開発できないわけです。当たり前ですが、これめっちゃ大事な事実です。
例えば、パソコンやタブレットを開いて仕事をするという日常の行動一つに、あるいは、朝起きて顔を洗ってという一連のルーティンの中に、様々な「モノの技術」の恩恵を受けています。それらは、誰かが開発し、誰かが専門的な技術を持っている。そうでないと、水道が壊れても水漏れ工事ができる人がいなくなります。漏れっぱなしです。
それらも自動的にやるような技術が今後は出てくるのでしょうが、それは未来の話だし、何よりその「人がいらなくなる技術」も、人が開発するわけです。私たちが何気ない日常を過ごすためには、ありとあらゆるところで専門的な技術が必要で、それぞれの分野の技術者が開発したものの恩恵に授かりながら、毎日生きています。

※高度な技術は人が作り、人が動かす
なんか当たり前のことを言ってる感じがしますね。何が言いたいのかというと、M&Aに関わっていると、業種によっては『人』の重要度が以前に増して大きくなっているとことを実感するのです。理由は、言うまでもないですが人材不足。そして、今後加速度を付けて益々足りなくなることは目に見えているからです。
人材不足の時代は『人』が最大のバリュー
私のような文系50Gが言うのもアレですが、特に理系が足りません。技術者を目指す人が少ない。IT業界ですら、エンジニアは慢性的な人材不足。私が地方でWeb系のプログラマを募集しようとしたときは、「そもそも登録者が少なすぎる」という理由で大手の求人企業から断られました。
ちなみに、それ名古屋ですよ。地方と言っても、東京、神奈川、大阪に次ぐ人口がある愛知県の中心です。愛知はほぼ名古屋です(三河の人に怒られそうだけど)。東海市あたりの人もみんな「名古屋」と言うくらい、愛知は名古屋です。そこで大手の求人企業から断られるのです。そこよりもさらに地方に行くと、もうIT技術者の採用なんてほぼ無理なのです。

※名古屋のいい写真がなかったので、熱田神宮の信長塀
M&Aの決め手も『人』
別の例で言いましょう。M&Aの案件で、例えば自動車整備工場が売りに出ているとします。これから急速にEVシフトすると、需要がなさそうな業種です。でも、当面EV化しそうにない、例えばトラックなんかはまだまだ需要があります。そういうニッチに特化しているところは買い手が付きやすい。加えて、業界は慢性的な整備士不足。整備士の専門学校に入る人、資格を取る人は年々減少していると聞きます。30~40代の比較的若い整備士が複数いるのなら、余計に売りやすいのです。
M&Aの案件で、こういうのもありました。ある製造業の設備に関して、人は引き継がないことが前提なので、そのプログラムは誰がやるかと悩む買い手。そのプログラムをする技術者の目途が付くまで、案件は宙に浮きました。自社の設備にはないプログラム言語だったんですね。結局、当面の仕事のプログラムは予め売り手にしてもらうということでM&Aが決まりましたが、買い手にとってはその技術者を採用することが当面の課題です。
結局、M&Aの決め手になるのも『人』なのです。高度な技術を有する設備があるならなおさら、それを管理する人が必要で、設備がバリューになるわけではないのです。人がいないとそもそもM&Aも成立しない。
会社を成長させるのも人
今の技術は、人がいなくてもできるという方向性に進んでいることは確かです。しかし、その技術を作るのは人です。プログラムがプログラムを作るようになっても、元のプログラムは人が作る。禅問答のようなやり取りですが、無人化技術も有人開発が必要という当たり前の前提に立てば、企業のバリューは人なんだということが改めてわかってきます。
「技術」をもっと広い概念で捉えると、会社の中で人材を育成するのも技術です。もっとも、人間の場合は変数の塊なので、技術に偏向しているとマイナスになることもありますが、育成、管理(個人的に嫌いな言葉ですが)はやはり技術が必要です。そして、それらは人じゃないとできません。その仕組みを作るのも人です。
将来、M&Aによるイグジットを想定しているベンチャーの人も、そのことは頭に入れておいた方がいいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
