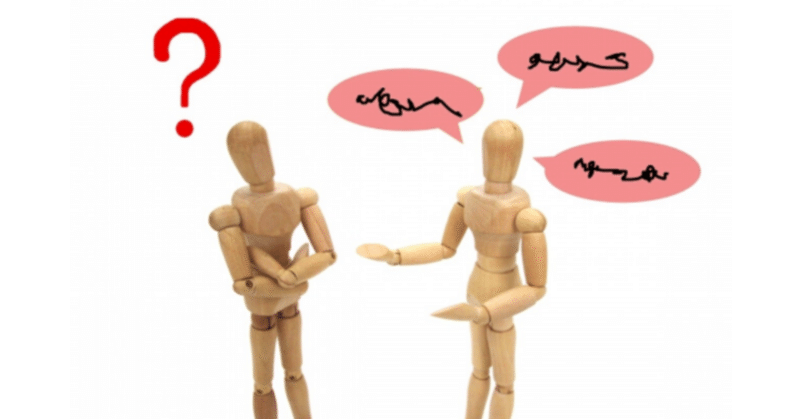
伝わるのが当たり前なのか?伝わらないのが当たり前なのか?
どうも、高尾トンビです!
「人とのコミュニケーションがうまくいかない・・・」と悩むことがありませんか?
僕は、結構それで悩むことも少なくありません。
コミュニケーションから派生する様々な問題について、「コミュニケーションの本質」をどう捉えるのか?によって、対処の仕方が変わってくると思います。
伝わるのが当たり前という前提に立つと

コミュニケーションの本質について、基本的に「伝わるのが当たり前」という前提で捉えると、伝わらないのは相手の理解力に問題があるという風に捉えがちになります。
小さなお子さんをお持ちの方はわかると思いますが、小さな子どもは自分の伝えたいことが伝わらない場合、「なんで分かってくれないの?」と怒ってしまうことがよくあります。
親はなるべく子どもの気持ちを汲み取ろうとしますが、それでもうまく伝わらないことがあります。
しかし、それは小さな子どもだけではありません。大人も同じようなことがありますよね。
伝わらないのが当たり前という前提に立つと
一方、コミュニケーションの本質について、「伝わらないのが当たり前」という前提に立つと、伝わらないのは自分の伝え方に問題があるという風に考えることが多くなります。
「ああ、やっぱり伝わらなかった・・・」と考えるので、伝え方を工夫するようになります。また、なんとか頑張って伝えようと努力します。自分の伝え方が悪いだけなので。
そして、伝わったときは単純に嬉しくなります。「ああ、やっと伝わった!」と。
相手を変えるのか?自分が変わるのか?
相手を変えるのはなかなか難しいです。
相手に原因があると思ってしまうと、コミュニケーションの問題は解決するのが辛くなってしまいます。
一方、自分に原因があると思うと、少なくとも努力しなければ・・・という意識は芽生えると思います。
どちらが良いか悪いかはさておき、僕は自分に努力する余地があると考える方が好きです。
多様性の話についても理解しやすくなる。

多様性の話についても、コミュニケーションの問題と同じような構図で考えると理解しやすくなります。
「伝わらないのが当たり前」という考え方と同じように、「人それぞれ違うのが当たり前」だと。だから他人を尊重するとか受け入れるとかいう以前に、「そもそも違う部分があるのだから、その違いをどのように調整するのか?」という話になります。
「理想論」や「正論」を語るつもりはありません。
理想論やカッコつけた正論を語りたいのではありません。
ただ、少しだけ自分の話をすると
僕はどちらかというと、みんなと少し違う部分があるような子どもでした。例えば小学生で口ひげが生えていてバカにされたり、中学生の頃に哲学にはまってそれを周りの友人に話したら浮いてしまったり、高校時代は運動部に入っていましたが、部活以外の時間も部活メンバーと一緒にいるのが嫌で単独行動をしていたので、「一匹オオカミキャラ」にされていました。
いま、思うと全く大したことがないのですが、当時は「なぜ、みんなと同じでなければいけないのか?」と思いながらも、「みんなと同じになれない」自分が少しコンプレックスでした。
そんな僕でしたが、19歳になって東京の大学に行ってから変わりました。
東京は超個性的な人がたくさんいたからです。

いまは、インターネットがあるので、世の中にはいろんな人がいるし、自分は対して変わった人でもないということは理解できますが、僕は学生時代は周りには同じような価値観、同じようなライフスタイルの人がほとんどだったので、しんどいと思っていました。
でも、自分が理解できないような価値観の人、びっくりするようなライフスタイルの人と出会う機会があって、ホッとしました。
コミュ障という言葉
コミュ障という言葉が世の中に浸透してから辛い思いをしている人がいると思います。
でも、伝わらないのが当たり前だと思えば、そもそもコミュ障なんてないのかもしれない。
もっというと、「すべて伝わっていると思っている人たち」も実は「伝わっていると錯覚しているだけ」かもしれない。伝わっていないことの方が多いかもしれない。そもそも完璧に伝わっている必要なんてないのかもしれない。
本当に伝えたいことがあるなら
本当に伝わらないと困ることがあるなら
どんなに苦労してでも伝えるべきだし、簡単に伝わらなかったとしても嘆く必要はないと思う。
何度も同じことを、工夫しながら伝えようとすれば良い。
今回は、なんかうまくオチはつけられませんでした・・・。
発信力を鍛えていきたいと思っています。いただいたサポートは本などのインプットに活用したいです。
