
失敗した原因を分析する時に重要な視点
どうも、高尾トンビです!
失敗するのが怖いなら「実験」だと思いましょう!ということを別のnoteで書いています。
今回は、「失敗した原因」を分析する時に重要な視点について書きたいと思います。
そもそも「失敗」とは

失敗の意味を辞書で調べるとこんな感じです。
「失敗」とは
やりそこなうこと。目的を果たせないこと。予期した効果をあげられないこと。
『三省堂 大辞林』より引用
行動したけど、目的を果たせない。当初予定していたような効果、成果をあげられない。
まあ、だいたいこんな意味ですよね。
でも、「失敗」をこういう「ざっくりしたイメージ」で捉えてしまうと本質を見誤ります。
失敗には質的な失敗と量的な失敗がある。
そもそも失敗には質に関する失敗と、量に関する失敗があります。
例えば、「ブログを始めてみて記事を1本書いてみたけど、うまく文章が書けなかった。」というケースを「失敗」だと捉えた場合
「うまく文章が書けなかった」という点に着目すると、質に関する失敗だと思いますよね。
だから、もっとうまく文章が書けるようになるために、「文章をうまく書く」コツについて書いた本やブログなどを読もうと思う人も多いと思います。
でも、それだけでは改善しない場合が多いです。
量が足りないだけというケースも多い

なぜかというと、先ほど述べたように失敗には「量に関する失敗」があるからです。
先ほどのブログの例を質に関する失敗ではなく、量に関する失敗だと捉えると話がちょっと変わってきます。
「記事を1本書いてみたけど、うまく文章が書けなかった。」
→「2,000文字の記事を書いてみようとしたけど、1,000文字しか書けなかった」
こうなるとどうでしょうか?
ちょっと失敗の捉え方が変わってくるので、改善するための方法も変わってきますよね?
この場合は、「文章をうまく書く(質をあげる)」ための努力じゃなくて、「書ける文量を増やす」を増やすための努力が必要です。
実は多くの段階では「量が足りないだけ」のことが多いです。
なぜなら、量をこなさないと質も向上しないことが多いからです。
質の問題か?量の問題か?
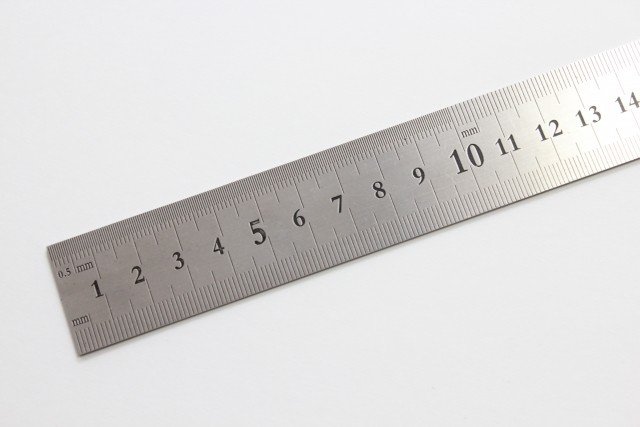
その失敗は質に関するものなのか?質が低いせいで目的を達成できなかったのか?
それとも量が足りないせいで目的を達成できなかったのか?
もしくは質と量の両方か?
きちんとそのあたりを分析しなければいけません。
質なのか?量なのか?で改善方法も違うからです。
目標設定も同じ
ということは、そもそも目標を立てる段階から「質に関する目標」と「量に関する目標」の両方を区別しておく必要があります。
質に関する目標のことを「定性目標」(性質について定める目標)といいます。
量に関する目標のことを「定量目標」(量について定める目標)といいます。
目標設定の段階で「定性目標」と「定量目標」の両方の目標を立てておけば、失敗した時に、「質の問題なのか?」「量の問題なのか?」の区別が楽になります。
「そんなのわかってるよ」というけれど・・・

こういう話をすると、「そんなのわかってるよ」という反論もあるかもしれません。
しかし、僕が数年前までコンサルの業務をしてだ時、結構多くの人が「定性目標」と「定量目標」がごっちゃになっていました…。
目標設定や現状分析、失敗した原因について話す時に、定性的なことと定量的なことを混ぜて話をする人が本当に多いです。
僕も時々そうなってしまう傾向があるので、なるべく定性的なことと定量的なことを区別して書き出したりして「意識する」ようにしています。
まとめ
1.失敗には質が足りないものと量が足りないものとがある。
2.量が足りない失敗の方が多い。
3.定性的な目標、定量的な目標、両方大事!
最後までお読みいただきありがとうございました!
もし、この記事が気に入ったら「スキ」をお願います。
よければ、「フォロー」もお願います。
あなたの「スキ」と「フォロー」が次の投稿のエネルギーとなります。
では、また!
発信力を鍛えていきたいと思っています。いただいたサポートは本などのインプットに活用したいです。
