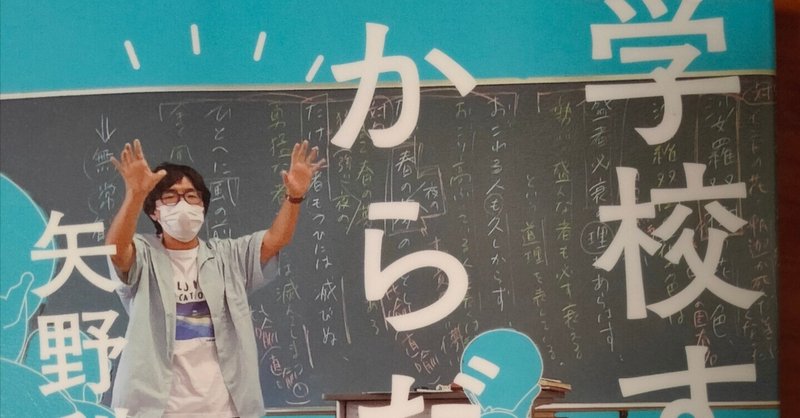
矢野利裕『学校するからだ』~規律と自由は両立するか
本書は学校現場のほっこりするエピソードを集めたエッセイだ。読みやすく、真面目で善良な教育本として読まれているのだろうと思う。尖ったところはないし、だいぶ保守的な教育観を示しているし、まあ誰が読んでもすんなり読めると思う。
本稿では、本書から読み取れる矢野の教育思想を整理しつつ、私の個人的な関心に基づいて検討を加えたいと思う。
教員は芸人?
矢野には憧れの教師はいないそうだが、爆笑問題の太田光のことを「最も敬愛する先生」と呼んでいる。
僕が教員としてモデルにしたのは、それまで出会った先生ではなく、お笑い芸人やコメディアンだったのだ。
こんな教師はめったにいないと思うので、矢野の個性をよく示していると思う。ここを出発点にしていることが、矢野の教育思想を決定づけているように思える。
僕が芸人のような教員を夢想するとき、そこで思い描くのは、コミュニケーションを円滑にまわすMCの姿とは少し異なる。もちろん、そういう資質も必要なのかもしれないが、個人的により追求したいのは、受け手が否応なしに巻き込まれてしまうような圧倒的なパフォーマンスのほうである。
チャイムが鳴ったら、ふいにあらわれ、1時間で空気をがらりと変えて、そのまま帰っていくような。その意味では、すぐれたミュージシャンのありかたにも通ずるのかもしれない。いずれにせよ、教員としての自分が考えることは、生徒がこれまで触れたことがないようなワンダーを与えたい、ということだ。
そんな彼らを振り向かせる「弁舌」とともに、生徒を退屈な日常の外に連れ出さなくてはいけない。教壇とは、そのような非日常の「ドラマ」を披露する芸能の舞台でありうる。
芸人はMCとして上手に場を盛り上げることができる。教師にもそのスキルが求められるだろう。しかし矢野が理想とするのはそれではなく、「受け手が否応なしに巻き込まれてしまうような圧倒的なパフォーマンス」なのだという。学校教師はすべてのクラスに同じ授業を実施するので、まるで落語家のようだと矢野は言う。話の仕方、身振りの仕方、時間配分など細部に渡るまで計算し尽くして講義しているらしい。そうなると当然教師主導の授業になるだろうし、生徒にマイクを渡す時間は限られるのだろう。実際、本書にはアクティブラーニングやファシリテーションに対する懐疑的な意見が繰り返し出てくる。
「自由に発言していいよ」などと中途半端に開かれているときこそ、おうおうにして、声が大きい生徒や表面的に社交的な生徒ばかりがのさばる。反対に、コミュニケーションが苦手な生徒や吃音傾向の生徒などが隅に追いやられる。中途半端な「自由」な空間ほど実質的な「自由」からほど遠い、という危うさがある。
独演会のような講義によって生徒を否応なく巻き込もうと目論む教師というのは、どうだろう、あまり民主的には見えないし、場合によってはハラスメントのリスクさえありそうだ。(矢野はハラスメントになるリスクを否定しない)
以上、教師を芸人に見立てる矢野の考え方を見てきた。私の個人的な感想を付けておくと、私は個別指導の講師なので教師像がまったく違うという印象を受けた。教壇に上る学校教師というのはそういうものなのかという多少の驚きもあった。私から見れば学校教師は表の世界の教育者であり、自分たち私教育の講師はそれを補う存在として、学校では手が届かない所のケアを引き受けていると思っている。それでも予備校などの集団授業の講師であれば、芸人のようなつもりで講義している講師は多いだろう。というか、矢野のほうが学校教師にしてはやけに予備校講師のようなマインドを持っているといえる。ともかく私はあくまで個別指導の講師なので、授業を芸能に見立てたことはないし、授業を非日常にしようと思ったこともないし、自分が喋ることよりも生徒に話してもらうことのほうが大事だと思っているし、そのためにはこちらも自然体でいたほうがいいし、カリスマ性を発揮する必要もなければ面白おかしい話をする必要もないと思っている。ただ、後で述べるように、矢野が重視する「身体的交流」によってコミュニケーションが成立しているという実感は私にもたしかにある。
規律と自由は両立する?
規律と自由の問題が本書の主題だと思う。これについては矢野はかなり保守的であり、基本的に規律を擁護する。そして、規律の中でも生徒たちは自由さを発揮できていると主張する。第1章「部活動」ではサッカー部、ダンス部、吹奏楽部を例に挙げてその主張が反復されている。これは、教壇から一方的に行う教授型の授業にこだわる矢野にとって、それを横から支える傍証として重要な章である。だが私は説得されなかった。
まずサッカーから見ていく。
ちなみに、戦術が高度化した現代サッカーにおいては、かなり細かなチーム内の約束事が確立している傾向がある。見方のゴールキーパーがボールをもったらセンターバックはワイドになり、サイドバックは高い位置を取る、ボランチは低い位置に降りてくる……など。
これを個人の自由の抑圧と見る向きもあるが、個人的にはそういう印象はあまりない。ヨーロッパのプロリーグなんかを観ていても、サッカーの自由さは保たれているどころか、これまで以上に発揮されていると思える。だから、現代のサッカーにおいて、チームの約束事はむしろ、個人の自由を発揮するためにこそ練られていると言える。個人の自由が発揮できる状況こそが組織的に整えられている。それは、民主的な近代社会の理念そのものである。
個人的な印象論に対してケチをつけても仕方ないのだが、私は同意しない。細かい約束事があることにより自由さを発揮できるとはどういうことか。抽象的すぎて理解しかねる。そこで言う「サッカーの自由さ」とは具体的にどういうものなのか。それは民主主義などの政治的概念としての自由とどの程度近いものなのか。私の直感では、それは全然異なるものだと思う。私はサッカーよりバスケのほうが詳しいのでバスケの例で言えば、NBAも組織化、システム化が進んでいるリーグだが、選手たちが自由を発揮しているとは思わない。自由を発揮しているのは特にクリエイティブな一握りの選手たちだけだ。
そもそもスポーツにおける「自由」とか「クリエイティブ」という概念は相当に限定された意味である可能性が高い。それは即興であり、ほとんど反射神経の為せる業にすぎない。精神の自由ともおそらく関係がない。それを「民主的」等の言葉に紐づけるのは相当無理があると思う。
次にダンス部の話。サッカー部の真面目な主将がダンス部の昼休みの公演を観たくて仕方ない様子だったというエピソードの後、矢野もその公演を見てみたら、露出多めで腰をシェイクする煽情的なものだったという。そこから矢野は次のように論理を展開する。そもそもダンスとは日本が近代化するにあたり、号令に合わせて一斉に同じ動作をする「近代的身体」をインストールするために学校教育に取り入れられたものである。つまり、学校におけるダンスとは「もっぱら統制的な身振りなのである」。しかしそのダンス部の公演には解放性があった。
だとすれば、ダンス部のパフォーマンスの解放性とは、学校的な統制を打破するような解放性だったのではないか。ただ単に盛り上がるということではなく、一体感ということでもなく、ほんのつかのま、学校教育に真正面からアンチを突きつけるような、「ズレる身体」のパフォーマンスこそが、学校的な日常を生きる高校生たちの心を奪うのではないか。
本当だろうか?どうしてそんなに深読みをする必要があるのだろうか。普通に考えればそのサッカー部主将は女子たちのエロいダンスを観たかっただけだろうし、「ただ単に盛り上が」っていただけだと思う。
このように、第一章での矢野の論理にはかなり無理がある。矢野は基本的に規律を擁護しつつ、それでも生徒たちはそこからはみだすような自由さを見せるものなのだということを言いたいのだろうが、うまく行っていない。規律あってこその自由というビジョンに対して実例がうまくかみ合っていない。
次に吹奏楽部。悪名高いブラック部活動の筆頭格とされる吹奏楽部だが、ある公演で学校唱歌の「故郷の空」がスウィングジャズで演奏されたことに矢野は感銘を受ける。
統制的で集団的な部活動の論理を抱えざるをえない吹奏楽部だが、ステージのうえに立ったとき、当然のことながら、そこには音楽の喜びが存在している。いかにも学校的・部活動的な統制の論理は音楽の全体を覆うことはできないのだ。
というか、教員の立場からすれば、このような自由に到達してほしいからこそ、ある程度の統制を求めるようなところがある。個人の自由は全体との関係性によって明確になるからだ。
しかし、学校唱歌がスウィングジャズで演奏されたからと言って何を驚くことがあるのか。「顧問のひとりにプロのジャズミュージシャンがいる」とちゃんと書いてあるではないか。私に言わせれば矢野が勝手な深読みで感動しただけであり、自分が読みたいストーリーを読み取っていただけに見える。だからこれらを例をもとに次のようにまとめられても、私はまったく説得されないのだ。
吹奏楽部員にかぎらず、学校に生きる生徒たちは、少なからずそのような自由を得ている。学校という規律訓練が求められる場所にありながら、だからこそ生徒は、そのすきまを縫うように、自由に、クリエイティブにふるまっている。
ちなみに私は吹奏楽部の部長だった生徒を指導したことがあるが、その子は不登校だった。顧問に対する呪詛もよく聞かされたものだ。私は学校教師に対する不平不満をよく聞く立場でもある。だから本書を読んでいても、ずいぶん楽天的なんだなという印象を持つ。しかし、表の世界の教育を引き受ける教師はこのくらいポジティブでちょうどいいのかもしれないとも思う。
サッカーは民主的、松本人志も民主的?
上述したように、矢野はサッカーを民主的なスポーツと考えている。それにも驚かされたが、もう1つ驚いたのは松本人志に対する評価だ。
ちなみに言うと、このようなバラエティの世界の”民主化”を目指したひとりは、ダウンタウンの松本人志さんだったと言える。松本さんの代表的な著書『遺書』などを読むと、松本さんが、それまでの徒弟制からなる芸の世界になかば反発するように、ルール主義的で誰でもチャンスがあるような『M-1グランプリ』や『IPPONグランプリ』を構想・実現させたことがうかがえる。
これに関しては最近中田敦彦が物申していた通り、松本はこれらお笑いコンテストの審査員を務めることによって業界の権威を独り占めしていると批判されてもいる。2022年(出版時)の今、こんなに素朴に松本人志を評価していいものなのか、ひょっとして矢野は芸人というものに対する評価が甘すぎるのではないか?という疑いも出てきた。それは芸能一般に対してもあてはまるかもしれない。『ジャニーズと日本』もこの後読む予定だが、少し心配になってきた。
「身体的交流」はごく普通の意味だった
「現代思想」2023年4月号の矢野の論文では、最後に「身体の重要性」が取り上げられていた。だから本書でも「身体的交流」が最重要キーワードなのだろうと予想して読んだのだが、そうではなかった。
矢野が言う身体的交流とはごく普通の意味だ。時間と場所をともにすること、傷つけあったり助け合ったりすること、声をかけること、相手の話にうなずいてみること、というように説明されている。それは大事だ、というか社会の根本だとした上で矢野は補足する。
もっとも、そのような身体的な交流が、いかにも学校的な体罰やいじめにもつながるのだろう。
同じことは「現代思想」でも書かれていた。身体的交流の重視とハラスメントは表裏一体の関係にあり、ハラスメントを撲滅するために身体的交流そのものをカットしてしまうのは本末転倒だという。それはそうだ。私の仕事でも、オンライン授業の設備があってもほぼすべての生徒が対面授業を希望する。子どもたちは身体的交流を思いのほか強く求めている。毎週同じ時間に同じ場所にいること。それだけでいいらしい。
しかし、この身体の話よりも本書の主題は「規律と自由の両立」にある。それは部活動の話でも、国語科の指導の話でも変奏され繰り返される。部活動の話については無理があるとして批判した通りだが、教育の一般論としては無難で保守的なものだといえるだろう。矢野の主張を要約すれば、「学校は基本的に規律重視の場でよい。それでも生徒たちは自由さを発揮するのだから。」となる。私としては楽観的すぎて拍子抜けする気持ちもある。ただ、本書はあちこちで自由にやらせることの難しさを強調しているので、現実的な態度としてそうあらざるをえないのだろうとも思った。以上で矢野の教育論を見てきたことになる。
1つ思ったのは、教師にも個性があるので、壇上から独演会のような講義をするのが性に合っている教師もいれば、ファシリテーション的に対話型の授業を進めるほうが得意な教師もいるだろう。子どもたちの顔色を機敏に察知できる繊細な感受性がなければ上手にファシリテーションをすることはできないだろうし、向き不向きがあると思う。各教師が才能を発揮できるように、指導の方法はぜひ教師自身に任せてもらいたいものだ。
付論:批評的な「つなぎあわせ」について
以下は本筋から逸れる話になるが、ちょっと気に留まったので引用したい。
このような考え方は、学問的な分類以上に批評的な「つなぎあわせ」に魅力を感じる僕の性格によるところも大きいかもしれない。授業をするにせよ、批評を書くにせよ、無関係と思われていたものをうまくうなげて驚かせたい、という欲求が強い。
それと近いことを高校の論文指導においてもしているらしい。先行研究をたくさん調べた上で、独自性のある主張するように指導しているそうだ。そして、どうすればオリジナリティを出せるのかというと、次のように矢野は言う。
組み合わせよう。すでにある研究成果をオリジナルな仕方でサンプリングして、フレッシュな見方を提示しよう。オリジナリティは、その組み合わせの仕方にこそ宿る。たくさん存在する先行研究のどの部分を切り取ってどのようにつなげるか、という点にこそ、論者のユニークな主張が宿る。
どうしてこの箇所が気に留まったかというと、私はこのような人文学の論文の書き方をつい最近批判したばかりだったからだ。
まさに矢野が書いた通りのやり方で人文学者たちは論文を書いている。批評家はもちろん、アカデミックな学者の論文も似たようなものだと思う。何が問題かというと、何とでも言えてしまうことだ。元々自分が言いたかったことを過去の研究によって肉付けして理論武装すれば論文の一丁上がりである。別の言い方をすれば、自分の体質に合う言説を選り抜いて繋いでみればオリジナリティのある論文になるだろう。それはたしかに面白いかもしれないが、私に言わせれば「自己紹介」をしているだけに見える。論文を読めばその人がどういう人なのかは分かるが、その論文に誰かを説得するポテンシャルがあるかどうかは不明だ。もっとも、論文を書くことを通して自分を知ることができればそれだけでも十分な成果だとは思うが。
そして、本書全体もそのような書き方(「つなぎあわせ」のロジック)で書かれているのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
