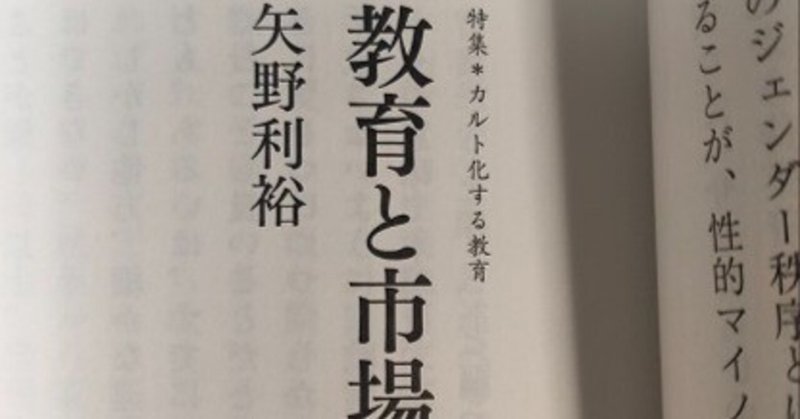
矢野利裕『教育と市場、ときどき身体』 ~「新自由主義」批判の何が問題か
雑誌「現代思想」は毎年4月に教育特集を組んでいる。近年その特集の舵取りをしているのが大内裕和と三宅芳夫であり、彼らは日本の教育の現状を語るときに頻繁に「新自由主義教育改革」が悪いと言う。2023年4月号の巻頭対談でも「新自由主義」という単語が何回出てきたか数えたくなるくらい頻出していた。しかし、その数ページ後ろに掲載された表題の矢野論文には「「新自由主義」批判を超えて」という副題が付いており、まさに上記巻頭対談のような言説に待ったをかけている。私たちはつい「新自由主義」という超便利なワードを用いて何かを語ってしまいがちだし、そういう言説をついすんなり受け入れてしまいがちだと思う。私の個人的感覚としても、なんとなく違和感なく読めてしまうものだ。しかしよく考えると何を言っているのか分からないような気もしないでもない。矢野は具体的に何が問題だと考えているのか。
まず、大内らが指摘する教育における「新自由主義化」とは、とりわけ教育と経済の結びつきのことである。90年代以降、日本社会が「新自由主義」化したとされており、それと並行するように公教育の領域が縮小され、市場原理に巻き込まれながら教育が私的な消費空間となっていったという。教育現場にはつねに生徒・保護者へのサービス提供が求められ、競争原理が働くようになった。ここまではおかしなところはない。
矢野が指摘するのは、教員の過剰労働の問題だ。大内に言わせれば新自由主義のせいで人員を削減されつつサービス提供の負担が増しているという嘆き節になるのだが、事実としては教育改革による公教育の縮小の結果、学校の週五日制が実現したのだった。「新自由主義」的な教育改革が教員の労働時間を削減したといえるのである。また他にも、教員の労働削減を大義とした部活動の外注やICT活用の議論も進行中だ。民間企業は教員の負担軽減を謳いながら教育市場に参入してくる。もし教員の過剰労働が問題なのであれば、「新自由主義」を批判することは的外れになってしまうのではないかと矢野は言う。
次に矢野は、教師の権威主義の問題を取り上げる。大内が「新自由主義」的と捉える「公教育の縮小」は、大枠として管理教育の反省という文脈も持っていることを矢野は確認する。
例えば、「学校に通うことを義務づけることは子供たちを教師集団の中に強制的に収容することであ」るとして、教育の官僚支配化および学校制度そのものを批判するイヴァン・イリイチは、興味深いことに、「新自由主義者」として名高いミルトン・フリードマンが唱えた「教育購入権利証」(教育バウチャー)を評価している。「脱学校化」を目指すイリイチは、はからずもと言うべきか、教育が市場に開放されることを肯定しているのだ。
そして矢野は内田樹のことも批判する。内田は教育における「市場原理の導入」を強く批判していることで知られているが、その論法は権威主義的であると矢野は言う。その論理は簡単だ。まず内田の発言を引用すると、
場合によってはなんの役に立つのか教育現場にいる人間にもよくわからない「取り決め」や「約束」がある。それを現代人の感覚で「よくわからない」から廃止するというようなことはしないほうがいい。
そして、この内田の発言はそのまま「ブラック校則」を正当化する論理にもなってしまうではないかと矢野は批判しているわけだ。これは教育における「新自由主義」批判の言説がもつ問題点を極めて簡潔に示す例だと思われる。
このように、「新自由主義」批判の論理においては、「市場原理主義の導入」への批判と教師の権威主義への批判は、意外と両立しづらい。
以上が矢野の「新自由主義」批判に対する指摘だ。整理すると
1)教員の過剰労働に関しては「新自由主義」は良いものである可能性があること
2)「新自由主義」批判が教師の権威の称揚に繋がってしまうこと
これに対する矢野の結論は「ほどほどにやるしかない」ということになる。
ほどほどに学校の消費空間化を認め、ほどほどに権威主義性を維持すること。あるいは、そのような相反する方向性をうまく共存させること。求められるものが多様になっていくなかで、状況を見ながらほどほどにやるしかない。
たいへん凡庸な意見だが、筆者からすればむしろ、このほどほどという水準が出てこない「新自由主義」批判の論理のほうが問題に思える。「新自由主義教育改革」における「新たな「抑圧」」への「対抗」ではなく、粘り強い不断の軌道修正のほうが必要ではないか。
たしかに「新自由主義」批判論者を見ていると、なにか左翼運動家か何かのように見えることがある。折しも巻頭対談の三宅芳夫はその後ドワンゴらのZEN大学にクレームをつけて川上量生から反撃される一幕があった。どうやら三宅の批判は事実誤認を含むものだったようで、名誉毀損訴訟に発展するようである。三宅は過ちを認めて謝罪するどころか強硬な姿勢であり、大内もそれに同調する構えに見える。こういう振る舞いを見ると、イデオロギーが先行してまっとうな議論が置き去りにされている印象を受ける。
(長文)数日前より、千葉大学の三宅芳夫教授が事実誤認の想像に基づくZEN大学への批判をネット上に公開しています。主張の根幹はZEN大学は多額の補助金を貰っているから、さまざまな説明責任があるというものですが、そもそも発表会当日に鈴木寛チェアマン(予定)が公開の場で宣言したようにZEN大学…
— かわんご (@gweoipfsd) June 14, 2023
さて、「新自由主義」批判批判といえば稲葉振一郎である。
稲葉が「「新自由主義」はバカが使う言葉で使ってるとバカになるから使うのやめろ」といったのに対して報告者たちは「そうは言っても現実に使われているのだからその概念分析にもそれとして意味はあるだろう」と返した。
ことは教育の文脈に限らず、とくに人文系の文学研究者や文芸批評家が好んで使う概念になっていると稲葉は言う。これについてはトークイベントがあったのでテキスト化が待たれる。(下記はその感想ブログ)
ここまでで「新自由主義」批判という論理が持つ問題点について、とりあえず矢野論文に書いてあったことは整理できたと思う。ここからは論文の最終部で、唐突に「身体の重要性」という話が出てくるところを読みたい。この箇所は正直言ってよく分からなかったが、矢野の独自の思想が一番表れているはずの箇所でもある。
矢野は教員を芸人になぞらえる。教員はエンターテイナーであり、巧みに生徒に知識を売りつける存在と位置付けている。
「まだ世界を知らない」子どもと「世界」を代表する大人という非対称性を想定するのであれば、大人(教育者)による子ども(生徒)への「世界」への導きはむしろ、「命がけの飛躍」として市場における交換関係とともに考えるべきである。
シチズンシップの理念こそ、市場を通じて教育なされるべきなのだ。芸人的な「教える/売る」身体とともに。
ここで矢野が何を言いたいのか私はいまいちよく分からないのだが、少なくとも教育者の権威主義に居直るのは違うと言っている。教師から差し出されたものを生徒は拒否する権利を当然にもつ。生徒は何から学んでもいいし、学ばなくてもいい。しかし教師としては押し売りしてでも生徒を振り向かせたい。ともすると詐欺のようにも見える、危うい交換関係として「教えるー学ぶ」の関係モデルを捉えているようだ。
ここまで述べてきたような身体性の重視は、教員の「権威」を強めることにつながるし、
どうして権威を強めることになるのか。生徒に対して有効な身体性を持っている教師をイメージしてみれば分かるだろうか。身振り手振りが巧みで、人を惹きつける声のトーンを身につけた芸人的な教師は、なるほど警戒すべきカリスマ性を帯びるかもしれない。そういう話だろうか。
さらに言えば、身体的な交流こそがハラスメントの温床になっている、という問題もある。
しかし、自分はいつでもハラスメントに手を染めるかもしれない、という非対称的な関係の自覚や恐れなくして、なにを教えることができるだろうか。
ここで分かるのは、矢野は身体的な交流によって教育が成り立つと考えていることだ。ここが分かりにくいところで、人格的な交流によって教育が成り立つというなら分かる。しかし矢野は教員を芸人に見立てているために、人格そのものとは少し違うものによって教育は駆動すると捉えているのだろう。「人格」と言ってしまうとまた大内らと同じく教師の権威を称賛する論理になってしまうと懸念しているのかもしれない。もっと即物的で、軽薄で、商品的な要素(つまり身体)によって教育が成り立つと考えたいのかもしれない。このあたりは『学校するからだ』を読めばもう少し矢野の実感が伝わってくるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
