
「見えなくなるもの」に自覚的でありたい。【LIFULLドキュメンタリー視聴レポート】
先月、株式会社LIFULLからご案内をいただき、同社制作のドキュメンタリー・フィルムの試写会に参加させていただいた。エイジズムをテーマにした『年齢の森』と、ジェンダーと多様性をテーマにした『ホンネのヘヤ』の2本である。
【タイトル】『年齢の森 -Forest of Age-』
【監督】 今中 康平
【タイトル】『ホンネのヘヤ』
【監督】 関根 光才
わたしはエイジズムやジェンダーについて問題意識を持つライターのつもりだったし、LIFULL社もそのように思ってくださっているからお声がけいただけたのだと思う。しかしフィルムを見ながら自分のあれこれを振り返った時、(ああ、わたしの目からは見えなくなってしまうものがあるんだなあ)としみじみ感じた。今回はライターによる情報発信というよりも、ひとりの視聴者が自分を顧みた体験記として、「見えなくなるもの」について書きたい。
気にしないことと、見えないこと
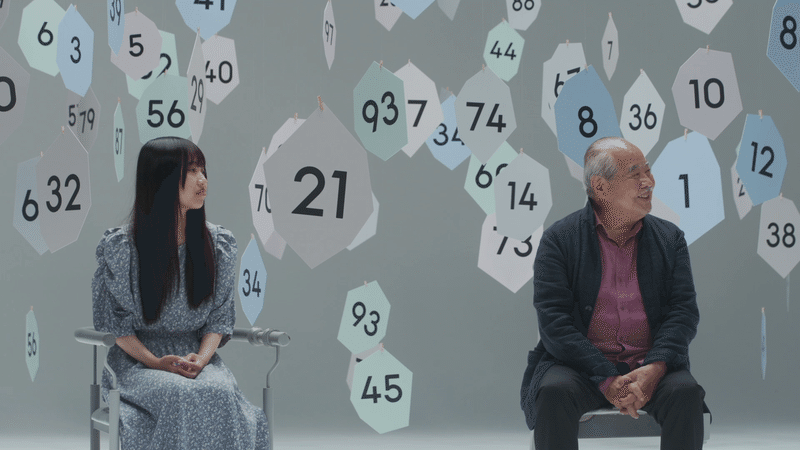
これまでわたしの書いた「アンチ・エイジズム讃歌」的エッセイの代表例といえば、『年の差恋愛は、ご高齢男女の特権。だから若さにこだわるな。』『ノーブラ天国:高齢女子の大人げないファッション雑話』あたりが挙げられるのではないかと思う。これらは縮めて言えば、「女の若さに執着しなさんな」「高齢になったからこそ、好きな格好したらいいじゃないの」という話である。シルバーヘアにしたって(一般的にはグレイヘア、という言葉を使うようだが)、別に加齢を肯定的に受け入れようとしたわけではない。若い頃から、甥姪に「おばちゃん」と呼ばれて何の抵抗もない。
なので正直に言えば、『年齢の森 -Forest of Age-』出演者の皆さんが語る年齢にまつわるモヤモヤや葛藤の経験には、(世間ではそうらしいね……)みたいな、ちょっとした距離感を感じながら聞いていた。あまり葛藤した経験がないからだ。わたしがあれらのエッセイを書いたのは、「そんなに葛藤する必要ないよね?」という感覚の方が強いのだ。
フィルムを観ながら、似たような感覚を思い出した。「どんな高校からでも大学くらい合格するよね?」という感覚である。わたしはかなり本気でそう思っている。田舎の県立高校(同級生の3/4は就職し、進学組の大半は高看と専門学校に進む)から旧帝大に現役入学したからだ。最近になって様々な情報を得て、どうやらそんな単純ではないらしいことがわかったが、経験から出来上がった感覚はなかなか抜けない。
年齢に戻るが(性別や職業もそうなのだと思うけど)、年齢によるイメージや先入観に人を閉じ込めるのは、他者からの役割期待なのかもしれないな、と思った。「おかあさんにはおかあさんらしくいて欲しい」というような。わたしがエイジズムから比較的フリーでいられるのは、結婚をあっという間に辞めたり、子どもがいなかったり、職場を何度も変えて出世なんかしてなくて、何の地位にも就いてなかったりすることと、無関係ではないと思う。わたしには多分、「〇〇らしい」ところがほとんどない。シルバーヘアを面白がれるのも、作品上で自分を「ババア」呼びして平気なのも、実際のところ自分を「婆」だと思っていないからで、社会的な役割に嵌らずにふらふらと浮遊していられるからなのだと思う。
勿論わたしが『ノーブラ天国』のようなエッセイを書くのは、社会にある「どうでもいいことを大したことであるかのように迫ってくる規範」や「こだわらせようとしつこく付き纏ってくる枠組み」の方を笑い飛ばし、吹っ飛ばしたいからではあるけど、そこにはわたしのナチュラルな傲慢さが見え隠れする。「大学くらい普通に行けるでしょ?」と平気で言い放ってしまうような。
年齢にまつわる小さな擦り傷や深い刺し傷、それらを持つ人たちの姿が見えていないとき、「年齢なんて大したことないでしょ?」「別にこだわらなくていいでしょ?」と無邪気に言ってしまうのは、とても乱暴で怖いことだと思った。勢いよく軽快にごおっと駆け去っていくわたしの周りで、わたしの目に入っていないたくさんの人たちが、吹っ飛ばされてさらに傷を負っているかもしれない。
知識と言葉が語らせるもの、黙らせるもの

一方『ホンネのヘヤ』はわたしにとって、扱い慣れた言葉、扱い慣れた文脈、扱い慣れた物語の情景だった。わたしは今、男女共同参画系の公共施設で相談の仕事をしているので、「いつもその中にいる」場のような感覚がした。実際、出演者の方々が吐露する傷つきの体験の語りは、相談室の中の日常が蘇るようで、聞いていて少ししんどくもあった。
しかしながら、慣れた言葉が優位性を持つ場にいることに、つまりそれは「それが普通」である場ということなのだが、最近危惧を感じてもいる。
例えば仕事する中本を読む中勉強する中で、当たり前のように使われる様々な用語、「ジェンダー」だったり「多様性」だったり、「マイノリティ」や「搾取」「支配」、「構造的差別」「アンペイド・ワーク」「アンコンシャス・バイアス」 「トキシック・マスキュリニティ」 ……それらの用語を使うとき、わたしたちはどれだけ、わたしやあなたや彼ら彼女らの、個別で具体でそれこそ多様なたくさんの現実の日常を、消さずにいられるのだろうか。
わたしは相談の中で「ジェンダー」という言葉は使わないようにしている。ジェンダーという視点はわたしの中に持てばいいことで、今向き合って話を聞くあなたの現実に「ジェンダー」とラベルを貼ることは、何か違う気がするからだ。同じように、「母娘」という言葉も使わない。「母娘」と表現した途端、目の前の彼女が語る親子関係のリアルが、何か別のものに収束されてしまう気がするからだ(ある種の女性相談において「母娘」という用語は、独特の意味合いを帯びる)。DVの相談の中で「支配」という言葉も使わない。被害者は支配された人じゃない。どれだけ疲弊しか細くなろうと、ずっと抵抗し続けていると思うからだ。(カウンセリングの基本と言われる「傾聴」も、無頓着に使ってはいけない言葉なんだろうなあ!自分が相手の語りを真摯に傾聴できたかどうかは、「傾聴」という言葉の中にはない。)
勿論、フェミニズムやジェンダー・スタディの用語は、うまく言葉にできなかった女性たちの経験に輪郭を与え、共通の問題を浮かび上がらせ、繋がり合う力をくれた。言葉は、埋もれて無視されてきた現実を、表に引っ張り出し可視化してくれる。自分の身に起こった理不尽な出来事、その理不尽さをどうしても表現することができなかったわたしたちに、(こういうことだったんだ!)と目醒める光をくれる。けれどわたしたちは言葉を使い、言葉に口が慣れ耳が慣れ頭が慣れするうちに、言葉の意味の内側に閉じ込められてしまう。言葉には、そういった両方の作用がある。
「わかったような」言葉を使うとき、途端に見えなくなるものがある。わたしたち一人一人の生きた現実が、消えて何か違うものに取り込まれてしまう。言葉の内側の世界しか見えなくなるとき、わたしたちは確実に誰かを無き者にし、傷つけている。
多様性とは「自分には何が見えないか」を知ることなのかもしれない

わたしたちは、自分自身の体の中、心の中、頭の中に閉じ込められている。その意味で、どうしようもなく限界を持っている。あなたの目に見えるものはわたしの目に見えるものと同じではなく、あなたの言葉の語るものはわたしの言葉の語るものと同じではない。でもそれは、絶望ではないのだと思う。むしろ自分の限界を知って初めて、人を知るスタートラインにつけるのだと思う。(余談だが、大学生の頃ヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」をほんのちょっとだけ知り齧ったときは、その頃のお若いわたしは、人と人との交わらなさに絶望しましたよ。)
「ジェンダーについて語るのは難しい」と言われる。勉強してからじゃないと口を開けないように思われている節もある。しかし本来フェミニズムの実践は、そこいらのただの平凡な一般の女性たちが、それぞれの経験や実感を語るところから始まった筈だ。そしてあなたの経験や実感はわたしの経験や実感とは異なるから互いに尊いのだし、唯一の絶対の正解なんか、ない筈だ。
わたしたちは、ジェンダー「を」語らなくてもいいんじゃないかな。ジェンダーという概念を知って、その目で自分の生きてきた世界を見直したとき、今まで見えなかったものが見える。それを自分なりの言葉で、語ればいいんじゃないかな。自分にぴったりくる言葉は、それぞれにある筈だ。多分ジェンダーへの気づきと語りの言葉は、専門家の手の中や特別な場に限定された言葉じゃなくて、わたしたちすべての(男性でも女性でもそうでない性でも、詳しくても詳しくなくても!)生きる場の中に、こんなにも日常的にありふれて転がっている筈だから。(エイジズムもまた、ジェンダーとイコールではないけれど、強く関連した観念だろうと思う。)
「男を降りたい」ことについても考える。男を降りたら、わたしたちは他者を加害せずに済むのだろうか。罪悪感から解き放たれるのだろうか。この言葉が意味するところも人によって違うだろうから難しいのだけど、個人的には、男の人には男であり続けて欲しい。
わたしは女だが、女だからといって誰も踏まず誰も殴らず生きてきたわけではなくて、加害性や攻撃性や傲慢さや残酷さの履歴が、振り返れば屍累々だ。わたしはいつも「いい人」への憧れと羨望と心苦しさがある。でも、わたしがわたしを降りたら他の人になれるわけではない。
自分は死ぬまでやめられない。そしてわたしたちは、必ず誰かを殴ったり踏んだりしてしまう。見えないもの、見えなくなるものを存在しないことにしてしまう傲慢さは、わたしたちはみんな持っている。自分が人から殴られたり踏まれたりした、無きものにされた経験と痛みを持つ人であっても、多分、別のときにはやってしまう。わたしたちにできることは、内包する自分の加害性を抱えながら、自分に見えないものは何か、吹っ飛ばし駆け去ってしまうものは何か、自分の視界の限界はどこか、何度でも何度でも気づきながら生を進めていくことなのではないか、という気がする。
「見えなくなるもの」に、常に自覚的でありたい。改めて考える機会を頂戴し、ありがとうございました。感想をまとめるのが遅くなってしまったことを謝しつつ。
(※this article is not sponsored)
アマゾンギフト券を使わないので、どうぞサポートはおやめいただくか、或いは1,000円以上で応援くださいませ。我が儘恐縮です。
