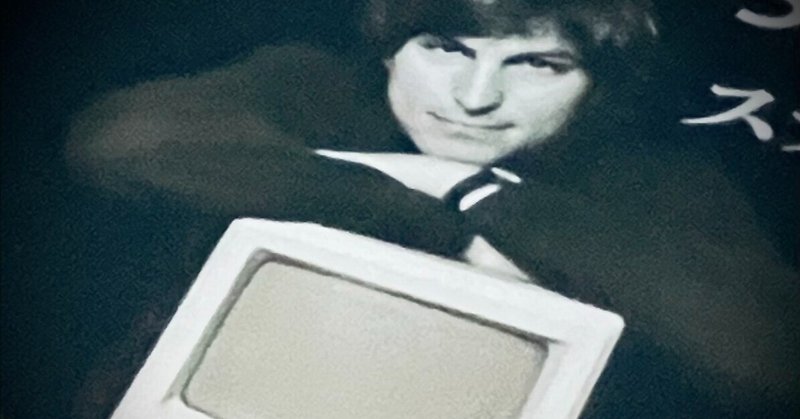
1995年のスティーブ・ジョブスに何があったか。Chat GPTとさがす私的コネクティングドット(後編)
前回からの続きです。
新しいテクノロジーがもたらす機会のためにリスクとどう伴走するか?
前回は成長機会のためにどう新しい技術やテクノロジーに関わるかについてChat GPT4を相棒にまとめています。
特にそのリスクと伴走するかについて検証を進めていたら、自分でも思いがけないストーリーに。
対話の面白さ、AIは答えをくれませんが、刺激はくれるようです。
お互いに情報のキャッチボールをしながらどんどん思いもよらぬ方向へ。
複雑な軌跡を読んでもらえると嬉しいです。
*リスクとの向き合いという表現に違和感があったので、Chat GPT4とのやり取りを踏まえて、「リスクとの伴走」にします。やり取りの詳細はこちらです。以下、ケース2:言葉のチョイスで取り上げています。
Chat GPTとのケースをめぐるやり取りを通じて新しいテクノロジーをマーケティングの観点でどうパッケージしていくのか、非常に気になり始めます。
そして、あるインタビュービデオの存在を思い出し、Chat GPTに訊ねてみることにしました。
こちらのビデオです。
以下、前編の後半部分から再度書き出します。
意地悪な展開:Steve Jobさんのあるインタビューについて
今回に限らず一連のChat GPTとのやりとりはその回答と僕が持つ「知識」のぶつけ合いです。
そこで「変化球を投げて」みます…回答のクオリティに対するチェックをしたいので、プロセスの中で、こちらが持っている少し変わった事実をぶつけています。
今回はSteve Jobsさんの1995年のインタビューで、技術とマーケティングについて語っているものがあります。
このインタビューは盟友であり宿敵でもあったJohn Sculleyさんについて話しているもので、その点を考えただけでも興味深いものです。
質問:"Steve Jobs on what happens when the marketing/sales people take over from a 'product' founder."の詳細をご存知であればこの内容をテキストで共有してください。
Steve Jobsは、製品のビジョンとその実現に関する強い信念を持っていました。彼の哲学は、製品とユーザーエクスペリエンスを最前線に置くことで、本物の革新を生み出すというものでした。彼はそのキャリアの中で、製品開発に重点を置く企業文化と、マーケティングや営業を中心とした企業文化の違いについて独自の見解を持っていました。
1995年に行われたインタビューで、Steve Jobsはこのトピックについての見解を語っています。彼は以下のように述べました:
"What happens is, like with John Sculley, John came from PepsiCo, and they at most would change their product once every 10 years. I mean, to them, a new product was like a new-sized bottle, right? So if you were a 'product' person, you couldn’t change the course of that company very much. So, who influenced the success of PepsiCo? The sales and marketing people; therefore they were the ones who got promoted, and therefore they were the ones who ran the company.
Well, for PepsiCo that might have been okay, but it turns out the same thing can happen in technology companies that get monopolies. Like, oh, IBM and Xerox. If you were a product person at IBM or Xerox, so you make a better copier or a better computer, so what? When you have a monopoly market-share, the company's not any more successful. So the people who make the company more successful are the sales and marketing people, and they end up running the companies. And the product people get run out of the decision-making forums.
The companies forget how to make great products. The product sensibility and the product genius that brought them to this monopolistic position gets rotted out by people running these companies who have no conception of a good product versus a bad product. They have no conception of the craftsmanship that’s required to take a good idea and turn it into a good product. And they really have no feeling in their hearts, usually, about wanting to help the customers."
このコメントは、製品中心の哲学とマーケティング/営業中心の哲学の違いを示しており、後者が優勢になると、企業は本物の革新を失ってしまうという警告として語られています。
インタビューを日本語に訳して要点をまとめてもらいましょう
質問:ありがとうございます。1:この内容を日本語にしてください。2:そして技術とマーケティングの関係から最も大事なことを書き出してください。
1. 日本語訳:
「問題は、ジョン・スカリーのような人々が来た時に起こる。ジョンはPepsiCoから来た。PepsiCoは、最大で10年に1度製品を変えるかもしれない。彼らにとっての新製品は新しいボトルのサイズのようなものだった。だから、あなたが「製品」の人であっても、その会社の方針をあまり変えることはできなかった。だから、PepsiCoの成功に影響を与えたのは誰か。それは営業とマーケティングの人々だった。だから彼らが昇進し、会社を運営することになった。
PepsiCoにとってはそれで良かったかもしれない。しかし、技術企業が独占的な市場シェアを持つと、IBMやゼロックスのように同じことが起こることが判明した。IBMやゼロックスの製品担当者であれば、より良いコピー機やコンピュータを作ることができますが、それがどうしたというのでしょうか。独占的な市場シェアを持っている場合、企業はそれほど成功しない。だから、会社をより成功させるのは営業とマーケティングの人々で、彼らが企業を運営することになる。そして、製品の人々は意思決定の場から締め出される。
企業は素晴らしい製品を作る方法を忘れてしまう。彼らを独占的な立場にもたらした製品の感覚と製品の才能は、良い製品と悪い製品の区別がつかない人々によって運営される企業で腐食されてしまう。良いアイディアを良い製品に変えるための技量についての認識がない。そして、通常、顧客を助けたいという気持ちが心の中にない。」
2. 技術とマーケティングの関係から最も大事なこと:
技術とマーケティングの間のバランスは非常に重要です。真のイノベーションは、技術的な洞察と顧客のニーズへの深い理解の交差点に生まれる。Jobsの指摘によれば、企業がマーケティングや営業の側面だけを強調すると、製品の質やイノベーションの源泉を失いかねない。真に成功するためには、製品の品質、ユーザーエクスペリエンス、そして市場への適切なアプローチが必要です。このバランスを維持し、両方の視点を組み合わせることが、持続可能な成長と革新の鍵となります。
テクノロジーをマーケティングにおいてどう位置づけるか?
Jobsさんはマーケティングの重要性を理解しています。
では、テクノロジーについてはどのような認識を持っていたのでしょうか?質問します。
あえて、技術とマーケティングの概念を対立させる形で訊ねます。
質問:ありがとうございます。Jobsさんは技術とマーケティング、どちらに重きを置いていたのでしょうか?このインタビューとそのほかの情報を集約して端的にまとめてください。
Steve Jobsは、製品とユーザーエクスペリエンスを中心に考える「製品中心」の哲学を強く持っていました。彼のキャリアを通じて、Appleの製品は独自性と使いやすさで知られ、それはJobsのこの哲学の反映でした。
1. 製品の質と革新:
Jobsは、ユーザーエクスペリエンスとデザインの優れた製品が、長期的な成功の鍵であると信じていました。彼の言葉や行動から、技術的な革新と優れたデザインがマーケティングや販売よりも重要であるとの信念が見て取れます。
2. マーケティングの役割:
しかし、Jobsがマーケティングを全く価値がないものとみなしていたわけではありません。彼の理解において、マーケティングは製品の物語性やビジョンを伝える手段でした。実際、Appleのマーケティングキャンペーンは業界内で多くの賞を受賞し、非常に影響力がありました。ただし、彼は製品そのものが素晴らしくなければ、マーケティングだけで成功することはできないとも考えていました。
結論として、Steve Jobsは製品の質とユーザーエクスペリエンスを最優先としていましたが、マーケティングもその製品の物語性やビジョンを伝える重要なツールとして認識していました。彼の成功は、これらの要素を巧みに組み合わせ、革新的で使いやすい製品を作り上げる能力に起因しています。
ユーザーエクスペリエンスを最優先する発想
この指摘には改めて重要な気づきがあります。
テクノロジーをマーケティング(営業)の対立概念として捉えるのではなく、ユーザーへの提供価値を伝えることを優先して、どうパッケージしていくか、についての示唆がなされています。
「Marketing is about values」
いよいよ「Marketing is about values」に関わる質問をします。
今回の試みはChat GPTが学習している知識と自分が持っている知識の競争・共創に重きをおくので、どんな応答になるか期待しつつ…。
質問:Jobsさんは”Marketing is about values”と彼がAppleに復帰した際に「Thing Different」キャンペーンを市場で展開するにあたっての背景情報として社内的な会議で話しています。このプレゼンテーションをふまえて(Jobsさんは技術とマーケティング、どちらに重きを置いていたか)、彼にとっては顧客)とはどういうものなのかをまとめてください。
Steve Jobsの「Think Different」キャンペーンに関するプレゼンテーションは、彼のビジョンやマーケティングに対する考え方を示す象徴的な瞬間のひとつです。このキャンペーンは、JobsがAppleに復帰した直後の1997年に開始されました。
Jobsの考え方の要点は次のとおりです:
1. 価値とマーケティング: Jobsは「マーケティングは価値についてのもの」と語りました。これは単に製品を売ることではなく、会社や製品が持つコアバリューを顧客に伝えることを意味します。
2. 「Think Different」キャンペーン: このキャンペーンはAppleのコアバリューを象徴しています。それは革新的であること、異なる考え方や視点を持つこと、そして変革をもたらすことです。キャンペーンの中で取り上げられた歴史的な偉人たちは、彼ら自身の分野で異端者でありながら、世界を変える革新をもたらした人々でした。
3. 顧客との関係: Jobsにとって、顧客は単なる製品の購入者ではありませんでした。彼は顧客をAppleのビジョンや価値観を共有するコミュニティの一部として見ていました。顧客はブランドとの深いつながりを持ち、それによってAppleの製品やサービスを選択していました。
4. 技術とマーケティングの統合: Jobsは技術革新とマーケティングを分離して考えることはしませんでした。彼にとって、両方は製品の全体的なエクスペリエンスの一部であり、顧客がAppleとの関係を形成する際に重要な要素でした。
結論として、Steve Jobsは技術とマーケティングの間に明確な境界線を引かず、両方を組み合わせてAppleのブランドを構築しました。彼の強いビジョンと価値観は、Appleが世界中の顧客と深いつながりを持つことを可能にしました。
Chat GPTは平気で嘘をつく
ネットで指摘されていることです。
「嘘をついている」かどうかを見極めることは使う側の知識が試されていることです。
上記のChat GPT4の応答は満足がいくものです。
Marketing about valuesについてはこちらに詳しくまとめてあります。
一旦総括しましょう
ここまでの議論を総括してもらいます。
応答の振り返りはChat GPTの最も優れた(便利な)機能です。
質問:ありがとうございます。今までの議論を踏まえて、新しい技術、そのリスクマネージメントと機会創出と損失について端的に整理してください。また企業が提供する商品サービスをマーケティングを通じて顧客に提供するにあたって一番大事なことは何ですか?キーワード化してまとめてください。
了解しました。まとめると以下のようになります。
1. 新しい技術:
- 利点: 効率化、生産性の向上、新しい機会の創出。
- リスク: 技術的な問題、既存の事業モデルや職種の変革、社会的な受容性。
2. リスクマネージメント:
- 必要性: 新技術導入の失敗を防ぐ。
- 手法: 積極的な研究、教育、パイロットテスト、フィードバックの取得。
3. 機会の創出:
- 重要性: 競争力の維持、新しい市場への進出。
- 方法: イノベーション、顧客のニーズの理解、技術の適切な活用。
4. 機会の損失:
- リスク: 技術への適応が遅れることによる市場シェアの低下。
- 回避策: 迅速な意思決定、継続的な市場調査、技術トレンドの監視。
5. 商品・サービス提供:
- 重要性: 顧客ニーズの満足、ブランドの価値の向上。
6. マーケティング:
- 最も大事なこと: 顧客のニーズと価値観を深く理解する。
- キーワード: 顧客理解、ブランドストーリー、価値提供、戦略的コミュニケーション。
企業が商品・サービスをマーケティングを通じて顧客に提供する際の一番大事なことは「顧客のニーズと価値観を深く理解する」ことです。これにより、正確なターゲティング、適切な価値提供、そして効果的なコミュニケーションが可能になります。
もう一つのConnecting Dotsをさがそう
"Steve Jobs on what happens when the marketing/sales people take over from a 'product' founder."と"Marketing is about values."の関連が見えてきたことから、Steve JobsのConnecting Dotsという言葉を思い出します。
また、John Sculleyさんに言及したことを思い直した際に、あるnoteを思い出しました。
その人が何を知っているのか?本当に?期待は持っていなかった。けれど、接触したその人物は、「あなたが思っている以上に、ジョブズと日本とのつながりは深い」とメールに書いてきた。何より、この人の人脈がすごかった。オンラインで打ち合わせると、「人を紹介するよ」と言われた。
待つこと1ヶ月。2022年9月下旬、その人物から長文のメールが届いた。
差出人の名は「ジョン・スカリー」
そう。ジョブズと「ダイナミック・デュオ」と呼ばれた、アップル社の元CEOだった。
1995年にJobsさんは何をしていたか?
John Sculleyさんに言及したインタビューを受けた1995年、Jobsさんは何をしていたのでしょうか?
質問:(Steve Jobs on what happens when the marketing/sales people take over from a 'product' founder.)のインタビューが行われた1995年はJobsさんはアップルに復帰していましたか?
1995年の時点で、Steve JobsはまだAppleに復帰していませんでした。Jobsは1985年にAppleを去り、NeXT Computerを設立しました。彼は1997年にAppleに正式に復帰しました。この復帰はAppleがNeXTを買収する形で行われました。復帰後、JobsはAppleの再建をリードし、数々の成功製品を市場に投入しました。したがって、"(Steve Jobs on what happens when the marketing/sales people take over from a 'product' founder.)"のインタビューの際、彼はまだAppleに戻っていない時期の発言となります。
問答を続けます。
質問:ありがとうございます。Appleの歴史を振り返るとまさに”connecting dots”ですね
まさにその通りです。Steve Jobs自身がスタンフォード大学での卒業講演で「connecting the dots(点を結ぶ)」というコンセプトに言及しました。彼は過去の出来事や経験が、後に意味深い形でつながってくることを指摘しています。Jobsは自分の人生の中で起きた seemingly 無関係な出来事が、結果的に彼のキャリアや人生において大きな役割を果たしたと話しています。
Appleの歴史を考えると、NeXTの技術やPixarとの経験、そしてAppleへの復帰など、多くの出来事が「点として」存在していました。そして、それらの点が結びつき、今日のAppleの成功につながっています。Jobsの人生やキャリア、そしてAppleの歴史は、まさに「connecting the dots」の考え方を体現していると言えるでしょう。
Connecting the dotsに話が転じる
質問:ありがとうございます。Appleの歴史を振り返るとまさに”connecting the dots”ですね
まさにその通りです。Steve Jobs自身がスタンフォード大学での卒業講演で「connecting the dots(点を結ぶ)」というコンセプトに言及しました。彼は過去の出来事や経験が、後に意味深い形でつながってくることを指摘しています。Jobsは自分の人生の中で起きた seemingly 無関係な出来事が、結果的に彼のキャリアや人生において大きな役割を果たしたと話しています。
Appleの歴史を考えると、NeXTの技術やPixarとの経験、そしてAppleへの復帰など、多くの出来事が「点として」存在していました。そして、それらの点が結びつき、今日のAppleの成功につながっています。Jobsの人生やキャリア、そしてAppleの歴史は、まさに「connecting the dots」の考え方を体現していると言えるでしょう。
Appleの歴史とJobsさんのキャリアについて振り返る
質問:素晴らしい内容の会話ですね。”connecting dots”は彼の個人的なキャリアの話でもありますが、Appleの企業の歴史も同様に整理してみると非常に意味のあるものになりそうです。
はい、その通りです。Steve Jobsの「connecting the dots」の概念は、彼の個人的なキャリアだけでなく、Appleの企業としての歴史にも当てはまります。
1. Appleの初期の成功と挫折: Apple IとApple IIの成功、しかし、Macintoshの初めの困難なスタート。
2. JobsのApple退社後の経験: NeXTでの技術革新やPixarでの映画製作への進出は、彼が後にAppleで行ったイノベーションの基盤となった。
3. Appleへの復帰: NeXTの技術がMac OS Xの基盤となり、またPixarでの経験がAppleのデジタルコンテンツ戦略に役立った。
4. iPod、iTunes、iPhone、iPadの登場: これらの製品とサービスは、ハードウェア、ソフトウェア、およびデジタルコンテンツの統合におけるAppleの強みを強調しています。
5. App StoreとiOSエコシステムの拡大: このエコシステムは、第三者開発者の革新を促進し、Apple製品の価値を高めました。
上記のように、Appleの歴史を見ると、多くの「点」が存在し、それらが後から見れば意味深く結びついています。Jobsの哲学や彼の経験が、Appleの製品戦略やビジョンにどのように影響を与えたかを考えると、企業の歴史もまた「connecting the dots」の一例となるでしょう。
Jobsさんの経営者としての人間性・Humanityについて興味が湧きます。
パーソナリテイとヒューマニティの両方の観点での検討を依頼します。
質問:Connecting the dotsは彼のパーソナリティの話ですが、appleの企業の歴史で考える際は、彼のヒューマニティの観点も加えて整理したほうが良いと思います。
了解しました。AppleとSteve Jobsの「connecting the dots」の考え方を、Jobsのヒューマニティの観点で整理します。
1. 人間中心のデザイン:
Jobsは製品のデザインにおいて、ユーザーの視点を最も重要視しました。彼はテクノロジーを単なるツールとしてではなく、人々の生活を向上させる手段として捉えていました。このため、Appleの製品は直感的で使いやすく、美しさを追求するデザインとなっています。
2. アートとテクノロジーの融合:
Jobsは自身の若い頃のコールグラフィーのクラスが、後のMacintoshのフォントやユーザーインターフェースに影響を与えたと語っています。このように、彼の人生の経験がAppleの製品や技術に「点を繋げる」形で取り入れられています。
3. 教育への情熱:
Jobsは教育の革新に深い関心を持っていました。彼のヒューマニティの観点は、教育における技術の役割やApple製品を教育現場での利用を促進する動機としても影響を与えています。
4. 全体的な体験の追求:
Jobsは製品だけでなく、製品を購入するプロセス、サポート、ソフトウェア、ハードウェアといった全体のエコシステムを重視しました。Apple StoreやiTunes Storeの成功は、ユーザーに全体としての優れた体験を提供するという彼のヒューマニティの考え方が背景にあります。
5. 挑戦と革新の継続:
Jobsは、過去の成功に捉われることなく、常に次の革新を追求する姿勢を持っていました。彼のヒューマニティの観点は、人々のニーズや願望を理解し、それに応える新しい製品やサービスを開発する原動力となっていました。
総じて、Steve Jobsの「connecting the dots」の哲学は、彼のヒューマニティの観点と深く結びついており、それがAppleの製品、サービス、企業文化の核となっています。
非常に興味深いやりとりでした。
Chat GPTから以下のコメントをもらいました。
どういたしまして!Steve JobsやAppleに関する議論は、常に深く、洞察に富んだものとなります。ご質問や議論の中でお手伝いできたこと、嬉しく思います。何か他に質問や検討したいことがありましたら、いつでもお知らせください。良い一日をお過ごしください!
心地よい体験です。
ダイナミック・デュオ ジョン・スカリーさんについて
ジョン・スカリーさんについて研究してみましょう。
質問:ジョン・スカリーさんについて彼の経歴を教えてもらえないでしょうか?
もちろん、ジョン・スカリーについての簡単な経歴をご紹介いたします。
ジョン・スカリー (John Sculley)
1. 初期の経歴:
- 1939年にアメリカのニューヨーク州で生まれる。
- ブラウン大学とウィスコンシン大学で学び、MBAを取得。
2. PepsiCo:
- ジョン・スカリーはPepsiCoに入社し、急速に昇進。彼は若くしてPepsiCoの最年少の社長となった。
- Pepsi Challengeというマーケティングキャンペーンの成功が特に有名で、これによりPepsiはコカ・コーラとの競争で大きな成功を収めた。
3. Apple:
- 1983年にSteve Jobsに誘われ、AppleのCEOに就任。
- スカリーがCEOを務める間、AppleはMacintoshをリリースし、初めてのGUIベースのパーソナルコンピュータを一般の消費者に提供した。
- しかし、彼のリーダーシップ下でAppleは競争力を失っていき、Jobsとの対立も表面化。1985年にJobsはAppleを一時離れることとなる。
4. Apple退社後:
- 1993年にAppleを退社。その後は多くのスタートアップ企業や技術関連の企業に関わっている。
- 特にヘルスケアやテクノロジーの分野での起業や投資に注力している。
ジョン・スカリーは、Appleにおける彼の時期が特に有名ですが、彼のキャリアはそれだけにとどまらず、多岐にわたるものとなっています。
質問を続けます。
質問:ありがとうございます。ジョン・スカリーさんとJobsさんの関係について時系列で教えてもらえませんか?
もちろん、ジョン・スカリーとSteve Jobsの関係について時系列で説明いたします。
1983年:
- Steve Jobsは、Appleの成長と競争力を強化するために、経験豊富な経営者を求めていました。
- Jobsはジョン・スカリーに目をつけ、彼をCEOとして迎え入れることを決意。スカリーは当時PepsiCoの社長を務めていました。
- 有名な逸話として、Jobsがスカリーに「あなたは残りの人生、砂糖水を売り続けるつもりですか?それとも、私たちと一緒に世界を変えるつもりですか?」と問いかけ、彼を説得しました。
1983年-1985年:
- スカリーがAppleのCEOに就任した当初、彼とJobsは非常に良好な関係を築いていました。彼らは協力し合い、新しい製品開発やビジネスの方向性について議論していた。
- 1984年には、彼らの共同リーダーシップの下でApple Macintoshが発売されました。
1985年:
- しかし、1985年になると、二人の間の関係が悪化し始めます。主な対立点は、Macintoshの販売戦略や会社の将来の方向性に関するものでした。
- この対立は、スカリーとJobsの間で公然と争われるようになり、結果としてAppleの役員会はスカリーの側に立ちました。
- JobsはMacintosh部門のリーダーシップから外され、彼はこれを不満に思い、1985年にAppleを退社。NeXT Computerを設立します。
1985年-1997年:
- JobsはAppleを去った後、NeXTとPixarの成功を築き上げます。
- 一方、スカリーのリーダーシップの下でAppleはいくつかの製品をリリースしますが、市場での競争が激化し、Appleの業績は下降し始めます。
- 1993年にスカリーはAppleを退社します。
1997年:
- Appleは業績不振により困難な状況に直面しており、この時点でJobsはNeXTとともにAppleに戻ります。
- Jobsの復帰後、AppleはiMac、iPod、iPhone、iPadなどの一連の革命的な製品をリリースし、再び技術業界のリーダーとしての地位を築き上げます。
二人の関係は、協力と対立の繰り返しであり、その中でAppleの歴史が大きく動いているのが見て取れます。
太字にしましたが、Appleに誘うさいの有名なエピソードがカバーされています。
感傷的な質問
個人的に気になる質問をします。
質問:Jobsさんが亡くなる前に二人の関係は元に戻ったのでしょうか
Steve Jobsとジョン・スカリーの関係は、1980年代の彼らの公然たる対立後、公の場で和解したという明確な瞬間が報じられたわけではありません。しかし、両者がその後の年月を通して互いに認識や感情を変えていったことは確かです。
後のインタビューや報告によると、ジョン・スカリー自身は、彼とSteve Jobsとの関係について悔いを持っていたとされ、また彼のAppleからの退去を後悔していることを公然と語っています。スカリーは、自分とJobsとの対立がAppleにとって最善の結果をもたらさなかったことを認め、その点については責任を感じていたようです。
一方、Steve Jobsも成熟し、自分のキャリアや人生を振り返る際に、Appleを去った時期が彼自身の成長や新しい視点を持つための重要な時期だったとの認識を示していました。NeXTやPixarでの経験が、後のAppleでの成功への礎となったことは間違いありません。
公には和解の瞬間が報じられていないものの、時が経つにつれて両者ともに反省や新しい視点を持ちつつ、過去の出来事を受け入れる姿勢を見せていました。しかし、Jobsが亡くなる前に二人が直接、個人的に和解の瞬間を持ったかどうかの詳細は一般には知られていないようです。
この応答は先ほどのNHK取材ノートと読み合わせるとさらに感慨深いものになりそうです。
だんだん対話が深くなっていく
議論の内容に引き込まれることで、こちらのChat GPTへの働きかけが「質問」から一歩踏み出していきます。
質問:ありがとうございます。二人のような優秀な人間が憎しみだけではなく尊敬できる間柄であったことはともて大事ですね。友情とは言えないかも知れませんが、彼らの人生から学ぶことも多くあるように思います。
確かに、Steve Jobsとジョン・スカリーの間柄はビジネス界の歴史の中でもユニークで教訓に富んでいます。彼らの関係は、単純に「敵」と「味方」、または「対立」と「協力」の二項対立で捉えることはできません。
彼らの間には確かに対立や摩擦があったものの、初めから互いに認め合う部分も多く、それがAppleを成長させる原動力の一部となっていました。JobsがスカリーをAppleに招聘した際の熱意や、スカリーがPepsiを離れてAppleの冒険に参加した背景には、彼らの共通のビジョンや野心がありました。
しかしながら、組織の成長、ビジネスの複雑性、そして各々の役割やビジョンに関する違いなど、様々な要因が絡み合い、彼らの関係は緊張と対立に至りました。
それでも、時が経過し、両者が自らのキャリアや人生を振り返ったとき、過去の出来事を冷静に評価し、互いの存在の価値を再評価することができたのは、彼らの人間性や成熟度を示すものと言えるでしょう。
彼らの物語は、才能やビジョンを持つ人々が共に働く場面での対立や協力の難しさ、そしてそれを乗り越えるための人間の成熟や柔軟性の重要性を教えてくれます。
そしてお互いの感想のやり取りに
Chat GPTからの応答に関して、感想を一言で伝えます。
質問:ありがとうございます。大事なポイントです。
はい、絶対にそうです。人間関係やビジネスの舞台裏には、表面上では見えない複雑な要因や感情が絡み合っています。ジョブズとスカリーのようなケースは、成功と挫折、友情と対立、そして最終的には互いの理解と尊重という過程を通じて、私たちに多くの教訓を提供してくれます。
こうした歴史的な事例を振り返り、考察することで、現代のビジネスや人間関係にも役立つヒントや示唆を得ることができると思います。
Chat GPT自体に感情はありません。
こちらの感情が上記の応答を読むときに反映されます。
リスクマネージメントのやり取りから始まった「興味」「探究」のプロセスをもってとても感動的なまとめになりました。
学習AIはすごいなーと思います。
間違いなく質問者が学習する機能が提供されています。
当初の懸念事項として挙げた教育現場での活用は本当に重要だと思います。
生成AI活用のリスクをもう一度訊ねてみます
質問:教育について質問です。例えば今後教育領域でChat GPTをはじめとした生成AIの活用が進んでいきます。その時に最も気をつけること、リスクのマネージメント、新しい可能性ついて端的にまとめてください。
この質問に対して「応答1」と「応答2」が提示されます。
*すみません、Chat GPT4とのやり取りのテンポを優先してしまって、スクリーンショット撮り忘れてしまいました。
内容を吟味して、応答1を選んでコメントをつけて再度質問を投げます。
質問:(応答1を選んだ理由)最も気をつけることについては応答2が、リスクマネージメントについては1が、新しい可能性については応答1が、まとめについても応答1が優れています。
理解しました。ご指摘いただいた内容を元に、改めてまとめた内容を提示いたします。
最も気をつけること:
1. 過度の依存: AIに過度に依存せず、生徒や学生の独自の思考や分析能力を磨くこと。
2. データの正確性: AIが提供する情報や解答の正確性や信頼性を確認すること。
3. プライバシー: 学生や教師のデータの取り扱いに関するプライバシーの確保。
リスクのマネージメント:
1. 教育的バイアス**: AIが有する潜在的なバイアスを理解し、それが教育結果に影響しないようにする。
2. 誤解の拡大: AIの回答や内容が絶対的な真実であるとの誤解を拡大させないこと。
3. 技術の更新: 進化するAI技術に合わせて、使用するAIツールやシステムの定期的なアップデートを行う。
新しい可能性:
1. 個別指導: 学生一人ひとりの学習スタイルや進捗に合わせた指導が可能となり、効率的な学習を実現。
2. 教育の平等化: どの地域や背景からの生徒でも質の高い教育にアクセスできる。
3. インタラクティブな教育: 従来の学習よりも実践的で双方向的な学習を実現。
生成AIの活用は、教育領域においても多大な可能性を秘めていますが、適切な運用と管理が不可欠です。
まとめ
新しい技術・テクノロジーのリスクとの伴走について、マーケティングの役割、Value共有のための顧客理解の重要性の議論はAppleのケースを引き出すことになり非常にダイナミックなものでした。
教育現場での生成AI活用についても視点をつくることができました。
個人的にはJobsさんのもう一つの「Connecting the dots」が見つかったことがとても幸せな驚きでした。
今回の生成AIと伴奏する意味・意義をみなさんが見つけてくれたとても嬉しいです。
おまけ:Jobsさんのスタンフォードでのスピーチ
とても有名なスピーチですのでご覧になった方が多いと思います。
最後にアップさせてください。
15分のスピーチです。日本語の字幕をつけることも可能です。
まだの方はぜひご覧になってください。
Chat GPTによる要約です。
*一部に誤訳や誤字がありましたので、僕が手直ししています。
ビデオを見るにあたって参考になるとうれしいです。
スティーブ・ジョブズが2005年にスタンフォード大学の卒業式で行ったスピーチでは、彼自身の人生経験を元に、3つのエピソードを中心に話しました。以下、それら3つのエピソードを要約いたします。
1. 「ドットをつなぐこと」についてのエピソード:
ジョブズは、リード大学を正式に中退した後も、しばらくの間キャンパスに滞在しました。彼は公式には授業を受けていなかったものの、自分の興味を引く授業を聴講生として受けることができました。その中で、彼はカリグラフィー(西洋の書法、特に美しい手書きの文字)のクラスに参加し、書道の美しさと洗練された文字の形を学びました。
この経験は、後にMacintoshの美しいタイポグラフィへと繋がったと述べ、人生の中で起きる出来事が後に「ドット」として繋がることを強調しました。
2. 「愛と喪失」についてのエピソード:
ジョブズは、Appleを設立し、10年で大企業に育て上げた後、30代の若さで自らが設立した会社から追放される経験をしました。しかし、その追放が結果的に彼にとっての解放であり、その後のNEXT、Pixar、そしてAppleへの復帰、そして多くの革命的製品の開発へと繋がったと述べました。
3. 「死」についてのエピソード:
ジョブズは、パンクリアスがんの診断を受けたことを公にし、人生の終わりに直面することで、本当に大切なもの、そして生きる意味についての洞察を得たと話しました。死は人生の変遷の一部であり、自分の直面している死が彼を前向きに行動させる原動力となったとも述べました。
スピーチの結びとして、ジョブズは「Stay Hungry, Stay Foolish(飢えたままで、愚かでいること)」という言葉を卒業生たちに伝えました。これは彼が若いころに影響を受けた「Whole Earth Catalog」の裏表紙に書かれていた言葉で、絶えず学び、新しいことに挑戦し続けることの重要性を伝えるものでした。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
Chat GPT活用のワークショップや、Chat GPTを利用した「質問力強化」とレニーングを実施しています。
研修・トレーニングについてはこの記事を参考していただけるとありがたいです。
特に「質問力」強化は問題発見から課題生成のスキルアップにつながります。
お役に立つと思いますので、ぜひお問い合わせください。
それでは、また。
よろしければサポートをよろしくお願いいたします! みなさまのお役に立てるようにこれからも活動を続けます! 今後ともどうぞご贔屓に!
