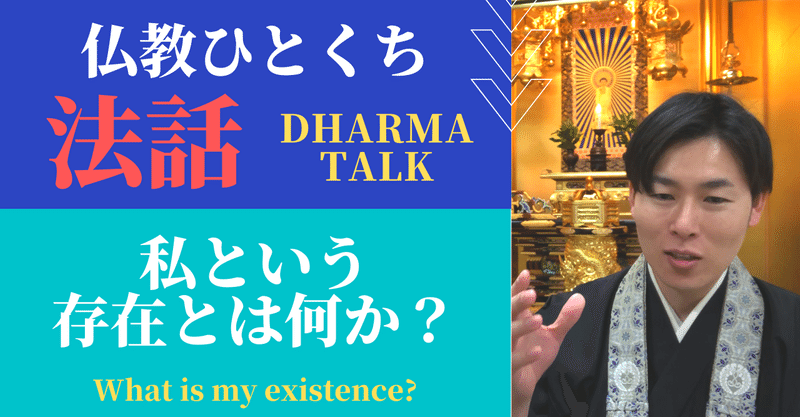
私という存在とは何か?【仏教ひとくち法話】#013
この内容は、お寺の朝会「ヘルシーテンプル@オンライン」での法話を文字起こししたものです。
▼この内容は動画でもご覧いただけます
「ヘルシーテンプル@オンライン」。本日は信行寺版でございます。
「幸せを育む法話の時間」ということで、毎週のように法話を通して、人生や幸せについて、ご参加の皆様と考えさせていただいております。
さて先週は、「ヘルシーテンプル」の全国版のほうになりますけれども、「人はなぜ苦しむのか」というテーマについて、考えさせていただきました。
その時にお話させていただいた内容は、このような内容になります。
・我々は自己への執着があり、そのために物事や出来事を自分中心に見て考えてしまう性質をもっている。
・おおよそ自分の思い通りになっていれば、快という心地良い感情を抱き、思い通りになっていなければ、不快という苦しみの感情を抱く。
・人はなぜ苦しむのかというと、自己への執着があるため、自分の思い通りにならない時に苦しみの感情が生まれる。
このような内容について、お話をさせていただきました。
もちろん、身体に痛みがあれば苦しいですし、苦しみの要因で言えば、人間関係や健康といったことも主要因として挙げられるかと思います。
こうした様々な要因がありつつ、我々の根本的なところでいうと、自己への執着というものがあり、自分を中心に物事や出来事を見て考えてしまうがゆえに、
思い通りになっていかない時に、不快という苦しみの感情がうまれてくる、そうした苦しみの構造について、前回みたところでした。
今回は、前回の話に基づいてお話をしていきたいと思います。
我々はどうしても自分中心に物事や出来事を見てしまう、自己への執着というものがあります。
では、いったい「私という存在とは何か?」について、考えてみたいと思います。
◆動的平衡
「私という存在とは何か?」について話を進めていくにあたり、参考にさせていただきたいのが、2011年2月におこなわれた「親鸞フォーラム」での対談講演です。
「仏教と生命ーいのちのゆくえー」というテーマでの講演で、大変興味深い内容ですので、ご関心がある方は、Youtubeに動画がありますので、ご覧になってみてください。
その対談講演の中で、生物学者の福岡伸一先生が、ドイツのシェーンハイマーという1941年に亡くなった学者の研究を紹介されていました。
その研究について福岡先生がお話になったことを簡単に申し上げると、我々は食べ物を食べると、それが体内の至る所に取り込まれて、自分の身体の一部となり、そして同時にこれまで自分の身体の一部であったものが抜け出ていくということでした。
つまりこれは、我々の身体は日々、そして一瞬一瞬入れ替わっているということです。そして、一瞬一瞬中身が入れ替わりながらも、バランスを保ちながら、私という存在が成立しているということです。
一瞬一瞬、身体の中身が入れ替わりながらも、私という存在が成立しているのはなぜでしょうか。それが、福岡伸一先生が言われる動的平衡(どうてきへいこう)というものです。
動的平衡とは、それを構成する要素は、絶え間なく入れ替わっているにも関わらず、全体として一定のバランスが保たれている状態のことを言うそうです。
詳しくは、福岡先生の『動的平衡』という本に書かれていますので、読まれたことがある方もおられるかもしれません。
こうして、構成する要素が絶え間なく入れ替わりながらも、全体として一定のバランスが保たれているのは、生命現象もそうですし、実は環境もそうですし、自然もそうだと言えるそうですね。
色々なものがつながり、入れ替わりながら、動的な流れやよどみとして、自分という存在が成立している。それが生命現象ということだそうです。
◆諸行無常と諸法無我
少し仏教に寄せて考えてみますと、世の中の色々なものは移り変わっているという考え方は、仏教では諸行無常といいます。諸行とはあらゆるものがという意味で、無常とは常でないということ。
あらゆるものは移り変わっているし、この私という存在も一瞬一瞬移り変わっているんですよと読み取っていけるのが、仏教の諸行無常という考え方です。
そして、単独で変わらずに存在するものはなく、様々な要素が寄り集まって仮に私という存在として成り立っているという考え方を、諸法無我といいます。
諸法という言葉もあらゆるものがという意味で、無我とは、単独で変わらずに存在するもの(我)はないということです。
我々は、私という存在は確かにあるものと思い、存在しているものと思うのですが、実は分解してみると、色々な細胞などが集まって構成されていて、単独で存在しているわけではありません。
そして、細胞レベルだけでなく、人と人との関係においても、互いの支え合いがないと、我々人は生きてはいけません。
今日のテーマである「私という存在とは何か?」ですが、我々が私と思っている存在とは、実は様々な要素が集まって仮に成り立っている存在ですよというのが、諸法無我という仏教的な見解です。
そして、その私と思っている存在も、諸行無常ですから、移り変わっていくものですね。
福岡先生の動的平衡という考え方も加味していえば、構成する要素が絶え間なく入れ替わっているわけですから、昨日の私と今日の私とは、物質的には違うということになります。
日々移り変わっている、諸行無常の私ですね。
そして、要素が寄り集まって、全体として一定のバランスが保たれながら私という存在も仮にある。諸法無我の私です。
◆いただいたいのち
仏教では、この話からどう展開して考えられるかというと、本来は移り変わっていく諸行無常の私、要素が寄り集まって仮にある諸法無我の私であるものを、確かな私として執着してしまうがゆえに苦しみが生まれるということを考えることができます。
我々は、この私というものを、変わらないものと思ってしまうことがあるかもしれません。
実際は、老病死といって、歳を重ねたり、病になったり、亡くなったりしていくように、移り変わっていく諸行無常の私です。
しかし、歳はとりたくないし、病気にもなりたくないし、死にたいとも中々思えないのも我々です。我々は、こうありたいという自分の像を描きます。しかし思い通りには中々なっていかない現実に苦しむことがあります。
そしてまた我々は、ともすれば自分が良ければ良い、自分が自分がという殻に閉じこもって生きてしまうこともあるかもしれません。
我々が私と思っている存在とは、実は様々な要素が集まって仮に成り立っている諸法無我の存在です。
しかし、日常の中では、私は存在しているというのは当たり前の前提としていますし、私が存在していることを疑うこともあまりないのではないかと思います。
そして、自分の欲を満たしていくことが幸せであると思いがちな我々です。自分の欲は見えやすいですし、それを満たしていくことで良くなっていきそうですからね。
したいことをかなえていこうとすることは良いことですが、しばしばそれが独りよがりになってしまったり、いつまでも欲が満たされず、自分が良ければ良いという生き方に虚しさを感じることもあります。
それは、自分という存在は、様々な要素が寄り集まって存在していることや、互いに支え合って生きていくような生き方から反したあり方に
なってしまっていることへのサインかもしれません。
生命とは、絶え間なく入れ替わり、消滅変化をして引き継がれていく、その営みの一点であり、かつ全体であるかと思います。
常に動的な流れの中にあるものであり、様々な構成要素が寄り集まって成立しているものが生命といえるかと思います。
移り変わっていき、要素が寄り集まって仮に存在している私かもしれませんが、そこからご縁というものを感じるならば、様々なご縁により、今いただいているのが、私という存在であるともいえます。
仏教から考えられることとして、諸行無常、諸法無我の私であるものを、確かにあるものとして自己に執着するところから苦しみが生まれているということが一つ。
そしてまた、諸行無常の生を生きながら、諸法無我のつながりの中で大きないのちを生きている、生かされていることにも目覚めてほしいというのが、仏教の説くところでもあり、仏様の願いでものではないかと思います。
今回は、苦しみの原因となる自己への執着というところから、では「私という存在とは何か?」という問いを立てて考えてみました。
限られた時間の中で、お話をしつくすことは難しいですけれども、幸せを育む法話の時間ということで、今回はこのようなお話をさせていただきました。
一旦閉じさせていただきまして、ご参加の皆さんにもお話を伺っていきたいと思います。
___
最後までご覧いただきありがとうございます。
合掌
福岡県糟屋郡宇美町 信行寺(浄土真宗本願寺派)
神崎修生
▼過去の記事
___
更新情報は各種SNSにて配信しておりますので、宜しければ是非、「フォロー」いただけますと幸いです。
▼各種SNS
https://linktr.ee/shuseikanzaki
▼ブログマガジン購読
https://note.com/theterakoya/m/m98d7269f59de
購読者限定のブログマガジン「神崎修生の仏教部屋」では、さらに味わい深い仏教やお寺の内容を記しています。ご関心がある方は、是非ご購読ください。
いただいた浄財は、「心豊かに生きる」ことにつながる取り組みに活用させていただきます。
