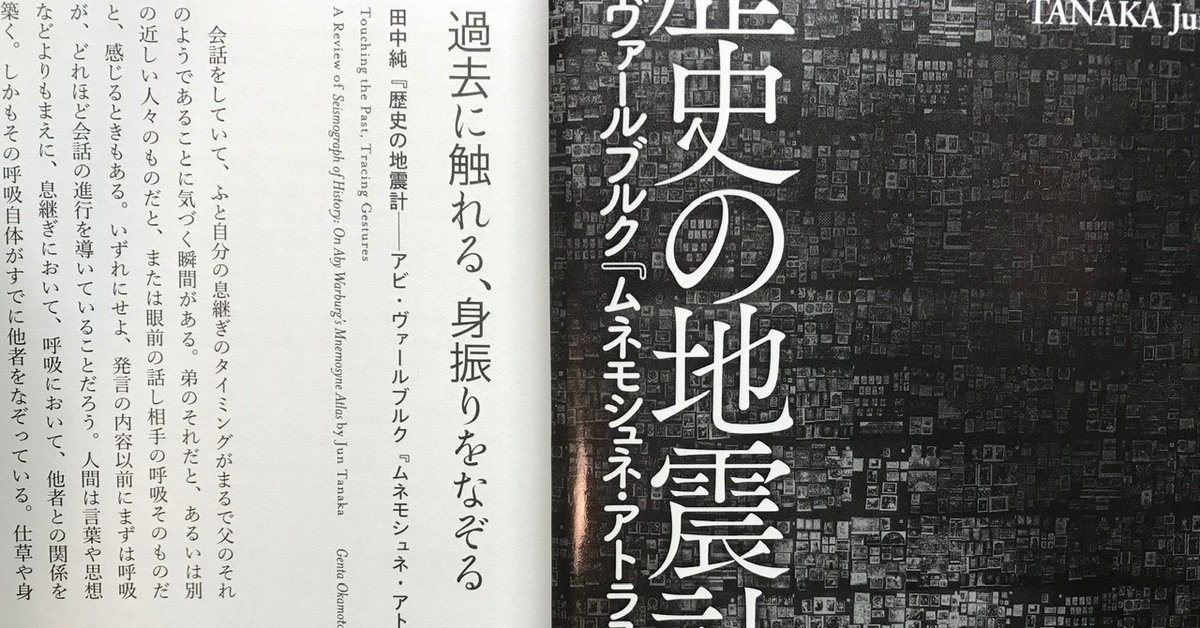
過去に触れる、身振りをなぞる──田中純『歴史の地震計──アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』書評
会話をしていて、ふと自分の息継ぎのタイミングがまるで父のそれのようであることに気づく瞬間がある。弟のそれだと、あるいは別の近しい人々のものだと、または眼前の話し相手の呼吸そのものだと、感じるときもある。いずれにせよ、発言の内容以前にまずは呼吸が、どれほど会話の進行を導いていることだろう。人間は言葉や思想などよりもまえに、息継ぎにおいて、呼吸において、他者との関係を築く。しかもその呼吸自体がすでに他者をなぞっている。仕草や身振りについても言を俟たない。本書『歴史の地震計』*1で著者は、アビ・ヴァールブルクの身振りをなぞりながら、彼の晩年の名高い図像集『ムネモシュネ・アトラス』の未完の試みを分析し、敷衍し、拡張していく。そのとき、分析される対象であったはずのヴァールブルクのほうがむしろ著者に本書を書かせているかのような、転倒現象が起こっている。ヴァールブルク自身も「ブルクハルト演習最終日」でブルクハルトとニーチェについて論じた際、彼らを考察対象としてよりも倣うべき手本として、パラダイムとして、その手つきをなぞっていた。身振りはかくのごとく伝播する。つまり、身振りはそれ自体でつねにすでに身振りをなぞる身振りだ。しかも呼吸のように無意識的になぞってしまっている身振りである。こうして、分析していたはずの過去の対象によって現在の自分のほうが導かれることになり、現在から過去を回顧するどころか過去のほうが現在へと侵入してくることになる。著者はそのありようを、まさにヴァールブルクの「ブルクハルト演習最終日」原稿や「蛇儀礼」講演メモに登場する「地震計」の比喩でもって捉える。本書の表題にある「歴史の地震計」の謂いである。
本書の目論見や構成、そしてヴァールブルク研究としての意義は、著者自身が明快にまとめているのだから、ここで繰り返すまでもない。ヴァールブルクという「歴史の地震計」を論じつつ、みずからもその振動を伝える地震計たらんとしている本書を読み終えたならば、まっすぐにこう問いかけるべきだろう──歴史はどこにあるのか、と。失われた過去の時空にだろうか、それとも歴史家の叙述にだろうか。歴史とはむしろ、身振りをなぞる身振りそのものではないのか──。
「歴史をめぐる私記」として書かれた前著『過去に触れる』(二〇一六)で、著者は「私記」という形式でなければ叙述できないような「歴史経験」の水準を問題にしていた。つまり、「過去に触れる」としか言いようのない、生々しい身体的な経験としての歴史との関係である。本書はそうした歴史経験にともなう多感覚的・共感覚的な身体性を、ヴァールブルクに見いだす。第一次世界大戦という危機の瞬間を潜り抜けて全感覚が鋭敏になり、あらゆる細部を「しるし」として感得するにいたったヴァールブルクの過敏な身体性が、『ムネモシュネ・アトラス』のパネル上で震えるかに並ぶイメージの数々に看取される。それは、著者によれば、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンが「モンタージュ」と呼ぶイメージ同士の構成以前にある、分散したまま細部が並列している「パラタクシス」の状態だという。著者は『ムネモシュネ・アトラス』におけるこのパラタクシスを執拗に記述し、それに導かれるがまま、野心的な第五章「ニンフとアトラスをめぐる『ムネモシュネ・アトラス』拡張の試み」で、パネル上には不在のイメージにまで連鎖を辿っていく。
『過去に触れる』で論じられたごとく、歴史経験から希望が生じるのだとすれば、『ムネモシュネ・アトラス』から生まれる希望はいかなるものだろうか。躁状態のニンファと鬱状態の河神のあいだでイメージに翻弄される西洋の分裂症を診断したヴァールブルクを受けて、著者はニンファをグラディーヴァ=始祖鳥=ハルピュイア/セイレーンの形象へ、河神をアトラス=せむしの小人=プルチネッラの形象へと延長し、そのいずれもが卵と翼のイメージに到達することを示す。ジョットやピサーノの翼ある希望の寓意像がそこから生まれるかのような卵──こうしたイメージの連鎖は、人類史の太古からの記憶、苦悶のなかで人々が抱いた解放への歴史的かつ無意識的な願望のなせるわざだろうか。
ニンファとアトラスの系譜についてはディディ=ユベルマンも、『近代のニンファ』(二〇〇二)、『アトラス、あるいは不安な悦ばしき知』(二〇一一)、『漂うニンファ』(二〇一五)、『深みのニンファ』(二〇一七)といった著作で自在に敷衍している。また、ベルトラン・プレヴォーが論文「方向/次元──ニンファとプットー」(二〇一三)で、ニンファとプットーとを対になる脱領土化と再領土化の運動の形象としてあとづけ、ダヴィデ・スティミッリの論文「ヴァールブルクのインプレーザ」(二〇〇四/二〇一三)でもアトラスの図像誌が考古学的な手つきで綿密に辿られている。だがそれらに対して、ニンファとアトラスの系譜の先に希望の図像を手繰り寄せるのは、歴史経験を問う著者ならではの鮮やかな離れ業だろう。
ここで思い出されるのは、中井正一が『近代美の研究』(一九四七)や『美学入門』(一九五一)で、今日の国際機構などにおいて形成されつつある集団的主体性を、ほかならぬアトラスになぞらえていたことである。エルンスト・カッシーラーによってプロメテウスになぞらえられたルネサンス以後の近代の個人的主観性が、発明と創造の才能によって世界を意味づけるものであったとすれば、中井の語る現代の集団的主体性は、アトラスとして世界を背負う。テクノロジーの発達により全世界の運命を左右するまでに巨大になった人間社会──このアトラスが背負う世界は、しかし中井によれば人類の歴史性そのものでもあり、中井はアトラスの眼差しを、歴史のなかで苦悶に喘いできた人類が抱く解放への無意識的な願望をまっすぐに見つめるものと語っている。しかもアトラスたる集団的主体性は、映画という、中井にしたがうなら繋辞なしに──意味づけを欠いたまま──イメージとイメージをただ並列する装置によってこそ、もっとも触発されるという。この意味で中井の映画理論は、モンタージュというよりもパラタクシスを論じているかのようだ。『ムネモシュネ・アトラス』に結実するヴァールブルクの美術史学が映画装置に比すべきものであることは、ジョルジョ・アガンベンやフィリップ=アラン・ミショーが指摘していた。あわせて思い起こしておこう。
ともすればカッシーラー流の進歩主義的な精神史観をとっているかに思えるヴァールブルクだが、しかし彼は「未開から文明へ」という図式から逸脱する歴史的事象に、細部に、つねに鋭敏だった。『ムネモシュネ・アトラス』も、そうした図式的な理解をたえず擦り抜ける。もしパネルの一枚一枚をある時代精神の挿絵として眺め、パネルの連なりを西洋人の(あるいは人類の)精神構造の図解──これはたんに範囲を際限なく広げただけの時代精神の挿絵にすぎないが──として読もうとするなら、そのとき見えるのは(細部に目をつむるのでなければ)まさにそのような図式の解れと綻びばかりだろう。『ムネモシュネ・アトラス』は、歴史を鳥瞰するような普遍的な視点も座標も想定していない──それがアガンベンの先駆的な指摘であった。『ムネモシュネ・アトラス』と歴史(学)の関係は、一見したところよりもはるかに複雑である。時間を消去してすべての図像を等価に配列できるという錯覚、いまここにいる自分だけは歴史の外側から鳥瞰できるという錯覚を回避して、いかに歴史に向き合えるのか。「歴史の地震計」とは、この問いに対してヴァールブルクと著者が示唆する答えだろう。
このとき重要なのは、言うなれば歴史を経験することであって、もはや認識することではない。ディディ=ユベルマンは、「可視性」に対して「視覚性」を重視しながら、視覚には不可視なものが浸透していることを指摘した。認識にはつねに認識されない領域がともなう。本書で著者はそれを歴史経験の多感覚性・共感覚性の考察へと拡張する。とはいえ、多感覚性・共感覚性が認識論の枠内でのみ理解されてしまえば、過去はなおも認識の対象のままにとどまってしまう危険がある。認識の主体はあいもかわらず歴史の外側から鳥瞰しているかのような錯覚を抱きつづけるおそれがある。おそらくはそれゆえに、著者はヴァールブルクの身振りをなぞるだけでなく、その身体性をベンヤミン的な「模倣の能力」を通して経験しようとし、またその昂揚する文体でもって読者にも経験させようとするのだろう。「たんに知的にではなく、膚に触れるように生々しく、冥界からの息吹をともなって」、と。
歴史はどこにあるのか──すなわち、「冥界からの息吹」はどこから届くのか。「冥界からの息吹」とは、どこかからかそよいでくるものというよりも、実はいまこのわたしの呼吸そのものではないのか。身振りはつねにすでに身振りをなぞる身振りであり、最小の身振りたる呼吸もつねにすでに他者の呼吸をなぞっており、わたしの呼吸自体が「冥界からの息吹」である。本書を読む経験は、歴史をどこか別のところ──失われた時空や歴史家の叙述──にではなく、わたし自身に浸透してしまっているものとして感得させてくれるように思う。この経験は、どこか魅惑的であると同時にはっきりと恐怖を抱かせもする。美しきニンファのごとく人間を誘っては死の淵に引きずり込むイメージというものにヴァールブルクが認めた魅惑と恐怖の源泉が、ここにある。『ムネモシュネ・アトラス』は、実のところイメージの歴史を考察したものではないのだろう。歴史こそがイメージ──魅惑し恐怖を抱かせる身振りの身振り──であるからだ。*2
*1 田中純『歴地の地震計──アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』、東京大学出版会、2017年。http://www.utp.or.jp/book/b307545.html
*2 岡本源太「過去に触れる、身振りをなぞる──田中純『歴地の地震計──アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』書評」、『表象』第12号、2018年3月、254-256頁。
