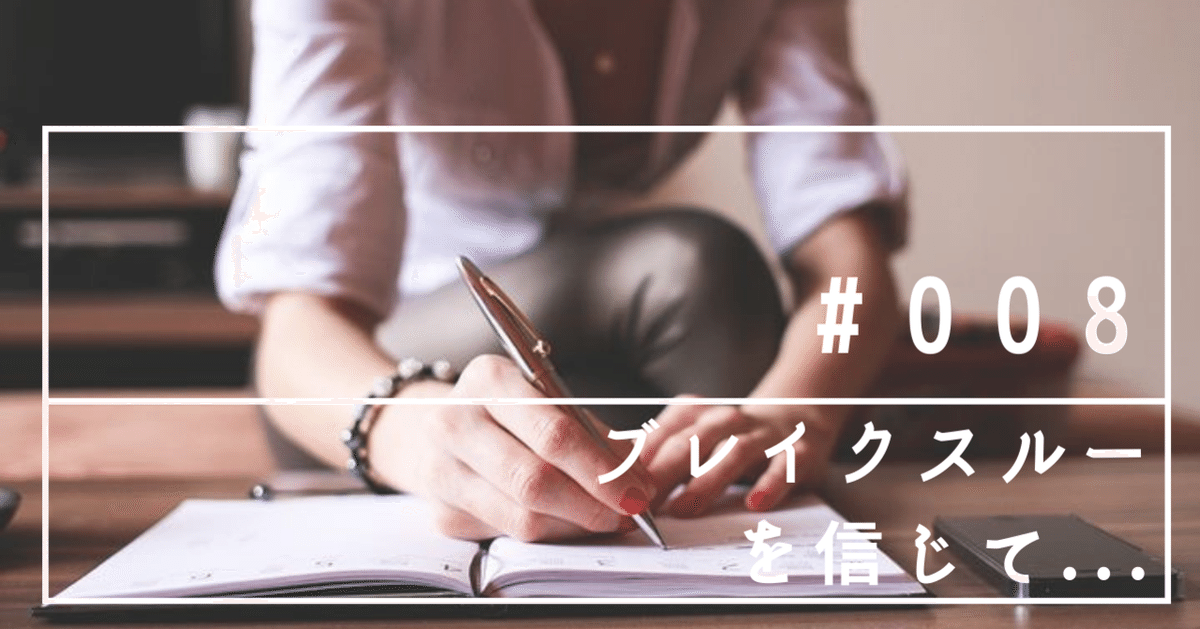
そろそろ会社で幸福の話をしよう #008 「ブレイクスルーを信じて...」
34歳女性 - 時短勤務(中途入社)Cさん
「自分の幸福って何だろう」という問いって、女性にとってはかなり普通のことというか、むしろ人生の節目節目で「考えなければいけないこと」だったりするんじゃないでしょうか。女性は男性よりも、生き方のバリエーションが多いので、結婚するかどうか、どんな人と結婚するか、子どもを欲しいと思うか、いつ産むのか、がむしゃらにキャリアを積むのか・・・自分にとって何が幸せなんだろうって考えながら、可能な範囲で生き方を選択したり、選べなかった生き方を諦めたりしているんだと思います。自分の本当に生きたい生き方を選べればいいですけれど、どちらかというと、諦めることの方が多いような気もします。
だからこそ、自分の生き方を「これが私の幸せなんだ」って思いたいわけなんですけれど、そうすると、違う生き方の人との間にすごい溝ができるんですよね。昔、既存女性と未婚女性の間の溝について書かれた「負け犬の遠吠え」っていう本が流行りましたけれど、同じように会社で働く女性同士でも、家庭の状況やキャリアはそれぞれ違いますし、正直、たくさんの溝があります。
生き方が違うんだから、幸せを比べてはいけないって、みんな分かってるんですよ。でも、相手の持っている幸せは、自分が諦めた幸せだから、やっぱり心の奥の方に、ないものねだりをしてしまう自分が出てきたりするんです。私は2人の子どもがいて、すごく幸せです。でも、時短で仕事には全然十分に取り組めていなくて、子供が熱を出して休んだりして周りに迷惑をかけてばかりで。同期の子がバリバリ働いて大きなプロジェクトをこなしているのをみて、大変そうだけれどやっぱりめちゃくちゃ羨ましいんですよね。そんなこと言えないですけれど、誰にも。
なので、幸福の話題を人とするっていうのは、結局人と比べてしまうことになる気がして、自分にとってもマイナスな感じがしますし、そもそもそんな話題を会社でしたら、正直、人間関係が取り返しのつかない感じになりそうです。
僕の思い
「自分の幸福って何だろう」という問いって、女性にとってはかなり普通のことというか、むしろ人生の節目節目で「考えなければいけないこと」だったりするんじゃないでしょうか。
いきなりガツンと来た。 僕の今の視野・視座・視点に、OS変更レベルの動きを加えた上で、全力かつ真摯に向き合う。その覚悟がないと、Cさんに失礼だと瞬間的に察知した。
女性は男性よりも、生き方のバリエーションが多いので、結婚するかどうか、どんな人と結婚するか、子どもを欲しいと思うか、いつ産むのか、がむしゃらにキャリアを積むのか・・・自分にとって何が幸せなんだろうって考えながら、可能な範囲で生き方を選択したり、選べなかった生き方を諦めたりしているんだと思います。自分の本当に生きたい生き方を選べればいいですけれど、どちらかというと、諦めることの方が多いような気もします。
属性による違い。これは普段の人事業務においても常に存在する重要なテーマだ。僕はどちらかというと前向きに捉えている。「違い」を尊重し、真剣に対応していくことで、革新的な着想に至るケースを経験したことがあるからだ。今回もCさんの思いを、逆に良い方向に導きたい。何が言いたいかというと、「Cさん、一緒にブレイクスルーを起こそう。」
だからこそ、自分の生き方を「これが私の幸せなんだ」って思いたいわけなんですけれど、そうすると、違う生き方の人との間にすごい溝ができるんですよね。
さっきあった「諦める」という文脈を考えると、簡単には受け入れづらい自分の幸せが目の前にあって... さらには、諦めなければ同じように実現したかもしれない他人の幸せも周りにたくさんあって... それも割と近場に... それは確かに色々と思うところが出てくると思う。これは、単純な「比較」とはまた少し違う種類の「比較」だと思う。
昔、既婚女性と未婚女性の間の溝について書かれた「負け犬の遠吠え」っていう本が流行りましたけれど、同じように会社で働く女性同士でも、家庭の状況やキャリアはそれぞれ違いますし、正直、たくさんの溝があります。
「諦めざるを得ない状況が、男性より女性に多く発生する」という傾向を踏まえると、次のことが予想できる。
・溝が生まれる機会もその分多くなる。
・溝の種類も多くなる。
・溝に対する理解や納得感も複雑になる。
これでもまだまだ全てを捉え切れないほど、女性同士の溝には、男性同士のそれとは異なる特有の難しさがある。このことをしっかり理解しておかなければならないと強く感じた。
生き方が違うんだから、幸せを比べてはいけないって、みんな分かってるんですよ。でも、相手の持っている幸せは、自分が諦めた幸せだから、やっぱり心の奥の方に、ないものねだりをしてしまう自分が出てきたりするんです。
諦めた幸せだから、諦めざるを得なかった幸せだから、余計に消えにくいし、羨ましさを感じてしまうし、ないものねだってしまう。「生き方が違うんだから、幸せを比べてはいけない。」という表現だけでは、到底包み切れない領域があるということを、今回まざまざと思い知らされた。
女性ならではの「比較」「溝」「妬みや羨望の感情」がある。話し手・聞き手の両方が、その存在を認識しておく必要があると感じた。同時に、その認識があれば、ブレイクスルーに近づけるかもしれないとも感じた。
私は2人の子どもがいて、すごく幸せです。でも、時短で仕事には全然十分に取り組めていなくて、子供が熱を出して休んだりして周りに迷惑をかけてばかりで。
という状況のCさんだからこそ、感じる幸せがあるはず。見える幸せがあるはず。それがCさんの幸せだと思う。背景と幸せはセット。背景含みで自分の幸せを考えてみるのはどうだろうか。そうすれば、今ある幸せへの愛おしさ・納得感みたいなものがより重厚になってくるような気がする。どうだろうか?
同期の子がバリバリ働いて大きなプロジェクトをこなしているのをみて、大変そうだけれどやっぱりめちゃくちゃ羨ましいんですよね。そんなこと言えないですけれど、誰にも。
いや、もしかしたら「羨ましい」と口に出して言ってみても良いのではないだろうか。言われた側は、自分がその状況にいることを実感し、当たり前にある幸せを、それこそCさんと比較することで、有り難い幸せと感じるようになるかもしれない。また、言われた側は、逆にCさんの状況を羨ましいと思っていて、それに関するコメントが出てくるかもしれない。そうすればCさん自身にとっても流れ・考え方に変化が起きる可能性が出てくる。
ポイントは、やはり幸せ部分だけを切り取らず、背景含みで捉えることだと思う。話し手は、幸せを背景とセットで語ることで、その幸せによりオリジナリティを感じ、愛おしさ・納得感を高めながら、聞き手に「自分だからこその幸せ」を伝えることができる。一方、聞き手は、幸せ部分だけでなく背景についても意識を傾けることで、その幸せは「相手だからこその幸せ」と捉えられるようになる。今回の難敵であるあの「比較・溝・妬みや羨望の感情」とも、良い感じの距離を取れるようになるはずだ。そう考えると、対話を始めてみるのも悪いことだけではないかもしれない。
なので、幸福の話題を人とするっていうのは、結局人と比べてしまうことになる気がして、自分にとってもマイナスな感じがしますし、そもそもそんな話題を会社でしたら、正直、人間関係が取り返しのつかない感じになりそうです。
比べてしまうのは仕方ないことだと思う。ただ、今後比べる際に、少しだけ意識してみてほしい。「幸せと背景、セットで比べているかどうか」を。その感覚やコミュニケーションが定着してくれば、自分にとってマイナスなことばかりではないと気づく瞬間が増えてくるはずだ。同時に、相手の幸せを「相手だからこその幸せ」と捉えられるようになり、自分の幸せを「自分だからこその幸せ」と捉えられるようになる。その先にあるのは相手・自分へのそれまで以上の尊重だと思う。そこからお互いの関係性が、ワンランク・ツーランク上がるのだとすれば、お互いが尊重し合うことによる相乗効果が生まれるのだとすれば、それはマイナスどころか新たな次元でのプラスだと思う。ブレイクスルーだと思う。
これから、印象ギャップを埋めていくにあたり大切だと感じたこと。
「幸福の話題を人とするというのは、結局比べることに繋がり、自分にとってマイナス… 」と感じるかもしれないが、そうでない流れもあるということを啓発したいと思った。自分の幸せ・他人の幸せをきちんと理解する。そのために、幸せを背景と共に捉える。幸せ・その人のストーリー、2つをセットで対話できれば、人間関係はマイナス方向ではなく、むしろ良い方向(新たな信頼関係の構築など)へと繋がるかもしれない。その効果は想像以上のものかもしれない。この一歩踏み出す感覚や空気感を、Cさんに対してはもちろん、会社全体に対しても広げていくことが大切だと感じた。
合わせて、次のメッセージについてもしっかり発信することが大切だと感じた。
僕は今、会社での幸せ対話を増やしたいと思っている。その延長線上に、「会社・社員の持続的成長」があると信じているから。よって、みんなには、幸せについて語ることを少しずつ受け入れてほしいと思っているし、これからどんどん踏み出してほしいとも思っている。ただし、次のことを皆に伝えるのを忘れてはいけないとも思っている。マイナスな気持ちを語ることも大切に扱うこと。マイナスをすべてプラスにしようとしなくてもよいこと。比較・溝・妬みや羨望の感情を無視せず、(誰だって時にはマイナス感情を抱く。そして、そのマイナス感情を、そのままにしておきたい時だってある。)それらを含めて、話し手・聞き手がお互いを尊重できる道を、僕はしっかり考えていく。この点についても合わせて展開したいと考えた。
今回は、上記内容を、印象ギャップを埋める補助線(Tips)として項目立てたいと思う。
引き続き、様々なメンバーに声をかけ、幸せについて語ること、幸福に対する印象について聞いてみたいと思う。その中で、実際の声に対応する「印象ギャップを埋める補助線(Tips)」をどんどん整理していきたい。
幸せへの支援を起点に、会社・社員の持続的成長を支えるために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
