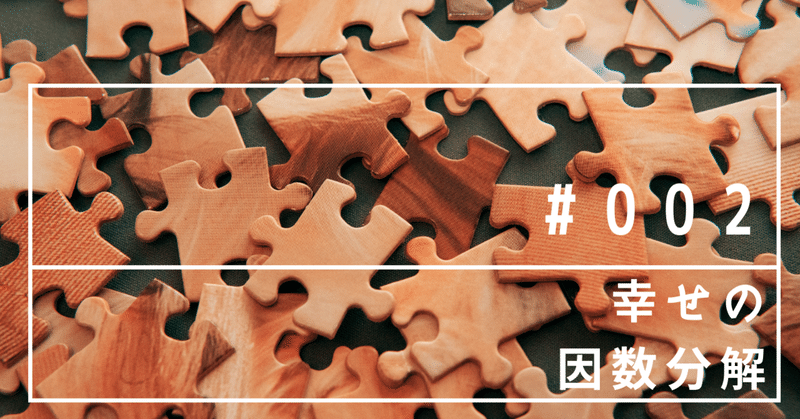
そろそろ会社で幸福の話をしよう #002「幸せの因数分解」
学生時代、数学の図形問題が嫌いだった。周りの友人たちには見える補助線が、僕にはなかなか見えなかったから。
補助線が引けると一気に進む。ゴールに近づく感覚がある。途端に楽しくなる。あの「見つけたぜ感」は本当に羨ましかった。
これから会社で、幸福という概念の理解を広げていくにあたり、僕はこれを上手く使いたいと考えた。皆の理解が進むよう「補助線的な情報」を提供するのだ。
解答や解説の提供、そんな偉そうなことはできる立場にない。その自信もない。ただ、補助線的な情報提供であれば、少し気楽に、そしてその分たくさんできそうだ。一緒に進んでいく感じも楽しそうだと思った。
✳︎
ということで早速、その流れに挑戦してみる。まずは情報。会社で幸福概念の理解を広げるにあたり、どんな情報が初回に相応しいかを考えた。
「幸せの因数分解」はどうだろう?ふと浮かんだので、自分の直感を信じることにした。
以下、今回、僕が参考にした内容。
主観的な幸福の要素としては、以下の3つがあると考えられている。
1)快楽的・感情的な要素
2)評価的・認知的な要素
3)エウダイモニア的・意味的な要素
・快楽的視点は、幸福を感じるか、快楽を経験するか、苦痛がないか、といった点に注目する。
・評価的視点は、人生や人生のさまざまな領域に対する見方や総合的な満足度といった点に注目する。
・エウダイモニア的視点では、個人が自己実現を達成したと感じているかどうか、あるいは完全に機能しているか、目的意識を満たしているかどうか、といった点に注目する。
<引用参考文献>
VanderWeele, T. J., Trudel-Fitzgerald, C., Allin, P., Farrelly, C., Fletcher, G., Frederick, D. E., … Kubzansky, L. D. (2020). Current recommendations on the selection of measures for well-being. Preventive Medicine, 133, 1–6.
上記内容を参考に、自分なりの解釈も加え、「幸せの因数分解」という情報のまとめに入る。
幸福は十人十色。ただし、心理学的にはある程度まとめられて報告されることもある。主観的幸福についても上記の通りまとめられる。少し乱暴だが、よりコンパクトにまとめてみると、以下のようなイメージになる。
● 主観的幸福は、①快楽、②満足、③達成、の3要素から成る。
ちなみにこの3要素に、幸福の質・時間の視点を加えると、一気にイメージが膨らむと思う。「快楽」として存在する幸福の質・時間(例えば持続時間)と、「達成」として存在する幸福の質・時間、2つの印象は全然違うと思う。「満足」はその間に位置するイメージ。個人的に、この捉え方はかなりしっくりきている。
更なるしっくりを求めて、主観とセットで考えたい客観についても触れてみる。客観的幸福は、その人を取り巻く環境要因(教育や医療の受けやすさなど)から成る、と聞いたことがある。
合わせて考えると、以下のようなイメージになる。
● 幸福は、主観的幸福(快楽・満足・達成)と、客観的幸福(その人を取り巻く環境要因)から成る。
しっくりしてきた。この考え方を今回のまとめにしようと考えた。
✳︎
が、しかし、ふと思った。仮にこの考え方で(この考え方をベースにした何かしらのサービスで)、自分の幸福を測定したとしたら、自分はどう感じるか?
非常に重要な問いだった。
出てきた結果と自分の幸せが同じかどうかは、慎重に考える必要があると感じた。
つまりそれは、「幸福は、主観的幸福(快楽・満足・達成)、客観的幸福(その人を取り巻く環境要因)から成る」という考え方が「全て」ではないということ指しているのだと思う。
「上記のような考え方によって出てきた結果」としての幸せもあれば、「自身がそう思ったもの・自身がそう決めたもの」としての幸せもある。そう捉えておく方が間違いが少ないはずだと考えた。
結果として出てきたものだけで、「あなたの幸せはこうだ」と言い切られると、「いや、それはそうだけど…でも自分としては….」となると思う。
✳︎
ということで、記念すべき初の補助線的な情報提供(「幸せの因数分解」)、今回は以下のようにまとめてみようと思う。
● 幸せは、「主観的幸福(快楽・満足・達成)、客観的幸福(その人を取り巻く環境要因)」から成る。ただし、「自身がそう思ったもの、自身がそう決めたもの」としての幸せもあることを忘れてはいけない。
特に後者、大切にしたいなと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
