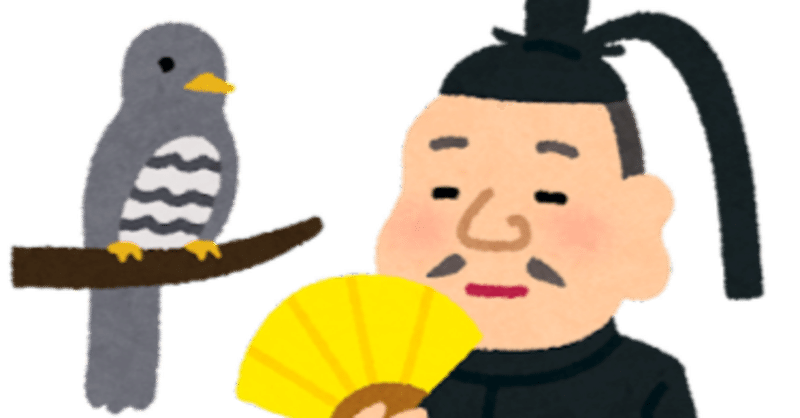
「どうする家康」第20回「岡崎クーデター」 どうする瀬名~瀬名が運命の歯車を回すまで~
はじめに
第20回は、早々に家康が倒れてしまったため、実質、前回に引き続き、瀬名の話となりました。
迫る武田軍の脅威、静かに進む陰謀を描きながら、本質は織田との清須同盟の問題点を浮かび上がらせるという構成の巧さが光りました。勿論、前髪の美少女戦士(今回も女装あり)、虎松の初陣と家康とのやり取りも見所です(笑)
そして、以前の記事でも仄めかしていた瀬名と望月千代女との対面で幕を引きます。
ところで、今回の背景である大岡弥四郎事件は、江戸時代に書かれた『松平記』や『岡崎東泉記』では、築山殿が関与したとの記述があります。つまり、築山殿が武田と内通したという通説の出所です。『松平記』では唐人医師との不義密通も伝えられます。
山岡荘八『徳川家康』、及びそれを原作とした大河ドラマでは大岡(大賀)弥四郎と不義密通の果ての内通として描かれました。
しかし、「どうする家康」で描かれた瀬名が、こうしたことを起こす要素はありません。ましてこれまで登場してもいない大岡との不倫は更にあり得ません。それだけに、これら流布された通説をどう描くのかは興味深いところでした。言い方を変えれば、「築山殿が弥四郎に唆されて武田に内通したこと」をどう翻案するかが、第20回を読み解く鍵ということになるでしょう。
そこで今回は、いかにして瀬名が『岡崎東泉記』の記載にもある歩き巫女との出会いに至ったのか、そしてその出会いの意味を考えてみましょう。
1.勝頼の才覚に潜む問題性
(1)歴史ドラマ史上、最強の武田勝頼
冒頭、光秀を相手にワインを飲み干す信長は、勝頼の才について「武田四郎勝頼、恐るべき才覚と俺は見る」と危惧しています。この発言は、信長が上杉謙信に当てた書状にある「四郎は若輩ながら信玄の掟を守り表裏を心得た油断ならぬ敵である」からの引用でしょう。この引用元の「表裏を心得た」という言葉には、信玄がそうであったように、勝頼もまた正攻法の武勇にも長け、また諜報や調略といった知略にも長けた将ということが示されています。武田家を滅亡させたことから、信玄に劣る凡将に描かれがちな勝頼ですが、実際は信玄の死後も終始、家康を圧倒しており、近年では再評価されています。
そして、その再評価どおり、家康は信玄死後も件の高天神城をまたも落城させられ、苦境に立たされています。大久保忠世の「信玄が死んでも武田は武田か」の言葉どおり信玄の残した武田軍という遺産の強大さです。
そうした中、静かに瞑想し、信玄の遺言を守り、三回忌(数えで三年)まで時を待った勝頼が遂に動きます。父の具足を前にするその姿は、かつて義元の具足を前にした氏真とよく似ています。
しかし、振り返っての発言は、ここからは自分のやり方でやるというものでした。いつまでも父の影に引きずられず、一方で信玄の遺産は十二分に利用する強かさ。氏真と違う強敵の二代目であることをその対比的な描写で表しています。そして、前回のルシウス信玄の不安を払拭し、その期待のみに応えていると言えるでしょう(今後は分かりませんが)。
ただ、いささか気になるのは、勝頼の「穴山、戦況はどうか」との問いに対する穴山信君の反応です。「順調でございます」との応答自体は問題ありませんし、そのとおりでしょう。しかし、ひれ伏し答えるその様子には恐怖が入り混じっているように感じられなくもありません。猛将であり気質が勝頼に近い山県ならば微塵も感じないでしょうが、知将タイプの穴山だからこそ恐れを感じているとすれば、ここに勝頼率いる武田軍ならではの問題がありそうです。
おそらく、若く優秀であるがゆえの苛烈な二代目、その裏側には家臣にすら自身と同じものを要求する面があるのではないかと察せられます。それは当然、家臣に必要以上のプレッシャーを与えますから、より過酷になるでしょう。そうなると、勝頼の主君としての本質は、(信玄以上の)「恐怖」ということになってきます。
勿論、これは思い過ごしの可能性もありますが…穴山のその後の動向が描かれるのであればあるいは…というところです。
ともあれ、ゴードン勝頼は岡崎に標的を定め、狙いを信康、瀬名と定め、軍略を進めていきます。同時に岡崎では大岡弥四郎による謀反の計画が進んでいます。彼らの連判状と武田菱が重なる演出が巧いですね。勝頼の狡猾さが岡崎を襲うという危機を端的に示しています。
(2)家康の中に生き続ける信玄
さて、この勝頼の才覚を恐れるのが、現実問題として彼と対峙する家康です。信玄並の巧みな軍略に圧倒され、心身、疲労困憊、ついには倒れてしまいます。病身となり、彼にとって最も大切な岡崎へ救援に行けぬことを情けないと独り言ちます。しかし、三方ヶ原合戦をとおし結束を固めた家臣団は柔軟です。宿老である忠次は家康の意を汲み、すぐに武勇に長けた忠勝、康政+オマケ(虎松)を差し向けています。
そうした忠次の気遣いを分かった上でなお、家康は「武田勝頼は恐ろしい男だ。あやつは信玄の知略、軍略全てを受け継いでいる」と述べます。家康が、現状、最善の策を施したにもかかわらず勝てる気がしないのは、勝頼もまた調略に長けていることを危惧しているということです。頭のよい家康ならではの現実的な理解として正しいと言えます。
しかし、後に続く勝頼の存在そのものを指した「信玄はまだ生きている」というこの言葉は、示唆的です。信玄がまだ生きているのは勝頼の中だけではありません。家康自身の心に恐怖として巣くっている、つまり家康の中にこそ生きているのです。それは、つまり、家康は未だに「弱き主君は害悪なり」という信玄の闇に囚われているということです。後年、家康は、数正離反の現実面と信玄への尊敬の二つの理由から、軍制を武田流に改めますが、「どうする家康 」の家康は尊敬からではなく、自身の弱さへの恐怖心とその克服からそうしてしまいそうな、そんな予感すらします。
ですから、家康の勝頼評は、表向きは勝頼が「わしが全てを注ぎ込んだ逸材」という信玄の発言(第19回)どおりの人物であったことを家康が裏打ちされた台詞ですが、それよりもそこに恐怖する家康の心底のほうが問題になるでしょう。既に戦国大名の弱肉強食の中にいる家康は、国を治めるということよりも武将として勝たなければならない、そこにしか目がいっていない状態です。無論、生き残ってこそ、夢は叶えられるのですが…
こうして見てくると、武田勝頼は近年稀にみる知勇に優れた猛将として描かれ、眞栄田郷敦くんの凛々しさも相まって、今年こそ長篠の戦いで勝利しそうです。しかし、一方で彼の才覚はあくまで武将としての知勇の器としてのみ評価されていることには留意しても良さそうです。武将としての評価は、統治者、主君としての評価とは決してイコールではありません。例えば、本多忠勝は武将としては家康に過ぎたるものの一つとされるほど優秀です。しかし、彼が幕府を築いた家康のような主君になれるかと言えば、それはNOですよね。
ただ、主君たることと武将として優れていることの違いを、家康も見失っている面がありますね。正確には価値観が揺れているのですが。だからこそ、彼は信長との同盟を切ることが出来ませんし、また次回、完全に信長に従属する選択をすることになるのでしょう。そして、この判断が近々、悲劇を招くことも…
2.岡崎城内にある人間関係の亀裂~若き城主夫婦の未熟さ~
さて岡崎城では、裏で進められている謀反に気づくこともなく、武田勢襲来に備え活気に溢れています。戦に備えて城内に詰めることにした瀬名と亀姫に意気込む信康ですが、そこに五徳が「浜松の殿は病に伏せっておいでとかで頼りになりませぬでなあ」と水を差します。思えば、この二人、幼い頃から「ああ言えばこう言う」という関係ですが、事ここに至って皮肉を言うのは空気の読めないことです。無論、この台詞に瀬名への当てつけが含まれているのは言うまでもありません。前回、浜松に追いやったはずの姑が、岡崎城に舞い戻ってきたことは、五徳には面白くありませんから。
空気を察した信康が「あれこれ命じられるばかりで、助けもよこさず、頼りにはならぬがな」と半ば諭すように信長を揶揄します。この揶揄は、信長のみならず五徳にも向けられています。つまり、信長から援軍も引き出せない五徳は嫁としての役割を果たせていないだろうと言うのです。何故なら、この当時の嫁は実家に属しており、嫁ぎ先との間をつなぐ外交的な役割を担っているからです。例えば、第14回でお市が長政の裏切りに対して「男なら切腹もの」と言ったのは、こうした役割があったからです。
この揶揄を真に受けた五徳は「我が父には天下人としての役目があるのです」と織田家の娘としてのプライド全開で悪びれもなく答えます。このときの立ち上がって信康に対して抗弁する五徳という構図は、彼女が信康を城主として立てる気持ちが無いことを表していますね。
ですから、まるで通じない五徳に、流石の信康も「御立派なことじゃのう」と嘲ります。同盟者の苦難も省みず、天下という絵に描いた餅を追う信長に失笑を禁じ得ない、そんな本音が漏れてしまいます。プライドを傷つけられ激昂した五徳は「父上(信長)に言いつける」と眦(まなじり)を上げ、収集のつかない夫婦喧嘩になりかけます。
今も昔も夫婦喧嘩は当事者同士で収めなければいけません、実家を持ち出して批判を始めると離婚か家庭崩壊の始まりですね(苦笑)
しかし、実はこのやり取りは、信長と家康の同盟のあり方を反映しているという点が重要です。清州同盟は当初から十年ほどは対等の同盟でしたが、浅井・朝倉とケリをつけ西への基盤が盤石になった後半十年は従属関係であったと指摘されています。そして、第20回はその浅井・朝倉との決着がついた時期に当たります。わずか数年のことですが、信長と家康の間は大きく変化しているのです(次回、第21回で描かれそうですね)。
「どうする家康」では当初から従属的な関係でしたが、一旦は信長の一心同体発言(第17回)で収まってはいました。しかし、また従属関係は更に強化されているのでしょう。外交的な役割を持つ五徳が事あるごとに「父上に言いつける」と言うのは、その関係性を示しているのです。
ただ五徳は立場上、信長の方を持つの仕方ありませんが、両家を取り持つ役割という観点からすれば、嫁ぎ先を蔑ろにする態度はバランスを欠いています。瀬名に対する態度も実家が滅び後ろ盾がないから余計に強く出ていることも察せられます。
だから、三河に馴染んでいこうとしないこの態度が、今後の不和の火種として禍根を残します。とはいえ、15歳という年齢を考えれば、いくら当時では大人だとしてもその未熟さは致し方ない面もありますね。
さて、信長の「天下一統」の理想に対する信康の「御立派」という指摘は、信康自身はあくまで本音から漏れた揶揄に過ぎませんが、一方で信長の覇道が、彼のみが描く独り善がりな空疎なものであることを図らずも示しています。誰も彼と夢を共有していないのです。清州同盟が、実はその成立したときから、信長に対する恐怖によって機能していることも、それを証明しています。
そして、恐怖による支配に対する反応は、家康のような従順か、浅井長政のように裏切り奇襲かの二択しかありません。だからこそ、信玄の言うとおり、信長は「天下一統」の理想に反して戦乱を広げているのです。直接、描かれることはほとんどありませんが、「どうする家康」における信長包囲網らしきものは、結局は信長が招いたものなのでしょう。自分で招いた反乱を鎮圧する…マッチポンプそのものですね。
こうした、劇中の何気ない、あるいは話者自身にはその自覚がない言葉が作品という大枠で別の意味を持ってくることは、ままあるので注意したいところです。
ともあれ、勃発しかけた夫婦喧嘩は、瀬名の「我らが心を一つにする時ぞ」で納められますが、この場面は岡崎城の不安そのものです。何故なら、家臣の前で不毛な夫婦喧嘩をする、それを自分たちで納められず瀬名に嗜められる、これが二人の日常茶飯事ということだからです。画面では今一つ分かりませんが、信康は17歳、五徳は15歳です。こうなってしまうのは、二人がまだまだ若く、上に立つには幼いからなのですが、事態は二人の成長を待ってくれません。
そのため、この夫婦喧嘩が、ギスギスした夫婦関係、それによる岡崎城全体の士気や団結を壊すおそれ、そして、その背景に信長の存在があることを暗示しています。
このことからも、前回、瀬名が「わたくしから見たらまだまだ」と岡崎城に留まる判断をしたことは納得するしかありません。この岡崎城の危機を乗り切るには、瀬名が陰ながら中心にならざるを得ないのです。かくして、第20回は、瀬名が主役の回となるのです。
3.政治に必要なものはなにか~優しさか恐怖か~
(1)家臣たちを心から気遣い、尽くす瀬名の真心と機転
既に武田の調略の中にある岡崎勢の戦いはことごとく失敗します。城内では負傷者で溢れかえっています。そうした中、彼らの血にまみれることも厭わず、治療のため奔走する瀬名の姿があります。素直な亀姫が初めて人の死を目の当たりにしながらも頑張ろうとする健気さも光りますね(というか、次回の伏線でしょう)。
そうした手当てする負傷兵の一人が山田八蔵です。その傷の酷さと手当のいい加減さから、瀬名は自ら薬を塗り、手ぬぐいを巻きます。奥方に手当てされることなど考えてもいなかった八蔵は「汚れます」と辞退を申し出ますが、「そなたらの血や汗ならば本望じゃ」と引きません。彼女もまた、自分たちが誰に生かされているのか、何に、誰に感謝すべきなのかを理解しているのですね。そして、それが上辺だけのものではなく、こうした必死の言動や公正な振る舞いとして表れるから、相手にその想いが伝わるのですね。傷ついた彼らに対して心から気遣い、慈しむ…前回、お万が述べた「おなごの戦い方」は確かに瀬名に託され、そしてそれが息づいていることも分かりますね。
この山田八蔵は謀反の一味ですが、結局、このことへの感謝の念が彼に翻意を思い止まらせます。通説では葛藤の末、忠義から大岡弥四郎の謀反を信康に伝えることになる八蔵ですが、「どうする家康」では、ホモソーシャルな男性同士の関係を象徴する「忠義」ではなく、瀬名の下々の者たちに対する「慈しみ」という徳によって思い止まります、この八蔵の行動は、前回のお万の「お方さまのような方なら」という台詞を巧く引き取っていて、政治において必要なものは恐怖ではなく、優しさや慈しみ、「徳」であることを改めて主張していますね。
因みに謀議に加わる仲間を裏切ることも、親身になってくれた瀬名を裏切る謀反もツラくて男泣きする八蔵が良いですね。女房衆は、その風貌から八蔵を邪険にしますが、瀬名は、そんな彼を目ざとく目にとめ、そのすすり泣きを聞きとめます。そうして彼に声をかけたことが、謀反を封じる機転へとつながります。瀬名は単に優しいだけではなく、常に家臣たちに目を配っています。これこそが奥向きに必要な能力でもあるのですね。
そんな彼女と対照的なのが五徳です。五徳は、皆が血汗にまみれて負傷兵の治療にあたる中、戸惑うようにポツンと部屋の奥に突っ立っています。このことから、五徳にとっても戦の悲惨な現実を目の当たりにするのが初めてであったことが窺えます。ですから、横を向いて、負傷兵を直視できずにいるのです。
周りに目を配る瀬名は、そんな五徳を見つけ「そなたに命じることが出来る者はおらぬ。」と自ら、手当をして動き、女房衆たちに手本を見せるよう促します。彼女が織田家の娘であること、岡崎城の奥を取り仕切る者をなること、それを最大限配慮しての叱咤であったことは容易に想像がつきます。
しかし、痛いところを突かれ、そして戦の現実に恐怖している自分を知られないため、彼女は思わず「このような汚い男どもに触れるなんてできません」と答えてしまいます。このとき、柱の影に隠れてうつむき加減に下に目を逸らしていることから、五徳が戦の現実に恐怖していることが分かります。一方で信長の娘としてのプライドもあり、逃げることもできない。だから、ポツンと立っていたのです。
ただ、この言葉は、家臣たちに生かされている主君側の人間として見過ごせるものではありません。ですから、流石の瀬名も「そなたのも三河のおなごであろう!」叱責します(八蔵の世話をした後ですから、その言葉には説得力がありますね)。それに対してもプライドの高い五徳は「信長の娘じゃ」と致命的な強がりで返してしまいます。
この期に及んで、役に立たない信長の威光にすがるしかないところに五徳の幼さと孤独があるのでしょう。そして、自ら瀬名たちに背を向けているので、更に始末が悪い。そして、こんなところからも、彼女と三河衆、徳川家との溝がより顕在化していきます。
ここに戦場から帰った信康が表れます。瀬名たちのただならぬ様子に何かあったかと訝しみますが、「何もない」と瀬名はその場を納めます。ここでも瀬名は五徳の立場と恐怖を尊重し、信康に心配かけまいと五徳を庇っています。しかし、叱責された五徳は、瀬名を恨むことしかしないでしょうから、その優しさが後々、仇になりそうなことは明白です…
(2)大岡弥四郎の弁明に込められた厭戦と信長への悪罵
謀反は無事、防がれ、大岡弥四郎たち一味は殺されたものを除き、全て捕らえられます。今回の場合、主犯が大岡弥四郎であったことが生きていますね。出陣に際しては、留守居を任され、岡崎城の増築に関しては彼がかなり知恵を出し、骨を折ったことが劇中で言及されています。つまり、彼は家臣団では知将の部類にあたり、それゆえに重用されていたのです。『徳川実紀』では、専横が過ぎた佞臣と書かれていますが、本作では留守居を滞りなく行えるようですからある程度、人望もあったと見て良いでしょう。そんな彼だからこそ、武田は調略の対象として目をつけたのでしょう。結果から言えば、他の家臣を言いくるめ、かつ彼らを謀反に加担させることが出来、また頭が回るからこそ今の信長に従属する家康の統治の先が見えてしまい不満を持つ、そういう人物こそ謀反を起こす人材だったということですね。
穴山が知恵が回るゆえに勝頼の欠点に気づいているかも、ということと少し似ていますし、また後年、家康から離反する石川数正も頭の回転の速さが仇になっていますね。ああ、そう言えば、浅井長政も信長の覇道の先が見えて滅びてしまいましたね。なんとも、頭が良すぎるのも考えもの…というのが「どうする家康」にはあるかもしれません。
話を戻しましょう。ある種の知恵者である弥四郎は、何故、謀反を起こしたかについて「ずっと戦をしておる。ずっとじゃ。織田信長にしっぽを振って我らに戦って死んでこいとずっと言い続けておる」と、厭戦気分を吐露し、現在の家康の統治に未来がないと述べています。「ずっと戦をしておる。ずっとじゃ。」、この言葉にハッとしたような反応をするのが瀬名です。瀬名は、それまでも「戦は嫌なんじゃ」「どうして戦はなくならぬのでしょう」と度々、言っています。惨い形で両親を失い、岡崎で生きていくしかなくなった経験から出たその想いは、彼女の心の底にずっと流れています。
思えば、三河一向一揆編のラスト家康ならこの世に「厭離穢土欣求浄土」という極楽を築けると「なんとなく」思うと言ったそのとき(第9回)から、彼がそれをなせるよう影日向で家康を支えようとしてきました。築山に庵を結んだこと(第10回)も、信康たちのために政治を学ぶことにしたこと(第15回)も全て、その想いです。終始一貫した言動をしてきた彼女の真摯さに、疲弊しきった弥四郎の吐露が響かないはずがありません。
同時に自分たち主君の側の努力がまだ足りず、家臣たちを苦労させていることへの自責の念(これは負傷兵への看病にも表れていますね)、また、彼らの疲弊した心を巧みに突く武田の謀略に対する憤りも起きたであろうことは、今回の終盤の流れから察するに余りあります。
さて、弥四郎のこの言葉に「お前らに忠義の心はないのか!」と平岩親吉が怒りを向けます。親吉は家康が幼いころから仕えてきた家臣ですから、そう言うのも分からないではないのですが…いやいや、その彼も三河一向一揆編では裏切るかどうか悩んでいたじゃないかとツッコミを入れるところです。それを知ってか知らずか、すかさず弥四郎は「くだらん!ご恩や忠義だの我らを死にに行かせるためのまやかしの言葉じゃ!終わりにしたいんじゃ…」と返します。この台詞は、山田八蔵が謀反を思い留まった理由が、瀬名から受けた慈しみであり、家康への忠誠心でなかったことと響き合っていますね。
第17回「真・三方ヶ原合戦」の記事などで度々、触れていますが、「どうする家康」では主君が家臣を選ぶのではありません。家臣が自分と家族らの生活と安心を保証してくれる主君を選ぶのです。家臣が主君のために命をかけるのは、自分たちが死んでも、この主君が生き延びれば、残った家族、家臣、領民の生活と安心を守ってくれる、そう信じるからです。ご恩、忠義という言葉は、その実益に添えられたものでしかない。だから、そう信じられなくなった時点で「まやかしの言葉」へと成り下がるのです。かつて平岩親吉が裏切ろうと考えたのも同じことです。
「終わりにしたいんじゃ…」との言葉に心底、疲れ切った弥四郎の本音が込められており、瀬名の表情を暗くします。
そして、家康が「信長にくっついている」限り「無間地獄」(終わらない地獄)だと判断した弥四郎は、そこから開放されるためだけに、今よりもマシかもしれない武田へ寝返ります。
この弥四郎への密書を届けた望月千代女が密書を押さえるものとして石ではなく、干し柿が使われたのは意味深です。金平糖の一件を見ても分かるとおり砂糖は貴重品です。因みに日本における砂糖の国産化は17世紀以降。つまり、戦国時代において、干し柿は貴重な甘味源なのです。古くから宮中でも栽培され、信長もルイス・フロイスに岐阜の名産(堂上蜂屋柿ですかね?)として与えています(フロイスはイチジクのドライフルーツと勘違いしたようですが)。
となると、密約の内容は分からずとも、それが武田の甘言と端的に示しています。だから、家康の元で戦を繰り返し、苦渋を舐めた弥四郎が、それを口にするのはとても印象的ですね。彼はそれを口にするしかないほど追い込まれていたのです。
弥四郎は、「どうせ終わらぬなら」、「せめて最後に」現状から解放され好き放題したいと言い、牢内の賛同を得て、これこそが三河の民の声だと信康に突き付けます。この破れかぶれの態度から、弥四郎には、例え謀反が成功してもその先は武田方の最前線に立たされて死んでいく末路も見えてことが察せられます。頭の良さから信長の支配の結果が見えた弥四郎ですから。
しかし、心身の疲れからくる破れかぶれのクーデターは、ひたすらに日々を生きることに必死な領民の支持を得られるはずはありません。彼らが望むのは、日々を少しでも豊かに生きることですから。したがって、民の代弁を嘯いた弥四郎が、その民たちに鋸引きにされるという史料に書かれた末路もまた当然でしょう。
さて、大岡弥四郎の弁明で繰り返されたのは、戦が終わらない理由は信長にあるということです。頭の良い大岡弥四郎は、今の過酷な現状の原因を信長と見ていました。彼もまた浅井長政が恐れ、信玄がいたずらに戦乱を起こすと言ったように、信長の天下一統が目指す弱肉強食の論理による過酷なものでしかないことを看破しています。
そして、それを聞いていた五徳が、槍の石突で弥四郎のみぞおちに一撃、黙らせます。そして、五徳は、この一件を全て信長に報告することを信康らに告げ、「この上なく惨いやり方でなあ」と謀反人らへ厳しい処断を下すよう促します。城内の負傷兵に対して「このような汚い男ども~」と思わず言ってしまったのは、信長の娘というプライドと戦の真実を目の当たりにした恐怖心との葛藤でした。しかし、それが弥四郎の裏切りによって、完全に三河武士への不信と侮蔑へ移行したのが、五徳の表情から読み取れます。演じる久保史緒里さんが表情の違いをきちんと演じたおかげで、最後のこの顔は怪演と言える芝居になりましたね。
この五徳の言う苛烈な処断こそが、「兄は裏切者を決して許しませぬ」(第14回)のお市の台詞そのものであり、家康が判断を間違えないよう恐れ慎重になった理由です。二度と誰も裏切らないよう徹底的に処分する。こうした信長のやり方が、不信に支えられた孤独感と小心の結果であることは、以前の記事で指摘したとおりです。そして、それは信長の天下一統が、彼の信用を得るために成果を上げ続けなければならない過酷さを要求していることも意味しています。
先にも触れたとおり、大岡弥四郎は領民らによる鋸引き刑、そして妻子は磔(はりつけ)という極刑が与えられます(凄惨なせいか描かれませんでしたが)。そして、徳川家がその処断を下したのは、本作では五徳の信長への報告を恐れたためとなります。家康が「信長にくっついている」限り「無間地獄」という弥四郎の指摘の正しさが、図らずも証明されましたね。
因みに、「この上なく惨いやり方でなあ」と言った五徳ですが、三河衆への侮蔑と信長の物真似による浅はかな発言であり、その凄惨さを理解しての発言ではないと思われます。戦の惨さを城中で遠巻きに見たくらいしかない15歳という幼さが言わしめた台詞。その浅はかさが、後々の信長への讒言へとつながっていくよう思われます。そこまでの大事になることを理解できないワガママ娘のしでかしたことが悲劇を呼ぶとすれば哀しいことです。
また、弥四郎の言葉は、かつて家康を裏切りかけ、今なお戦う家臣団には理解できる面がありました。呆然とし激昂する信康の方を優しく、それでいてがっしり掴んで止めている忠勝の表情にも、その複雑さが表れています。しかし、17歳の若き信康にとっては、受け入れられるものではありません。忠臣と信じた家臣らに裏切られ、父を罵倒され、家臣らの本音を聞き、妻は信長への告げ口を宣告します。岡崎城の混乱の体は、信康の心理状態そのものです。
ただ、「戦の真実に恐怖し、家臣の裏切りに動揺する」と言うのは、家康&瀬名も体験したのですよね。彼らには援軍すらなく、家康もその弱さから引きこもりもしましたが、それでも自力で解決する強さがありました。
それだけに、援軍もいて、周りも揃っていながら、信康と五徳には幼さと弱さが垣間見え、それゆえの危うさが印象に残りますね。初陣でここまで深く傷つけられた信康がどうなるか、また五徳のとの関係はどうなるか…不穏な空気は立ち込めるばかりです。
(3)虎松の願いと瀬名の戦いに見る主君に必要な要素
さて、岡崎のクーデターを鎮めた家康は、その功のあった虎松を呼び寄せ、何故、恨んでいたはずの家康個人に仕える気になったのかを問い正します。この際、「わしは武田に負けっぱなしじゃ。民はわしをバカにしておるらしい」と自虐的ですが、正直に言うのが彼の良さです。つまり、自身の弱さを他人(この場合、遠江の民)にも隠さない。以前にも触れたことですが、これこそ孤独で小心な信長、信玄にはない家康の美徳です。
それゆえ、虎松は「だからこそ」と応じます。民の苦しみばかり見てきた虎松は、領主のことを笑って語らせる、つまり恐怖で支配しない家康に希望を見出します。「民を恐れさせるより、民を笑顔にさせる殿様のが、ずっといい。きっとみんな幸せに違いない」との台詞は、家康の魅力の全てを語っていると言えますね。
前回の記事で、虎松について「自分を許し、民がバカにするのも放ってある懐の深い家康が生き残ったことの意味を考え始めていますね。家康の懐の深さこそ、家康が瀬名のもとに預けてある弱さと優しさです。」と読み解きましたが、これはそのとおりだったようです。そして、虎松は「殿にこの国を守っていただきたい」と遠江の民を代表して願います。
繰り返しますが、家臣が主君のために命を張るのは、安心した生活を保証してもらうためです。「戦に行かせるだけの忠義などくだらん」と言った弥四郎の罵倒も「民の笑顔のため遠江を守ってほしい」という虎松の願いも、その根っこは同じなのですね。虎松と弥四郎の言葉は、ささやかに響き合い、家康の行くべき道を照らしています。その道は、瀬名が謀反を未然に防いだ慈しみの心と重なります。
こうして遠江の民の心を得たことを確信した家康は「勝頼を叩きにいく!」と虎松に力強く宣言します。家康は、やはり揺れていますね。心のどこかで徳こそが主君に必要な要素だと分かっている。でも、それだけでは現実を勝ち抜けない…そこが、どうする家康なのでしょう。
しかし、虎松、「武田では出世できそうにないから」と打算的な茶目っ気を見せ、血筋の良さを宣伝し、自分を「おいら」呼びして愛嬌も売り、なかなか自己PRに長けた子ですよね。まったく「変ちくりんばかり」の一員に相応しい逸材です(笑)そんな彼も来週には、万千代に名が改まるでしょうか。楽しみですね。
さて、揺れる家康とは真逆に、自身が持つ慈しみの力で、この大事に当たることを決意するのが瀬名です。彼女は山田八蔵を使い、この謀反を唆した黒幕である武田の間者、歩き巫女の望月千代女を築山に呼び出します。
因みに歩き巫女と築山殿とのつながりは『岡崎東泉記』などに残っています。そして、千代が巫女であることは別の史料に残っています。その千代を後世の研究者が間者かもしれないと言い出し、「千代=くノ一」の俗説が広まりました。この俗説と『岡崎東泉記』と逸話を組み合わせたのが、今回の瀬名と望月千代女との対面です。
秘かに、内通につながりそうなこの件が到来しないことを願っていました(以前の記事でも何回か書いていますね)が、まさか自ら呼び出し対決しようとは…いや、ここは、人の好い瀬名が巻き込まれるという危惧自体が浅はかだったと認めましょう(笑)
今川家の姫の頃とは違い、数々の苦難を乗り越えた今の瀬名は、そんな弱い人間ではありません。三河一向一揆編以降、瀬名は三河の「家」を守る(=領民や家臣を守る)と決意は固く、また言動においても常に相手を立て、相手の意を汲み、そして良心に恥じない最善の方法を模索してきました。その忍耐強さと真摯さの裏側にあるのは、彼女の芯の強さとお万たちが願いを託すほどの揺るがない優しさと慈しみです。そのブレなさは揺れ続ける家康とは対照的な強さと言って良いでしょう。
だからこそ、「家臣に手を出されるくらいなら、私がお相手をしようと思って」と述べるのです。彼女の優しさは、攻撃に転じる際に静かな怒りと強い自負が伴うのが良いですね。今、岡崎城にいる面々で、この対決は、瀬名にしかできないことも理解できます。数正でもダメなのです。ここまで組み立ててきた演出陣と有村架純さんの確かな芝居の積み上げが生きてきます。
そして、単に優しいだけの甘い人ではないことが、ここで明かされます。いけしゃあしゃあとやってきてお為ごかしを言う千代に対し、「久しぶりですね、お千代さん」と先制攻撃をかけます。瀬名は、10年前、本證寺で一度会ったきりの彼女を覚えていたのです(たぶん、家康は覚えていないでしょう)。瀬名は本證寺を「あんなにいいところ」とまで言い、民たちと共に躍った人ですから余程に当時が印象的だったのでしょうが、彼女が築山で多くの民の声に耳を傾けてきましたことも大きいでしょう。それは、瀬名には、人の話に耳を傾ける聞く力と注意深い観察力があることを証明していますね。
更に弥四郎たちの心身の疲労困憊を攻めた策であることを知って、「こたびも、あなたではないかと思っておりました」と追撃を加えます。家康も知らず、家臣団も我がことの問題として近視眼的に見ており、策を講じて扇動した正信すらも気づかなかった黒幕に、瀬名だけが気づいた。
このことは、瀬名が、10年もの間、ずっと本当に領民や家臣のことに心を砕き、考え続け、政治を勉強し続け、自分が何をすべきかを模索してきた、人知れず重ねたその苦労を想像させます。その一つとして、三河一向一揆の原因も考え続け、答えも得ていたのですね。こういう中で、瀬名の洞察力は磨かれていったのでしょう。
だとすれば、今回、瀬名が八蔵のわずかな異変に気づき、機転を利かせてクーデターを防いだのは偶然ではなく、必然であったと言えるでしょう。見事、彼女は千代の策を打ち砕いたのです。
だからこそ、それを武器に牽制をしかけ、更に「お友達になりましょう」と懐柔策まで示せるのです。恐るべき交渉術…信玄と密約を結んだ家康の狼狽を考えると連れていくべきは瀬名だったかもしれません(笑)
「どうする家康」では、男性たちの戦場での活躍は比較的控えめですが、それでも瀬名たち女性の苦労は後ろへ行ってしまいます。しかし、女性たちにも多くの戦いがあった。その当り前を瀬名は見せてくれます。とはいえ、ここまで真摯であったとすれば、脱帽する以外にありません…というか、お万が期待したとおり、彼女こそが主君の資格を持つ者だったという他ありません。
そして、「どうする家康」の世界が男性ホモソーシャルな社会である以上、それこそが、彼女の悲劇の始まりなのでしょうね。更に言えば、この戦いは、男たちの誰も知らない秘かで孤独な戦いです。この点も悲劇に拍車をかけそうですね。
というわけで、この件がどういう結果になるにせよ、彼女の死へとつながることは否定できません。しかし、少なくとも彼女は、事件に巻き込まれたのではなく、徳川家を守るための彼女自身の全てをかけた能動的な選択であったことは重要でしょう。彼女は悲劇的な死を迎えることになるかもしれませんが、広次同様、その人生を、燃え尽きるそのときまで全うしそうです。視聴者はただただ、彼女を応援し、見守るしかなさそうです。
おわりに
「どうする家康」における大岡弥四郎事件は、信長の天下一統の裏側にある独善と過酷さと歪さを大岡弥四郎に言わせ、それを五徳に聞かせ、そして徳川家を分断に導いていくという構成で描かれています(毎熊克哉さんは美味しい役を演じましたね)。そして、その脚本の狙いが勝頼の策とも重なるという点が秀逸ですね。
そして、弥四郎が述べた「戦が終わらない」哀しみは、瀬名に武田と直接戦う決意をさせます。つまり、弥四郎の吐露が、瀬名に歩き巫女との対決という静かな決意を促すのです。これが、「大岡弥四郎に唆されて武田に内通した」という逸話の真実ということになります。言い換えるなら、瀬名の「家臣や領民を守りたい」という強い信念と彼女の持つ優しさと慈しみ、そして政治的な才覚を、通説を翻案する中から浮かび上がらせたということですね。
脚本が、序盤からこの出会いに至るまで入念に描いていたであろうことは、度々、挿入された瀬名が主人公の回にもよく表れています。
そして、もう一点、注目しておかねばならないのは、そんな瀬名のあり方の対比として置かれているのが、武田家や信長に代表される男性的なマッチョイムズです。特にホモソーシャルな社会を指向する織田家において、瀬名のような能力が高く、それでいてその政治的本質が真逆の女性は、武田家以上の敵としかなり得ません。具体的にそれが描かれるかどうかは分かりませんが、信長がそれを知れば排除するでしょうね。
家康はいよいよ信長か瀬名か、武断か徳治か、そうした選択をせざるを得なくなってきました。その歯車を瀬名、自らが動かしたのが第20回です。勿論、この選択がその最後ではありません。虎松とのやり取りにあるように、家康の中に徳治という答えはあるのです。ただ、そこへたどり着くには紆余曲折が待っているのですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
