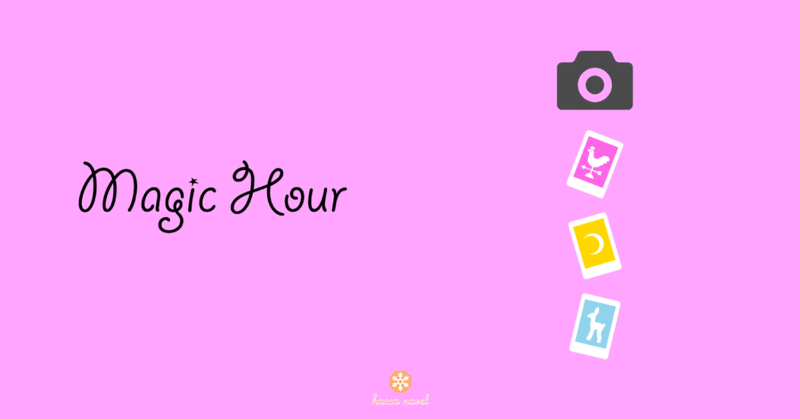
【中編小説】 マジックアワー vol.2
そうそう、わたし、さっきからヒーコって呼ばれているけれど、本名は高階柊(たかしなひいらぎ)。たからぎ、から始まって、らぎ、とか、ひぃ、とか呼ばれていたけれど、最近はヒーコに落ち着いている。文月とクラスも一緒の高校2年生。今年の冬で17 歳、写真部に所属している。高校の写真の活動だと「写真インターハイ」という大会があるのだけれど、わたしは今年入部したばかりなので、作品は提出されなかった。3年生の先輩の写真が選考会に提出されていたのだけれど、残念ながら予選で敗退してしまった。ブロック審査にも進めなかったのはずいぶん久しぶりのことだったらしい。
わたしの写真も選んで欲しかったけれど、技術的に足りないのと、わたしの写真へのアプローチが根本的に違うために採用されなかった。
応募する写真は撮って出しのものとなる。撮って出しというのは、現像ソフトを使わずに、カメラで写したそのままの写真のこと。わたしみたいに色をいじったりするのはNGなんだ。でもわたしはデザイナーのお兄ちゃんの影響で、写真の絵作りの方が楽しいと思っている。海外だとそういうアプローチの方が多いと思う。
フォトグラフィーを日本では真を写すという写真と訳しているんだけれど、それはあんまり正確じゃない。本来の意味は、『光で描かれたもの』という意味で、絵画に対して光画とも呼ばれる。お互いに近いジャンルの芸術と考えられていて、それで、海外の写真は大胆な色付けをする。やりすぎなのもたくさんあるけれど、わたしはそちらの方が好きだからそれにならうことにしているんだ。
とはいえ、写真インターハイでは写真の現像の腕は問われない。それよりも、もっと基本的な、構図の組み立て方、空間認識能力、めまぐるしく変化するシチュエーションへの対応力、撮影時のコミュニケーション能力、そういうものが試される。それらを駆使して、限られた場所と時間の中で、ぐっとくる、いわゆるエモい写真を撮らなくちゃならない。だから、そのための勉強も必要なんだけれど。
ほどなくわたしたちは、メイドさん? に案内されて、奥の部屋に向かう。その間の廊下にはたくさんの絵画が飾ってあった。蝶々や蛾が描かれているものが多かった。
「失礼しまーす」
その部屋でマダムは肘掛け椅子に腰掛け、すでに準備は万端だった。カワセミのような青い色のドレスを身に纏ったマダムは、まるでどこかの国の女王さまのようだった。マリー・アントワネットが着ていたドレスと言われても大げさじゃないくらい。
「さあ、思う存分撮ってちょうだい」
わたしはポートレート撮影などしたことがないので躊躇した。でも、いつもお世話になっているし、お茶もご馳走になったし、と心を奮い立たせて、何枚も写真を撮った。
ポートレートに適切な露出とかよく分からなかったから、とにかく枚数を撮影することにした。
「マダム、三脚はありますか?」
マダムは、メイドさんにうなずいてうながす。しばらくすると、カメラが乗ったままの三脚が運ばれてきた。それは中判のフィルムカメラで、ほんとはこちらで撮った方が綺麗な仕上がりになるのだろうけれど、と思いながら、自分のカメラに付け替える。わたしのフルサイズのミラーレスカメラは、随分と華奢で、鉄の三脚にはミスマッチだった。それでも自由雲台が付いていたので、縦位置の写真も問題なく撮影することができた。
撮影はそんなに時間がかからなかった。それは、マダムが柔らかい微笑みを湛えたまま、身じろぎひとつしなかったからだ。
わたしは絞りの値をF8からF16の間で撮影した。もちろん瞳オートフォーカス機能にも頼った。そうすれば、ピントを外すことはまずない。ホワイトバランスは電球色にセットした。マダムのお屋敷に蛍光灯はなく、どの部屋も白熱球が灯されている。ストロボもなく、電球色で柔らかな明るさの部屋ではシャッタースピードが遅くなる。それでもノイズを減らすため、わたしはISOを100に設定する。
シャッターの、カッ………シャン、と長く落ちる間も、マダムは1ミリも動かなかった。
「マダム、すごいです。動きがなくて時間が止まっているみたい。これなら、感度を高くしなくても撮影できます」
「昔は肖像画のモデルも務めたのよ。そのくらいなんてことはないわ」
撮影が終わり、画面を見せる。しかしそこに写っているのは、とても暗い写真。
「今は真っ暗に見えますが、必ず素敵な写真に仕上げます。約束します。そのドレスの色、目に焼き付けました。マダムのお肌の色と合わせて、それを綺麗に丁寧に仕上げるまでがフォトグラファーの仕事です」
わたしは、うまく仕上げられる自信があった。だから、何より肉眼で見たマダムの凛とした美しさを覚えておくことが大事だと思った。
帰り際マダムは、もう一度庭へ出るようにとわたしたちに言った。玄関にくると、ソックスが一揃えずつ置いてあった。レースがふんだんにあしらわれた、すごくロマンチックなソックス。躊躇していると、メイドさんが、
「その靴下は差し上げますから遠慮なくお履きになって」
と言ってくれる。わたしたちはそのソックスを履く。とても履き心地がいい。そしてローファーは汚れる前よりもピカピカに磨き上げられていた。わたしたちは、それらを履いて外に出る。暗がりから花たちが発する匂いが漂ってくる。
「そろそろやってくるはずだけれど」
マダムは空を見上げている。あたりはすでに真っ暗で、星々も瞬き始めている。
「あ、来た!」
マダムの弾むような声にわたしはびっくりする。指をさしたその先には、バサバサと何かが飛んでいる。
「きゃ」
と、おののくように文月が声を上げる。
わたしはその羽ばたきを凝視する。それはとても美しい翅の蛾だった。ドレスを着たマダムが姿を変えたのじゃないかと思うくらいそれは美しかった。カメラを構えたけれど、マダムと蛾の目配せを邪魔したくなくて、シャッターを切ることができなかった。
「いいのよ。撮りなさい。あなたは写真を撮る人なんだから」
わたしは、オートフォーカスでその美しい蛾を撮影する。そして、子どものような笑顔のマダムの横顔も何枚も何枚も撮影した。
***
「お、オオミズアオ。よくこんなの撮れたな」
わたしは、その日の夜、さっそく撮影した写真を自分のタブレットで現像する。RAWで撮った写真はそのまま出力するととても眠い写真になってしまう。眠い写真というのは、メリハリがなくてのっぺりした写真のこと。そこで、現像という作業が必要になるわけ。タブレットの中には現像用のアプリがインストールされているから、わたしはそれを使って明るさや色の補正をする。スライダーを動かして暗い部分を持ち上げると、隠されていた本来の色が蘇ってくる。
「この蛾、オオミズアオっていうんだ。すっごい綺麗だね」
写真を覗きに来たお兄ちゃん。
「綺麗だけど、ちょっと怖いよな。結構でかいんだろ」
「うん」
そう言って、わたしはマダムとオオミズアオが一緒に写っている写真までスクロールする。
「うわ、でか!」
オオミズアオの写真をズームする。多くの写真はブレていたけれど、何枚かはピントがしっかりと合っている、すごくよい写真が撮れた。
「解像感がハンパないな。これ、マクロレンズで撮ったのか?」
「そう。分かる?」
「分かる分かる。さすがカミソリマクロって言われるだけあるよな」
写真の解像感っていうのは、どう説明したらいいだろう。セピアとカラー、というのはちょっと違うな。解像感の高いセピアの写真もあるもんな。そうだ! 時代でいえば昭和と令和くらいの違いかな。ほら、昭和のものって、カラーなのにすっごく懐かしい色合いというか風合いがあるでしょ。生まれてもいないのに、そういう風に感じちゃう。使い切りカメラで撮ると、そういう写真ができるよね。フィルムのカメラで撮られる写真は、そういう柔らかい感じがある。それに対して、今のカメラはレンズの性能もよくなって、カリカリに撮れるって表現したりするんだけれど、自分の目で見た以上のものがその写真には写されている。そういう驚くようなきめ細やかさが解像感と呼ばれるものの正体のような気がする。
マクロレンズで撮影したオオミズアオは、木の葉のアンテナみたいな触角の一本一本まで撮影できている。マダムの目元のシワのスジまでもしっかり写っているけれど。でも、そのシワの陰影がなんともいえず美しくて、わたしは、ほっと溜息をつく。
そしていよいよマダムの肖像画の現像に取り掛かる。
こちらも数十枚あるけれど、レンズの開放値による明るさ以外は、ほとんど変わりのない写真が撮れている。パンフォーカスされているので、背景の壁や少し写り込んだカーテンもしっかり解像されている。
現像ソフトの中には、プリセットといって、あらかじめ数値の設定されたフィルターが用意されている。フィルグラのフィルター効果と似たようなもの。でも今回は、それを使わず、なるべく撮影時に近い、わたしのまぶたの裏側に焼き付けたあのヒスイ色とマダムの肌の白さを表現しようと思っている。
「柊はポートレートも撮るようになったんだ」
「うん。今度お兄ちゃん撮ってあげようか」
「お、いいぞ。ばっちりスーツで決めてやる」
「えー。お兄ちゃん、スーツ着ると、なんかチャラくなるから嫌だな。普段のボーダーTとかの方がいいよ」
「オレ、チャラいか……?」
「うん。チャラいね」
心なしか、お兄ちゃんがとぼとぼとリビングを出ていったのは気のせいだろうか。
ともかくわたしは、しっかりとこのポートレートを仕上げなくては。仕上がったら、お兄ちゃんの部屋(仕事場だ)にあるA3ノビまでプリントできるプリンターで、印刷しよう。
「あ、待てよ」
わたしは、時々お世話になっている写真屋さんの存在を思い出した。あそこなら銀塩プリントという、写真の印画紙に薬品を使った焼き込みをしてもらえるはずだ。インクジェットのプリンターでも十分綺麗なんだけれど、なんか、写真を焼くという方が、マダムの好みかもしれない。時間が経っても退色が少ないはずだしそれがいいね。
そうと決まれば、現像したデータをjpgに書き出さないといけないな。USBメモリに入れて持っていけばいいから、お兄ちゃんにお願いして貸してもらおう。
マダムのポートレートの現像には一晩かかってしまった。寝落ちして、気がついたらカーテン越しの外の気配がほんのり明るい。
「やば……。お風呂入ってない」
時計を見るとまだ午前5時。今日は土曜日で、授業は午前中に終わる。学校にゆく前にデータを転送して、帰りに写真屋さんに寄ろう。
わたしは、勢いよくカーテンを開ける。外は予想に反してどんよりと曇っていて、雨がしとしとと降っている。
「梅雨入りするかなあ」
タブレットから、クラウドサーバーに写真をアップロードする。そのURLアドレスをお兄ちゃんにメールする。それをUSBメモリに保存してもらいたいということも付け加える。
「オーケー」
と返信がすぐに入る。あの人、また徹夜したな。お兄ちゃんとは10歳年が離れているのだけれど、いつでもやさしいお兄ちゃんがわたしは大好きだ。
お兄ちゃんは、前に働いていたデザイン事務所で体を壊し、なし崩し的にフリーのグラフィックデザイナーとして独立した。フリーランスって自由でかっこよさそうだけれど、大変な部分も多いみたい。とにかく体には気をつけてよ。
「サンキュー」
と絵文字入りのメールを送り、わたしはシャワーを浴びにお風呂に向かう。
さっぱりした気持ちで部屋に戻ると、そこにはもうUSBメモリが置かれていた。
また、サンキューとメールを入れる。返信は返ってこない。もう眠ったかな。土日くらいしっかり休んでよ。
学校への通学路の途中で文月と待ち合わせをする。今日は少し文月を待たせてしまった。
「ヒーコ、おはよう。昨日の写真、フィルグラにアップしてないじゃん。楽しみに待ってたのに」
「あー、ごめんごめん。寝落ちしちゃって」
そんな風にごまかしたけど、本当は知らない不特定多数の誰かに見せるよりも、マダムに最初に見せるのがいいんじゃないかなあと思ったのが理由だ。いいねをもらうのも楽しいけれど、見てもらうべき人に先に届ける方が大事かなあ。
「今日さあ、写真屋にゆくんだけど、文月、ヒマ?」
「もう、ずっとヒマ!」
わたしたちはそんな話をしながら教室に入る。自分の机に着いた時、その机に薄く影がかかる。そして、わたしの背後から声がかかる。
「まだ、あんたら映えー、とかやってんの?」
「……うわ。ヒーコ、またあとでね」
文月がそそくさと自分の席に着く。
「ま、ね。写真好きだし」
話しかけてきたのは、エミリー。華山英美里。ウチのクラスには、いわゆるスクールカーストというのはないけれど、ちょっと前の時代なら、エミリーは確実にヒエラルキーの頂点にいるであろうタイプだ。
「今は、動画じゃん! コックテイルやってないの?」
コックテイルっていうのは、今一番流行っているアプリかな。短い動画をスマホで撮影してすぐにアップできる。フィルグラの動画版みたいな感じ。もちろんいいねを集められる。
「わたし、動画向きじゃないんだよね」
「ハイ、ワンツースリー!」
いきなり掛け声をして、エミリーは踊りだす。片手にスマホを持って上下左右に大きく回す。わたしは笑顔を作ってそれを見つめる。
わたしたちの間には、エミリーが選曲したK-POPが流れている。
決めの笑顔。小刻みに手を振るエミリー。スマホを降ろすと、びっくりするくらい素の顔に戻ったエミリーが言う。
「今、アップしたから、ヒーコもいいねつけてね。よろしくー」
有無を言わさず、エミリーは去ってゆく。わたしは仕方なしに、スマートフォンのロックを外し、コックテイルの風見鶏のアイコンをタップする。一番上に今見たばかりのエミリーのダンスが載っている。口角を上げて、でもどこか無表情にエミリーが踊る。片手持ちだというのに、奥行きのあるダンスが撮れていて、へえ、すごい、とわたしは素直に感心する。そして、いいねする。
「いいね、いただきましたー!」
窓際の方から、声と笑い声があがる。わたしは、お愛想で手を振る。エミリーのグループのみんなも手を振り返す。決して仲が悪いわけじゃないんだけれど、その薄っぺらい氷のような関係を割らないように気を遣う。別にハブられたっていいけどさ、とも思うけれど、そうならないのなら、その方がいいだろうと思っている。ちょっと、胃が痛い。
<< マジックアワー vol.1 | マジックアワー vol.3 >>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

