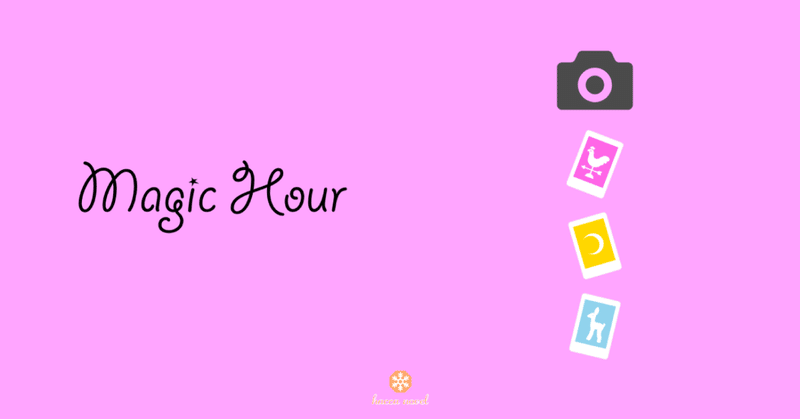
【中編小説】 マジックアワー vol.1
坂道の途中で振り向いたわたしは、わあ、と小さく叫び、慌ててカメラを構える。すばやくシャッターを切る。
激しい通り雨のあとの夕焼けの景色。そのグラデーションはまるで、グランデサイズのフラペチーノ。
むくむくとしたホイップの雲。青みが残る空はミントシロップ。横に伸びる太陽の光は雲にからまるマンゴーソース。そしてカップのほとんどを占めるショッキングピンクは甘酸っぱいラズベリーフラッペ。
ストローをさして吸い込んだら夢のような味がするんじゃない?
わたしは一心不乱にシャッターを切る。
シャッターを重ねるうちに、したたるようなラズベリーフラッペは、どんどん赤みをましてジャムのようになる。やがてカップからこぼれ出し、遠くに見える白いビルを飲み込み、真っ赤に染める。瞬く間に街は燃えるよう。なんだか世界の終わりみたいな風景に変わる。
その景色から目を離すことができず、わたしの指はジャムの赤い手につかまれてシャッターを切り続ける。
「ヒーコ! 何やってるの! はやくはやく! たっくさん蝶が飛んでる!」
背中に文月の声がかかる。その声で、ようやく赤い手からほどかれたわたしは、
「すぐゆく!」
大きく返事をし、振り返って坂道を駆け上がる。
わたしの視界に、古いけれど立派な洋館の屋根が飛び込んでくる。駆けるごとにそのお屋敷はぐんぐん大きくなる。
鉄柵の門をくぐり抜け、その洋館の敷地に足を踏み入れる。文月は庭の真ん中に立ち、はやくはやく、とわたしを呼んでいる。
そこで待っていたのは、息をのむような光景。何十匹、いや100匹以上の蝶が飛び交っている。逆光に次々と浮かび上がるシルエットは優雅なリズムで、クラシカルなダンスのよう。
わたしはこの瞬間を絶対に逃してはいけないと、力を込めてカメラのシャッターを切る。
目まぐるしく変わる構図に慌てながらもファインダーからは目を離さない。
耳元を蝶の羽ばたきが横切る。全身に鳥肌が立つ。うー、綺麗だけどこんなに近いと背中がざわざわする。それでもわたしは、このシチュエーションは奇跡だよ、逃してはダメ、と自分に言い聞かせ撮影に集中する。
連射モードにして、ISO感度はカメラ任せ、レンズを絞り込んで隅々までキレのある写真を目指す。
蝶は花に群がっている。他の花弁の蜜を吸おうとして、ばらばらと舞い上がる。その度にわたしはシャッターを切る。連射モードのまま、ISO感度を800に固定、レンズの絞り値を2.8まで開く。マクロレンズをつけてきて正解だった。花と蝶、めいっぱい寄れるところまで寄る。その時に今、ここで飛び交う蝶がクロアゲハだということに気づく。ファインダーの向こうで、もったりと翅を動かしながら、クロアゲハは蜜を吸っている。わたしはレンズをマニュアルフォーカスに切り替え、きりきりと微調整しながら、蝶の食事の風景をとらえる。ボケの効いた綺麗な写真になっているといいけれど。レンズを開放にしても暗くなってきた。ISOの感度をオートに戻してひたすら蝶を撮る。蜜を吸い上げる蝶のストローがくるりと仕舞われるその瞬間を秒間5コマで撮り続ける。
カメラは熱を上げる。
蝶はふわりと飛び立つ。
太陽の光がギラリとファインダー越しのわたしの目を射る、その瞬間、音もなくクロアゲハは散り散りに真っ赤に染まる空の高みへ舞いながら飛んでいってしまった。
「コウモリみたい」
文月がつぶやきながら見上げた光景を、わたしは、まだ夢中のまま撮り続けていた。
「はあ……。なんだかすごかったね」
わたしは黙ってうなずく。手に持ったカメラはまだ、じんじんと熱を帯びている。
カタン、と音がして窓が開く。人の動く気配。
「また勝手にわたくしの庭にあがりこんで。少しは礼儀をわきまえなさい」
放心しているわたしたちに窓の内側から声がかかる。叱責するような強い言葉。それなのにその声は、夏の日にこんこんと湧く冷たい水みたいに、耳に気持ちがいい。
「マダム、こんにちは。勝手に入り込んでごめんなさい! でも、」
「でももヘチマもありません。きちんとわたくしにあいさつをしてから入ってきなさい」
マダムが部屋の暗がりから姿を現わす。銀髪を後ろでひとつにまとめたマダムの表情は、言葉の強さと裏腹に少し笑みをたたえている。ゆったりとした着心地のよさそうなワンピースは、きっとオーダーメイドだろう。
「はい……。ごめんなさい」
わたしたちは、しゅんとしてうなだれる。マダムから笑うような息が漏れ、言葉をかけられる。
「それで、いい写真は撮れたのかしら?」
声のトーンが一段明るい。わたしは顔をあげ答える。
「ばっちり! ……だと思う。ちゃんと現像しないとなんとも言えないんだけれど」
「あら、あなた、フィルムカメラで撮影しているの?」
身を乗り出して聞くマダムに、わたしはなんて説明しよう、と考える。デジタルカメラで撮影しているんだけれど、RAWというファイル形式で撮影しているわたしは、デジタル処理の現像という作業をしないと思い通りの画にならない。それをうまく説明できるかな。
わたしは答える。
「いえ、デジタルなんですけれど、なんて言えばいいのかな。今、撮った状態だと、ほとんど構図を撮影したに過ぎないので、これからパソコンで色付けをしてあげないといけないんです」
「デジタルなのに、面倒なことだこと」
苦手なものを口に含んだようなマダムの表情。でも、これはとても大事なことなんだ。
「それがいいんです!」
張り切って答えるわたし。
「まあ、ともかく少しあがっていきなさい。そんな泥まみれであなた方を帰したら、わたくしの評判に傷がつきます」
マダムにそう言われてわたしたちは自分の足元を見た。ローファーは泥まみれ、白いソックスもほとんどグレーになっている。雨上がりの庭はわたしと文月の足跡でぐちゃぐちゃになっている。
「やっばい」
マダムはわたしたちの慌てぶりを気にもとめず、お屋敷の奥に入っていく。わたしたちは、どうしようかと顔を見合わせる。すると奥の方からマダムの声がかかる。
「玄関で靴下も脱ぎなさい。用意してあるスリッパを履いてあがってらっしゃい」
わたしたちは、言われるがまま、おずおずとお屋敷のエントランスにまわる。
「おじゃましまーす」
大きな玄関の扉は音を立てずに開いた。中に踏み込むといきなり大きなシャンデリアが目に入る。いつも玄関先でマダムを待つわたしたちが、このお屋敷の中に入るのははじめてのことだった。
「やば。このツボとか高そう」
「文月、きっとこのラグとかスリッパもいいものに違いないよ」
マダムの物腰から予想していたこととはいえ、外から眺めることしかしていないわたしたちは、お屋敷の中に別世界が広がっていることに圧倒される。この空間にはわたしの暮らしとはかけ離れた時間が流れている。
わたしたちは、サンルーフのある部屋に通される。いつも庭から見えている部屋だ。
そこにはすでにお茶の用意がされている。紅茶のいい香り。そういえば、蝶を撮るのに夢中だったから気に留めないでいたけれど、お庭も花の匂いでむせかえるようだった。
「さあ、おかけになって。紅茶とスコーンを用意しましたよ。ジャムとクリームをつけて召し上がれ」
こんな時間におやつを食べたら夜ご飯食べられなくなっちゃう、なんて思ったけれど、スコーンがあまりにも美味しそうだったので、
「いただきます!」
わたしたちは遠慮しないでいただくことにした。筒型のどっしりとした熱々のスコーンはお腹のところで割れている。そこから半分にして、まずは何もつけずに頬張る。
「お、おいしい……!」
しっとりした生地は口に含むと甘く広がる。ふんだんなバター、本場のスコーンというものを知らないけれど、間違いなくこういう食べごたえがあると思う!
今度はジャムを乗せる。あんずのジャムかな? とろっとしていて、スコーンに吸い付く。それをひとかじり。
「! うま!」
ほどよい酸味がとっても上品! 文月もたまらず、わあ、と声をあげる。
「ジャムだけじゃなく、クリームも。クロテッドクリームだからおいしいわよ」
マダムにうながされるままに、わたしはクリームをつけてスコーンをいただく。すうっと吸い込まれるように溶けてゆくクリーム。
「何これ、おいしい!」
濃厚なのにバターよりさっぱりしていて、ほのかに甘くて、スコーンとの相性はばっちりだ。ジャムの余韻とクリームの広がりを残したまま紅茶をひとくち飲めば、口の中はまるでメリーゴーラウンド。これって、現実にあるメルヘンだよ! そして、鼻に抜けてくる紅茶のその香りがかぐわしい。
うっとり夢見心地なわたしたちを見て、マダムは満足そうに微笑んでいる。マダムは口に添えていたティーカップをソーサーにおろすと、わたしに尋ねる。
「ねえ、あなた。さっきの写真は、パソコンで現像しないと見られないのかしら」
「あ、はい。綺麗な写真はパソコンで現像しないと見られないです。マダムはパソコンやスマホは持っていますか?」
「今は手元にないけれど、必要なら用意いたします」
「そのパソコンかスマホにアプリを入れてもらえたら、そこにアップした写真を見ることができます」
「アップ? なにか大きくするの?」
写真をアップロードすることの説明は少し難しいな。
「クラウドサーバーにアップしてっていうのは、雲の上に乗せる感じなのかな、うーん……」
「写真を雲に乗せる?」
マダムの疑問は、きっと雪だるま式に増えている。わたしはどう説明したらよいか分からなくなり、頭を抱える。あ、でも待てよ。カメラの画面で見せればいいんだ。
「マダム、今言ったことは忘れてください。まだ現像前で、画面は小さいけれど、ここで写真を見ることができます」
わたしは立ち上がり、マダムにカメラの液晶画面を見せる。連写をして撮っていたので、まるで動画のように、先ほどの場面が浮かび上がってくる。マダムは、ほお、と驚いたように息をつく。
「これでもまだ現像前なの。それなのにとてもよく撮れているわ。わたくしも、あんなに蝶が集まってきたのを見たのははじめてのこと。もしあなたが許してくださるなら、蝶がたくさん群がっている写真と、このクロアゲハのアップの写真、現像した後でいただくことはできないかしら」
「もちろん、喜んで! パソコンではなくて、実際の写真として、印画紙に焼いて持ってきます」
マダムはにっこりとほほ笑む。そのあと、少し小首をかしげ、なにか考えるそぶりのあと、わたしを見つめ、問いかける。
「それと、お願いがあるのだけれど。いいかしら」
神妙な視線を投げかけるマダムをいぶかりながらも、わたしは、いいですよ、と答える。
「今から、わたくしの肖像を撮影してはくれないかしら。撮影料はしっかりとお支払いします。よろしくお願いします」
深々と頭を下げるマダムに、わたしたちはびっくりして顔を見合わせる。わたしは、あんまり人物を撮影したことがないから、と断ろうと思った。でも、マダムの態度に何か切実なものを感じたので、
「分かりました」
とだけ答えた。
「では、お茶が済んだら、奥の部屋へいらしてちょうだい。あちらのものが案内します。わたくしは着替えに時間がかかりますので、ゆっくりお茶をお飲みになって。あと、ご家族に連絡はできるかしら。お夕飯には間に合うようにします」
わたしたちは、それぞれ自分のスマートフォンで家族に連絡を取る。少し遅くなる、マダムの家でお茶している、とメッセージを送った。
「このスコーン、マジでおいしいわ。あ、スマホで撮るの忘れた。フィルグラにアップしたかったぁ」
文月は悔しがりながらも、食べる手は止まらない。文月の言っているフィルグラというのは、フィルムグラムという写真を投稿するタイプのSNSで、綺麗な写真や可愛い写真には『いいね』のハートマークがたくさんつく。わたしもいちおうやってはいるけれど、なかなかいいねの数は多くならない。絶対、文月の写真よりもいい写真なのになんでだろ。
「ヒーコ、こういう食べ物の写真とかをアップすればいいんだよ。そうしたら、映えーとか言われて、いいねがいっぱいつくよ。あと、タグね」
「タグ?」
「そうハッシュタグ。その付け方がヒーコ甘いんだよ。みんなに拾ってもらえるように、たくさんつけなきゃ。英語でも」
「ふうん」
タグ付けかあ。今度ちゃんとやってみよう。いいねの数は多くても20個くらいしかつかないわたしだけど、やっぱりフィルグラでバズってみたい。通知が止まらないっていうのはどんな気持ちなんだろ。そこまでいかなくても、せめて周りの友達並みにはいいね、もらいたいなあ。
クラスメイトの間でもフィルグラは流行っていて、みんなだいたいスマホで撮った写真をアップしている。その点、わたしは写真ガチ勢なので、フルサイズのミラーレスカメラを使っている。といってもこれはデザイナーをやっているお兄ちゃんのおさがりなんだ。レンズ交換式の本格的な一眼カメラで、わたしは2本のレンズを持っている。どちらも単焦点のレンズ。単焦点ていうのは、ズームすることができないから自分の足で動いて画角、写真の写る範囲を決めなくちゃならない。でもその方が写真が上手くなるってお兄ちゃんに教わった。1本は50mmの単焦点をお兄ちゃんからゆずってもらった。50mmっていうのは、人間の視野に近い焦点距離だから、標準レンズと呼ばれている。もう1本はどうしても花の写真を撮りたくて、マクロレンズを自分の誕生日プレゼントに買ってもらった。いや、誕生日まで待ちきれなくて(だってまだ8ヶ月も先だったから)誕生日の前借り、というのをしてしまった。マクロレンズは、小さな被写体をクローズアップして撮影することができるレンズのこと。花や昆虫を撮影する人には必須のレンズだ。そしてこのレンズ、6万円もしたから一生ものだって思ってる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

