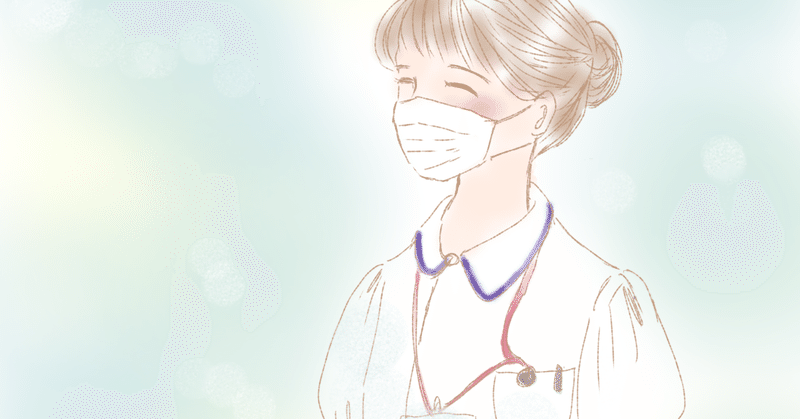
長編連載小説 Huggers(12)
永野はある不思議な現象について裕子に語る。
裕子(2・続き)
「そういう時期?」
「外側に広がっていく時期です。何事にもリズムがあります。宇宙も地球も人間も、うちのような組織も、収縮と拡散を繰り返しています。今まではどちらかというと守られた空間で内面を充実させてきました。そろそろバランスをとるために外に開いていくことが必要なのかもしれません」
「私がしたことは違反ではないでしょうか?」
「西野さん。実はあなたに起こったことはすでに欧米の一部のハガーに起こっていることと一致します」
「そうなんですか?」
驚いて思わず大きな声になった。永野はうなずく。
「あえてあなたたちにお知らせしなかったのは、こうしたことが自然発生的に起こるのかどうか確かめたかったからです。何かにとりつかれたように、とおっしゃいましたよね。自分で自分の言動をコントロールできなかったと」
「はい」
「すでにおなじような例が数十件、報告されています。いずれも、セッションを受けるためにやってきたのではない、通りすがりの人や、知り合ったばかりの人に突発的にハグを行っています。もうひとつ共通している点は――」
永野は言葉を切り、少し上目遣いに裕子を見た。
「西野さんは、後悔してます?」
「後悔?」
裕子は永野の真意をはかりかね、困惑した表情になった。
「沢渡さんをハグしたこと。間違ったことだったという感覚がありますか? しないほうがよかったと」
「それは……」
唐突に、沢渡の上着のすぐ下に触れたごつごつした脊柱の感触や、柑橘系の整髪料の匂いが混じった香りが記憶によみがえり、苦しくなる。
「いいえ」きっぱりと言った。
「後悔はしていません。あれでよかったのだという確信があります」
「それはどうしてですか?」
目をそらさずに永野がたずねる。
「最初はとても動揺しました。取り返しがつかないことをしたと思いました。でもあれから何度思い返してみても、ほかにどうしようもなかったのだという気がするんです。あれが唯一自分が取るべき行動だったと。あのとき――」
裕子は口ごもる。
「うまく説明できません。ですが、悲しみを感じたんです。それが沢渡さんのものなのか、それともほかの誰かのものなのかわかりません。すさまじいほどの深い悲しみでした。ハグせずにはいられなかったんです。手続きとか、予約とかそんなものと無縁なところで、ただハグの必要性を感じました」
顔の下半分が緊張でふるえ、うまくしゃべれない。
「恐がらないでください。それでいいんです」
「え?」
「欧米の経験者もみなそう言っています。なぜそうしたのかはわからないけれど、後悔はしていない。自分のしたことは間違っていなかったという確信がある、と」
「そうなんですか」
少しだけほっとして、裕子は深く息を吐き出した。
「それで本部としては、この件に関してはどんな方針なんでしょう」
永野は視線をテーブルの上に組み合わせた自分の手に落とした。
「今はまだ情報収集の段階で、特に方針などは決まっていないようです。実は、これは内密にしてほしいんですが、本部の中で内部分裂が起きかけていて、それどころではないらしいのです。……なので、私たち日本支部では独自の路線を行こうと考えています」
「独自の路線って?」
「思い切って、外へ開いていこうと思うのです。まずは雑誌に広告を出します。今までのようにつてをたどってきた人たちだけでなく、興味のある人は誰でもセッションを受けられるようにしたいのです」
「誰でも?」用心深く、裕子は言った。
「もちろん、安全面には十分留意します。こちらでできる限りの選別をして、ハガーが危ない目にあうようなことだけはないように。同性のセッション希望者のみという条件もそのままで結構です。ただ今までよりはずっとリスクが高くなることは覚悟しなくてはなりません。マスメディアにも露出するかもしれないし、ネットでの批判や中傷もあるかもしれません」
「やめたい、という人も出てくるでしょうね」
「実は、ハガー候補生の公募もしようと考えているんです」
「公募ですか」
「はい。今はボストンの代表が、各地のハガーや情報担当者が推薦した候補者を選別しているわけですが、そのやり方は非常に手間も時間もかかります。かつての西野さんのように、自分の力をまだ自覚していない潜在的なハガーはきっとたくさんいるはずです。その人たちがみなさんあなたのように偶然発見されるとは限りません。そういう人たちを効率よく集めることができたら、もっとずっと早く、みんなが幸せになるはずです」
裕子は永野を見た。「効率よく」「みんなが幸せになる」と言った永野の言葉に何ともいえない違和感を感じた。何かが間違っているような気がしたが、その言葉の何がどう間違っているのか分からなかった。永野の目は輝いていて、少し熱っぽく見えた。
「でも日本支部だけが勝手にそんなことして、いいんでしょうか?」
「大丈夫です。今や世界をとりまく動きは加速しています。あちこちで政治的な反乱が起こり、今までの体制が次々に崩壊している。地震や津波、噴火なども頻繁です。『それ』がさらなる加速を望んでいるに違いありません」
「『それ』って?」
裕子が口をはさむと、永野はハッとしたように口をつぐみ、そしてごまかすように笑った。
「今日はなんだか僕、しゃべりすぎているみたいです。西野さんはやっぱりどこか、包み込むような優しいエネルギーをお持ちですね。あなたのそばにいるとつい安心して、余計なことまで口にしてしまいます」
「そんな」気恥ずかしくなって、裕子は意味もなく背筋を伸ばして座り直した。
「まあとにかく、西野さんは余計な心配をせず、今までどおりセッションを続けてください。何か心配なことがあれば、小倉君を通してでも、今回のように直接私に言っていただいても結構ですからそのままにしないで相談してください。一人で抱え込まないでくださいね」
「わかりました」裕子はうなずいた。
永野は腕時計にちらっと目をやって言った。
「ではいつもの確認事項を」
「どうぞ」
「ご家族とは頻繁に連絡されていらっしゃいますか?」「ペットは飼われていませんか?」「特定のパートナーはいらっしゃいますか?」ときかれ、いずれの質問にも「いいえ」と答えた。
これはハガーになってから何度か繰り返された問答で、その全部の条件を満たさなければセッションを続けることはできないのだと聞かされた。どうしてかとたずねても、幹部にさえ理由はわからないらしい。もし嘘をついたらどうなるのかと思ったが、今のところ裕子には嘘をつく必要がない。
これから成田に向かうという永野を玄関まで見送った。永野に靴べらを渡したとたん、急にひとつ聞き忘れていたことを思い出した。
「あの、沢渡さんのことなんですけど」
「ええ」
「ほっといていいんでしょうか」
永野はしばらく靴べらを手にして考えていた。それから思い出したようにゆっくりと靴をはき、靴べらを裕子に返しながら言った。
「モニタリングしましょうか」
「何かそういう機械があるんですか?」
とたずねると、永野は楽しそうに口をあけて笑った。
「そんなハイテク機器はうちにはないです。もっと原始的な方法ですよ――まあとにかく、沢渡さんのことは僕たちにまかせてください」
夜勤の若い女性医師は裕子の顔を見ると「あ、よかった。今日は西野さんなんだ。助かる」とうれしそうな顔をしたので、「はい先生、まかせてください」と胸に手を当てて笑ってみせた。その医師はごく最近育児休暇から復帰したばかりで、夜勤のシフトにはまだ数回しか入っていない。
裕子が夜勤の日には急患、急変が少ないという噂があるのは知っていたし、それがある程度事実であるのもわかっていた。だがどうしてそうなるのかは自分でもよくわからず、単なる偶然ではないかという気もする。ハガーには人の心に働きかける力はあっても、肉体的な苦痛を取り除く力はないはずだ。
日勤スタッフからの申し送り事項を頭の中で確認しながら、夜の薬を配る。夜勤は三人体制で、五十人からの患者をみなくてはならない。
夕飯の介助、排泄の介助、点滴の交換、体位交換、やるべきことは山ほどある。職務の性格上、ついミスをしないことが最優先になり、一人一人の患者にきめ細かいケアができないことが心苦しい。
眠前の薬や歯磨きなどが終って、夜九時には一応消灯になるが、夜勤の仕事はむしろこれからが本番だ。
二時間おきの見回りの際にはレスピレーターと呼ばれる人工呼吸器の装着状態や、酸素や点滴のチュ―ブがはずれたりしていないか確認し、またバイタルやむくみなどの状態もチェックする。その合間に点滴の追加や交換、おむつ交換をし、寝たきりの患者に対しては、褥創を避けるため少なくとも二時間ごとに体位交換をしなくてはならない。
ナースステーションに戻ってほっと息をつくまもなく、ナースコールを示すランプがいっせいについてブザーが鳴り響く。
ひと通り呼ばれた病室を回って戻ってくると、新人スタッフの太田が1025号室の患者の体位交換を手伝って欲しいと言った。
その患者、園田幸生(そのだ・ゆきお)は二週間前に脳内出血で倒れ、救急外来に運ばれてきた四十代の男性患者で、裕子がプライマリーケアを担当している。
緊急手術後はICUにいたが、生命の危機を脱して病棟に移されてきた。しかしその後も意識を取り戻すことなく、ずっと眠り続けている。
「園田さんて、いつも穏やかな顔されてますよね」
連携プレーで横向きだった患者を仰向けにし、ベッドまわりを整えているとき、太田が感心したように言ったので裕子もうなずいた。
自分でナースコールを押せない園田のような患者は特に注意して見守る必要があり、できるだけ頻繁に病室をのぞくようにしていたが、彼の表情はいつも安らかで、ときに微笑みを浮かべているように見えることさえある。
「こんなこと言ったら変かもしれないですけど。私、園田さんを見てると、逆にいやされるような気がするんです」
病室を出て廊下を歩きながら、太田が首をすくめて笑う。
「全然、変なんかじゃないわ。私もけっこう、患者さんにいやされてるわよ」
そう言いながら、裕子は太田が「いやされる」と言った意味は、ねぎらいの言葉をかけてくれたり、冗談を言って和ませてくれたりというようなこととは少し違うということに気づいていた。
園田は独身で、家族は母親だけだった。その母親も高齢で自らも介護を受けており、滅多に見舞いには来られない。
園田の仕事は確か教師だったはずだ。彼は今までどんな人生を送ってきたのだろう。2週間もたつのに、担当患者のことをあまりにも知らないことを恥ずかしく思った。
カルテに書かれていないようなことで、意識を回復させるための手がかりになることが、何かあるかもしれない。後で調べてみなくては。そう心に決めながら、頭はもう午前零時に回収しなければならない蓄尿袋の数を忙しく数え始めている。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
