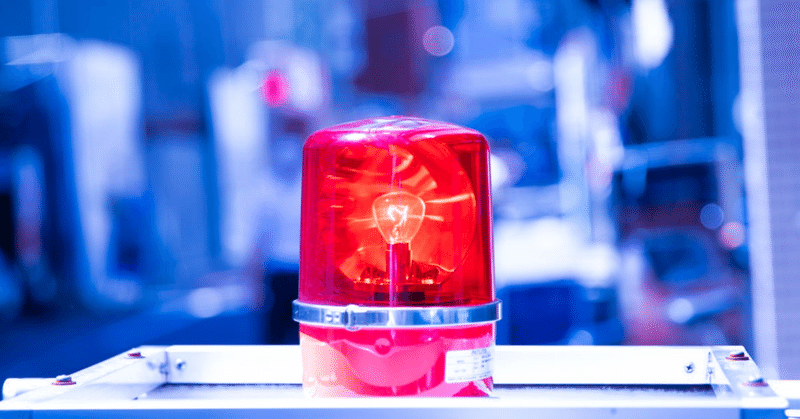
救急車を呼ぶとき親は意外とあてにならない
呼吸困難と胸の痛みで、救急車を呼んだことがある。37歳のときだ。「なんか呼吸が苦しいな」と思ってから、ものの30分くらいで立ち上がれないほど悪化した。
例えるなら、浸水して天井まであと5cmしかないところで溺れながら呼吸している感じ。
このとき私は、心膜炎というのを起こしていたらしい。つまり、心臓を包む膜が炎症を起こしたということ。恐らく持病が関係しているだろう。
私の持病は顕微鏡的多発血管炎と言って、血栓や壊疽が毛細血管で起こりやすいのが特徴。以前医師から、
「血栓が飛んで、血流に乗って、脳に行けば脳梗塞。心臓に行けば心筋梗塞ね」
と言われたことがあったが、今回は心臓へ行ったわけだ。
救急搬送されて、そのまま数日入院して、無事に退院はできたが、医師から
「心臓本体じゃなくて良かった」
と言われたので、不幸中の幸いだったと思われる。
当時たまたま里帰りしているさなかの騒動となったわけだが、このとき学んだことは、救急車を呼ぶとき、親は意外とあてにならないということだった。
*
救急搬送されるのは初めてではなかったし、入院に至っては片手で足りないほどの回数を経験している。こんなこと慣れてもしょうがないが、着々と呼吸困難になっていく中、私は二階の部屋で救急搬送される準備を始めた。
呼吸が苦しいと思った時点で時刻は確認している。紙に発症時刻と症状を書く。それから症状の変化も具体的に書き加えていく。
普段から保険証や難病手帳、受給者証、お薬手帳は持ち歩いているから、救急車には普段使っているバッグだけ持って乗り込めばいい。受給者証には病名が書いてあるし、症状をメモした紙も救急隊員へ渡せば、まともに話せなくなっても大丈夫だろう。
どんどん呼吸が苦しくなっていく。少し休めば治るかも、という期待はもうあきらめた。まったく呼吸ができなくなって倒れてしまう前に、家族へ現状を伝えなければならない。たまたま二階へ来た母に、私は意を決して伝えた。
「……お母さん」
「はいよ。……何、何した。具合悪いの?」
母が私の顔を見て、すぐに何かを察してくれた。あとで聞いたら、このとき私はすでにチアノーゼを起こしていたらしい。
これ、と症状を書きつけた紙を母に託す。
「えー? 何、本当に具合悪いの? やだー、大丈夫なの?」
元看護師の母を頼りにするつもりだったが、にわかに浮足立つ様子に、これはあまり頼りにならないかも、とあきらめ始める。やはり自分の娘のこととなると、仕事のようにテキパキとはならないか。
私は大きく息を吸い込んで告げた。
「救急車、呼んで……!」
母はいよいよ慌てた。
「えーっ、本当にー? どうしよ、サイレン鳴らさないでって頼むべか。ご近所さ聞こえてしまうから……でも――」
「いいから早く呼んで……!」
こっちはすでにいつ呼吸が止まるかと戦々恐々なのだ。私の鬼気迫る様子が伝わってくれたのか、母はビシッと背筋を伸ばし、
「あっ、そうね、そうね!」
と慌てて父のところへ向かった。
「お父さん! 和珪が具合悪くなったから、救急車呼んでって! こういうのあんだがいいんだ! お父さん救急車電話して!」
聞こえてくる母の言葉に不安がよぎる。父の声は、無声音っぽいというか、ささやき声というか、とにかく聞き取りにくいのだ。そんな父に頼むより、声にハリがありすぎる母から電話してほしい。
部屋でうずくまっていると、
「ア……救急車を……」
父のかすかな声が聞こえてきた。やっぱりだ。絶望的に声が弱い。
「え……年……? ……おぅ、お母さん……和珪の年、なんぼや」
娘の年、父知らず。
すかさず母が何やらガミガミと言う。きっと年を教えているのだ。
答えを得た父が、電話口に言った。
「あー……28です」
37ですー!
娘の年、まさかの両親とも知らず。
ほどなく救急車が到着。日本の緊急車両の到着の速さには毎度感心するし、ありがたく思う。
階段の途中でいよいよ動けなくなっている私を担架に乗せ、救急隊員さんたちが残りの階段を下る。そのとき目に入ったのは、父が愛犬(日本スピッツ)を大事そうに抱えてこちらを見守る姿。いや愛犬よりも娘を心配してくれまいか。パニック状態の愛犬をダッコしておくのも大事な役目ではあるけども。
庭へ出ると、すでにご近所の奥様方が集まっていた。皆、当時存命だったうちの祖母がいよいよなのだと思ったらしいから、私が鼻に管をつけ胸を掻きむしりながら運ばれる姿に、とても驚いたようだ。
――余談だが、このとき私は口呼吸しかできなかったので、鼻へ入れた酸素の管はまったく役に立たなかった。
愛犬をダッコする父と、救急車が来たことすら知らずに寝ていた祖母を残し、救急車へは母が同乗した。救急隊員さんへこれまでの経過を伝えようと、母が握りしめたメモを必死に読もうとしている。
違う。そうじゃない。
「お母さん……そのメモ、渡して……」
そのメモを用意したのは、救急隊員さんへ渡すためだ。
「え? ああ、そうね!」
ようやくメモが渡る。それとともに母の口から私の持病のことと、かかりつけ病院がどこかの情報も渡る。
「病名は?」という質問に、母がまた慌てる。
「お母さん……バッグに受給者証あるから……出して……」
「あっ、そうね!」
しかし今度は受給者証を見せられた救急隊員さんがもたつく。
「病名、どこに書いてありますか?」
――マジか。いや仕方がない。薄暗いし、文字は小さい。見つけられないこともあるだろう。受給者証を一旦返してもらい、薄暗い中、目を凝らし、息も絶え絶えに病名を指さす。
無事病名が伝わり、かかりつけ病院への搬送も決まり、ようやく出発。
しかし私にはもうひとつ、やらなければならないことがあった。
声を振り絞り、私は救急隊員さんに告げた。
「私の年、28じゃなくて37です……」と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
