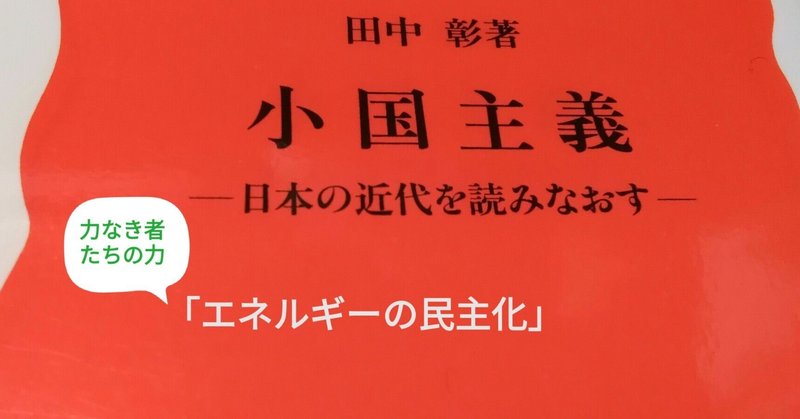
【原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち】と【後世への最大遺物】 ③
長島 彬さん ソーラーシェアリングの親
ながしまあきら
1943年神奈川県生まれ。農機具メーカーで開発設計に携わる。定年退職後、慶應義塾大学に入学し、生物学の教科書から植物の光飽和点を知り、ソーラーシェアリングを発案。2010年千葉県市原市に実験試験場を設立。CHO技術研究所代表。(パンフレットより)
痛快「エネルギーの民主化」🌟
ソーラーシェアリングは「エネルギーの民主化」という長島彬さんのことばに、目の前がパッと開けて明るくなり胸踊りました。正確なことばを思い出せませんが、権力を握っている者たちから、市民が自らの力を奪い返す実践のひとつで、大きな潮流となる力を持つ方法だと感じたからです。「大国主義」で「事大主義」の人たちは喜ばないでしょうねー。
小規模発電装置のソーラシェアリングは手軽に設置できる上に、どこかが停電すれば近隣の地域から電気を送って助けることが可能だ。つまり災害に強い。小規模で手軽に設置できるということは、市民の手で発電が広がる。長島先生はそれを「エネルギーの民主化」と言う。すでにソーラーシェアリングは世界中に広まっているが、残念ながら当の日本は原発を維持したくて仕方がない勢力のせいで広まりが覚束ない。
植物には光が必要だが、程度を超えると有害になる。水をやりすぎると根腐れするように光が過剰だと植物はバテてしまうらしい。それならば、ソーラーパネルですだれのように日陰と日向を作り、太陽光をパネルと植物で分かち合えばいいとお考えになった。ソーラーシェアリングは農地だけのものではなく、公園に設置すれば人々の憩いの場になり、牧場に設置すれば、牛や羊たちの日陰になる。太陽光を地上にあるものとシェアし合うということだ。
羊も日除けがほしかったのでした⇩
江戸時代の米農家は、お米だけではなく薪などのエネルギー供給も担っていました。だから江戸時代は町民よりも農家の方が裕福だったんです。ところが、戦後の農地法でエネルギー供給の役割が奪われ、農作物の供給に限定されることになりました。それで経済的に苦しくなった面があるのです。農業では生活が厳しいから、農家は息子を大学に入れて公務員にしたり、会社員にしました。誰もが「農業人口を減らす事が文明の発展」かのように勘違いされてしまったのです。
でも都市部の生活が成り立つのは、地方で食料生産してくれる人たちがいるからです。ぼくは食料生産こそが最も大事な仕事だと考えています。今は農業が儲からないから職業としての魅力が全くない時代ですが、ソーラーシェアリングが普及すればそれが変わります。そして農家がエネルギー供給するということは、歴史をたどれば決して特殊ではなく、実は本来の仕事でもあったということなのです。(↑強調はスケッチブック)

成り立ちから異なる信用金庫と銀行/一九世紀イギリスから/
二宮尊徳が定めた金融の仕組み「仁義礼智信」/
ただ公共事業に尽くせ/信用銀行か信用金庫か/(略)
反原発の立場で研究を続けている京都大学原子炉実験所の小出裕章助教から、こんな話を聞いたこともある。
「原発こそが地球温暖化の原因の最たるものです。”地球温め器„です」
原発は 発電の際に生じる熱の七〇パーセントが排熱として捨てられる。原子炉内の冷却水の温度は排熱によって約七度上がり、周辺の海へ垂れ流されていく。
発電においては、熱効率という言葉がよく使われる。発生した熱がどれだけ電気に変わるのかを示す数字で、原発は約三〇パーセントと低い上に、東京までの遠距離を送電線で運ぶため電力の半分がロスとなる。実際に利用できるエネルギーの効率は極めて悪いのだ。
「小国主義」を推します❗(「推し」ってはじめて使った)
藻谷浩介著「里山資本主義」を10年ぶり?にパラパラ眺めていたら飛びこんできたことばに目が💛
第五章「マッチョな二〇世紀」から「しなやかな二一世紀」へ
──課題先進国を救う里山モデル
(NHK広島取材班・井上恭介)
「マッチョな大国主義」から「しなやかな小国主義」へ
「既得権益を握りしめている大国の権力者たち」が搾り取り踏み倒す対象-人口-数字としか見ていない人間が、ひとり、ひとり、またひとりと、「大国の俺様たち」を尻目にぞろぞろ去ってゆき、大河のようになるのが目に浮かぶ、ふふふ。

⇧2023年現在のことを調べることができませんでした。
⇧JFS ジャパン・フォー・サステナビリティ
省エネのチカラ 1.7兆円、原発13基分
経済産業省によれば、2010年度から2013年度に、火力発電は1900億kwh(134%)増加した。一方、同時期に省エネなどにより減少した発電量は789億kwhだった。仮にこの全量を化石燃料で代替した場合を考えれば、1.7兆円の節約効果と言える。この間GDP(国内総生産)は約10%減少したが、それでも2012年は1960年以降最高を記録し、2013年も同年以降、6番目の規模となっている。なお、減少した789億kwh(一般家庭2200万世帯分)は、原発13基分の年間発電量に相当する。
二酸化炭素の排出量の推移に、原発停止前から目立った変化なし
全般的に見て、福島原発事故後の日本の二酸化炭素排出量は驚くほど変化が緩やかである。日本の原発保有量は世界第3位だが、事故後わずかの期間にすべての原子炉が稼働停止したにもかかわらず、二酸化炭素排出量の増加は予想よりもはるかに少なかった。エネルギー部門の二酸化炭素排出量は、原発事故以前・以後でさほど変わらず、2009年から2010年の年間排出量は約7%増加したのに対し、2010年から2012年の年間排出量の増加は8%未満である。つまり、原発事故後の二酸化炭素排出量は急激な増加とはほど遠く、2008年の金融危機からの景気回復による影響を一部受けつつ、それまで問題となっていた排出増の傾向が続いていると言える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
