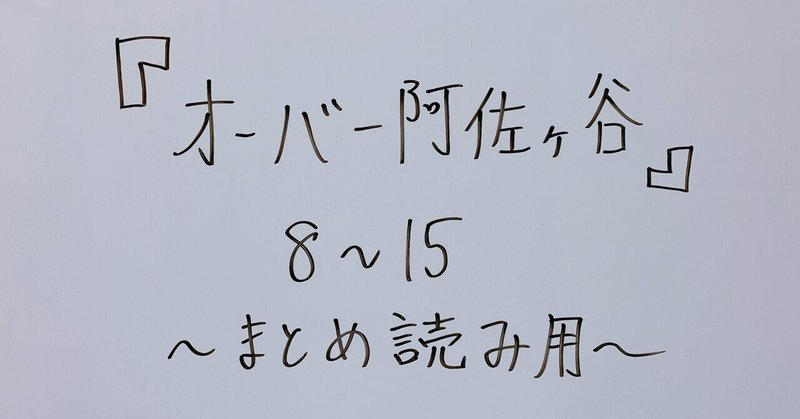
『オーバー阿佐ヶ谷』8〜15(まとめ読み用)
8.
陽光が頬を突き刺す暑さで目を覚ます。夏の死臭漂う秋の日だった。枕に顔を埋め、自分をゆっくりと取り戻す。自分という人生を構成する記憶の一つ一つが戻ってくる。名前や生い立ち、今の状況。過去に付いた傷やドープな出来事。別に戻って来なくて良いものばかり遠心力のかかったブーメランが如く手元に還ってくる。途中、体毛の濃い怪物が割り込んできたが、それは見ないことにしてやり過ごした。
寝起きの頭で珈琲を淹れ、煙草と共に嗜む。オールドスクールな紳士のスタイルを継承している日本で唯一の男、それが私だ。
ーーーStyle is Everything.
そう、いつだって私はクールであり、いつだって寝起きの煙草は美味い。
手帳で日付を確認する。今日という日が赤ペンを使って二重丸で囲ってある。その下には『10時に高円寺。重要!』の文字。なんだかとても重要な日のように思えた。かつての私がそうしたのだ。きっとそうに違いない。
それは先日飲み屋で知り合った編集者と再び会う約束だった。私が丹精込めて生み出したアートを見てもらうことになっている。栄光への道を歩き出す手筈は整っている。この日の為に寝る間を惜しんで創り上げた作品だ。抜かりはなかった。
鏡に向かって、長い髪を頭頂部から半分に分ける。かつてかけたパーマの残る毛先にヘアマヨネーズを丁寧に揉み込み、両耳の後ろで三つ編みを編んでいく。死を賭した闘いに挑むギャングスタ・スタイル。手首に吹きつけたディオールの香水を首筋になすりつける。どこからどう見ても完璧だった。阿佐ヶ谷の安居酒屋で酔っ払っている男には見えない。
ーーーしかし中央線沿線には出版社の社員が多く住む、という噂は本当だったみたいだ。阿佐ヶ谷に住み始めて二年弱、私はようやくそのカードを引き当てた。それがスペードのエースなのか、はたまたジョーカーなのかはまだ分からない。分かっているのは、今日会う相手はグラマラスな女編集者だということだけだ。枕営業も辞さない覚悟で待ち合わせ場所に向かった。
*
途中、阿佐ヶ谷駅そばの西友に寄って手土産を買った。GODIVA。これを手にした女は皆、堕ちると噂の高級チョコレート。私の財布から札束が飛び去った。
ーーーこれは未来への投資だ。数年先には何千倍にもなって返ってくる。
そう思うことにした。何せチョコレートは金塊に似ている。
*
待ち合わせ先は高円寺駅からほど近いビルの二階に昔からある喫茶店だった。夜はパプスタイルになるそこは薄暗い照明と喫煙可能席を持つ現代の貴重な資産だった。店内を見回すも、待ち合わせ相手の姿はまだない。酔った時の記憶をいくら手繰り寄せても似た人間はいなかった。私は席に着き、アイス珈琲とケーキのセットを頼んだ。甘党は誤魔化せない。たとえ目の前にインスリン注射器が置かれていたとしても。
9.
待ち合わせ相手の女編集者が来るまで、三十分の時間を要した。その間、私はケーキを平らげ、珈琲を二杯飲み、煙草三本を灰にした。備え付けの新聞を読み、電線に留まった鳩の数を数えた。窓から見える駅のホームに女の姿を捜し、いないと分かると次の電車が来るまでまた鳩の数を数えた。自分の持ってきたアートを取り出しては眺めて悦に入り、ウェイトレスの短いスカートの奥を想像してはトイレに立った。
左右の乳首を隠すように垂らされた三つ編みはしっかりと編み込まれていた。私は鏡に向かって顔を作った。悪くはなかった。少なくとも平和ボケした顔ではなかった。
席に戻る途中で、店に入ってくる編集者を見つけた。特徴的な丸い銀縁眼鏡に長い黒髪。私は片手を上げて合図した。編集者はあからさまに迷惑そうな顔をした。三つ編み男と知り合いだと思われるのが嫌だったのかもしれないし、自分より髪の長い男が嫌いなだけかもしれないし、ドラッグディールに巻き込まれるとでも思っているのかもしれない。そこらへんに関しては自分の不運を嘆いてもらう他ない。
席に着くなり「後悔しているんです」と編集者は言った。
「全部、酒のせいさ。お互いベロベロだったからね」
傍で聞いていれば、我々は一夜の過ちを清算するかりそめのカップルのように見えたことだろう。
「こんな約束するんじゃなかった」と編集者は呟いた。
「少なくとも、守ってもらえて感謝してるよ」
後悔はしばらく収まりそうもなかった。ただ、自分の心情を正直に吐露する姿勢には好感が持てた。たとえそれがネガティヴワードだったとしても。私はバッグからアートを取り出した。
「これを…読めばいいんですね?」
「なんなら出版してもらっても構わないよ」
編集者は盛大な溜息で灰皿に溜まった灰をテーブルいっぱいに舞い散らせた。
沈黙の時間が続いた。沈黙は金なり、と古人は言った。だから黙っていることにした。
「読み終わった…です」
「感想は言わなくても顔に書いてあるよ」私は煙草に火を点けた。「でも何故、読めば読むだけ馬鹿になる自己啓発本や大多数に害しか及ぼさないインフルエンサーのビジネス書は出版されて、俺のリリック集は日の目を見ないんだろう」
「売れないからです。出版業界では、毒にも薬にもならないものに価値なんてないんです」
率直だった。申し訳無さそうに言う割に辛辣だった。図書館で知り合った女が清楚そうに見えてクソbitchだった時の衝撃を上回る何かがそこには渦巻いていた。
「でも、君たちは売るのが仕事だろ?その為に印税をごっそりと持っていくのと違うかい?それともなにかい?もの書きって職業は君たちを養う為だけに文章を書いている、養父や乳母のようなものなのかい?営業を放棄した出版社なんて脱がない売春婦と一緒じゃないか」
最後の方はコンプライアンス的に問題発言だった。謹んで訂正した。
「仕方ないんです。ビジネスですから」と編集者は言った。
「そうだ。全てはビジネスだ。それじゃあお望みの通り、ビジネスの話をしようじゃないか」
言葉尻を捉えてまくり返す。フリースタイルの基本だ。
10.
編集者が注文していた珈琲がようやく届いた。きっと豆の栽培から始めていたのだろう。もしくは焙煎豆を瞬間凍結→粉砕した黒い粉を買いに走っていたか。どちらにせよお湯を注げば黒い水になることに変わりはなかった。どんなに手を入れたところで珈琲が銀色に光ることはない。
「いい話があるんだ」私は編集者の目の前で指を一本立てた。「それは一つの寓話であり、都市伝説でもあり、同時に真実を含んでいる」
編集者の眉間にあからさまな皺が寄った。
「ワタシは出版社のしがない一社員ですし、歳のいった両親もおりますし、もうすぐボーナスも近いですし。将来を誓い合った恋人もおりますし、そのうち猫も飼いたいですし。…だから反社会的なことはちょっと…困ります」
途中にどうでもいい情報やさりげない自慢話を混ぜ込んでくるあたりの手法は、さすがビジネス書をメインに据える出版社のそれであったが、別に今から非合法ビジネスの話をする訳じゃないので、水に流すことにした。
「昨日ね、怪物を見たんだ」
編集者は「それなら非合法な話の方が良かった」、みたいな顔をした。
「実際に証拠もある」
私は持ってきた『マイルズ・デイヴィス自叙伝』の真ん中辺りのページを開いた。そこには四本の縮れた黒い毛が挟まっていた。編集者は目を背けた。
「違う。これは”そういう毛”じゃない」煙草を揉み消す。「よく見てくれ。ホラ」
私は本を編集者の鼻先に近づけた。編集者は頑ななまでに首を背け続けた。
「…セクハラです。訴えますよ」加虐性をそそる弱々しい声だった。
そばを通った店員が訝しげな目で我々二人を交互に見やった。今通報される訳にはいかない。誰がどう見たって、私は女に陰毛を押し付ける犯罪者だった。いや、そもそも論として【自分の陰毛を引き抜いて、それを他人に見つけることで興奮するような性癖】があるのなら名前を教えて欲しい。随分と屈折した痴漢行為だ。
揉み消した煙草に再度火を点け、ゆっくりと吸い込む。シケモク特有の黒っぽい匂いがした。編集者は相変わらず顔を背け、斜め下を向いていた。
「信じないなら仕方ない。でも、本当に昨日、怪物に遭遇してその背中からむしり取った体毛なんだよ」
私の憐れな声が功を奏したのか、編集者はようやく顔をこちらに向けた。若干、目が赤かった。なんだか”無理打ち(=強姦)”でもしてしまったような気分になった。
震える手で珈琲カップを握りしめる編集者相手に、昨日の出来事のあらましを話して聞かせた。
珈琲を飲んで落ち着いたらしい編集者はようやく本の上に乗った黒い四本の毛に目をやった。
「”コレ”が”それ”…なんですか?」
「そうさ。抜きたてのホヤホヤだ。どうだろう、これで一冊”都市伝説系の本”が作れると思わないか?今ブームでしょ、そういうの。”コレ”で一発当てて、その余剰金で俺のリリック集を出版してもらえないだろうか」
「でも、それはウチじゃなくて、『月刊ムー』に持ち込んだ方が無難かと」
「やっぱりそう思うかい?」
編集者は四本のうちの一本をつまみ、間接照明に照らして上下左右から眺めた。そして、「なんか…見れば見るほどチン毛みたいですね」と言った。
11.
高円寺の駅前で編集者に別れを告げ、私は阿佐ヶ谷までの道のりを高架下を歩いて帰った。途中にあるカレー屋で芝生を眺めながらクラフトビールを飲んだ。なんだか休日の町散歩のような平和さだった。バッグの中の本に挟まれた黒い四本の毛を除いて。
状況は何一つ好転していなかった。メイクマネーの道は再び閉ざされ、謎の怪物問題まで抱え込んでしまった。どちらかと言えば、大いなる後退だった。見えない力学に阻まれるように行く先々で扉は閉じられる。鼻先をかすって閉まる扉の感触は何度味わっても慣れるものではなかった。極楽鳥を取り逃すのはこれで何度目だろう。それは己の努力とは無関係に勝手に羽ばたく。
空転する歯車に組み込まれたパーツの一部のような足は、怪物が飛び上がって消えた釣り堀の前まで来て歩を止めた。無意識の自動操縦がそうさせた。今を遡ること十数時間前にここで起こった一連の出来事がありありと眼前に浮かぶ。今も目をつぶって手を伸ばせばその背中に触れられそうな気がした。眉毛の太い女のパンツの中に手を突っ込んだ時のような感覚と指先で触れ得た”ごわごわ”しい触感。生温かくはあったが、別に濡れてはいなかった。それで良かった。私は中に入った。
平日ということもあり、客はまばらだった。大体に於いて老人が多い。スーツ姿の若い男が一人いたが、竿を垂らした池の水を見つめたまま微動だにしなかった。病んだ日本の象徴のような男だった。
ーーー怪物はここに逃げ込んだ後、何処に消えたのだろう。釣り堀の敷地の周りには古い住居が多い。まさかその中の一軒に住んでいる訳もなかろう。怪物がエプロンをして台所に立つ様を想像してみる。裸エプロンの部類の中でも最低レベルの妄想となった。
特に手がかりになりそうなものは見つからなそうだったので、敷地を一周して釣り堀を後にした。
*
先程編集者から聞き出した『月刊ムー』編集部の電話番号に電話をかけた。何度かけても”話し中”の為通じなかった。世の中は自分の体験した都市伝説を伝えたい人間で溢れているのかもしれない。もしくは、何か見えない力によって阻まれているのか。ーーー馬鹿らしい。リアルを売りにするラッパーとは到底思えない台詞だ。電話番号の書かれたメモは折り畳んで『マイルズ・デイヴィス自叙伝』に挟んでおいた。
夜はまだ来なかった。昼すらまだだった。財布の中身は寂しく、天候は生理前の女の子の心みたいに不順だった。携帯電話のアドレス帳を開き、溜め息をついてから、もう一件別の場所に電話を掛けることにした。ビッグマネーには程遠い、さりとてサグライフには付き物のアルバイト先に。
12.
十三階の1314号室に無事、荷物を届け下に降りると、私の原付を二人の制服警官が取り囲んでいた。恐るることはなかった。所持していなければ捕まることもない。1314号室が今日最後の配達だった。
ジャイロ付き三輪原付のボックスの横には『野菜直送便』のロゴが印刷されている。これで産直の新鮮、というよりは乾燥させた野菜を運ぶ簡単なお仕事だ。
ーーー今日は合計十三件のデリバリーだった。愛好家はなかなか多いものだ。多ければ多いだけ私の出来高も上がる。お互いにとって得しかない。アメリカ辺りじゃ多くのセレブが参入しているビッグビジネスだっていうのに、法の壁に阻まれた日本じゃ未だにイリーガルビジネス。野菜に罪はない。あるとすれば富への抜け道。
私はゆっくりと原付に近づいた。ハリウッド俳優がレッドカーペットを歩くみたいに。手は振らなかった。生憎、そこまでのサービス精神は持ち合わせていない。
「このバイクの所有者さん?ボックスを開けてもらってもいいかな?」と警官の一人が言った。もうこれ以上の昇進は望めそうにもない中年だった。
「オーケー」私は素直かつ恭しくボックスを開けた。ボックスの中は折り畳んだコンテナが二個あるだけだった。
「なんだ空っぽじゃないか」
「そうっすね。今配達終わったところですから」努めてにこやかに話した。
先程まで二つのコンテナ一杯に積まれていた野菜は今ごろ客の手元で煙になって消費されていることだろう。野菜の調理方法は詰めるか巻くか、はたまたボングするか。一番好みの方法で摂取すれば良い。所詮、健康に良いこと尽くめの嗜好品の花形なんだ。
「なんか変なもの積んでないかなー、と思ってさ」
「やだなぁ。野菜しか積んでませんよ」
「ホラ、”野菜”って”アレ”の隠語じゃん?」と中年の警官が馴れ馴れしく肩を叩いてきた。
「”アレ”とは?」
一瞬だけその場に緊張が走った。
「まぁいいや。それじゃさ、顧客リスト、いや、今日の配達のルート表みたいなのがあれば確認させてもらえない?」
「それは個人情報だし、そもそも頭の中に地図が入ってるからそんなものは無いっすよ」
「そうかー。とりあえず免許証だけでも拝見するね。ちょっと、その前にーーー」警官がもう一人の若い警官に目配せをした。
「じゃあ身体検査だけすいません」若い警官が近づいてきた。
私は両腕を上げた。無骨な手が私の身体を無遠慮に触っていく。胸元、胴回り、足首から上がって尻ポケット周辺を執拗に撫でられた。
「すごい三つ編みだね。女の子みたいだ」と言いながら股の間を弄(まさぐ)ってきた。鼻息が荒かった。
私は”Fuck Fuckin’ Faggot.”、と呟いた。
「なに?」
「”職務ご苦労様です”って言ったんだよ。気にしないでくれ」
私が痴漢の憂き目に遭っている間、中年の警官は私の財布を調べていた。
「お兄さん、すごいお金持ちじゃない」
「月初の集金があっただけですよ、お巡りさん」
中年警官はカードの束から免許証を引き抜き、その小さな瞳に近づけたり遠ざけたりしながら眺めた。偽造かどうか調べているのかもしれないし、単に目のピントの問題かもしれない。数十秒を要して、どうにかちょうど良い距離感が定まったらしい。うん、歳は取りたくないものだ。
「へぇ、ーーーーさんね」
「止めろよ。本名で呼ぶんじゃねぇよ」
「なんで?芸能人の人?」
私は何も言わなかった。答える義務も無かった。
「普段は何やってる人なの?これが本業?」
警官が一つ質問し出すとこちらが答えるまで続けるのは何故だろう。期待した餌を貰えなかった犬のように付き纏ってくる。
「まさか。配達に一生を賭けるつもりはないっすよ。もう行っていいかな?」私は後ろのボックスを閉め、原付に跨って駐車ロックを下ろした。「まぁ何というか、アーティストだね」結果的に捨て台詞のようになってしまった。
「へぇ。すごいね。サイン貰っとこうかな」
警官二人は顔を見合わせて、下卑た笑みを交わした。軽い乾杯、みたいに。
何も見つからない以上、ここで足止めされている理由もなかった。私はヘルメットを被り、セルを回した。エンジンのアイドリングに混ざるように、警官の舌打ちが聞こえた。
13.
日払いの給料を受け取り、一度家に帰ってから日大二高通りにあるスタジオに個人練の枠で入った。壁に染み込んだ煙草の臭いが絶えずホロコーストのガス室のように出入りする、そんなスタジオに。
MacBookをスピーカーに繋ぎ、GarageBandに自分で打ち込んだトラックを流す。緩めのBPMに怠惰なベースライン。時々、思い出したようにオルガンが鳴る。一、二音で途切れるそれはセロニアス・モンクが寝しなに鍵盤を叩く様を想像しながら創ったものだ。
私はマイクを握り、そのトラック上でフリースタイルにラップをしていく。韻というハシゴで言葉と言葉を繋ぎ、グルーヴという粘着剤でそれを接着させる。トラックが鳴り続けている間は言葉を途切らせないのがマイルール。そうしてマイクに向かって大量の言葉を吐いていくうちに、自分でも思ってもみなかったようなワードが飛び出すのを待つ。脳の何処かを経由して形を現した、神の言葉。手持ちの語彙が枯れ尽きた果てに辿り着く墓場の卒塔婆に書かれた大日如来のSiddha。綴るリリック、啜るメドエイク。What’s メドエイク。そんな言葉、既存の辞書にはない諸刃の刃。
ーーーーとはいえ。
一時間五百円を費やした割に、さしたる生産性はなかった。芸術と資本主義は相容れない。ワインを丼鉢に入れるようなものだ。そこには情緒も優美さも反省すらない。
まぁそういう日もある。全てが上手くいく訳じゃない。常にいつもgoodだったら、それはbadであるのと変わらない。
*
スタジオという密閉空間で煙草臭くなった服を着替え、遅い昼飯を作った。パスタを茹でている間に、ニンニクと唐辛子を刻み、アボカドを細切れにする。フライパンにオリーブオイルを敷き、ニンニクと唐辛子を炒める。茹で上がったパスタのお湯をよく切ってからフライパンに投入し、アボカドと一緒に軽く混ぜる。そこに永谷園松茸の味お吸い物の粉を振りかけ、余熱で絡ませる。皿に盛りつけてから鰹節と醤油を振りかければ、和風アボカドペペロンチーノの完成だ。カフェで出せば千五百円は取れる出来だった。
飯も食って煙草を吸ったので、昼寝でもしようかと思う。ーーーなんていい身分なんだろう。人はそれを現実逃避と呼ぶのかもしれないが、これが俺の現在。社会からはとうにつまみ出されている嗚呼、無常。
宣言通りに寝転がる。俺は俺の言葉にだけ忠実だ。ラッパー on the 畳。全く絵にならなかった。金が出来たら引っ越そう。港区辺りのタワーマンションにでも。一部屋をスタジオにして、そうだ、ヘネシーを並べたバーカウンターも併設しよう。そこでの私はもう”何者か”になっていて、きっと葉巻でも吸っているだろう。カストロの一声が生んだキューバ産コイーバでも。勿論、太巻きのブラントでも良い。歯で噛むように咥えて、下肢の細巻きは歯立てさせないように咥えさせる。ーーー細巻き、だと?うるせぇな。
夢は夢として見たままに、傍らのスマートフォンを掴み、今やアーティストの主戦場の一つとなったSNSというバトルフィールドを開く。別に「いいね!」が付いたことを知らせる(福音にも似た)通知があった訳じゃない。そんなものアカウントを作ってから来た試しがない。来るのは、雨後の筍の如くに現れる捨て垢によるFXへの勧誘詐欺くらいだ。そしてそんなものに引っかかるほど情弱じゃない。
私が今朝、投稿したリリックには何の反応もなかった。ハートマークは空欄の灰色。リツイートの横に数字は空白。
聴衆は周りの無視を踏襲。
嘲笑噛み殺してスルー。
だけど俺は猛将。
まるで曹操。
三国志一の人気者。
9回裏でひっくり返す俺は英雄。
そのうち銀座で豪遊。
間違いない未来はすぐそこ。
私の投稿の上下に表示された#詩には百を超える「いいね!」が付いていた。
14.
その夜、私はいつも通り『ソルト・ピーナッツ』に行った。酔っ払う為に、我が世の春を無駄とする為に、演出家の男から更なる怪物譚を聞き出す為に。日付け的に遡れば、今日の深夜に怪物と遭遇したのだが、歳のせいもあってか、もう何年も昔のことのように感じる。遠い昔はつい最近のように、数時間前は山のあなたの空遠く。そうやって記憶は曖昧に混ざり合い、人生はその色を深め、歳だけはしっかりと取る。
私はランダム味の酒を頼み、演出家の男を待った。二杯、三杯と杯を重ねるにつれて、苛立ちだけが増していった。客は入れ替わるが、目当ての人間だけは姿を見せない。いずれ来るのが女ではないのに、こうも待ち焦がれている自分が無性に腹立たしかった。四杯目を注文する傍ら、私は尋ねた。「昨日いた演出家の男、今日は来ないの?」自分がゲイなのではない、ということを強調する為に、あくまでもさりげなく。
「殺されたよ」と店主は言った。昨日は酔い潰れて寝ていた男とは思えないほど聡明な声だった。
「殺された?なんで」
急転直下に物事はその様相を変えていく。肺が空気を取り込み、心臓が血液を廻し、肝臓が解毒したものを腎臓が濾過し膀胱へと流す、そんなどこにでもいる当たり前の人間でも次の瞬間には肉と骨の塊と化す。別れの挨拶はそのまま永遠の決別となり、交わしたくだらない冗談は温かい思い出へと変わる。いや、そこまで親しかった訳じゃないが、それでも。死者を想うことは物事を美化させる。
「そんなこと俺にも分からん。さっき警察が来て色々聞かれたんだ。俺も充分に混乱してる」と店主は言った。
店主が警察から聞いた話を総合すると、あの演出家の男は『ソルト・ピーナッツ』を出た後、すぐに殺されたらしかった。家に帰る途中の阿佐ヶ谷の暗がりで。死因は撲殺による頭蓋骨陥没とそれに伴う脳内の大量出血。凶器はまだ見つかっていない。加害者と思しき者も未だ闇の中。怨恨と通り魔の両面で操作中。今は演劇関係者を中心に当たっているらしい。
よくもまぁ警察からの尋問の中、ここまで情報を絞り取れたものだ。店主の磨き抜かれたコミュニケーションが羨ましいくらいだった。
我々の話を又聞きしていた他の客達は静まり返った。店全体で通夜のムードでも出そうか、というみたいに。ーーー死んだ?嘘だろ。これで永久に怪物の謎はそのままとなってしまうのか。
いや、まだ希望はある。それは目の前、手の届くところにある。阿佐ヶ谷でSince 1969から営業している、この年老いた『ソルト・ピーナッツ』店主ならば、何か知っているかもしれない。”怪物”は他ならぬ阿佐ヶ谷の都市伝説なのだ。私は酒を受け取りながら、店主に尋ねた。
「あの演出家のおっさんが言ってた”怪物”の話、あんた何か知らないか?」
「怪物?何のことだ」
訝しげな眼差しを向けられる。でも、そんな目で見られるほど酔っちゃいない。
「あんたも昨日聞いてたろ?」
あの時、店にいたのは我々三人だけだった。私と演出家の男と、この店主。場の共有者のうちの一人はもう抜けてしまった。残念ながら、とでも言うが正しいか。
「俺は酔っ払って寝てたから知らん」
「別に演出家のおっさんが言ってたことじゃなくても良いんだ。何かーーー」
「お前もいい歳してそんな夢物語を追うのは止しとけ、止しとけ」
届いた酒はストレートの焼酎だった。それは私が希求し、注文したそのものだった。
15.
ーーー解せん。何故、死んだ。
その問いが酔った頭の中をピンボールみたいに弾け飛んでいる。左側頭骨にぶつかり、後頭骨に当たり、前頭骨から右側頭骨へ。頭痛がする。単なる飲み過ぎで脳が浮腫んだだけかもしれないが。
ーーー私に謎だけを残して死ぬやつがあるか。馬鹿野郎。
演出家の残した大いなる負の遺産”怪物”。私一人でこれをどうしろというのだ。死者を責めても仕方ないが、それより他に術がなかった。
ーーーそういえば「馬鹿野郎」はあの演出家の口癖だった。そうだな、レストインピース。
不可解だった。それを言い出せば、産まれた時に既に定められている死に対して不可解だと言うのも筋違いなのだが、それにしても。病死や自然死ならまだしも怪物の話を吐露した夜に、その当人が死ぬ?多分、その同時刻に私は怪物に遭遇し、その毛をむしっている。これに何の因果も求めない方がどうかしている。
ーーー怪物の話と演出家の死との間には何かしらの繋がりがある。絶対に。お馴染みのシックスセンスがそう告げていた。これまで一度も正解に辿り着いたことのないシックスセンスが。
二十数時間前にはあれほどまでに輝いていた満月は見えない。分厚い雲が空を覆っていた。Tシャツでは肌寒く、パーカーを羽織るにはまだ早い、そんな中途半端な季節だった。こんな季節に死ぬっていうのはどんな気分なんだ。頭から流した自分の血を見ながら死ぬっていうのはどんな気分なんだろう。冷たくも熱くもないアスファルトに横たわるのはどんな気分?開き切った瞳孔で見つめる阿佐ヶ谷のストリートはあんたにはどう映った?
どれもこれも答えの出ない問いだった。生者から死者への問いかけは答えられた試しがない。それでも尚、人は問いかける。それだけが儚く脆い接点かのように。
*
追悼の酒の為に寄った小さなバーでは界隈で起きた殺人事件の話で持ちきりだった。まぁ持ちきりとはいえ、私を除いて客は一組のカップルしかいなかったが。
私はカップルから距離を取った席に座り、話に混ざっていたバーテンダーに軽めの酒を注文した。栓を抜いて差し出せば済むようなものを。
気にしてない時には目につかないものでも、知ってしまえば矢鱈と目につく。そのような習性が人には備わっているらしい。死はその代表格かもしれない。聞きたくもない話ばかり聞こえてくる。テリー・レノックスに酒を捧げたフィリップ・マーロウの静寂はここでは求められそうにもない。なかなか上手くいかないものだ、現実は。そう。現実には。
「犯人まだ逃げてるんだろ?怖ぇな」
「死体、酷い有り様だったらしいですよ」
「今もまだアスファルトに血がべったりだって」
「帰り、見に行ってみようぜ?」
「いいね!いいね!でも怖ーい」
「大丈夫だよ。俺が付いてっから」
「その被害者の人、結構多額の借金があったって話ですよ」
「じゃあ恨みで殺されたのかもな」
「劇団やってる演出家だって」
「今どき、演劇?売れないんだろうな」
「そんなものに人生賭けちゃって、歳なんか取った日には余計にもう引けないですよね」
「犯人は役者である。名探偵ワタシの推理!」
「ありそう!ありそう!劇団って内情、ドロドロそうじゃん」
「分かるー。偉い人と女優がデキてるってやつでしょ」
「キモいっすね。主演の座を勝ち取る為に汚いオッサンに抱かれるなんて」
「だいぶ酔っちゃったな。事件現場行くより、今日お前ん家行っていい?」
「えー。何もしない?」
「何もしないよー。帰るの面倒くさくなっちゃったし、寝るだけ寝るだけ」
*
馬鹿らしくなって店を出た。
#阿佐ヶ谷 #スターロード #バー #飲み屋 #酒 #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
