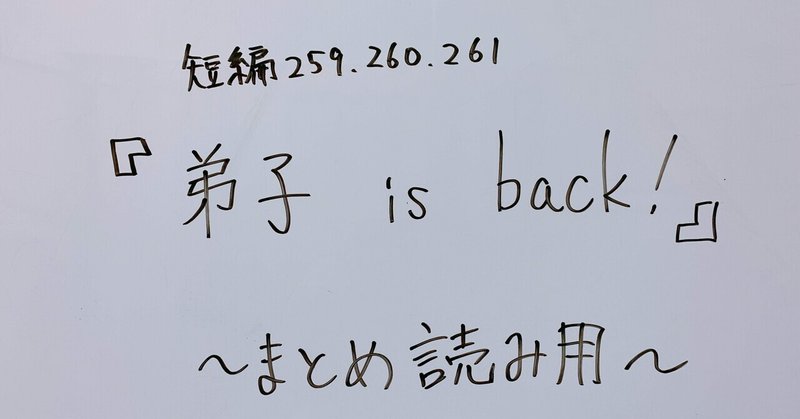
短編259.260. 261.『弟子 is back!』(まとめ読み用)
近所を散歩している時、必ず通る神社がある。どの町にもある、なんの変哲もない神の社(やしろ)。でも、人はそこで祈り、願い、通い詰める。いつかの私みたいに。
*
その日はおよそ十年ぶりに境内に入ってみることにした。別にこれといった願いごとがある訳でもない。もう願いごとは聞き届けられ、その後の日常を生きている身だ。金木犀の匂いに誘われたのかもしれない。
数百年前から変わっていないように思える石畳を歩く。ここに来ると相変わらずスニーカーの底を地面に擦るように歩いてしまう。もうその音に意味なんてないのに。四メートルはあろうかという巨大な石に彫られた日露戦争の慰霊碑、幹の枯れ切った大木、偉人の言葉が掲載されたガラス張りの掲示板。そのどれもが懐かしかった。
手水を済ませ、本堂に向かうべく歩を進めた。身体の線をなぞるように吹く風は秋のそれだった。柔らかさの中にどこか棘を含んでいる。これからやってくる厳しい冬からの警告状のように。
賽銭箱に十一円を放り込む。昔からここに来ると、必ずその金額だった。何せひと頃は毎日通っていたので、そうそう大金を投げられる訳もなかった。それが故の単なる習慣といえば聞こえは良いが、十年経っても相変わらず金は無かった。
ーーーおかげさまでなんとか生きてます。ありがとう。
これ以外、言うことは思いつかなかった。こうして今もまだ生きて在る以上に何を望めば良いのだろう。そこまで欲深くも出来ていない。
合わせた手を離し、薄目を開ける。その目の端を何かが横切ったような気がして、首を左に振った。視線の先には境内の隅にひっそりと祀られたお稲荷さんの祠。ーーー嗚呼、これもあったか。かつての懐かしい記憶に背を押され、私は祠に近づいた。
咲き誇る金木犀の花に囲まれ、いや、半ば埋もれるようにしてその祠は建てられている。狐を象った一対の石像は、まるで人目を避ける隠遁者みたいに無口だ。初見なら見落としてしまっても仕方がないような造りの小さな、とても小さな鳥居をくぐった私はゆっくりと息を吸った。マスクをしていても尚、それを突き抜けて香る金木犀の佳芳。人をセンチメンタルにする為にこそあるような香り。
賽銭箱に小銭の残りを放り込んで手を合わせる。願いごとはないが、伝えてもらいたいことはある。もし、狐が神様の眷属(けんぞく)であるならば。
ーーーそっちはどうだい?俺は相変わらずこんな感じ。会えなくなってとても寂しいよ。
我ながら感傷に過ぎるな、とは思いつつ目を開ける。木で組まれた小さな本堂が目に映る。風雨に晒された年月分、白く煙っている。格子状に組まれた扉の前、そこには見覚えのある色柄の猫が座っていた。
「弟子、じゃないか!」
私は喜びと共にその猫に駆け寄った。
この猫が何者(なにねこ)なのか説明する為には、少し時系列を遡らねばならない。
*
かつて”ミーちゃん”と呼ばれた野良猫がいた。正式名称は”八幡ミー”。八幡神社に暮らしていたから、そんな苗字を授けたに過ぎない。私が。勝手に。本当は猫に名前など必要ない。猫はただ猫であり、人の世の習わしからはどこまでも自由なのだから。しかし、人は猫に、時に野良猫にすら名前を与える。個体識別、もしくはアダムが神の前でやった行為の反復なのかもしれない。でもどこからも「良し」などという声は聞こえない。
そのミーちゃんと呼ばれる野良猫は地域猫として、近所の猫好きおばさん達に愛されていた。おばさん達の間に横のつながりはない。各々が各々、好き勝手に可愛がっていただけだ。撫でたり、餌をやったり、と。でも役割分担は勝手に出来上がっていたと思う。「私はごはん担当、あなたはオヤツ担当」みたいな。
ミーちゃんという名も自然発生的に付けられたものだろうと思う。別に示し合わせて「この猫をミーちゃんと呼ぼう」なんてことはなかっただろう。でも何せその猫は”ミーちゃん”っぽい顔をしていた。それが故に、ミーちゃんと呼ばれるようになった。それが真実だろうし、実際、野良猫の名前なんてそんなものだ。
物腰スマートで器量よし。人懐っこく甘え上手。それでいて、撫でてくれよ、と腹を出した反動で頭をアスファルトに打ちつける、強烈なお茶目さん。もし仮に人間に化けたとしても、相当な人気者になれることだろう。
私がまだ病人として、独りひっそりとこの世に生を送っていた頃、私もミーちゃんと出会った。そこらへんの話はかつて『野良猫と共に』というエッセイに書いたので省く(本当は百万遍語ってもまだ語り尽くせないけど)。今回は弟子の話だ。そのミーちゃんが連れてきた、まだ子猫だった野良猫の。
*
ある晴れた日の月明かり眩しい夜。ミーちゃんを呼び出す為に、わざと石畳にスニーカーの底を擦り付けるようにして歩いていた。この音を聞きつければ、必ず何処からともなく走り出るようにして一目散に私の元へとやってくる。そして案の定、やって来た。
しかし、その日のミーちゃんは様子が違った。足取り重く、後ろを振り返り振り返りしつつ、歩いてきた。このような姿を見るのは初めてのことだった。何か気掛かりなことでもあるのかと思い、ミーちゃんの後ろの暗闇に目を凝らした。
緑色に輝く二つの目。小さな猫だ。前にいるミーちゃんの五分の一くらいサイズ感だろうか。遠近法的錯視を取り除いた上でも圧倒的に小さい。その小さな猫は、まだこの世界のこの地面に馴染んでいない足取りでミーちゃんについて歩いている。
ミーちゃんは私の前に寝転んだが、その仔猫は遠巻きに我々を眺めていただけだった。幼くして既に発揮される警戒心。それは野生で身を守る為に備わった宿命としての本能なんだろう。
その日はそのまま終わった。私と遊ぶミーちゃんとそれを小首を傾げて見つめる子猫。そのような構図で。
*
あくる日も、そのさらに翌日も、ミーちゃんは弟子を連れていた。歌舞伎役者の子役お披露目みたいに。その日以来、私はポケットに二匹分のチーズを持ち歩くようになった。
持ってきたチーズをミーちゃんに差し出すと、まず自分が一口齧り、弟子の方を振り返る。恐る恐る近寄ってきた弟子はチーズの匂いを嗅ぎ、ミーちゃんを見つめる。アイコンタクトによる何かしらのやり取りが行われた後、弟子はチーズを齧った。口の端から何度も落っことしながら。
毎日がそのような繰り返しで、仔猫は日一日と成長していった。
ある時期、この世界の片隅は二匹と一人によって温められていた。それは混迷する世界にとっては何の役にも立たないことに違いないが、我々は我々にしか分からない友情を確かめ、我々なりのやり方で優しい世界を構築していた。
毛とチーズの世界。私の服は常に抜けた白い毛にまみれていた。
*
ある日を境に、ミーちゃんはまた一人でやってくるようになった。その後ろに弟子の姿はない。元々、天涯孤独の身ですから、というような顔をして。お試し体験無料版のような形で人間世界の成り立ちを垣間見せたら後は各々一匹でやっていく。それが野良の宿命なのかもしれない。
我々はまた一人と一匹に戻った。
*
それっきり会うことのなかった弟子が今、目の前にいる。
あの頃より何倍も大きくなった身体つき。黒とオレンジの特徴的な毛並み。顔つきだけはもう老年のそれであり、瞳は警戒心より優しさが勝っていたが、紛れもなく、あの弟子だった。
弟子は私の顔を見つめた。私も弟子の顔を見つめた。それで充分だった。元々、言語が違うものにとって、言葉なんて邪魔なだけだ。弟子は私の脛に頭を寄せ、私はその背を軽く撫でた。
*
十年というこの長い空白の期間を弟子がどのように生き抜いてきたのかは分からない。
首輪が付いていないことから、弟子がまだ野良としてやっていることを察した。ストリートに生きる者の誇りと矜持を背負って。
でも、太り方からすればきっと良い金主がいるんだろう。師匠であるミーちゃんからの教えは確と受け継がれていた。
十年。それは多くの物事を一変させるには充分な時間だった。
師匠であるミーちゃんはもう亡く、多くの猫にも世代交代の波が押し寄せていった。縄張りは拗れ、遊び場だった古い家々は解体され、ある猫は行方知らずとなり、またある猫は引き取られていった。(野良から足を洗うことが猫にとっての幸せなのかは分からない。安心や快適と引き換えに、自由を奪われることが幸せなのかは)
時の津波が洗い流したものと変わらないもの。それは天秤にかけるまでもなく明白だ。
ミーちゃんと会うことはもう叶わないが、こうしてまた弟子の姿を見ることが出来てとても嬉しく思う。ミーちゃんが幼き日の弟子に教え込んだ野良としての生き様がきちんと継承されていることにも。
*
通勤の折、散歩の折に必ず神社の前を通る。しかし、再びの邂逅の日以来、弟子の姿を見ることはない。かつての弟子がそうであったように。
会いたい、と願っても、そう会えるものではない野良猫の現実。それは私に一つの古語を思い起こさせた。
ーーー一期一会。
人生とはそういうものだ。きっと。だからこそ、その時その瞬間を全力で感じ切らなければならない。それが出来なければ、過去ばかり振り返るつまらない中年になってしまうことだろう。
あの邂逅は、十年振りに訪れた神社からのサプライズだったのだろうか。もしかすると、天のミーちゃんによる雲の上からの粋な配剤だったのかもしれない。そう思うことで、私もこの厳しい世の中を我が身一つで生き抜いていけるように。
*
野良猫を取り巻く環境は厳しい。身を隠す草むらは年々減少し、夏と冬の温度変化も著しい。愚かな人間からの虐待やウイルスの脅威だってある。(主語である猫を人に置き換えて考えてみれば、その現実が実に過酷な環境だということが理解出来ると思う)
そんな環境でも何食わぬ顔でてストリートを闊歩し、好みの場所を見つけては眠る野良猫。タフで孤独なハードボイルド。
ミーちゃんからは関係性の面白みを、そしてその弟子からは瞬間の大切さを学んだ。私にとっても野良猫こそ師匠だ。
この世界に生きる全ての野良猫に幸あれ。
#ミーちゃん #弟子 #猫 #野良猫 #神社 #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
