
司馬遼太郎「坂の上の雲 6巻」読書感想文
個性派の面々が、次から次へと登場する。
明石元二郎の活躍もある。
けっこうページが割かれている。
ロシア駐在の武官だった明石は、国交断絶の直後には中立国のスウェーデンに移る。
そこを拠点に、ロシア国内の革命運動を支援。
帝政を不安定にさせる。
これも日本の勝利の遠因となっている。
“ 諜報 ” の重要さもわからせる。
小村寿太郎だって熱い。
外務大臣としてアメリカで講和工作をして、ロシアとのポーツマス条約を締結する様子にも、けっこうページが割かれている。
ここに司馬遼太郎の余談がビシビシと挿入されて、当時のアメリカの情勢も描かれている。
“ 外交 ” の重要さもわからせる。
大山巌だって、いい味を出している。
満州総司令部では、どんな激戦のなかでも常に余裕がある振舞いをして、幕僚の動揺を抑えている。
あるときなどは、ロシア軍の砲撃音のなか、雑誌に紹介されていた人妻の随筆の論評などして、焦る参謀を落ち着かせている。
“ 統率 ” とはどういうことなのか理解ができた
東郷平八郎は、おそろしく無口。
豪気な雰囲気を漂わせずに、静かに指揮をとっていく。
その下につく秋山真之は、参謀として手腕を振るう。
“ 作戦 ” の可否もわからせる。
※ 筆者註 ・・・ 読書録は抜書きばかりになってます。感想文というより要約となってます。8000文字とけっこう長くなってしまいました。『15分で読める坂の上の雲 第6巻』といった内容になってます。
グリッペンベルクの作戦
満州ロシア軍は、第1軍と第2軍に割られた。
皇帝の命令である。
クロパトキンは、かろうじて総司令官となっていたが、降格ともいえる人事である。
本国からのグリッペンベルグが第2軍の司令官となって、さっそく作戦を立てた。
ロシア軍は偵察によって、日本軍の左翼側が手薄だと知っている。
その手薄な左翼陣地を、まずは第2軍が10万の兵で突破。
転回して主力の背後に回る。
同時に第1軍も、正面から前進する。
大軍しかにできない2面作戦だった。
その手薄な左翼側は、40キロの戦線となる。
守備する司令官は、秋山好古だった。
騎兵を中心に、歩兵と砲兵を加えた8000名の部隊となる。
秋山も偵察によって、ロシア軍の侵攻を予知している。
が、報告を受けた総司令部は、対策を打つことはなかった。
参謀長の児玉源太郎にしても、この極寒期に大規模な攻撃はない、また威力偵察だろうとの見方を変えることない。
報告は黙殺された。
惨戦がはじまろうとしていた。
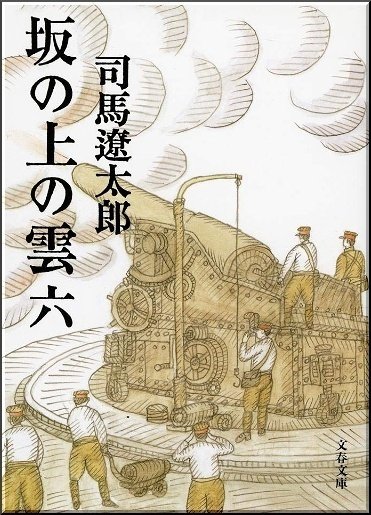
藝春秋 初出:1968年4月 - 1972年8月 産経新聞連載
表紙:安野光雅
黒溝台会戦
左翼側の、4つある大拠点のひとつが “ 黒溝台 ” だった。
ここを中心にして “ 黒溝台会戦 ” となる。
秋山の判断では、ロシア軍の攻撃は確信にちかい。
攻撃があった場合、総司令部が動くまでは、自力で防ぐしかないと、各拠点の長には厳重な警戒を命じていた。
大拠点からは塹壕を掘り、小拠点が多数ある。
前面には障害物を設け、城郭化していた。
敵が3万やってきてもなんとかやれる、という見込みはある。
しかしながら、現実にやってきた敵は10万以上だった。
ロシア軍は、飛雪のなかを砲撃しつつ進んできた。
1月25日。
ロシア軍は大波のように押し寄せた。
秋山部隊の各拠点は、海面に点々と散在する岩礁のごとく、わずかに存在を示すのみ。
最大に威力を発揮したのは、各拠点に設置してあった機関銃だった。
秋山の騎兵隊にだけ、例外的に機関銃が設置されていて、かろうじて各拠点が壊滅からまぬがれ続けた。
が、ロシア軍の目的は、防衛線を突破して主力の背後に転回することでなので、拠点は捨て置くようにして、どんどんと進撃していく。
この段になって、総司令部は援軍を向かわせる決定した。
第8師団の2万の兵である。
日本軍の予備隊は、この第8師団しかない。
以外には援軍が出せない状況だった。
立見尚文(たつみなおふみ)
第8師団は援軍に向かっていた。
“ 陸軍最強の弘前の第8師団 ” といわれていた。
その兵は、青森、秋田、山形、岩手の4県の出身者となる。
師団長の立見尚文は、元伊勢桑名藩士の61歳。
現役中将の最古参である。
幕末の戊辰戦争のときは、幕府軍を率いて各地を転戦。
官軍をしばしば潰走させて、その存在をおそれられた人物である。
以降、西南戦争、日清戦争と戦歴がある。
戦争をさせれば日本の軍人のなかで随一という定評があり、本人も秘かに自負していた。
その立見と第8師団は、開戦してからは、予備軍として日本国内に拘置されていた。
が、満州における兵力の激減のために、ついに大陸に渡る。
沙河開戦の終わりになってから戦場に到着。
そのまま、もっとも後方で予備軍となっている。
多少の不満で待機していたときの出撃命令だった。
降雪のなかの徹夜の急行軍
師団という大きな単位は、広大な地域に各部隊が散在して宿営している。
集結するのに7、8時間かかる。
その間にも総司令部からの電話や伝令は続いて、命令は二転三転して混乱を示した。
命令を受ける側の立見は、その点は場慣れしている。
「こっちで判断してやるしかない」と師団を動かした。
第8師団は徹夜で急行軍した。
黒溝台に向かっている。
この夜、気温は零下27度である。
風が強く、体感温度は零下35度を超えたであろう。
携行している、にぎり飯と水筒の水は凍ってしまう。
食べることも飲むこともできない。
それに加えて、降雪中の行軍であった。
降り積もったばかりの雪は、靴底に凍りつく。
数歩進んでは、靴底を蹴り叩いて氷を落とすという動作を繰り返さなければならない。
立見は、外套のえりを立てて、帽子を目深にかぶり、ヒゲに凍りつく息を絶えず払いながら進んだ。
ときどき馬から降りて徒歩で進んだのは、馬に乗りっぱなしだと血液の循環がわるくなり、靴の中の足が凍るからだった。
彼の長い戦歴の中でも、最も困難な行軍だったろう。
包囲された第8師団
黒溝台の手前で、事態は急変した。
第8師団は、ほとんど三方から、敵の大軍に包囲された。
師団長の立見には責任はない。
総司令部からは、あまい敵状しか知らされてなかったのである。
ロシア軍からすれば、手薄な日本軍左翼を突破して南下しようと思っていたところへ、突然にして第8師団が出現したため、全力をあげて攻撃を開始したといってもいい。
砲火が、第8師団を包んだ。
「第8師団が立ち往生している」という状況は、総司令部の狼狽を極に達させた。
最新鋭の第8師団が、秋山隊の援護どころか途中で全滅するかもしれない窮地となったのである。
そして、日本軍左翼を進攻しているロシア軍が、それほど分厚い大軍であることを、総司令部ははじめて気がついたのである。
さらに援軍を向かわせた。
中央を守備していた広島の第5師団である。
立見尚文は激を飛ばす
ロシアの大軍に包囲されている第8師団は、刻々と全滅に近づきつつある。
雪にうずもれた民家に、第8師団の司令部は置かれている。
そこには、各部隊からの急報が続いていた。
ある部隊は半分まで死傷。
ある部隊は壊滅。
他は推して知るべしだろう。
この状況で、広島の第5師団の救援をきいた立見は「これほどの恥辱があるかァ!」と怒声を上げて参謀長以下をてこずらせた。
ただちに、各部隊の曹長以上が集められた。
ときに地に伏して、ときには匍匐しながら、彼らは司令部に集まった。
参謀長は、必要な命令、および注意を書きとらせた。
その間にも、砲声が地を震わせている。
参謀長の声が聞き取れなくて、繰り返されもした。
次には立見だった。
その民家にあった衣装箱の上に乗り、激を飛ばした。
「わが弘前師団は長く国内に拘置された。前線に出るのがもっとも遅い。それが今、はじめて敵に見まえて、このていたらくはなんということであるか!」
立見は、伊勢桑名の出身でありながら東北弁であった。
なぜなら、桑名藩松平家は、奥州白河から転封してきた藩で、桑名の士族は奥州ことばだったからである。
「わが弘前師団は、すでに日本一の精強とうたわれながら、これしきの戦いで苦戦するとは何事であるか!」
立見は激を飛ばしながら、足元をドンッと踏みつけた。
「いくさとは、負けぬと思えば負けぬものだ!奥州の健児たるもの、ほかの師団にひけをとるな!」
ついに立見は、衣装箱の蓋を踏み破った。
満州の雪原の戦い
第8師団の兵士は、徹夜の強行軍から3夜の間、一睡もせずに酷寒のなか戦っている。
ある部隊は、小銃のみの装備でありながら、50門以上を擁するロシア軍の砲兵隊と戦う。
地に伏せて、転がりながら小銃を撃っているうちに眠ってしまい、撃たれて目をさまして、反撃の1発を放ってから死んだ兵士もいる。
雪原のなかで、拠るべく地物もない。
砲撃で多くの兵士の体が砕けていく。
死体は、雪原を覆った。
・・・ ちなみに、司馬遼太郎は戦車兵だった。
戦争中の21歳のときに満州へ配属されている。
だからか。
この酷寒の満州の戦いの場面には熱がこもっている。
書きながら興奮しているようだ。
雪原の中で戦う青年の兵士のことを思うと涙が出てくる、と40代になった司馬遼太郎は書いている。
秋山好古の作戦
秋山隊はどうなっているのか?
8000名の部隊に、10万のロシア軍が押し寄せている。
すでに防御線は突破されているが、拠点は残存している。
もう戦術もなにもない。
「逃げない」という意志だけだった。
退却をすれば「騎兵は逃げるのが専門か」と騎兵無用論をいう陸軍幹部の言を許してしまう。
彼の最大な悲痛な点は、進撃を基本とする騎兵旅団が、陣地にもぐりこんで、防御戦で死力を尽くしているところだった。
他の拠点から伝騎がやってきて「馬を無駄死にさせないために後方へ下げたい」と申し出もしてきたが「それはいかん!」と「騎兵は馬のそばで死ぬのじゃ!」と命じている。
今、馬が余分であることを認めればどうなるのか。
騎兵が馬に乗らないのなら、ただの歩兵になるという思いがあった。
第8師団の包囲は解かれた
1月27日の午前8時。
広島の第5師団が付近まで到着したが、救援に向かうどころか、大軍に苦戦をしている。
総司令部は、ようやくロシア軍の意図がわかった。
大軍をもって左翼を突破して、後方へ出て包囲しようとしている。
さらに、右翼を守備している兵力が割られた。
仙台の第2師団、名古屋の第3師団が援軍に向かった。
1月28日の朝。
丸2日経ってから、第8師団の包囲は解かれてきた。
第8師団は、休むことがない。
「黒溝台へ!」を合言葉に進む。
ロシア軍も、黒溝台にこだわった。
戦闘は、5時間に及んだが好転しない。
15時を過ぎてから、第8師団の200名が銃剣突撃をする。
ロシア兵を100余名を斬った。
200名余を捕虜とした。
第8師団は、行軍から3昼夜不眠で、戦闘を繰り返している。
これまでの死傷者は、約7000名。
3分の2の兵力となっていた。
夜襲
深夜2時になってから、立見は夜襲を敢行する。
師団での夜襲は成功例が極めて少なく、通常は行われない。
が、かつての立見が、戊辰戦争で官軍を悩ませのは夜襲においてだった。
飛雪のなかで、大夜襲が開始された。
立見は前線を馬で駆って、兵士を叱咤して進撃する。
激戦のうえ、1部が黒溝台の一端へ取りついた。
明け方の5時ころ、ついにロシア軍の退却を見た。
午前9時30分、黒溝台の奪還が完了した。
黒溝台会戦は、この夜襲をもって終わりを告げた。
朝の太陽が雪の大地を照らす。
散乱している敵味方の死体のために、雪原は見渡す限り血に染まっている。
この大夜襲での第8師団の死傷者は6248名。
うち戦死者は1555名。
埋葬したロシア兵の死体は、7834体を数えた。
両軍とも、ひとつの戦闘における最大の死傷者を出した。
立見尚文の評価
黒溝台の戦いは、日本軍にとっては勝利とはいえない。
いわば防衛の成功だった。
総司令部の作戦の甘さと錯誤を、秋山好古や立見尚文の兵が死力をふるって戦うことによって、常態に戻すことができたというのが正確な表現である。
立見尚文は、旧幕府出身であり、新政府の長薩閥の恩恵に浴することも全くなく、明治陸軍のなかでは孤独な存在だった。
このあと辛労のために病気となる。
戦後になって死去する。
死ぬ前に「俺は黒溝台で死ぬべきところだった。2年も生きてしまった」とよく口にしている。
第8師団の故郷である青森の弘前であっては、帰還した兵士たちによって「あの人がいたから勝てた」と多く語られて、永く軍神として慕われた。
ほかの地方では、ほとんど知られてない。
クロパトキンの満足
最終的に、黒溝台に終結した日本軍は5万3800名。
死傷者の通数は、9324名。
対するロシア軍は10万5100名。
死傷者の通数は、11743名。
なぜ、ロシア軍は、9割の兵力を残しながら退却したのか?
もう1日、戦闘を続けていれば、倍の兵力で日本軍を圧し潰すことは容易であっただろう。
そして当初の作戦とおりに、日本軍の後方に大軍で進攻すれば、総司令部自体が逃げ出さざるを得ない。
さらに作戦とおりに、同時に日本軍の正面から中央をつけば、結果がどうなるかは誰がみても明らかだ。
日露戦争は、この一戦で、ロシア勝利で終了していた。
原因の一端は、総司令官のクロパトキンである。
また、クロパトキンである。
児玉源太郎は、中央の兵力を左翼に移動させたと気がつかれないように、わずかながら偽装攻撃を仕掛けたのだった。
微弱な攻撃ではあったが、クロパトキンの過敏な神経は、みごとに反応した。
「日本軍が中央を衝こうとしている」と進攻する第2軍のグリッペンベルグに退却を命じた。
退却の翌日に、グリッペンベルグは辞職願を書いて帰国。
部下の前では、クロパトキンを罵ってもいる。
このことで、満州ロシア軍は、名実と共にクロパトキンが握り官僚抗争として彼は勝利した。
クロパトキンが、この結果に満足したのは確かである。
マダガスカルのバルチック艦隊

日本に迫っているバルチック艦隊はどうなったのか?
10月15日に、本国のバルト海のリバウ港から出港している。
35隻の大艦隊だ。
巨艦が多数あるために、近道となるスエズ運河は通れない。
大回りのルートで日本に向かっている。
ヨーロッパからアフリカ大陸沿いに航行。
南アフリカの喜望岬で転回。
マダカスカル島の漁港に到着している。
さらには、ロシア黒海艦隊の10隻がスエズ運河経由で合流。
45隻の大艦隊となる。
総乗組員は12000名。
士気は沈滞していた。
マダカスカル島で、2ヵ月も待機していたからだ。
ロシア旅順艦隊が全滅したからだった。
このロシア旅順艦隊と合流して、日本の連合艦隊と決戦するというのが、この大航海にロシア海軍があえて踏み切った理由の唯一のものである。
本国へ引き返すのか、作戦を変更するのか、本国からの命令を待っているうちに2ヶ月が経ったのである。
ロシア帝国の病理

中世そのままの独裁皇帝の専制国家のロシアだった。
官僚の怠慢や無責任も横行していた。
皇帝の気分と、その気分に便乗する側近たちによって南下政策をおこし、ついには日本を戦争へ挑発した。
それでいて、皇帝にも、その側近にも、勝つための計画も準備もなかった。
イギリスのタイムズ紙は、ロシアの政治体質の機能性の低さを、そのように論評をしている。
アメリカ大統領のルーズベルトも「専制国家が勝つはずない!」と日本の勝利に賭けていた。
理由は簡単である。
ロシア帝国は憲法を持たず、国会も持たない。
皇帝の専制政治を、批判も制御もする機関を持たなかった。
独裁体制の共通の心理として、全ての官史や軍人は、目の前の仕事に専念するよりも、背後に恐るべき猛火を感じているのである。
ロジェストウェンスキー航海

バルチック艦隊の遠征は、世界中が注目していた。
これだけの大規模な艦隊の遠征は、史上初だったのである。
率いる総督の名をとって “ ロジェストウェンスキー航海 ” と名付けられた。
そして、ロジェストウェンスキー航海は、途中、途中で国際問題を引き起こしながら進んでいた。
まず、本国を出港してから間もない頃。
「日本の軍艦が現れた」との報告があった。
全艦が警戒態勢をとる。
夜間であった。
もちろん、そんなところに日本の軍艦はいない。
が、緊張のあまりに、操業中のイギリスの漁船に砲撃を加えたのだった。
間違いだと気がついて攻撃を中止したときには、20隻あった漁船のほとんどが沈没していた。
当然、イギリスは猛抗議。
ロシア政府に航海の停止を求めたが、当のバルチック艦隊は大問題になっているのを気にせずに進んでいく。
イギリスの2隻の軍艦が追尾して、交戦も辞さないと、接近するなどして嫌がらせをはじめた。
外交では決着がつかないまま、ロジェストウェンスキー航海は続いている。
日英同盟
イギリスは報復として、航海の妨害をはじめた。
伊藤博文が結んだ日英同盟が働いた。
イギリスとしては、ロシアの南下政策が、植民地のインドに迫るのを早めに牽制しておくための同盟だった。
が、イギリスは、1度交わした同盟は破った前例がなく、履行する国だった。
イギリスは、石炭補給のための寄港を拒否するように、中立国に働きかけたのだった。
中立国としての厳正な態度を守らせようと、日本政府もたびたび申し入れをしていたが、海上王国のイギリスの圧力のほうが効き目があった。
予定していたポルトガルでは入港を拒否。
艦隊は海上補給を強行することになる。
アフリカ大陸のいくつかの港では、ロシアの友好国のフランスの植民地ということもあり拒否はされなかった。
が「本国の許可がでない」とやんわりと断られて、石炭補給は黙認という形で港の近くで行われた。
そのフランスも、満州でのロシア軍の退却が重なるのつれて、植民地への入港を拒否するようになっていく。
マダガスカル島で待機していたバルチック艦隊は、寂れた漁港に停泊していたが、それにはそのような経緯があった。
石炭補給も大問題となった
石炭も、膨大な補給が必要だった。
世界地図を広げて、補給地点を決めてゆかなければならない。
それ自体が世界的規模の大作戦であった。
ドイツの会社が、この石炭補給の一部を請け負っていた。
対抗するイギリスは、その会社へ良質なイギリス産の石炭を売らなくなった。
代わりに、カロリーが低くて煙が多く出るドイツ産の石炭が補給されるようになった。
これが大問題となる。
ロシア政府とドイツの会社の訴訟となる。
その訴訟もラチがあかない。
結局は「現地で解決せよ」とロジェストウェンスキーに丸投げされたのだ。
本来は、外務省や海軍省がやるべきことである。
艦隊を率いる司令長官に仕事と責任まで負わせてしまうのは酷であった。
石炭談判は長引いた。
これも2ヵ月の停泊の一因にもなる。
ロジェストウェインスキーの奇蹟
3月16日。
バルチック艦隊は、日本に向けて出航した。
12000名の乗組員の士気は、大いに上がった。
45隻の大艦隊は縦列で進む。
隊列の長さは10キロに及んだ。
インド洋を一直線に東進する。
すべての艦には、石炭と食料が積めるだけ積み込んである。
技師が転覆のおそれを抱くほどだった。
小型艦は、大型艦にワイヤロープで繋がれて引っ張られて、石炭の消費を抑えている。
極東への途中、1ヵ所も港に寄らず、航行しようとしているのである。
この事態に「ロジェストウェンスキー航海は成功しない」と、各国の海事専門家からも声が上がっていた。
艦船は絶えず故障をおこすものだった。
港を使わないで、それをどのように修理していくのか。
が、大艦隊は、すべてを洋上で行った。
工兵が潜水服を着込んでやるといった具合だった。
・・・ 司馬遼太郎は、クロパトキンもロジェストウェインスキーも “ 愚将 ” として描くが、この大航海については称賛している。
「ロシア人の気宇の大きさを評価すべき」「ロジェストウェインスキーの奇蹟とまでいわれた」「奇蹟にふさわしい」「ロシア人はやってのけた」と興奮を隠さない。
バルチック艦隊が、日本に向かうところで6巻は閉じられる。
以下、7巻に続く。
7巻と8巻の感想文について

7巻では、バルチック艦隊を目撃した沖縄の人々が “ 国家機密 ” を電報で届けようと船を漕ぐ。
ここも泣けてくる。
日本海海戦がはじまる。
東郷平八郎は、連合艦隊の先頭に立って進む。
連合艦隊は、バルチック艦隊を壊滅させる。
秋山真之は、降伏した敵艦に乗り込んでいく。
満州では、奉天会戦がはじまる。
10数万の日本軍に対して、20数万のロシア軍が退却していく。
日本有利で講和条約が結ばれた。
明治38年(1905年)日露戦争は終わる。
8巻では戦後処理に触れる。
そこから一気に時代が下る。
昭和5年(1930年)に秋山好古は71歳で没する。
ラストは、秋山好古の死ぬ間際の言葉になる。
満州で戦っているかようにつぶやきながら死んでいく。
そのように記憶していて、自分にしてはよく覚えているものだから、7巻と8巻の読書感想文は次のノートに書いてあると思っていた。
だけど、次のノートを確めても書いてない。
読書感想文は、6巻までしかなかった。
うむ・・・。
そうだったのか・・・。
しっかり書き忘れている・・・。
後で書こうと思っているうちに、いつの間にか書いたつもりになっていた、ということらしい。
感じ入るところが多い本というのも、読後の余韻に耽りすぎてしまって感想文も書けないものなんだな、と知った読書でもあった。
