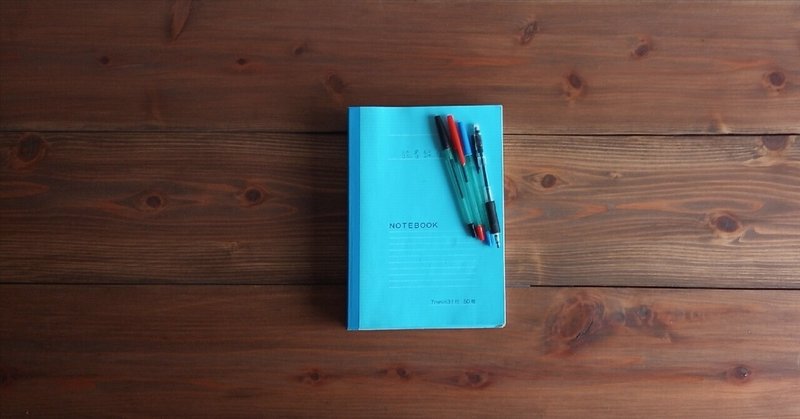
司馬遼太郎「坂の上の雲 5巻」読書感想文
「この本はおすすめです」と、書くのはむずかしい。
なかなかできない。
ベストセラーという本でも、人生必読の書といわれていても、日本中が感動したという本でも、やっぱ “ 合う合わない ” がある。
上記の本が “ 合わない ” と感じることが多々ある自分がいう「おすすめです」は、他人からすれば「おすすめではない」かもしれない。
そこまで自分に自信家じゃない。
それに、そこは趣味の問題。
自分の趣味を「おすすめ」はしたくない。
だから司馬遼太郎だって「おすすめ」はしないけど、どれだけおもしろいかは伝えたい。
それくらいはいいだろう!
ぜひ、読んでみてください
考えてみれば「ぜひ、読んでみてください」とも、今までに1回も書いてない。
いくら大好きな「坂の上の雲」だって、これからも「ぜひ、読んでみてください」と書くこともないと思う。
だって、いつ読む?
全8巻の長編を?
ここは実際の問題であって「ぜひ、読んでみてください」と一言で簡単にいうのは不親切かなと。
社会に生きる人は、あっという間に1日など過ぎてしまう。
読書よりも他にやることだってあるだろうし、考えることだってたくさんある。
期待をさせる分だけ、時間がない人にとっては酷な言い方になる。
それに読書よりも、人間社会での経験のほうが身につくのは確かなようだ。
読書をして、さらに本の解釈に時間をかけたとしても、言われるほど血肉などにはならないと感じるときもある。
所詮は、本は現実を超えられない。
現実のほうがよっぽどおもしろい。
いくら読書してもそう思う。
もっといえば、人と人が擦れ合わさって生じる熱だって、本の中のものは、現実には到底およばない。
読書での追体験なんて知れている。
・・・ だいぶ話が飛んだ。
要は、なにがいいたいのかといいますと「読んでみてください」とは言わないけど、どんな内容かくらいは伝えたいということなのです。
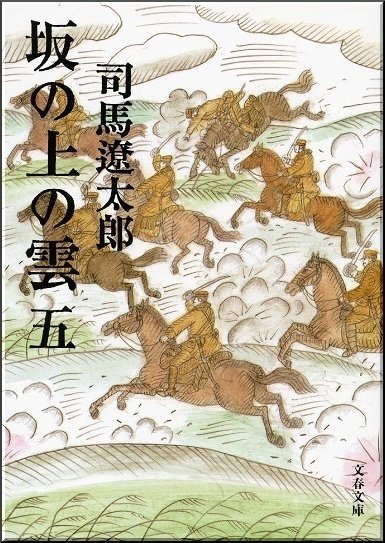
初出:1968年4月 - 1972年8月 産経新聞連載
表紙:安野光雅
203高地への攻撃
明治37年(1904年)11月29日。
日本軍は、旅順を攻撃している。
乃木希典を司令官とする第3軍である。
正面攻撃は失敗している。
ロシア軍の要塞の防御は堅い。
すでに2万人を超える死傷者が出ていた。
“ 203高地 ” を攻める作戦に変更されて、その日、3度目の一斉突撃が行われた。
斜面には、身を隠すものなどない。
猛進する以外にない。
日本兵は砲弾の火柱を抜けて、脚力が続く限り駈ける。
ある部隊は、地雷と機関銃で全滅。
ある部隊は、半数以上が死傷。
203高地の斜面を、日本兵の死体がびっしりと覆う。
その数は、5000とも6000とも推定された。
要塞から機関銃で射撃するロシア兵も必死だった。
恐怖していた。
日本兵は、撃っても撃っても突撃してくる。
死体を乗り越えて、殺されにやってくるのだ。
指揮する将校は「日本兵を人形だとおもえ!」と常に鼓舞して、兵士の恐怖心を除こうとした。
ある砲塁には、日本兵の一群が迫った。
すると、1人のロシア兵が飛び出してきた。
彼は多量の爆薬を背負い、両脇にも爆薬を抱えている。
いずれの爆薬にも、火のついた導火線がある。
彼は日本兵の一群に向かって突進し、自爆することでその猛攻を防いだ。
戦場では狂気が支配していくようになる。
500名が突破した
日本兵は、全滅はしてなかった。
死体に隠れ、匍匐前進していく。
約500名が生き残っていた。
この約500名が呼応して、ロシア軍の歩兵陣地に殺到。
その陣地には1000名のロシア兵がいた。
500名と1000名が、それぞれ銃剣をきらめかして格闘を開始した。
白兵戦を勝利にみちびく要素は、無我夢中の必死さだけしかない。
激闘は30分ばかり続き、ロシア兵が陣地を捨てた。
ここが足がかりとなった。
さらに日本兵は、203高地の山頂を目指して進む。
コンドラチェンコ少将
翌11月30日の22時。
ついに日本軍は、203高地の頂上の砲塁を占拠したのだ。
生き残った者は、100名足らずであった。
香月隊となる。
ロシア軍の前線指揮官のコンドラチェンコ少将は、指揮官を集めた。
203高地奪還の訓示を行う。
「兵は日本軍の突撃を恐れている。恐れさせないためには、日本軍に対し常に先制して、日本軍よりも先に突撃し、また日本軍よりも勇猛に突撃することだ。そのためには連隊長が自ら剣をふるって兵の先頭に立つ必要がある。勝利への方法は確立されている!行動だけが恐怖を忘れさせる!」
ロシア軍の指揮官たちは勇敢だった。
先頭に立って兵を率いて、剣を振り上げて突撃した。
が、日本兵も休むことなく突撃してきた。
深夜の山頂には、たちまち数百の火光がきらめく。
激しい戦闘となった。
わずか30分の間に、両軍の生存者は半数になった。
香月隊は、援軍も来ないまま、夜明けまで戦った。
弾薬も食料の補給がなく、水さえもない。
全滅は時間の問題といえた。
このような状況で、第3軍の参謀長の伊地知幸介は「203高地占領」と満州総司令部に報告の打電をしていた。
児玉源太郎と乃木希典
満州総司令部の総参謀長の児玉源太郎は、北部前線の沙河から、南部前線となる旅順へ向かっていた。
「乃木を更迭せよ」という声は、東京の大本営の一致した意見となっている。
その乃木の元へ向かっているのだった。
が、総参謀長として行くのではない。
総司令官の大山巌の代理という旨の命令書を持参していた。
乃木は、統帥の源泉である天皇から、第3軍に対する統帥権の執行を委ねられた軍総司令官である。
軍隊においては犯罪ともいえる “ 統帥秩序の奔乱 ” というのを形式上は避けるための命令書であった。
乃木の人柄も性格も能力も、児玉はよく知っていた。
同じ長州人同士で、強烈な郷党閥のなかにいる。
維新以降の長い親交もある。
明治10年の西南戦争では共に戦っている。
そのころから乃木は下手な指揮官であったし、今回のような近代戦には不得手なのもわかっている。
しかし、この命令書をかざせば、乃木は恥じて自殺するかもしれない。
でも乃木の窮状をなんとかしなければいけない。
児玉は気を揉みながら旅順へ向かう。
が、途中の停車場で、203高地占領の報を受ける。
児玉は喜んだ。
食事をとるが、まだ戦闘中であると追って知り「メシなど食ってる場合か!」と叫んで、急いで旅順に向かった。
参謀長の伊地知幸介
旅順に到着した児玉は司令部にいき、不正確な報告をした伊地知を罵倒する。
伊地知が軍刀に手をかけたほどだった。
乃木には、体面を傷つけないようにした。
友人として、窮状を変えるために力を借したいと説得して、命令書も使わずに第3軍を指揮する同意を得た。
すぐさま児玉は、作戦の転換に着手する。
まず、司令部が前線から遠すぎる。
現地の状況がつかめてない。
いくもの段階を経た報告で、分析ばかりがされていて、状勢が正確ではなかった。
それを確めるための前線視察も行われていなかった。
原因は伊地知だった。
前線にいけば動揺も生じて、作戦の立案に悪影響がでると、幕僚の前線視察を禁じていたのだ。
「参謀は状況把握のために必要とあれば、敵の砲塁まで乗り込んでいけ!机上の空案のために無益の死を遂げる人間のことを考えてみろ!」と児玉は怒鳴る。
その場で、3名の参謀を前線に向かわせた。
重砲陣地の移動も命じた。
24時間以内に、203高地の正面にだ。
移動が完了したら、昼でも夜でも、15分ごとの援護射撃を加えるようにも命じた。
悲惨な勝利者
翌日。
児玉は司令部の主だった者を連れて前線に出た。
頭上を砲弾が飛んでいく。
伏した児玉は、双眼鏡で203高地の頂上を展望した。
まだ山頂には、香月隊が生き残っていた。
彼らは、司令部から見捨てられたかたちになっても、全滅を覚悟で死守し続けていた。
もはや軍隊という程を成してない。
この残存者は、勝利者には間違いなかったが、どの戦史の勝利者よりも悲惨だった。
「あれを見て、心を動かさぬヤツは人間ではない!」と児玉は怒声で、今までの命令の進捗状況を確めた。
砲科の常識
12月5日、午前9時。
再度の突撃攻撃が開始された。
今度は、砲撃と同時だった。
前進する歩兵の頭上を、友軍の砲弾の傘ができた。
前線にいる児玉は、経過を注視し続けた。
この援護砲撃は、これまでなかった。
最初に敵陣に向けて砲撃してから、次に歩兵が突撃するのが砲科の常識だった。
味方に被弾する可能性があるから、という理由だった。
第3軍の参謀団は、砲科の専門家だった。
要塞の攻撃に対して、砲科の専門家の参謀を多くした人事が裏目に出ていたのだ。
突撃から1時間20分後。
203高地の一角を占拠した。
すぐさま児玉は、砲兵隊の観測班を登らせた。
歩兵の突撃にくっついて、砲兵の観測将校が有線電話を引っぱって駆け上るという戦闘も砲科の常識にはなかった。
旅順ロシア艦隊の壊滅
13時30分。
要塞の一角には、ロシア軍が留まり抵抗していた。
これに対し、銃剣突撃を敢行。
30分で制圧。
203高地の占領がぼ確定した。
が、目的は、203高地の占領ではない。
旅順港のロシア艦隊の撃滅だった。
有線電話が敷かれると、すぐに児玉は確めた。
「旅順港は見下ろせるか!」
「見えます!一望のうちにおさめることができます!」
すぐに旅順港の敵艦の照準が観測されて、伝えられて、児玉は先制砲撃を命じた。
が、砲兵司令官は「不可です」と答えた。
理由としては、砲弾の種類だった。
陸上の榴弾では、軍艦を沈めることができないという。
それに軍艦からの反撃に備えて、砲兵陣地の構築に3日が必要だという。
これらも専門家の意見だった。
「そういのはいくさが終わってからやれ。今はいくさの最中だ」
児玉は殺気立った低い声で、再度の命令をした。
10分後には、砲撃が開始される。
観測が行われた砲撃は、山越えであっても100発100中といっていいほどで、間もなく2隻の軍艦が沈没した。
砲撃は続けられて、2日後までに21隻を撃沈。
ロシア旅順艦隊は壊滅した。
日本軍のほうが優勢に
203高地の陥落で戦形は逆転した。
競争のようにして、ロシア軍の砲塁を陥落させていく。
砲兵が砲撃する。
工兵がコンクリート壁を爆破する。
歩兵が突入する。
要塞で最大の砲塁も陥落すると、退却する陣地が相次いだ。
日本軍は一帯を占領したのだ。
その日、乃木と幕僚たちは、203高地の斜面を登った。
将兵たちの奮闘をねぎらうためだった。
が、児玉は「腹がいたい」と同行はしなかった。
それをやるのは、司令官の乃木であるべきと考えていた。
今回やったことは、悪例を残すと十分に知っていた。
そのまま、北部戦線の司令部へ帰った児玉だった。
・・・ 以下は追記の余談となる。
司馬遼太郎は、乃木希典を “ 愚将 ” と書く。
けっこうな悪意を感じるほど。
でも、乃木希典は人気がある。
赤坂の “ 乃木坂 ” を上がったところに “ 乃木神社 ” があって、以前に偶然に通りかかったときに境内を歩いてみた。
神社の趣味はないからお参りもしなかったけど、よく祀られている雰囲気があって、いい神社だった。
で、江ノ島に “ 児玉神社 ” がある。
エスカーを使わずに、徒歩で坂を上がる途中にある。
そこも何気なしに「なんだろうと?」と境内を歩いてみたけど、寂れていて、味気ない神社だった。
人など来ることがない。
あの “ 児玉神社 ” は、児玉源太郎だったのか?
読書録をキーボードしながら気になって検索してみると、祀られているのは “ 軍神 ” としての児玉源太郎だった。
で、なんと、2021年に所有者により閉鎖されているという。
競売にかけられたという。
不動産会社が落札したという。
一方はアイドルのグループ名に。
一方は閉鎖されて競売に。
諸行無常じゃないかぁ!
旅順ロシア軍降伏
旅順のロシア軍は、降伏を申し入れてきた。
日本軍としては、降伏するとは誰も予想してなかった。
攻撃中止命令が出される。
降伏には、戦時国際法に則って手続きがいる。
その日は、正午から両軍の談判はじまり、それが無事に終了してから休戦命令が出される。
ところが、その日。
まだ正午にもならない夜明けから、ぞろぞろとロシア兵が陣地から出てきた。
休戦になるらしいという歓喜を狂うがごとく全身で表して、抱き合ったり踊ったりしている。
負けてもいい、勝ってもいい。
ともかくこの悲惨な戦いが終わるらしい。
人間としての歓喜の爆発を抑えることができないのだった。
驚くことに日本兵も陣地から出て、両軍の兵士が抱き合うという光景も見られた。
日本兵が敵の陣地である砲塁までのぼっていき、酒を酌み交わしたりもしている。
さらには酔った勢いで、両兵が肩を抱き合いながら、敵地であるはずの旅順市街まで出かけてゆき、酒場に入って、また飲むという光景さえも見られた。
交戦中の段階なので、すべてが軍規違反であった。
しかし、これを止めることができる将校は1人もいない。
しかも、両軍の兵士がこのように戯れながら、1件の事故も喧嘩沙汰もおこらなかった。
昨日まで、死闘を繰り返していた両軍の兵士がである。
このことは、人間というものが、本来は国家から義務づけられることなしに武器をとって殺し合うことに適してないのを証拠だてるものであろう。
旅順における両軍の兵員と死傷者はどうだったのか?
ロシア軍の兵員は、約4万5千人。
負傷者は、1万5千余人。
このうち戦死者は、約3,000人にすぎない。
日本軍は兵員が、約10万人。
死傷者は、6万212人。
このうち戦死者は、1万5千400人余りだった。
クロパトキンの焦り
明治37年、11月。
北部戦線は “ 沙河 ” を挟んで、両軍が陣地を構築して対峙している状態である。
ときには、零下40度まで下がる寒気の中にある。
日本人が経験することのない寒さだった。
銃を持つことさえ困難だった。
素手で持ったものなら、鉄に皮膚が張り付いてしまう。
夜間、歩哨に立つ場合は、絶えず歩き回っていなければ、足が凍傷になるおそれがある。
小便だってすぐに凍ってしまう。
日本軍の防寒服は、粗末なものであった。
ロシア軍みたいに、裏に毛皮がある防寒服などない。
シベリア鉄道の輸送量は増えていた。
欧州ロシア軍からは、1月いっぱいで10万の兵力が送られてくる見通しがあった。
完全主義の総司令官のクロパトキンは、火力と兵力が増えてから、一気に攻勢に出る作戦を立てていた。
が、1月2日に、旅順のロシア軍が降伏。
クロパトキンは、急いで攻撃にでる作戦を立てた。
旅順を陥落させた乃木軍10万の軍が北上して、満州軍と合流して兵力が拮抗するのを懸念したのたっだ。
実際の乃木軍は3万4千人だった。
が、クロパトキンは過大に兵力を見積もっていた。
ミシチェンコの威力偵察
黒溝台の戦いがはじまろうとしていた。
総攻撃に先立ち、ミシチェンコ中将が率いる1万の軍が、威力偵察に出撃する。
威力偵察は攻撃もおこなう。
騎兵部隊が中核となっていて、歩兵と砲兵が協同する機動力がある軍だった。
手薄な日本軍の左翼側を突破してからは、後方にある鉄橋を爆破して、補給拠点も襲撃してから引き返す作戦だった。
明治38年、1月9日。
ミシチェンコ軍は南下した。
中核となるコサック騎兵は、小銃を肩にして長槍を手にしている。
日本軍の斥候は、それを遠望した。
地平線を圧する大騎兵団の林立する槍を、ある者は川の堤防だと、ある者は森林だと、あれこれ言い合っているうちに軍隊だとわかる。
手薄な左翼側で戦闘がはじまった。
が、防衛線を突破したミシチェンコ軍は、すさまじく南下を続ける。
日本軍総司令部は、はじめて後方の補給基地を攻撃しようとしていることに気がつく。
ミシチェンコ軍は、8日間にわたり機動戦を行ってから自軍に引き返した。
永沼挺進隊と長谷川挺進隊
偶然というのが、戦場には星の数ほど散らばっている。
作戦にも偶然が多かった。
ミシチェンコ軍の1万騎が、南下を開始したのは1月9日。
が、同日に、秋山好古の手元からも、同じ目的の騎兵団がロシア軍後方に向けて出発している。
ちょうど流星がすれちがうようであり、もちろん双方は気がついてない。
“ 永沼挺進隊 ” というのが、それであった。
3日後には、第2の “ 長谷川挺進隊 ” が放たれた。
それぞれ、わずか170騎ほどに過ぎない。
しかし、純粋の騎兵のみの部隊というと点が、ミシチェンコ軍との差異がある。
さらには戦果の差異も大きい。
ミシチェンコ軍は、きわめて不徹底だった。
目標だった鉄橋爆破することもなく、補給基地を攻撃することもなく、8日間で作戦を切り上げて自軍へ戻った。
永沼挺進隊は、機動期間は60日余り。
行程は1600キロであった。
その間、補給倉庫の攻撃をして、数倍のコサック騎兵と激闘してこれを破る。
ついに鉄橋の爆破もした。
長谷川挺進隊も、1600キロを機動して敵中突破した。
鉄橋の爆破の機会をうががっていたが、やがて帰還する。
前線から600キロ後方からである。
「そんな作戦が成功するはずがない」と言っていた児玉も、1600キロの行程に驚いていた。
やらかしてばかりのクロパトキン
そして、日本の騎兵隊には “ 馬賊 ” が行動を共にした。
馬賊とは、現地の満州人が結成した自警団である。
清国から見放されて、ロシアに占領された満州では、自衛のために武装して馬に乗る集団が自然発生していたのだった。
同行した馬賊は1000騎に満たない。
しかし、彼らの行動がクロパトキンに報告されたときには「日本軍騎兵1万、馬賊2万、北行中!」という誇大なものになっていた。
クロパトキンは急いだ。
ミシチェンコ軍を1万から3万に増強して、前線から遠い北方に配置した。
これは、のちの奉天会戦の、日本軍の勝因にもつながった。
奉天会戦がはじまったときには、ロシア軍最強であるミシチェンコ軍3万は、すでに敵がいない北方を漂っているだけとなったからだった。
ここまでの戦果は、秋山にも予想ができてなかった。
偉大なミシチェンコ
予期しない戦果は、戦後の講和交渉のときにも生じた。
永沼挺進隊の鉄橋爆破のときだ。
戦闘となって、2名の騎兵が突撃して戦死した。
ロシア軍は、2人の勇敢さに感銘。
丁寧に葬り、墓碑を建てた。
この墓碑が、日本軍が最も進出して占領した地点となった。
当時の戦争法規では、そのように定められていた。
これにより、ロシアから日本への鉄道の割譲は、大幅に前方へ伸長されるという結果になる。
墓碑の高さは、3m60cmもある。
「墓碑を高くせよ」というミシチェンコの命令だった。
これについて、ロシア陸軍省では「ミシチェンコの騎士道趣味のためにロシアは鉄道を失った」と非難する者もいた。
一方では「ミシチェンコの偉大さはそこにあり、鉄道など問題ではない」と弁護する者もいた。
当時の戦争法規といい、ミシチェンコを弁護する者といい、この時代の戦争には愛嬌みたいなものがある、と司馬遼太郎は記して5巻は閉じられる。
