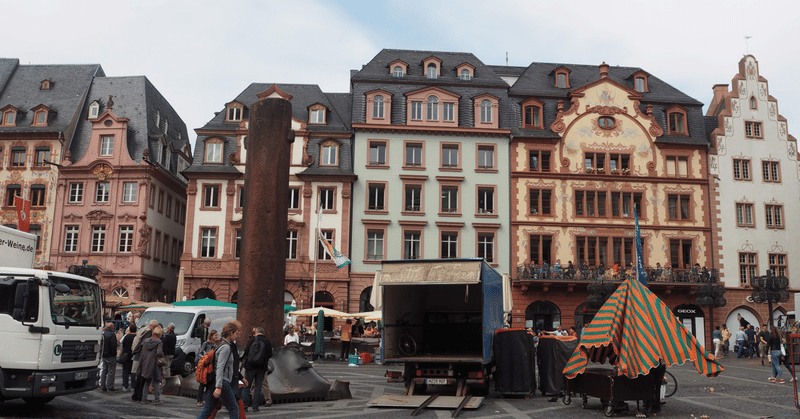
大人のカンニング
よい仕事をする上で、自分ごと化が大事だとはよく言われる。
対象となる課題の解決に、当事者意識をもってコミットできるかということである。
当然、当事者意識を持つためには、対象となる課題についての理解が必要だ。
理解のためには知識がいる。
誰もが知っているように有効な知識の獲得と理解にはそれなりの労力がいる。
つまり、知識の獲得と理解がそもそも課題解決にあたる以前の課題となるわけだ。
だから、実際の仕事に取りかかる前の、知識の獲得と理解というそれなりに労力が必要なことをするという初期課題に対しても、当事者意識は必要になる。
自分の知らないことを知ることが、自分ごととして捉えられるかどうか、だ。
「知らない」ことに向きあう
しかし、自分ごとの範囲を広げることが求められる、知識の獲得や理解のために、自分の関心を外へと向けることができる知的体力が普段からある人は、僕の経験上、そう多くない。
広げなくてはいけないことを意識するには、まず自分が「知らない」ということを認識しなくてはいけない。
だが、この自分が「知らない」ということに気づくだけでもそれなりのハードルがある。
関心の問題だ。
いろんなことに普段から興味をもって、関心のアンテナを張ってないと、自分が「知らない」ということに気づく機会は少なくなる。
いや、自分が「知らない」ということに気づいても、そこで思考停止になる人もいる。
知らないことを知るに変えるためにどうすればいいかわからないということなのか。
知らない対象にちゃんと向きあって、すこしずつでも理解しようとすればいいと思うのだが、知らない対象を前にどうしていいかわからず、立ちすくんでしまう人も少なくない。
というわけで、多くの場合、当事者意識を持つために自分が知らないことにちゃんと向き合えるかどうかが、よい仕事をできるかどうかを左右する、最初のつまずきとなる。
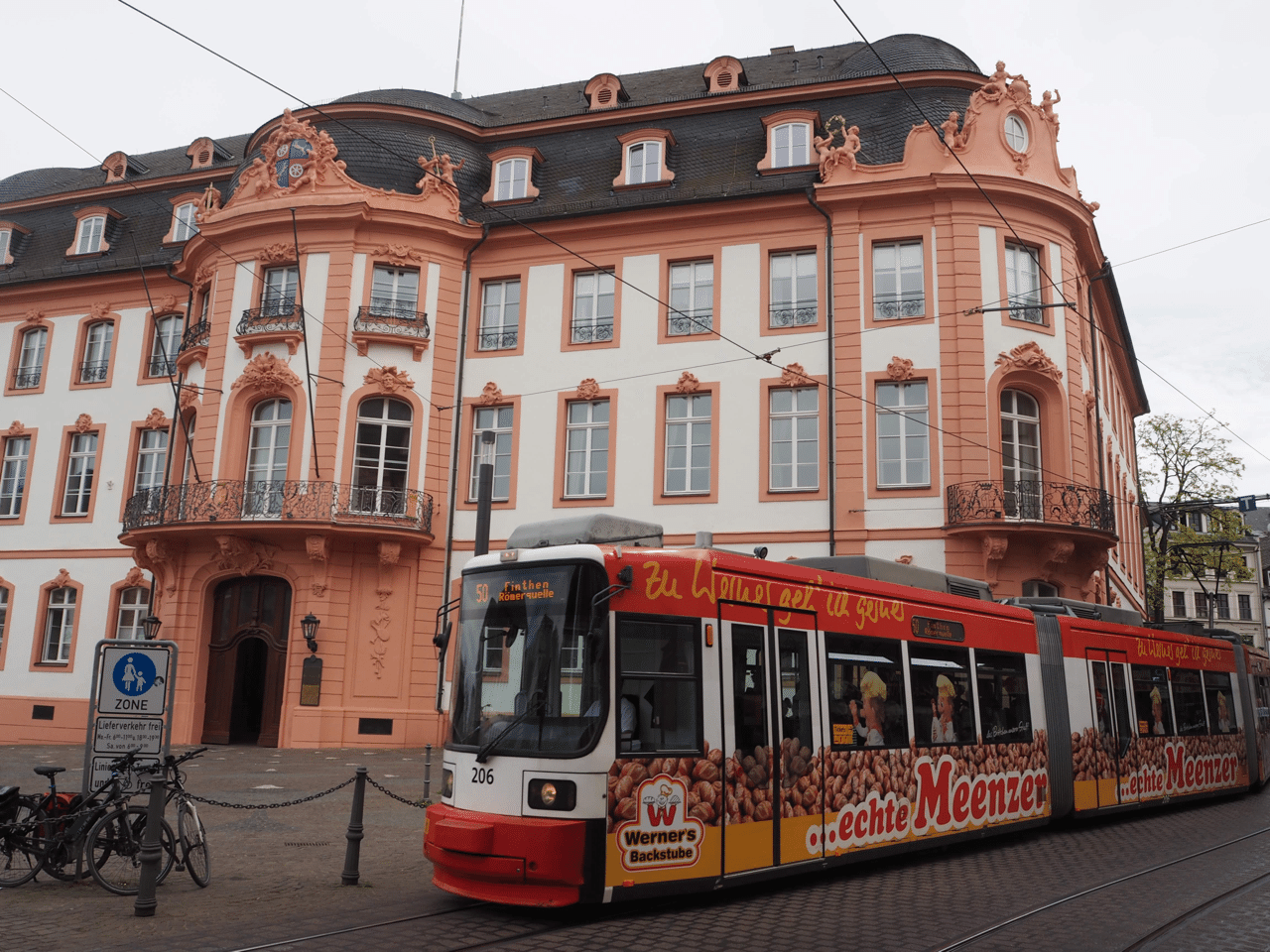
未知の領域に自分を置く
何か新しいものを創造する。
その創造の作業に自分ごととしてどう向きあえばよいかがわからない人がいるようだ。
真っ白な紙になんでもいいから描いてみようというと、どうやって描けばよいか困ってしまうかのように。
何か題材を与えれば、答えの参考になるようなものを探してきて、そのバッタモノのようなものを描いたりはできるんだけど、何かの物真似ではないものを自由な発想で描いてみてというと手がうごかない。
自由に何かを創造するということが、どのように行えばよいかがわからないということか。
とにかく未知の状態が苦手なのだろう。
手っ取り早く答えを教えてほしくなる。
いやいや、それではすこしでも自分ごと化して仕事に当たっていないではないかと思う。
答えを教えてもらって、ただそれをそのままやろうとしているなら、それはただの作業だ。
創造性のかけらもない。
未知に向きあうために、とにかく自分の知識を増やしていき、未知全体を少しずつ知に置き換えていく。
仕事をするというのはそういうことでないだろうか。
すくなくとも新しい価値を生みだして、他人に喜んでもらう仕事とは、そんな風に未知に対して自分ごととして向きあうことからしか生まれないはずである。

当事者意識とは、自分で理解した状態
新しく何かを創造できるようになるということは、創造のために、それが創造される場について自分で理解ができた状態になるということだ。
つまり、その場をコントロール可能になっているからこそ、その場で使えるものを用いて、その場で求められるものを、求められる形で機能し、その場に集う人々がそれを喜んで利用できるような形に組み立てられるということである。
これを、デザインする、と呼ぶのだと思う。
デザインには、それがデザインされる場のコントロール可能性をデザインする人がある程度持っている必要があるということだ。
人々に求められる新しい何かをつくりだすような、よい仕事ができるようになるために、当事者意識が必要で、仕事の対象となるものを自分ごととして理解することが必要なのも、すべてそのためだと思う。
自分でその場をある程度コントロール可能な状態まで理解してはじめて、新しい価値あるものを創造するデザイン作業は可能になるんだと思う。
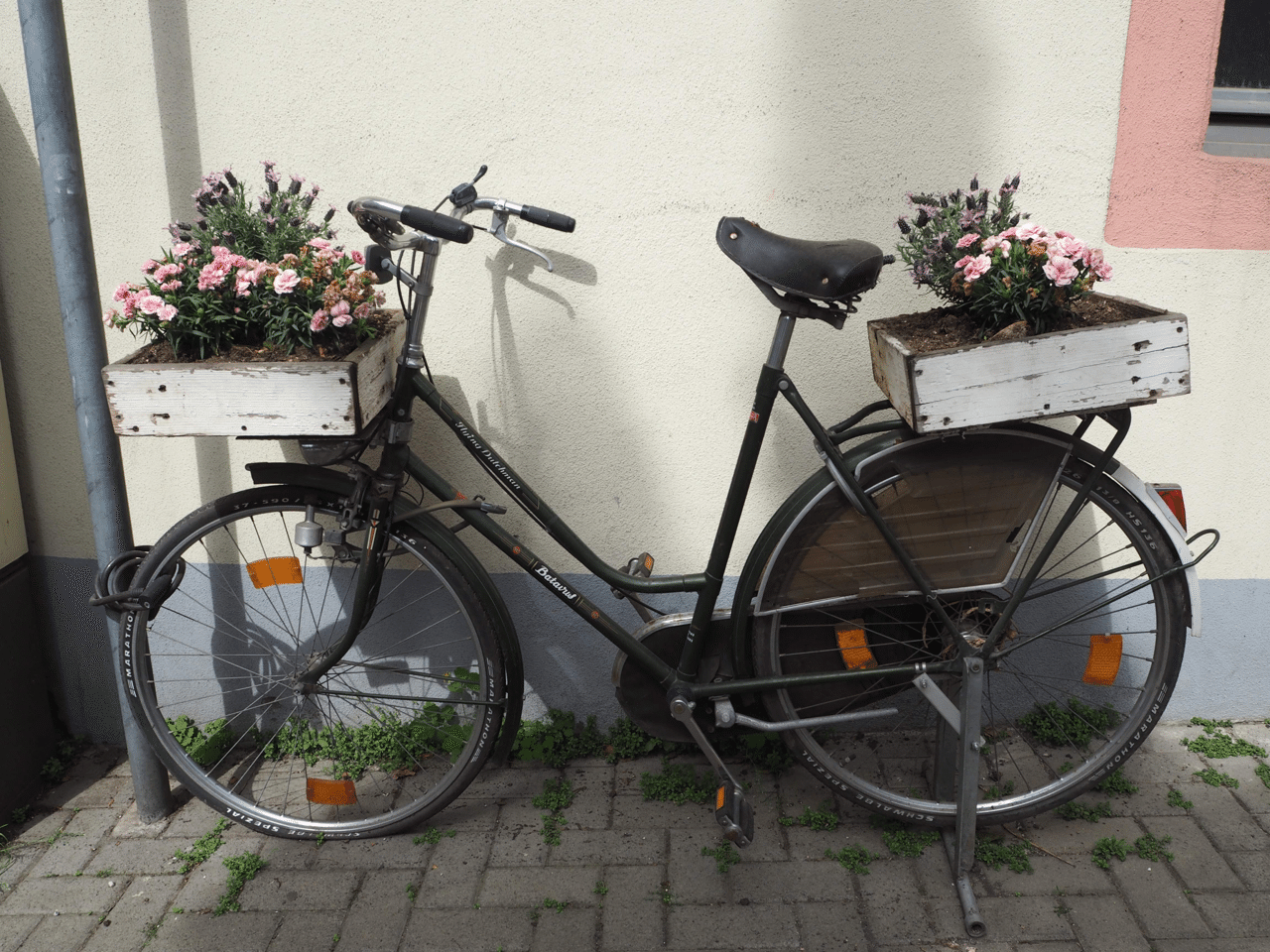
連結材の組み合わせで
ある場をある程度理解してはじめてコントロールが可能になり、新たな解を創造的にデザインができるようになるということに関連することとしては、『社会的なものを組み直す アクターネットワーク理論入門』で、ブリュノ・ラトゥールがこんな風に書いているが参考になるだろうか。
目に見えず、追跡できず、偏在している総体的な力と戦わなければならないのであれば、なすすべはなく、完膚なきまでに打ち負かされるだろう。このことを認めるのに、特別な能力も政治的な見識も必要ない。諸々の力がもっと小さな連結材でできており、その連結材の耐久力を1つずつ試すことができてはじめて、所与の事態を改める可能性が生まれるだろう。
ある意味では、場について理解するということは、その場を構成する分子的な要素として何が存在して、それらが互いにどう連結しているかを、調査を通じて理解するということなのだと思う。
そうであるがゆえに、デザインすることと文化人類学や社会学的な作法は相性がいいのだ。
ラトゥールはこんな風にも書いている。
社会的な結びつきをたどるとき、私たちはどのようなことをしているのか。私たちは、事実上、報告を書き留めているのではないか。
報告(アカウント)とは何か。それは、ほとんどの場合、テクストであり、レーザーで印字された厚さ数ミリの枚数の紙である。
場をコントロール可能にするというのは、結局こういうことだと思う。
場に対するアカウンタビリティーを一定以上、得たとき、はじめてその場はデザイン可能になる。
仕事を施すことができる状態になる。
それはちゃんと報告できるほど、自分ごと化できている状態になるということなんだと思う。

大人のカンニング
社会的なものを組み直したいならば、伝統的に思い描かれてきた社会的な紐帯の循環と定型化を脇に置いて、他の循環する存在を探索することが必要だ。この探索をもっと容易にするために理解すべきことがある。それは、「既に組み合わさった社会的なもの」を、「社会的なものを組み直すこと」と混同すべきでないということであり、そして、私たちが探し求めているものを、社会的な素材で作られた何かしらのもので置き換えないことである。
ラトゥールがここで比較して分類している「既に組み合わさった社会的なもの」と「社会的なものを組み直すこと」の両者のうち、よい仕事をするために当事者意識をもつということと同じものは、後者の「社会的なものを組み直すこと」の方だ。
僕ら人間は神のように、何もないところで何かを創造することはできない。
僕らにできることは「組み直すこと」で新たなものを創造することである。
それは組み直す際の素材はありものを使うけれど、「既に組み合わさった」ものをそのまま使うのとも違う。
それは自分で理解し直すことができないから他人の答えをそのまま使うありかただ。
それはいわゆるカンニングと大して変わらないのに、子供たちのカンニングを咎める大人たちがどうしてカンニングを避けるために、自分で未知に向き合い「理解する」こと、理解をベースに「新たに組み直す」ことができるようになろうとしないのか不思議だ。
カンニングは問題を解くことを自分ごと化しないことだ。
いろいろ調べて集めた素材を元に自分で組み直して答えをつくりだすことをサボることだ。
答えを見つけることに当事者意識をもてる人が増えるといいなと思う。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
