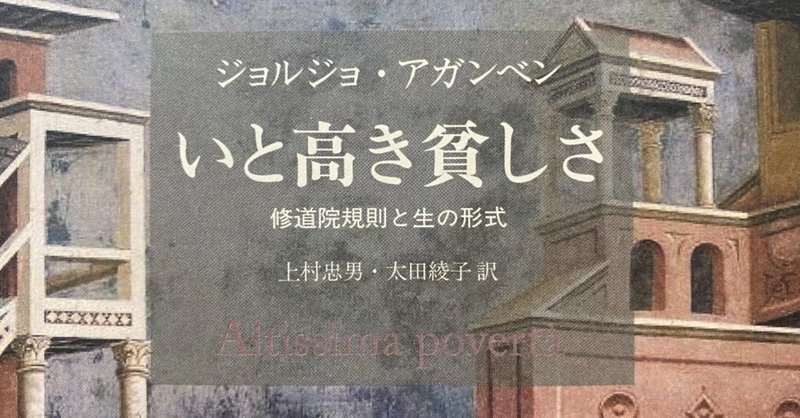
いと高き貧しさ 修道院規則と生の形式/ジョルジョ・アガンベン
サステナビリティに関心をもって、いろいろ本を読んだりしながら本格的に考えはじめたのは、2018年の秋頃だったと思う。
それから期間にすれば2年半、またいだ年を数えれば2018、2019、2020ときて2021年となって4年目に入ったことになる。
当初は主に、気候変動やら生物多様性、あるいはポストヒューマン的なことへの関心が大きかった。
でも、去年あたりからコロナ禍の影響もあって、それ以外の経済格差や各種の差別、移民の問題、専制的な政治体制などの問題に関しても、サステナビリティという観点で興味をもつようになった。
そして、これらがみんなつながった問題であって、具体的な問題として生じている症状だけみて対処療法的な処置をするだけでは足りないことにもこれまで以上に気づくようになった。
残念ながら問題は複雑かつ根本的なものだ。
再生可能エネルギー、電気自動車、人工肉など、新たなテクノロジーを用いて既存の方法を置き換えるような対処療法だけでは、個別な症状の緩和はできても、別の症状が次々に生じてしまうこの危機的状態そのものを良化させることはできそうにない。
そうした対処療法とは同時に、病気になりがちな体質そのものを変えるような改善方法もいっしょに考えないかぎり、ブルーノ・ラトゥールいうところの「移民の増加、格差の爆発、新たな気候体制――実はこれらは同じ1つの脅威である」という状況を脱することはできないだろう。
でも、どうすれば良いのだろう?
何から考えはじめれば良いのだろう?
そんな風に思っていた僕にはとてもタイムリーだった。
ジョルジョ・アガンベンが今回紹介する『いと高き貧しさ 修道院規則と生の形式』の序文に書いている、こんな言葉に出会えたのは。
どちらにしろ、フランシスカニズムのおそらくもっとも大切な遺産は十分に汲み尽くされることはなかった。しかし、そうした遺産は、後回しにできない課題としてつねに新たに西洋が向き合わなければならなくなるものなのだ。〈生の形式〉、すなわち、法権利の獲得から完全に解放された人間的な生のあり方や、所有となって実体化されることのない物と世界の使用のあり方を考えることはどのようにすれば可能か、というのがそれである。
こうした課題から今後必要とされるのは、使用の理論を練りあげることである。西洋哲学にはそれに関するもっとも基本的な原理さえ存在しないのだ。
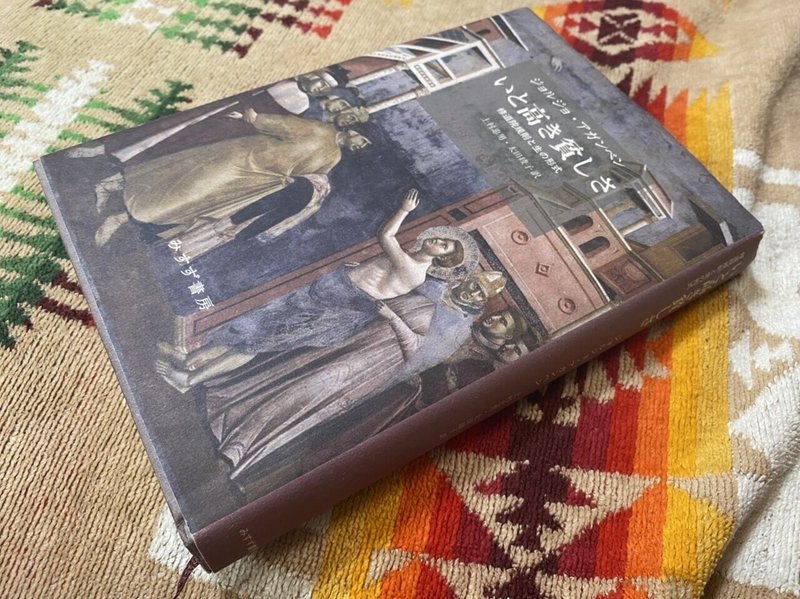
使用と所有
使用の理論。
気候変動にしろ、経済格差にしろ、移民の問題にしろ、ようするに財の使用が関わっていることは間違いない。
そして、使用が問題になるのは、そこに所有の問題がつねに絡んでくるからだ。
国有、私企業や超富裕層による占有。
持つ者と持たざる者。
誰もが生きていく上で必要な財に使用のためにアクセスすることが妨げられる状況が生まれやすいのも、所有の問題が絡むからだろう。
所有と法権利のつながりとその主体、そして、その主体によってときには暴力行使や搾取が行われる際に影響を受けうる人たちが、生きるための財の使用をどう捉えるのかという問題を考えてみることなく、現在のサステナビリティの問題に深く入りこむことはできない。
だから、この本でテーマとされる〈生の形式〉、特に、その形式に新たな画期的な視点を付け加えたヨーロッパ中世のフランシスコ会のキリストに倣った「所有をしない」という〈生の形式〉に着目するアガンベンの論をとても興味深く読んだ。
いと高き貧しさ
"vivere sine proprio"
「自分のものはなにひとつ所有することなく生きること」。
13世紀のアッシジのフランチェスコによって創設されたフランシスコ修道会における『未裁可会則』(1221年)の第1条では「規則および生」として、そのような記述があるという。
「われらの主イエス・キリストの[……]足跡をたどること」を「規則および生」として述べる創設者フランチェスコが「たどる」ことを望んだキリストの足跡というのが「自分のものはなにひとつ所有することなく生きること」だというのである。
この本の表紙には、イタリアのアッシジにある聖フランチェスコ大聖堂のフレスコ画「世俗の富の放棄」が使われている。

裕福な毛織物商の家に生まれたフランチェスコが回心したのち、家の商材を親に断りもなく売り捌いてそのお金を近隣の教会の修復のために司祭に渡してしまったことで、父親と口論となり、彼はアッシジ司教の前で服を脱いで裸となって「すべてお返しします」として衣服を父に差し出した様子を描いたものだ。
これが「世俗の富の放棄」である。フランチェスコはこのとき、キリストに倣って、財の所有を放棄した貧しさを受け入れる生き方=〈生の形式〉を選んだのだ。
そして、この本のタイトル「いと高き貧しさ」ということばは、そんなフランチェスコが創始したフランシスコ会の支柱となるものでもある。
法権利の放棄
フランチェスコがこのとき放棄したのは、裕福な商人である父の商品としての衣服に象徴される世俗の富だけではない。
これを機にフランチェスコは実の父と親子の縁を切り、彼にとっての父は「天の父」だけとなったし、何より富を所有するという法的な権利そのものを放棄した。
彼らフランシスコ会士たちにとって最初から最後まで不変のままでありつづけており、交渉の余地のなかった原則は、次のように要約できる。修道会にとっても、また創設者にとっても、問題であったのは"abdicatio omnis iuris"〔あらゆる法権利の放棄〕、すなわち、法権利の外において人間として生存していくことの可能性であった。
アガンベンが序文において、「〈生の形式〉、すなわち、法権利の獲得から完全に解放された人間的な生のあり方や、所有となって実体化されることのない物と世界の使用のあり方を考えることはどのようにすれば可能か」と書いて重要視したフランシスコ会の「遺産」こそがこれである。
この法権利、とくに財の所有に関する権利と、それと切り離された「物と世界の使用のあり方」の可能性に、現代のサステナビリティの問題を解く鍵があるのではないかと思う。
フランシスコ会の失敗
しかし、残念ながらことはそれほど単純ではない。
フランシスコ会は、自分たちの「法権利の放棄」という権利を守ろうとするために、徐々に法権利との関係へと巻き込まれていったからだ。
フランシスコ会士たちは、物の所有は放棄したが、生きるために必要な財の使用は放棄しなかった。
アガンベンはここにフランカシニズムの革新性をみてとっている。
ボナグラーツィアの言によると、「馬は事実上の使用をしながらも、自分が食する燕麦の所有権は持たないように、あらゆる所有権を放棄した修道士は、パン、ワイン、衣服の単純な事実上の使用をしている」のである。すなわち、ここでわたしたちに関心のある見方から言うなら、フランカシニズムは絶対的に法権利の諸規定の外にあって人間としての生活と実践を実現しようとする試みと定義することができるのである。そしてここにこそ、今日でもいまだに考察されておらず、社会の現状のもとではまったく考察不可能な、その斬新さはあるのだった。法権利によっては達成できないこの生を〈生の形式〉と呼ぶならば、"forma vitae"という連辞はフランシスカニズムのもっとも本来的な意図を表明しているということができる。
所有と使用を分け、そのことで生きるために最低限必要な財の使用は放棄せずにいる生き方。フランシスコ修道会の会士たちが実践した〈生の形式〉がそれである。
食べ物や衣服、そして、聖書などの書物など。会士たちは日々「いと高き貧しさ」という最低限の生活において必要な財の使用の放棄はしなかった。
いや、使用の放棄はできない、というのが彼らの主張だった。
パリの世俗の教師たちによる托鉢修道会への攻撃に答えて1269年に書かれた『貧しき者たちの弁明』で、ボナヴェントゥーラはこの世の財物への4つの可能な関係を区別している。所有権、取得権、用益権、単純な使用である(「この世の財物については4つを考慮すべきである。すなわち、所有権、取得権、用益権、単純な使用である」11.5)。これらのうち、使用だけが人々の生な必須であるため、放棄しえない(「そして前の3者はなくても生きていけるが、最後のものだけは生きていくのに必要不可欠である。この世の財物の使用を放棄するとは、まったくのところ、とても公言できたものではないのだ」)。
この主張は、いったんはローマの教皇庁でも認められていた。
しかし、14世紀に入り、教皇そのものがローマからフランスのアヴィニョンに強引に移されると(アヴィニョン捕囚)、事態は変わる。
ヨハネス22世が1322年の勅書『アド・コンディトーレム・カノヌム〔カノンの起草者へ〕』で「物の所有もひくは支配から切り離して、使用権や事実上の使用を設立したり保持したりすることはできない」として、使用は所有と不可分であり、よって修道会が使用している財産の共同所有を認めてしまったことで、フランシスコ会の法権利の放棄という前提も崩れてしまう。
形式にしたがって生きること
アガンベンは、この失敗を、フランシスコ会の理論家たちが「法権利との関係で貧しさを定義しようとしたものであった」ことに起因するものだと指摘している。
そうであったがために、フランシスコ会士たちの主張は「諸刃の剣となり、ヨハネス22世によってほかでもない法権利の名においてしかけれる決定的な攻撃への道を開くこととなった」のだという。
そして、アガンベンはいう。
この観点からは、フランチェスコが彼の"vivere sine proprio"が法的概念に分節化されるのを拒否してまったく無限定のままにしておいたのは彼の後継者たちよりも先見の明があったということができる。しかしまた、琺瑯修道士の小さなグループ(当初、フランシスコ会士たちはそのような存在だった)であれば許された"novitas vitae"〔生の新しさ/新しい生き方〕は、大勢の修道士からなる強力な修道会にとっては受け入れがたいものであったのも真実である。
"vivere sine proprio"〔自分のものとして所有するのとなしに生きること〕。
このフランチェスコの曖昧な概念に一貫性と正当性をもたせようとしたがために、使用"usus"を法権利の放棄という一覧の行為の実践に閉じ込めようとしてしまったことに、法権利の主権者側につけ入る隙を与えてしまったことをアガンベンは指摘したうえで、こんな可能性について述べている。
それを小さき兄弟たちの生の形式との感覚のなかで思考しようと試み、どのようにすればそれらの行為が"vivere secundum formam"〔形式に従って生きること〕となり、身についた振る舞いになりうるのかを問うほうが、はるかに実り多かったはずである。
もちろん、ここでいう"vivere secundum formam"〔形式に従って生きること〕は、法権利にしたがって生きることとは違う。フランシスコ会をはじめとする中世の修道院、修道会はそれぞれに会則、規則をもったが、それが法的なものと異なることもアガンベンはこの本で丁寧に考察している。
中世の修道院における規則は、文字通り生そのものと切り離すことのできない〈生の形式〉であり、生き方そのものだったのだから。規則に従うというよりも、求める生き方そのもの、そして日々の生活で実行される〈生の形式〉そのものが書かれたのが中世の修道院の会則であったのだ。
その意味において、〈生の形式〉を各自がみずから追求できている限りにおいて、法権利に縛られることなく、みずからの生を自治できていることになるのではないだろうか。
そして、さらにそれによって、そのための財へのアクセス=使用を所有関係に縛られることなくできる可能性が生じるのではないかと思う。
そして、その意味において、使用"usus"はまた別の可能性を切り開く可能性を持っていたとアガンベンは指摘する。
使用は、法権利と生、そして潜勢力と現勢力に対して、第3の要素として姿を現し、修道士たちの生の実践そのもの、彼らの〈生の形式〉を――否定的にだけでなく――定義することができたに違いないのだった。
と。
《ホモ・サケル》シリーズ
しかし、この可能性については、この本では具体的には語られていない。
序文ですでに「こうした課題から今後必要とされるのは、使用の理論を練りあげることである」としながら、アガンベンは「それについては、《ホモ・サケル》シリーズの最終巻で述べることにしたい」と書いているからだ。
そう、この本は昨年紹介した「ホモ・サケル」シリーズの1冊だ。
そして、『ホモ・サケル』をシリーズ第1巻として、計9冊、4巻から構成されるシリーズにおいて、この『いと高き貧しさ』は4巻の1にあたり、次の『身体の使用』が4巻の2であり、シリーズ最終巻となる。もちろん、すでに購入済みで、この本と同時に書かれたという第2巻の5にあたる『オプス・デイ』も面白そうなので、読んでいる途中に購入した。
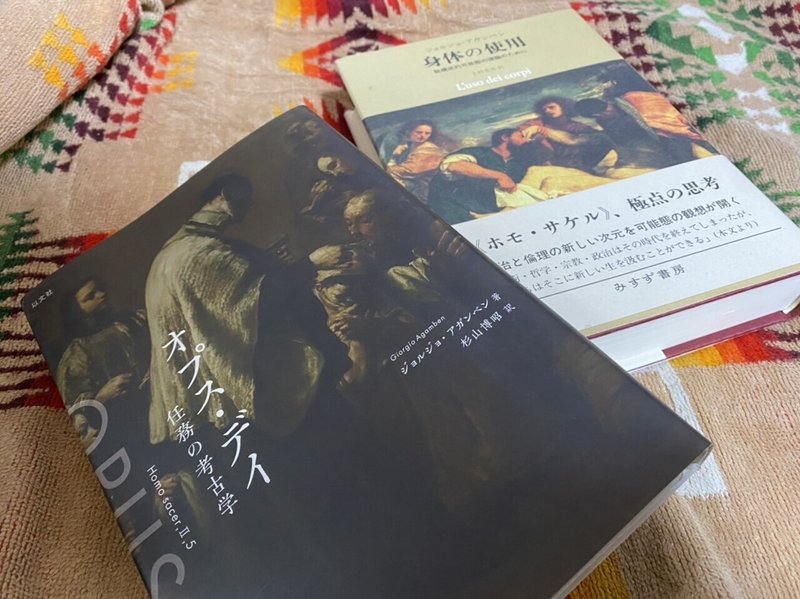
いや、それだけでなく、ひそかにシリーズで邦訳のない2巻の3以外を読破することを2021年の目標にしたいとも思う。
そのくらい、大事なことがこのシリーズでは展開されているように感じた。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
