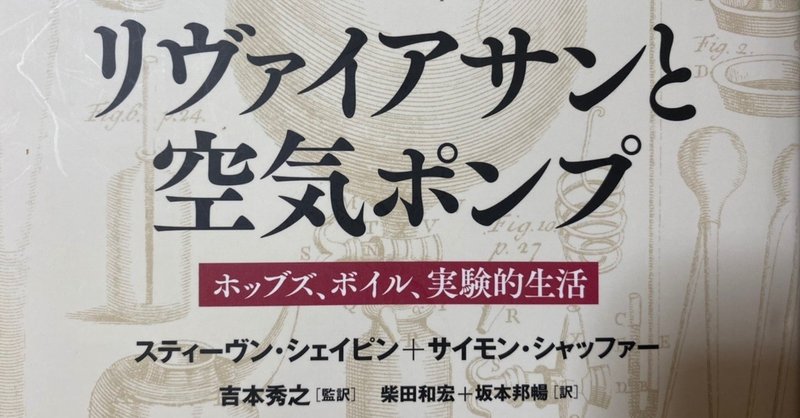
リヴァイアサンと空気ポンプ/スティーヴン・シェイピン+サイモン・シャッファー
きっとほとんどの人が意外なことと感じるだろうが、英語における"fact"という言葉がいまのように「事実」という意味で用いられるようになったのは、実はたかだか17世紀中頃のことにすぎない。
それまでの"fact"は「つくられたもの」という意味をもつ言葉で、いまでも"artifact"とか"factory"などにその名残はみられる。
だが、どういうわけで「つくられたもの」という意味の"fact"が、むしろその反対のような「事実」という意味をまとうようになったのだろう。
その答えは、今回紹介する『リヴァイアサンと空気ポンプ』という本のなかに見つかる。
そして、読み進めるうちに、それは現在のさまざまなコミュニティ間の分断〜内線状態の一因であることがわかってきて、心が落ち着かなくなる。
問題の根の深さに気づくからだ。
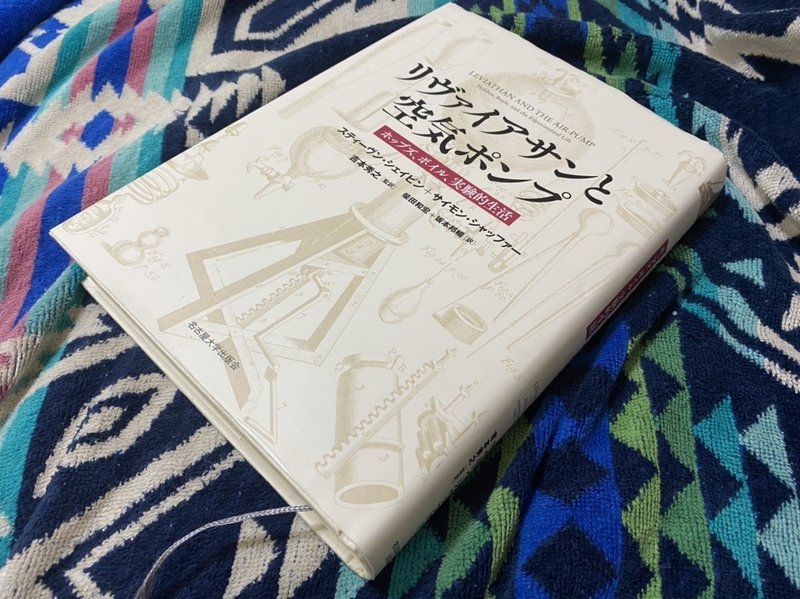
この本は、スティーヴン・シェイピン、サイモン・シャッファーという2人の科学史家によって1985年に出版された、空気の体積と圧力の関係を示したボイルの法則で知られるロバート・ボイルの空気ポンプをもちいた実験を中心に、17世紀後半の王政復古の時代における実験科学という知的生産の方法の成立をめぐる考察が繰り広げられた一冊だ。
僕は、ブルーノ・ラトゥールが『虚構の「近代」』での近代における人間の文化と自然とのあいだの偽りの分断の議論をこの本からはじめていたのを読んだときから、いつか読みたいと思っていた。
この偽りの分断がもとで環境における持続可能性の問題も、格差の問題や移民の問題も生じているからだ。この生命に危機すら及ぼしそうな分断がどういう経緯で生じたのかを知りたかった。
そうした現代の問題につながる一因が、この時代における実験科学の成立も含んだ、社会における新しい知の生産方法の確立というプロジェクトの実行がある。
そのプロジェクトに意義を唱え続けたのがホッブズである。あの『リヴァイアサン』の。
そして、この実験科学的方法の確立をめぐるこの時代の取り組みのなかにこそ、事実というものの意味の大きな変更が関わっているのだ。事実というものをいまのような意味にするために失われたものがたくさんあるのだ。ホッブズはその喪失に警鐘を鳴らし続けた。
ファクトフルネスが重視され、フェイクニュースが問題になり、かつ世界の様相を一変させたパンデミックが社会におけるさまざまな意味=価値を書き換え揺さぶるさまを鑑みても、あらためて事実とは何か?を問い直さなくてはいけないいまだからこそ、まさに必読だと感じた一冊なのだ。
社会的な同意を保証するにはどうすればよいか?
著者の2人も「事実ほどに所与のものはない」と書いている。
そして、こう続けている。
日常の会話においても、科学哲学においても、事実が強固で永続的であるのは、それがあらわれるさいに人間が関与していないからだとされる。人間は理論と解釈を生みだす。人間はそれゆえそれらを壊してもかまわない。しかし事実はまったくの「自然の鑑」であるとみなされる。
そう。事実は「それがあらわれるさいに人間が関与しない」。だから、事実は自然をありのままに映しだした鑑であると。僕らもだいたい、そう感じている。
しかし、その事実="fact"がこの本の考察対象となっている17世紀のなかばまでは「つくられたもの」をあらわす言葉だったのだという。
それがなぜ、この王政復古の17世紀の中頃になって、自然をありのままに映す鑑のような観念へと変化したのだろうか。
これは王政復古という時代にポイントがある。
「王政復古体制の危機によって、同意を保証する方法の提起がきわめて切迫した課題となっていた」と著者らはいう。同意を保証する方法が失われた時代こそが王政復古の時代だったわけである。
この本で扱われている時代の20年ほど前、クロムウェルらの清教徒革命によって、それまでの王の権威は否定された。その後、クロムウェルの存命中は彼を中心に新しい秩序=共和制はしばらく維持されたが、クロムウェルの死後、それは続かなかった。
そこで社会の秩序を維持する方法として、王政を復活させることになったが、とはいえ、一度破棄したシステムである。前のまま、リブートすれば良いものではない。何によって社会を束ねるのか、束ねるための臣民の合意をいかに得るのか、得られたと保証するのかが問題となっていたわけである。
内戦や共和制の経験は、論争中の知識が国家の内部での衝突を生みだすことをしめしていた。そもそもある形式の知識によって社会的な調和を生みだしうるということ自体、まったく自明ではないように思われた。
かつて信じていたものはいったん反故にされたし、内戦によって何が正しく何を信じればよいかわからなくなっま状況だったのだ。正しい知を新たに生みだす方法、そして、その知を正しいものだと合意し保証する方法が求められていたのである。
実験を通じて事実をつくる
同意を保証する方法が問題であるのは、まさにこの分断されたいまの状況も同じだと感じる。
議論をしようにもあまりに社会が分断されすぎてるし、信頼にたる権威もないから、同意をつくりあげるのがきわめて困難だ。何より何のために同意が必要なのかという社会的同意がない。
ホッブズは「公共の平和を確立することが哲学者の仕事」だと考えていたというが、僕らはその「公共の平和の確立」を目指すことすら同意できていない。各自が自分都合でSNSに良い悪いを主張するきわめて利己的な振る舞いだけが蔓延している。レビュー文化といえば聞こえはいいが、単に目的も持たずにそれぞれ自分視点で不満を言い募るだけの状態である。それでは社会に良いものが生まれ育つはずもない。
僕らもまた、王政復古の時代の人びとと同じように、新たに同意をつくりだす方法をつくりださなくてはならない状況に置かれているのだと思いながら、読み進めた。
王政復古体制は、無政府状態への逆戻りをふせぐ方法に関心を集中させており、そのために知識の生産と普及に規律を課そうとしていた。これらの政治的な配慮が、競合する自然哲学プログラムの評価を左右していたのである。
無政府状態になるのを防ぐために、知識の生産と普及に規律が必要とされる。そのことは政府がほとんど機能しているようにはみえない現在の状況をみてもわかる。
社会的な合意形成につなげるための規律がなくては、いくら新たに知識を生産しても、それはうまく流通しない、普及しないからだ。
だから、新たな知の創出には、その知を社会的な合意を得ながら普及させる仕組みがセットで必要になる。
当時のそうした社会的、政治的な背景をもちつつ、この新たな知の同意を保証する方法として、ボイルをはじめとする英国王立協会の科学者たちが確立したのが、実験を通じて得た事実によって仮説を裏づけるという方法だったわけだ。
ロバート・ボイルは実験によって生みだされた事実によって同意を確保しようとした。事実は確実であり、それ以外の知識は確実性においてはるかに劣るものであった。この点でボイルは、17世紀イングランドで知識をめぐって展開された運動のなかでもっとも重要な一人であった。
著者らはボイルが展開した実験という方法をこのような形で評価する。同意を確保する方法として、実験によって事実を生みだすのが、ボイルらがこの時代に確立した方法である。
ゆえに、事実とは、自然とそこにあるものではなかった。それはつくらなくてはいけないものだったのだ。
事実とは、ある人が実際に経験し、自分自身にたいしてその経験の信頼性を請けあい、他の人びとに、彼らがその経験を信じることには十分な根拠があると保証するというプロセスの結果としてえられるものであった。
事実をつくるプロセスをデザインする
このプロセスをボイルらはデザインしたのだ。
それが同意を保証するのに十分な根拠となるよう、事実がちゃんと経験、目撃されるよう、ボイルらは実験のプロセス全体をデザインしたのだ。
このプロセスのうちで根本的だったのが、目撃経験を増加させることであった。経験は、たとえそれが厳密に制御された実験の実施であったとしても、目撃者が一人しかいなければ事実をつくりだすには不十分であった。もし経験がおおくの人間に拡張されたならば、そして原則的にいってすべての人間に拡張されたならば、そのとき結果は事実となりえた。
当然、すべての人に実験を経験してもらうこと、その過程や結果を目撃してもらうことはできない。
だから、できるだけ複数の信頼できる人に実験を経験してもらうことや、実験のプロセスや結果をレポートして間接的に多くの人が実験に触れることができるようにする必要があった。

つまり、経験は、経験する人びとそれぞれの認識論的な課題であるのと同時に、そうした経験にいかに多くの人びとに触れてもらえるようにし社会的な合意を形成できるかという課題でもあったわけである。
このため経験は認識論的なカテゴリーであると同時に、社会的なカテゴリーでもあるとみなされねばならない。実験的知識の基礎をなす要素、また適切に基礎づけられていると考えられた知識一般の基礎をなす要素は、人為的につくられたものであった。それらをつくっていたのはコミュニケーションと、コミュニケーションを維持しその質を高めるために不可欠だと考えられたあらゆる種類の社会形式だった。
ようするに、ボイルらは単に空気ポンプを用いた実験を行っただけではない。実験を核にして、そこで起こることを経験して事実化するためには、どのようなコミュニケーションシステムが必要かをデザインしたのだ。
このデザインがうまくなされてはじめて、合意の保証となる事実はつくられるのだった。
事実をつくる空気ポンプ
この実験を行うのに欠かせなかったのが、人びとの経験や目撃を通じて事実となるための出来事が起こる仕掛け=実験器具としての空気ポンプである。空気ポンプがなければ、ボイルがみずからの仮説――空気には重さとバネがある――を確かなものとして合意を得るために必要な事実はつくりだせなかった。

その意味では、事実をつくるためには、先のような目撃や経験を増やすためのコミュニケーションデザインが必要であったのと同時に、物理的に事実のもとをつくりだしてくれる物理的な実験器具=空気ポンプが必要だったのだ。
それゆえ、空気ポンプはつくりだそうとしている事実がちゃんと生みだせるよう正確に機能することが求められた。特に、ちゃんと空気を漏らさずにすることである。
おもな難題のひとつに、漏れの問題があった。ポンプ、ないしは受容器に、空気の通り道が数おおくあるかもしれず、そこをとおって外部の空気が入りこまないよう細心の注意をはらわねばならなかった。これはけっして瑣末でたんなる技術的な問題あるというわけではなかった。事実を生みだすというポンプの能力は、機械の物理的な完全性に決定的にかかっていた。より正確にいうなら、いかなる実践上の目的にてらしあわせても機械は空気の侵入を防いでいると、集合的な同意がえられているという点にかかっていた。
事実を保証するのは、信頼に値する人びとがそれを目撃、体験することとともに、もうひとつ、事実として捉えられる出来事を生みだす機器が実験者たちが企図したとおり、機能することだった。正確に動く機器だけが事実を生成することができたわけである。
ボイルとともに、王立協会フェローとして、実験科学の成立に貢献し、1665年に発表された、自作の顕微鏡を使った観察記録『顕微鏡図譜』でも知られるロバート・フックは、こう考えていた。
フックの考えでは、おこなうべきは人間の感覚の「弱さ」を、「器具によって、あるいはこういってよければ自然の器官に人工の器具をつけ加えることによって」治療することであった。その目的は「感覚の支配領域の拡張」だった。感覚のうちでは視覚が他に優先していた。しかし「おおくの機械的な発明が私たちの他の感覚、すなわち聴覚、嗅覚、味覚、触覚を改善しうると考えるのは不適切なことではない」。
機械こそが非力な人間の感覚を拡張し、機械なしでは得られない事実を人間に経験させることが可能である。マクルーハンの「人間の拡張」というコンセプトを300年ほど先取りしたフックの見識である。
ここで僕らが思い当たるのは、現代において、たくさんの正確なデータを生成できる機器類が日々大量に生成するビッグデータと、そのデータをもとにさまざまな判断を生成するAIだ。
このビッグデータとAIによって、人間の生活に影響を与える判断が行えるようになる前提には、この17世紀の実験科学の成立と同時に所与のものとなった、正確に機能する機器こそが間違いのない事実を得るためには欠かせないものであり、それこそが個々の人間の独断を排するものであるという認識の社会的な合意であったはずである。
いまは事実の生成のみならず、さらに解釈の部分すら、人間を排除して機器に行わせる方向に進んでいる。そのことで属人的な独断を回避しているのが、ビッグデータ+AIによる判断なのだろう。
ボイルとその友人にとっては、才知は称賛されるべきであったし機械によって生みだされた知識は価値あるものとみなされるべきであった。
それが可能になったのも、この17世紀の半ばにボイルやフックら王立協会フェローたちが、実験機器と目撃者たちの組み合わせによる事実の生成と、その事実こそが社会的な合意の保証となるような知識生成の仕組みをデザインし、機能するようにしたからなのだ。
閉ざされたコミュニティ
しかし、この王立協会の実験科学者たちによる新しい知識の生成の方法に対して、真っ向から異議を唱えたのがホッブズである。
彼はまさに、実験科学者たちによる目撃と空気ポンプという機器の正確さという、事実をつくるための2つのポイントを的確に攻撃した。
まずホッブズは「信念や意見は諸個人に属するもなのであって、そうであるがゆえに、公共の秩序のための基礎へと仕立てあげることのできないもの」と考えていた。ゆえに「ホッブズは個人、その個人がもつ信頼性できない感覚の経験、または個人の信念というカテゴリーを避けようと」していた。
信念と意見は個々の人びとに属しており、その人の信念や関心の影響を受けるので、それらは社会的秩序の枠組みを構築する基礎としてはあまりにも変化しすぎて役に立たないのであった。
これらの根拠にもとづいてホッブズは信念をふるまいや理性とは対照的なものとみなした。ふるまいと理性の両者は公的な領域に属していた。
公的な秩序は、公的なものに属する「ふるまいと理性」からつくられるべきだとホッブズは考えていた。私的な領域に属する、個々の人びとの信念や意見は公的な秩序の基盤とするには相応しくなかった。
だからこそ、ホッブズは、ボイルらの実験プログラムがもつ、以下のような性質を否定したのである。
もしだれかが権威をもつ実験的知識(すなわち事実)を生みだしたければ、その人はこの空間にやってきて、他の人びととともにそこで働かねばならなかった。もしだれかがそれらの機械がつくりだす新しい現象を見たければ、その人はその空間に来て、現象を他の人びとといっしょに見なければならなかった。それらの現象はどこででも見られるものではまったくなかった。したがって実験室は規律づけられた空間だったのだ。そこでは有能なメンバーたちが、実験上の、言語上の、そして社会上の実践を集合的に制御していた。
事実は、実際に実験室に来る人たちによってつくられていた。その空間に来るためには、まず実験によって事実をつくることに同意している必要があった。
つまり、そのコミュニティはきわめて閉鎖的な性格のものだった。
完全に門戸を閉ざしていたわけではないが、門戸をくぐるためには実験科学の考えに同意する必要があった。
それに同意しなかったホッブズは自然哲学者ではあってもそのコミュニティからは締め出された(彼本人も入りたいとは思わなかったが)。
閉じた専門領域に事実を積み上げる
ようするに、この17世紀の半ばの新たな知識生成の方法の確立と同時に、分断された専門性の成立、内外の区切りが明確に引かれた学問領域の成立がある。
彼らの理想的な社会を特徴づけていたものは、実験家たちが推奨していた権威の源泉だった。実験哲学者たちは作業のなかで専制と独断論に警戒していた。いかなる孤立した強力な単一の権威も、信念を押しつけるべきではなかった。知識の力は自然から来るのであって、特権的な諸個人から来るのではなかった。コミュニティーが自由な状態において共同の同意をしめしたとき、事実は形成された。
コミュニティ内で自由で生産的な議論が行われるようにするためには、生産のための規律に同意する者だけがコミュニティに参加している必要があった。閉じた専門性の規律に同意できる者だけが専門家としてコミュニティに参加でき、そのコミュニティに蓄積された事実とそれに関連したナレッジを利用できるようになるというのが、この時代に生まれた新たな知の生産方法だったのである。
ボイルらがその事実とナレッジの一部をテクストの形でレポート化し公開していたのは、このコミュニティの真の閉鎖性を隠すものだったことがわかる。それは情報をオープンにすることで、情報の質と内容そのものによって、専門外の人を排除するのに効果的だった。
そうして外から守られた専門家コミュニティは、自分たちが主張したいことを自分たちの方法で主張可能な安全な領域となる。
安定的な同意が勝ちとられるのは、信念をもつ人びとが、限定され境界づけられた社会のうちに自分たちを組織化するからだった。この社会はよき秩序の基礎を受けいれない人びとを排除するような社会であった。統一は、その後に達成される成果として生まれるだろうと考えられた。そのコミュニティーの一員である、信念をもつ人びとにたいし、外部から課されるべきものではなかったのだ。
まず閉じたコミュニティ内での同意が形成され、専門性をもったコミュニティが保証するものとして外部に共有される仕組みがこの時代に成立する。宗教や王政のような旧来の権威を失った17世紀半ばの社会が同意可能な知識を生成する新たな方法がそれだったのだ。
内戦の引き金
そのコミュニティは門戸を閉じてはいないとはいえ、規律を受け入れないものを排除したし、実際その専門性によって誰もが出入りできる領域ではなかった。にもかかわらず、その閉じた内部で生まれたものを正しいものとするルールを社会的に承認させようとしていた。
ホッブズが批判したのもその点である。
ホッブズにとっては、絶対的な強制を確保できないいかなるプログラムからも内戦が生じた。グレシャムの人びとにとっては懸命で自由主義的な除外の戦略であったものが、ホッブズにとっては、万人の万人にたいする戦いに直結する扉をひらく端緒だったのである。
この本を読みながら、最初はホッブズの主張がボイルらの新しい知の生成方法に否定的な、古い権威にしがみついた独断的なものと感じられていたが、読み進めれば読み進めるほど、ホッブズの主張が、いまのこの分断された社会や、それ故に生じている利己的な行動ゆえの地球規模の全体的な調和や幸福を欠いた人間活動の源泉ともなった、閉じた専門性のコミュニティの形成のもつ危険性に対する正当な警鐘だったのではないかと感じられるようになった。
ホッブズは、知識人のどんな独立した集団も、世俗社会への脅威を構築してしまうことは避けられないと述べた。それどころか、そのような集団はそれ自体として危険なのであった。ここから引きだされる一般的な結論は、内戦の勃発と特権的な技能の領域をみとめることのあいだには関連があるということであった。聖職者や法律家は急進的党派と変わらなかった。
各専門領域コミュニティの専門家たちが生みだそうとしていた知識、その知識の生成の目的は、あまりに専門領域ごとの利己的な理由に傾きがちで、「公共の平和を確立することが哲学者の仕事」と考えたホッブズの姿勢とは正反対のものだった。
だからこそ、ホッブズは敵対する者たちに、独断的だとか、熱狂者だとか罵られ続けても、抗議し続けたのだろう。そのホッブズの姿勢を僕は素晴らしいと感じている。
各コミュニティごとに利己的に成果を求めるようになれば、当然、その結果、ホッブズが繰り返し言ったように、大なり小なり日々繰り広げられる内戦の引き金となり、「万人の万人にたいする戦いに直結する扉をひらく端緒」となる。実際、ホッブズが心配したとおり、それらは何ら社会全体あるいは地球環境全体の秩序の形成に寄与することなく、論争や戦争の口実ばかりを生み続けている。
しかも、その専門領域の生成と閉じた実験室での事実の蓄積による新たな知の生成と合意の保証の生成は、なにも実験科学の領域のみに起こったことではない。
法律家は、「研究と教育を完全に、あるいは主として哲学ないし数学の考察に向けている、いかなる他の人びととくらべても、この王国の法のいっそうふさわしい裁判官であり解釈者」なのであった。実務経験を積むという訓練によって、危険な論争のなかでも伝統と主権者権力とを確実に調停できるようになっていたわけだ。
という、法律と領域の例をはじめ、あらゆる専門領域が利己的な主張に正当性を与える武器の生成に寄与してしまったのだと思う。
事実に基づく議論の怖さがここにある。
ファクトフルネスの怖さも、AIの脅威も、結局、源泉は同じである。
それらはいずれも自分たちの安定的な議論の外側に対する配慮や寛容さをおそろしいほどに欠いているのだから。
事実が世界における自明なものになった
ホッブズとボイルは何度も互いに討論を繰り返した。そのなかで、ボイルは自分たち実験科学者の言論や活動の正当性を確立するための論の立て方を打ち立てていく様子がこの本には事細かに記述されている。
そして、そのロジックによって、ホッブズの主張はただの熱狂家の主張に過ぎないと規定できるようになった。
実験家たちと聖職者たちは、目撃され証言された事実には従わざるをえないと述べた。この技術をもちいたことで、うったえかけることのできる信者と目撃者のコミュニティの範囲がさだまった。事実によって意見を動かされることのない人びとはすべて、政治的および宗教的な国民の外部に位置するのだった。だからボイルは、ホッブズが実験によって生みだされた事実への同意を差しひかえるならば、彼は熱狂家である、と規定することができたのだ。
「事実によって意見を動かされることのない人びとはすべて、政治的および宗教的な国民の外部に位置する」という規定が成立する。
このとき、単に「つくられたもの」という意味しかもたなかった"fact"という語が、「事実ほどに所与のものはない」と思われるような、人間が手出しできない絶対的なものの領域に祭り上げられた。そして、それに疑義を挟むようなホッブズのような人間は、人間の領分を顧みない愚かな人間であるかのような規律がつくられ、それが当たり前であるかのようになったのだ。
ここに自然と人間文化のあいだの分断が成立する。人間が手出しできる領域と手出しできない領域の区分が。しかし、ラトゥールが指摘したように、人間はこの手出しできない領域に実際には手出ししまくって、すっかりその場全体を人新世の場へと変えてしまっているわけだ。自然が人間の不可侵の領域であるなんてのは、まやかしもよいところだ。
そして、この自然と人間文化の根本的な分断を祖型として、互いに不可侵な専門領域が成立した。この専門領域の壁によって、外の者はコミュニティ内部での知識生成に関与することができず、ただ外から文句を言うだけしかできなくなった。
ホッブズはこう考えていた。
公共の平和を確立することが哲学者の仕事であった。そして哲学者たちがこの仕事をなしうるのは、実験主義者たちが自然の研究と人間や人間にかんすることがらの研究とのあいだに引く境界を廃棄した場合だけだった。
これは、いまラトゥールが主張していることに近い。
僕らは、事実というものを根本的に疑いなおし、専門性を排した開かれた議論の場において、ホッブズが追いかけようとした「公共」についての探究こそを開始しなおす必要があるのだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
